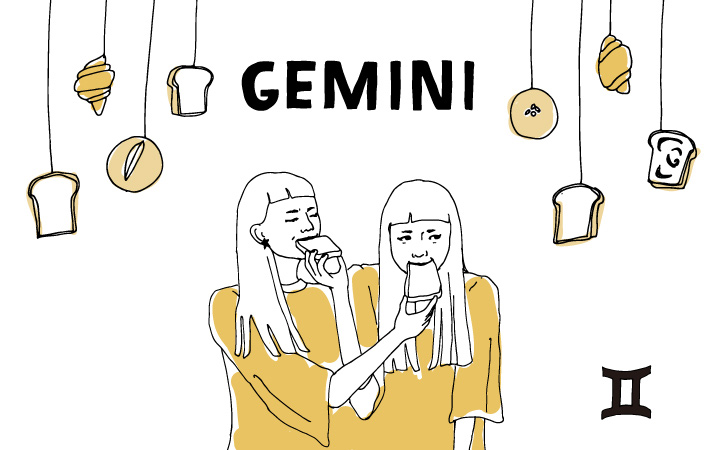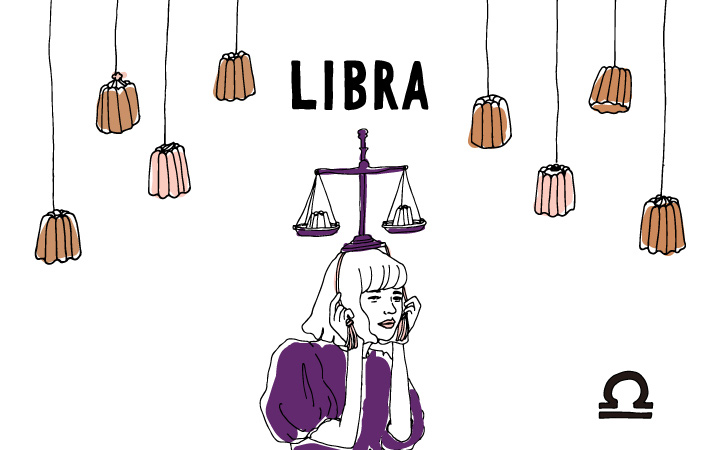角田光代さんの小説には、ポジティブな面とかなりダークな面が共存しています。なかでも最新刊『坂の途中の家』は恐ろしい小説です。三重の意味で恐ろしいのです。ジャンルは「犯罪小説」とか「法廷もの」などに分類できるでしょうか。内容は、都内に暮らす三人家族の主婦が、わずか八か月の乳児の娘を「虐待死」させた事件を、いろいろな角度から扱います。第一の恐ろしさとは、この一番前面にある題材の残酷さです。

とはいえ審理が進むにつれ、補充裁判員に選ばれた主婦の「里沙子」は被告人の「水穂」に感情移入し、自己投影していきます。つとめて忘れていた孤独でつらい育児体験が甦り、自分が「穏やかな暴言」や言葉の曖昧な含みに、どれほど傷つけられてきたか気づくのです。事件の背後に、見えづらい密やかな暴力が次第に浮かびあがってきます。この隠微な虐待の陰険さが、二番目の恐ろしさです。音羽お受験殺人に取材した先行作『森に眠る魚』や、心やさしいパートナーのモラルハラスメントを扱った『私のなかの彼女』などに連なる作品とも言えるでしょう。
この作品には、これまでの犯罪小説とは一線を画す果敢なアプローチがあります。作中の大半が法廷シーンでありながらも、そこに「○○」「✕✕」という会話体がほぼ一切使われていないのです。会話のない法廷小説なんて見たことがありません。普通は裁判官、検察官、被告人、弁護人、証人らが白熱のやりとりを交わし、容疑を晴らしたり、偽りを暴いたりするのを醍醐味とします。
本作の審理場面は、里沙子の目と耳を通した「要約」の形で書かれます。読者は被告人や証人が具体的にどんな言葉づかいで、どんなふうに話したのか、知らされません。そうすることで、里沙子の感じるもどかしさや疑心を読者にも感じさせようとしているのです。被告人と夫、被告人と姑、夫とその元恋人の間に、どんな言葉の応酬があったのか、それは当事者にしかわからない。いや、当事者も自分の発言がどんな棘と毒を持ちうるかわかっていない。だから言葉は残酷な刃物となりうるのです。人を虐げ、ときには殺すのです。
角田光代の真骨頂であり、新境地です。ぜひご一読を。

- TEXT :
- 鴻巣友季子さん 翻訳家・エッセイスト
Faceboook へのリンク
Twitter へのリンク
- クレジット :
- 撮影/田村昌裕(FREAKS) 文/鴻巣友季子