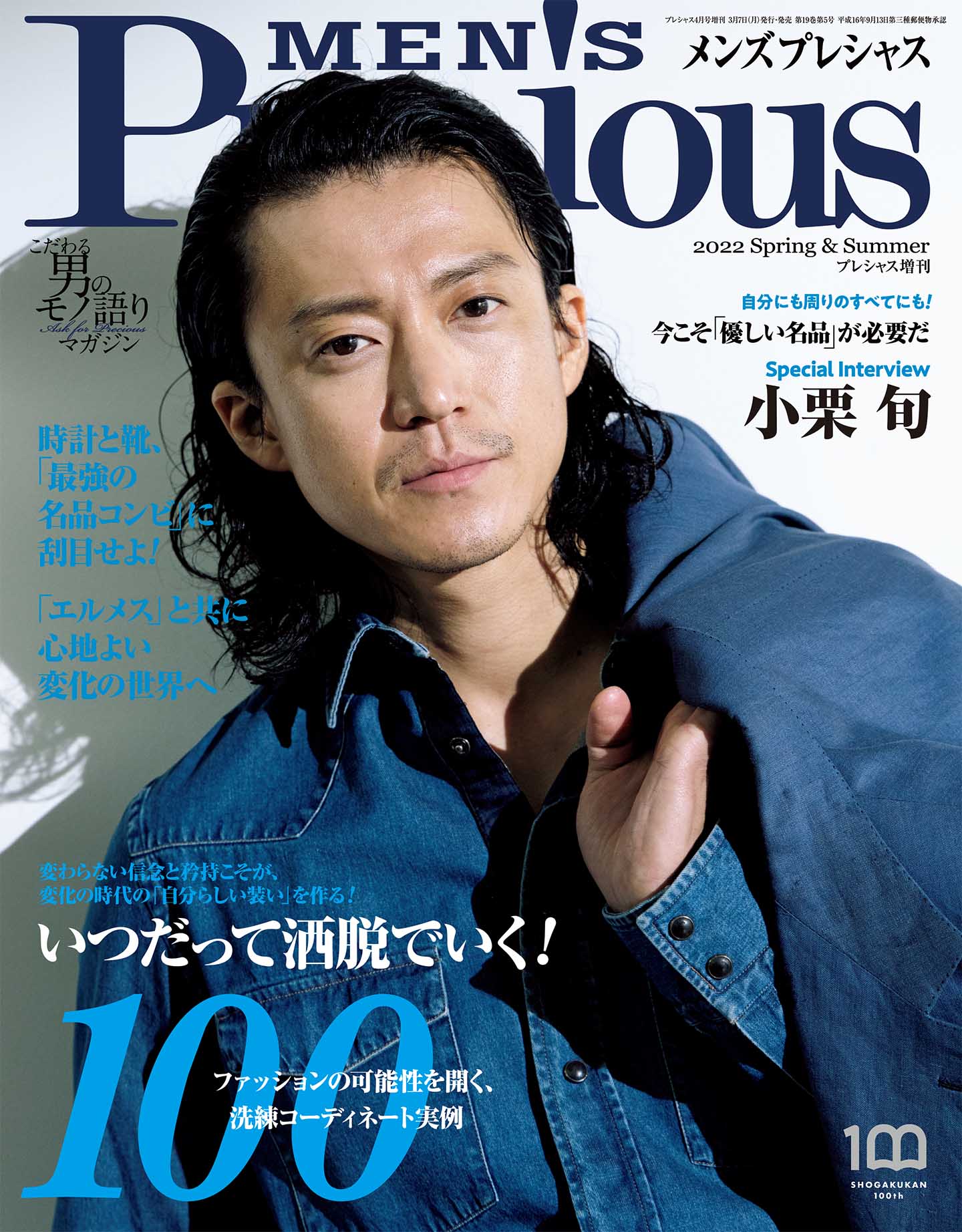著述家・田中誠司の「モーターサイクル・ハイライフ」
容赦ない、巨体である。そのホイールベースは、BMWラインナップの中で最も大きいことはいうまでもなく、ハーレーダビッドソンの大型モデルであるツーリング・シリーズと比べても100mm長い1725mmに達する。
映画「007 トゥモロー・ネバー・ダイ」でジェームズ・ボンドが操るバイクとして活躍した「R 1200 C」が生産を終えて以来、15年ほどご無沙汰していたクルーザー・セグメントに帰ってきたBMWは、まったく新しいフレームを設計し、まったく新しいエンジンを搭載、ただし古式ゆかしき空冷OHVを投入してきた。
エンジン始動で車体が一瞬傾くほどの反動が!

ほとんどのライダーがこれなら苦にしないだろうという低さのシートを跨ぐ。クロームが光るハンドルバーの中央には、円形のメーターがひとつだけ置かれている。
左右の眼下には、巨大なシリンダーヘッドが輝く。航空機由来の水平対向2気筒エンジンを長らくラインナップし続けているBMWだが、これほど明確に左右に張り出して存在を主張するモデルは前例がない。
比較的深く傾くサイドスタンドを払うため、左足に力を込めて起こす。重い。ヤマハSR400の2台分を軽く上回る車両重量374kgは、かなり脚力に自信のあるライダーでも負担に感じる質量であることは否定しない。
BMWモーターサイクル史上、最大排気量であるというフラットツインに火を入れる。右手にあるスターター・スイッチを押す時、ライダーは充分な注意を払わなければならない。エンジンを起動する反動で、バイクが一瞬、右側へ大きく傾くからだ。


ハンドルにしがみつきたくなるような図太い加速


やがて900rpm前後に落ち着くアイドリングの間こそ、少しばらついた振動を放つものの、クラッチをミートして走り出せばV型エンジンのライバルたちとは異なる、等間隔燃焼ならではのスムーズな回転フィールが伝わってくる。
1802ccのフラットツインは、2,000〜4,000rpmという幅広い領域で150Nm以上のトルクを供給。ハンドルにしがみつきたくなるような図太い加速を生じる。OHVというバルブ駆動方式ゆえか、そうして充分以上の力を感じている最中の3,000rpm+において、けっこうな振動がハンドルバーやシートに伝わり始める。
その先、がんばって回転上昇を待ったとしても、振動は高まる一方で、4,750rpmで発せられる最高出力も91psと際立ったものではないから、シーソー式のチェンジペダルの後方を踵で踏み込んで早めのシフトアップを繰り返すのが、この大きなクルーザーを走らせるマナーなのだと思う。


単なる移動の道具では味わえない「すごいものを操った感」


これほどホイールベース(前後輪間隔)が長く、車体も重く、タイヤも太いとなれば、操るのが難しいのではと想像するかもしれない。しかしそこはさすがBMW、ライダーの操作にバランスよく応えてくれて、少なくともデイリー・ライドにおいて扱いにくさを感じるシーンは一度もなかった。乗り心地も、着座位置の低さから想像するよりリヤサスペンションがよく動き、快適だ。
巨躯と車重により最も懸念される、駐車時の取り回し性を担保するために、R18の「ファーストエディション」には「リバースアシスト」が搭載されている。電動のスターター・モーターの力を利用するこのシステムなしに、少なくともぼくはR18とは過ごせないと思った。少しでも下った行き止まりで停めてしまうと、もうライダーの腕力だけでは後ろへ引っ張り出すことができないからだ。
R18と過ごした週末、ぼくは繁華街へ買い物に出かけ、目抜き通りのパーキング・メーターに駐車した。ほんの数kmのライドだった。行き交う人の波の向こうからBMWを眺めると、「ああ、こんなすごい乗り物を、おれは操れるんだ」という、得も言われぬ満足感に包まれた。あまり上手な喩えは見つからないが、たとえば登山を好む人が、下山して振り返って眺めた山が高く美しいほど嬉しい、というのと似ているのだろうか。
ひとりかふたりを移動させるだけなら、250ccのバイクでも充分だ。そうしたプラグマティズムと対極的であればあるほど、モータリング・ライフの印象は強くなる。



問い合わせ先
- TEXT :
- 田中誠司 著述家