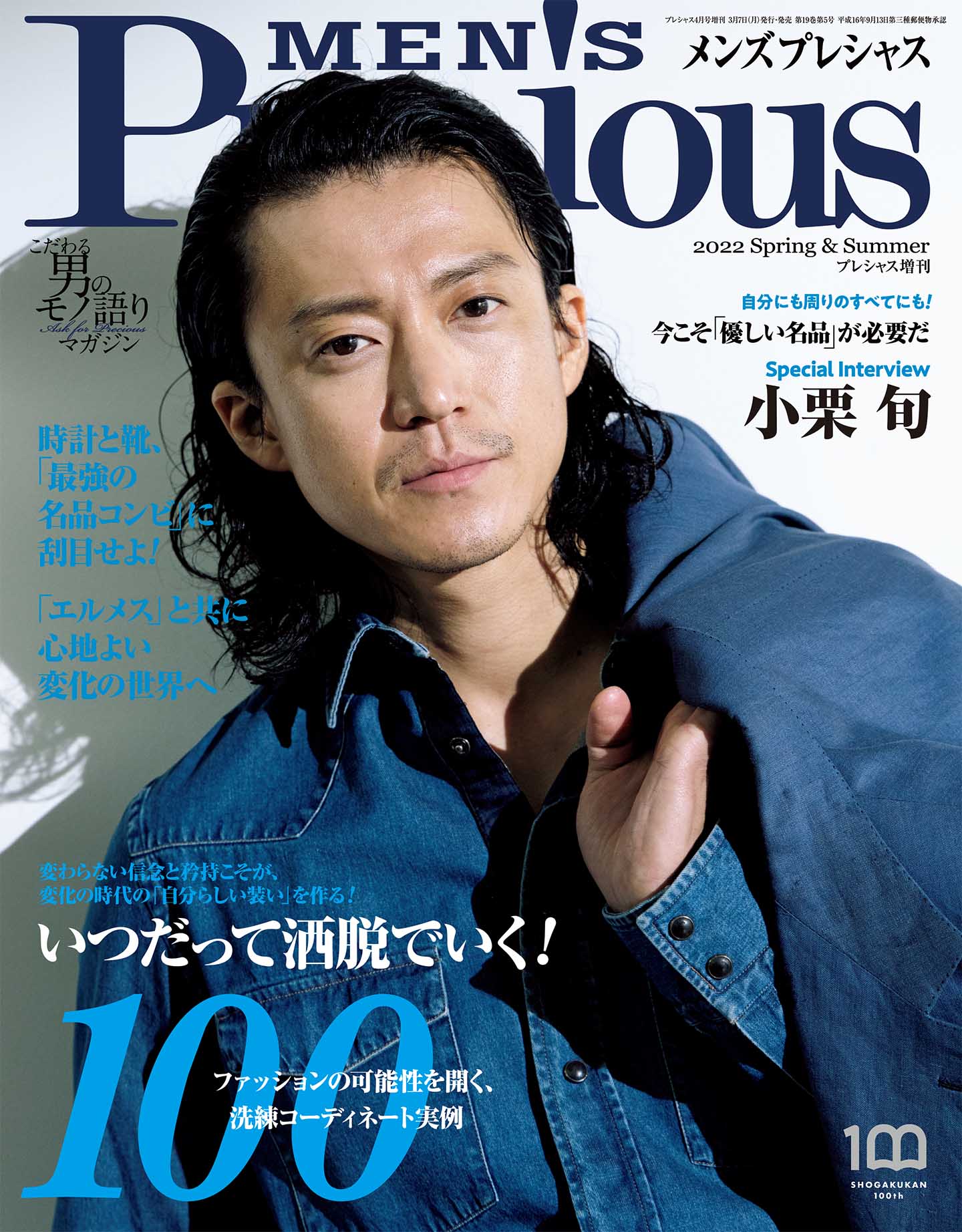“ラリーで勝つためのコンパクトカー”GRヤリスが人気だ。いわゆるホモロゲートモデル(ラリー参戦の基準をクリアするために市販される高性能車)は、これまでに幾度か欧州や日本のメーカーから発売され、クルマ好きの間で伝説的な存在となっているものも少なくない。GRヤリスも間違いなく後世に語り継がれるだろう。その卓越な運動能力の秘密を、プロトタイプ時から試乗してきたモータージャーナリストの大谷達也氏が解説する。
4WDに革新的なメカニズムを注入


高性能なスポーツモデルというと、パワフルなエンジンを積む重くて大きなクルマになりがちだけれど、GRヤリスは正反対。全長は4mを切るコンパクトサイズだし、エンジンだって1.6リッターの直列3気筒と決して大きくない(RZおよびRZハイパフォーマンスの場合。RSは1.5リッター)。
ハイパフォーマンスカーのトレンドに背を向けるようなクルマをどうしてトヨタが作ったかといえば、GRヤリスはそもそも世界ラリー選手権(WRC)を戦うために開発されたから。森の中の狭い公道を走ることも多いラリーカーは世界的に見てBセグメントが主流。ヒュンダイが作るi20は馴染みがないかもしれないが、トヨタ・ヤリス(先代ヴィッツがベース。間もなくGRヤリス・ベースに切り替わる予定)、フォード・フィエスタ、シトロエンC3(残念ながら撤退済み)といったコンパクトカーが覇を争うのがWRCなのだ。
WRCマシンのもうひとつの特徴は4WDを採用していること。これも悪路を走ることが多いWRCならではの特徴だが、GRヤリスはここに革新的なメカニズムを投入した。最新の4WDは電子制御式といって前輪と後輪のトルク配分をコンピューターによって可変できるシステムが主流だが、横置きエンジンの場合、後輪に伝達するトルクは基本的に0〜50%の範囲でしか調整できなかった。
ところがトヨタは「後輪に伝えるエンジン・パワーの回転数を前輪よりちょっとだけ速くする」という前代未聞のテクニックを使うことで、これを限りなく0〜100%に近づけたのだ。トルク配分と操縦性の間には密接な関係があるので、トルク配分の調整幅が広がる=操縦性の調整幅が広がると考えていい。とりわけ後輪に配分するトルクが増えれば、パワフルな後輪駆動のようにドリフト走行を楽しめる可能性が高まる。そこで、「トルク配分を自由に設定できる4WDシステムを使って、トヨタはどんなハンドリングにGRヤリスを仕上げたのか?」に注目が集まっていた。
というのも、公道試乗会に先立って行なわれたプロトタイプのサーキット試乗会では、雨で濡れたコース上でGRヤリスはテールを軽々と振り出す操縦性を発揮。強者にはたまらないクルマに仕上がっていたからだ。
上質な作りのRSは街乗りにおすすめ


いっぽう、今回の試乗会は乾いた舗装路の公道が舞台。タイトなワインディングロードにもかかわらず、コンパクトなボディのおかげで驚くほど俊敏なハンドリングを楽しむことができたほか、1.6ℓターボエンジンが低回転域からバツグンの瞬発力を発揮してくれるので、ストレスを感じることなくコーナーを攻めることができた。いずれもラリーカー・ベースだからこそ実現できたキャラクターで、日本のワインディングロードでこれほど痛快な走りを楽しめるスポーツモデルは滅多にないと断言できる。
いっぽうで、ドライの公道ではサーキット走行のときのようにテールスライドを引き出すことができなかったのは残念だった。この点は、ドライコンディションとウェットコンディションで前後のトルク配分の設定が異なるためなのか、はたまた私の実力不足によるものかは不明だが、走る舞台によってここまでキャラクターが極端に変わる点は意外だった。
意外といえば、4WD+ターボエンジンが基本のGRヤリスのなかにあって、唯一、前輪駆動+自然吸気エンジンを搭載するエントリーグレードのRSが驚くほどていねいに作り込まれていることも意外だった。
もちろん、ターボエンジンを積むRZやRZハイパフォーマンスほどの力強さはないものの、公道でそこそこコーナリングを楽しむなら十分パワフルだし、それ以上に高く評価したいのが乗り心地の質が高く、しかも前輪駆動とは思えないほどニュートラルなハンドリングに仕上げられている点。
ただのNA 1.5リッター・エンジンを積むFFコンパクトカーに265万円も支払うのはもったいないという指摘もあるかもしれないが、「サイズは小さくとも上質なクルマが欲しい」と願う層にとってはRSがベストなチョイスかもしれない。
問い合わせ先
- TEXT :
- 大谷達也 モータージャーナリスト