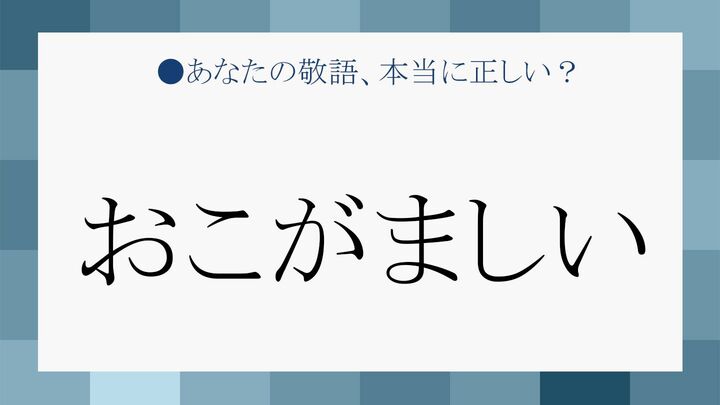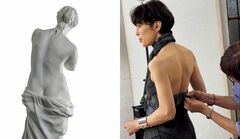【目次】
【「おこがましい」を漢字で書くと?「意味」と「語源」】
■「おこがましい」を「漢字」で書くと?
「おこがましい」を漢字にすると、「痴がましい」あるいは「烏滸がましい」となります。書くのも読むのも難しいですね! ご安心ください。一般的には平仮名で「おこがましい」と書くのが正解です。
■わかりやすく説明すると…「意味」
『デジタル大辞泉』によれば、「おこがましい」にはふたつの意味があります。
1) 身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。
2) いかにもばかばかしい。ばかげている。
ビジネスシーンでは、謙遜のニュアンスを込めて「私ごときがおこがましい」などと、1)の意味で使われることが多いようです。また、「おこがましいとは存じますが」というフレーズは、「差し出がましいとは承知しておりますが…」といった意味合いで、謙虚な姿勢を示すクッション言葉として使われます。このあたりのニュアンスは例文を参考にしてくださいね!
■「由来」と「語源」
「おこがましい」の語源は、ふたつあります。ひとつは古代中国・後漢時代にまでさかのぼります。「おこがましい」の「おこ」は水辺に集まるカラス「烏滸(おこ)」のこと。「おこがましい」とは、ギャーギャーと鳴きうるさいカラスに例えて、騒々しい人々のことを揶揄した表現です。
もうひとつは、漢字や外来語に由来しない日本独自の「大和言葉」の「をこがまし」。「をこ(馬鹿げている)」+接尾語「がまし」が付いた、馬鹿げていることを指す形容詞です。先に挙げた2)の意味は、これが語源です。
【ビジネスでの「使い方」がわかる「例文」】
■1:「身の程をわきまえない」「差し出がましい」「なまいき」という意味での例文
・「スタッフにおこがましい態度がございましたこと、心よりお詫びいたします」
・「自分で言うのもおこがましい限りですが、私は昨年度の最優秀賞をいただきました」
・(部下に対して)「君、お客様に対して、おこがましいことを言うものではないよ」
「差し出がましいとは承知しておりますが……」という意味合いで、「クッション言葉」として使用した場合の例文もご紹介しますね。
・「私がこの場で発言するのはおこがましいかもしれませんが…」
・「おこがましいとは存じますが先に申し上げたいことがあり、1分だけお時間いただけませんでしょうか」
■2:「ばかげている」「ばかばかしい」という意味での例文
・「同じミスを何度も繰り返すほどおこがましいことはない」
・「この見積もり金額はおこがましいとしか考えられない」
現在では「ばかげている」「ばかばかしい」という意味で「おこがましい」を使う機会はほとんどありません。そのため、意味が伝わりにくいかもしれません。
【「類語」と「言い換え表現」】
■差し出がましい
■厚かましい
■生意気な
■思い上がった
■僭越な
「分際をわきまえず出過ぎたことをすること」を「僭越」といい、「僣越ながら司会をさせていただきます」のように使われます。
■不躾な
「不躾」は「礼を欠くこと」「無作法なこと」。
【「対義語」】
■わきまえた
大人として物事に対応できる判断力や認識をもっていることを「わきまえる」と言います。
■謙虚
■思慮深い
【使える相手など「注意点」】
■同僚や目下の相手に対しては使わない
「おこがましい」は多くの場合、謙遜のニュアンスを込めて用いられるため、取引先や上司など、目上の人に対して使われる言葉です。部下や後輩など目下の相手に使うと、謙遜よりも嫌味と捉えられてしまうかもしれません。
■他人の言動に対しては、使用を控えるのが賢明
「おこがましい」は、基本的には自分のことをへりくだって言う際に使用します。部下や目下のものに対して使った場合、たしなめる意味合いが強くなることに留意して使いましょう。自分が指導者的な立場である場合は、問題ありません。
■相手が「おこがましい」を使ったら、否定するのがマナー
「おこがましいことを申しまして、失礼しました」などと言われたら、「いえいえ、そんなことはありません」「いいえ、大丈夫ですよ」などと、否定の言葉で返すのがマナーです。間違っても「そうですね」などとは返答しないでくださいね。
■多用しない
「おこがましいのですが…」というフレーズは、会話や発言のきっかけとなるクッション言葉として重宝します。ただし、頻繁に使用するのはかえって逆効果。本当に謙虚な気持ちのときに限定して使用しましょう。
***
「おこがましい」は謙虚な姿勢を表す際に使われる言葉です。古風な響きもあるため、この言葉を使いこなせば、奥ゆかしさと知性を表現することも可能に。ビジネスシーンで、ぜひ使いこなしてくださいね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館) :