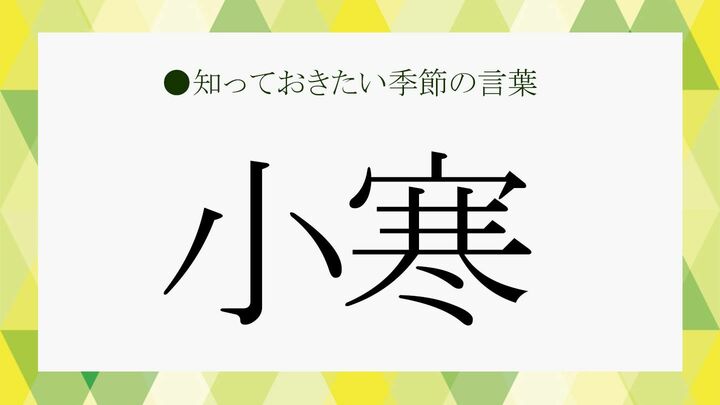新しい年を迎えると、何か“去年までとは違うこと”をしたくなりませんか? そこでおすすめなのが、日本の季節や風物、習慣を丁寧に感じること。暮らしぶりを変えるのは無理でも二十四節気を意識して生活するだけで、今までとはちょっと違った日々が訪れるかもしれません。今回は、新年最初に訪れる二十四節気の「小寒」についてさくっと解説します。
【目次】
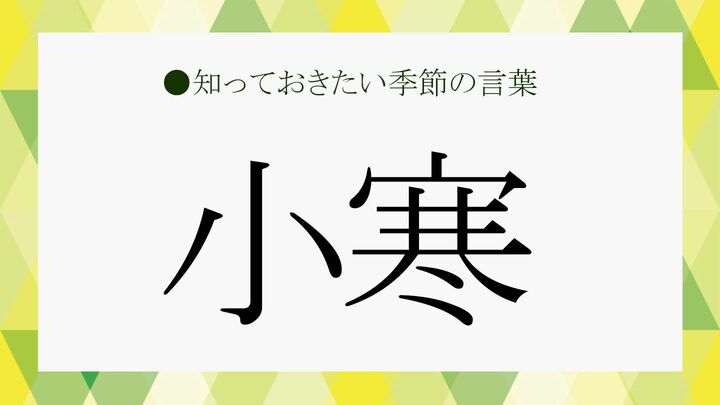
【「小寒」とは?「読み方」と「意味」】
■読み方
「小寒」と書いて「しょうかん」です。
■意味
「小寒」は二十四節気のひとつ。二十四節気とは12の「中気」と12の「節気」の総称で、中国の戦国時代に成立しました――と言われても、よくわかりませんよね。太陽暦で季節を正しく示すために用いた語のことで、1年を太陽の黄道上の位置によって定めた24の季節区分を指します。季節の移り変わりを知る目安と考えればいいでしょう。
「小寒」は太陽の黄経が285度に達したときをいい、新暦では1月5、6日ごろにあたります。この日からの約30日間を「寒の内 (かんのうち) 」と言い、1年で最も寒さの厳しい季節にあたります。
【2025年の「小寒」はいつ?】
12月22日ごろの「冬至」から約15日後に訪れる「小寒」。二十四節気はその日自体を表したり、次の節気が来るまでの約15日間を指したりします。「小寒」の初日を「寒の入り(かんのいり)」とも。
■2025年の「小寒」は1月5日
2025年は1月5日(日)が「小寒」にあたります。「小寒」のあとにくる次の節気「大寒(だいかん)」と合わせた約30日間は、日本列島が最も冷える時期。正月休みで日々のペースが崩れる人も多いでしょう。寒さにも日常にも、うまく対応する工夫が必要ですね。
【「食べ物」「花」など…「小寒」にまつわる「雑学」】
■食べ物
「小寒」で食べるとよいとされものや、おいしい旬を迎える食材などを紹介しましょう。
・七草粥:1月7日に「春の七草」を入れて炊く粥のこと。セリ、ナスナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの若菜を使用します。
・小豆粥(あずきがゆ):1月15日に食べる、米・あわ、ひえ、きび、麦、ごま、小豆を入れて炊いた粥。
・寒蜆(かんしじみ):「寒」の時期のものは栄養価が高く、上質といわれています。
・寒海苔(かんのり):「寒」の入りのころから2月ごろまでに採ってつくられた、希少な浅草海苔を特別にこう呼びます。
・寒仕込み(かんじこみ):日本酒、醤油、味噌など、この時期に仕込んだものを言います。「寒」の時期の冷たい水で仕込むと雑菌が繁殖しにくく、発酵がゆっくり進むので味に深みが出るのだとか。「寒仕込みの酒」など、いかにもおいしそうですね。
・花びら餅:薄く円形に広げた柔らかな白い餅に、上品な甘さの味噌餡、甘煮のごぼう、菱形の薄いにんじん色の羊羹を重ねてはさんだ和菓子。由来には諸説ありますが、平安時代に宮中で長寿を願う新年の「歯固め」の儀式で用いられた食事を、江戸時代にそれを模したお菓子として広まったものが原形なのだそう。
■風習
・鏡開き:1月11日に行うのが「鏡開き」です。年神様にお供えした正月の「鏡餅」をおろし、お雑煮やお汁粉にして食し、一家の円満と繁栄を願います。小さくする際に刃物で切るのは縁起がよくないとされ、木槌やトンカチなどで叩き割るようにします。小さくなった鏡餅を油で素揚げすると、簡単にかき餅がつくれます。
・寒中見舞い:近年では、松の内(1月7日)までに出せなかった「年賀状の返礼」として使われることが増えました。喪中でも出すことができ、喪中の相手に出してもOKです。
■花
春の訪れはまだ先、花屋の店先も少々寂しげですが、この時期ならではの植物も。
例えば「蝋梅(ろうばい)」。江戸時代初期に朝鮮経由で中国から伝来したとされる、小さな黄色い花をつける落葉低木です。その花びらが、まるで蝋細工のようであることから命名されました。ほんのり甘く石けんのような清潔感のある香りが特徴。新春に香り高い花を咲かせる貴重な存在で、中国では、ウメ、スイセン、ツバキとともに「雪中の四花」として尊ばれています。風水では金運や家庭運が上がるとされているため、「寒」の時期の開業祝いや新築祝いにも喜ばれるでしょう。花言葉は可憐な姿にピッタリな「慈悲」「奥ゆかしさ」や、「先見」「先導」など。

***
正月休みも終わり、なかなかエンジンがかからない…という人も多い「小寒」の時期。インフルエンザや肺炎などにも気を付けつつ、よい年のスタートを切りたいものですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社)/『日本文化いろは事典』(シナジーマーケティング) :