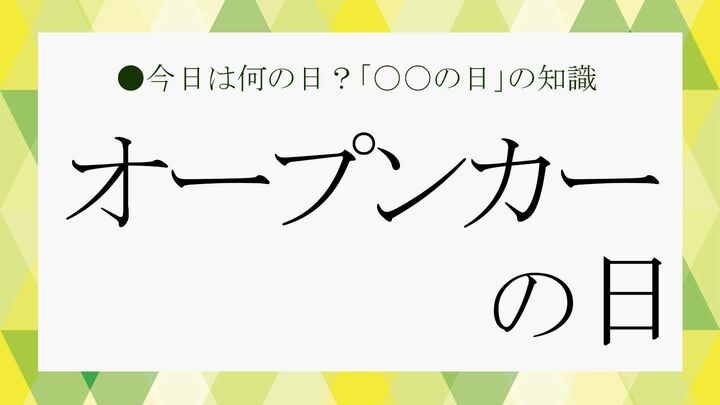うららかな春の光と風を受けて走るオープンカーは、本当に気持ちがよさそうです。車好きはもちろん、助手席専門の人も、この季節なら「1度乗ってみたい」と思ったことがあるのではないでしょうか。4月5日は「オープンカーの日」。日付の由来やオープンカーにまつわる雑学をお届けします。
【目次】
【「オープンカーの日」とは?】
■「いつ」?「誰が」決めたの?
「オープンカーの日」は、4月5日です。神奈川県横浜市に本部を置く、「日本オープンカー協会」が2016(平成28)年に制定しました。オープンカーの魅力を多くの人に知ってもらい、その快適さを伝えていくのが目的です。
■日付の「由来」は?
桜の舞うなかを走ることができる「4月」は、オープンカーにとって最高のロケーションの時期であること、そして、オープンカーは「五感」に訴えかける車であることから、4月5日になりました。
■「日本オープンカー協会」って?
日本に、オープンカーに対する正しい認識を広めることを目的とした団体です。コンセプトは、オープンカーの手軽さと快適さを広げていくこと、オープンカーを愛する人たちと共に楽しいカーライフを過ごすこと。完全不定期の活動を行っています。
【言い換え表現は?ビジネス雑談に役立つオープンカーの雑学】
■オープンカーは和製英語?
私たちは「屋根のない車」を「オープンカー」と呼んでいますが、皆さんのご想像通り、「オープンカー[open car]」は、「和製英語」です。英語圏では「コンバーチブル[convertible]」、欧州圏ではフランス語の『カブリオレ[cabriolet]」と呼ばれることが一般的で、どちらも折りたたみ式の幌(ほろ)を備えたオープンカーの名称です。
コンバーチブルは「複数の形式に変換できる」、カブリオレは「馬1頭・ふたり乗り・2輪の馬車」という意味の言葉。基本的に4シーターで、幌を閉じれば箱型のセダンと同じように使用できます。
■車の歴史はオープンカーから始まった!
今でこそ、オープンカーは特別な仕様となりましたが、実は自動車の黎明期である1900年ごろのガソリンエンジン自動車は、ほとんどがオープンカーでした。世界で初めてのガソリン自動車とされているモデルは、19世紀のドイツで開発された「ベンツ パテント モトールヴァーゲン」です。
そもそも、車の原型は馬車だったため、この車も三輪馬車に原動機を“載せただけ”ともいえるような形で、屋根はついていませんでした。「走る、曲がる、止まる」といった基本性能の開発に注力していたため、運転手や乗員の快適性までは配慮されていなかったのです。その後もガソリン自動車の普及は進みましたが、屋根付きの車(クローズドボディ)は高価だったため、しばらくはオープンカーが主流でした。
■車に屋根が付いたのはいつ?
「屋根のない車=オープンカー」に対して、「屋根がある(箱形の車室がある)車」のことを、「クローズドボディ」と呼びます。この「クローズドボディ」普及のきっかけとなったのが、1921年にアメリカで誕生した「エセックス・コーチ」です。
この車の登場以降、「クローズドボディ」の人気はうなぎ登りに。同時に、「オープンカー」の人気は世界的に低迷していきました。私たちがイメージする「カッコいい趣味の車」としての「オープンカー」の登場は、第2次世界大戦の後となります。
■オープンカーの別名は?
「オープンカー」の別名は、先にご紹介した「コンバーチブル」や「カブリオレ」がよく知られていますね。このふたつはどちらも「クローズド=屋根を閉じた状態」がデフォルト(基本)です。
このふたつに対して、「オープン=屋根を空けた状態」がデフォルトとなるタイプの「オープンカー」もあります。まずは「フェートン」。20世紀前半に「折り畳み式の幌を備えた2列シート、4人乗り、4ドアボディ」の車を指す言葉として使われましたが、1950年代以降、姿を消しました。
次に、日本人には「マツダ・ロードスター」として馴染みのある「ロードスター」も、「オープンカー」を表す言葉です。基本的にスポーツタイプの2人乗りオープンカーを指します。また、「ロードスター」同様、2人乗りのスポーツタイプのオープンカーによく使用されるのが「スパイダー」です。こちらの代表はアルファロメオ・スパイダーでしょうか。イタリア車に用いられる名称です。イタリアには2人乗りのオープンカーの名称として、「バルケッタ」という言葉もあります。イタリア語で「小舟、ボート」という意味があるそうですよ。
このほかにも、「スピードスター」や「タルガトップ」「Tバールーフ」と、「オープンカー」を意味する言葉は想像以上に多く存在し、詳しい人ならその名称でデザインやコンセプトがわかるのだそう。奥が深いですね!
■世界でいちばん売れたオープンカーは?
世界最大の生産台数を記録しているのは、日本が誇る「マツダ・ロードスター」です! 「マツダ・ロードスター」のデビューは、1989年2月の米国シカゴ・ショー。MX-5、MX-5ミアータのモデル名で発表され、、日本では同年9月、当時のユーノス・チャネル専売モデルとしてデビューしました。
海外ではデビューと同時に大きな話題を集め、2000年5月には「2人乗り小型オープンスポーツカー生産累計世界一」を達成。ギネス世界記録に認定されています。このときの台数は53万1890台で、2016年4月には100万台を突破しました。
■「自動車にまつわる記念日」あれこれ
自動車に関連する記念日は、「オープンカーの日」以外にもたくさんあります。いくつかご紹介しましょう。
・自動車保険の日:2月14日
1914(大正3)年2月14日に、東京海上日動火災保険株式会社(当時は東京海上保険株式会社)が「人とクルマの毎日を安心なものにしたい」という思いのもと、日本初の自動車保険の営業認可を取得。2014年に「自動車保険誕生100周年」を迎えたことを記念して「自動車保険の日」が制定されました。。自動車保険の大切さを多くの人に知ってもらうのが目的です。
・洗車の日:4月28日と11月28日
洗車を行い、愛車を「よい艶をもったクルマにしましょう」と、一般社団法人自動車用品小売業協会が4月28日と11月28日を「洗車の日」に制定。日付は、4と28で「ヨイツヤ(よい艶)」、11と28で「イイツヤ(いい艶)」と読む語呂合わせから。
・タイヤの日:4月8日
タイヤは自動車にとって必要不可欠なものであるにもかかわらず、ドライバーの関心があまり高くないことから、タイヤの正しい使い方をアピールし、交通安全に寄与しようと一般社団法人日本自動車タイヤ協会が制定。日付は春の全国交通安全運動が行われる4月と、輪(タイヤ)をイメージした8の8日を組み合わせたもの。
・CO2削減の日:4月2日
身近なことからCO2の削減に取り組もうと、静岡県浜松市の富士金属興業株式会社(サービス名・ドラゴンパーツ)が制定。自動車リサイクル部品(リビルト品or中古品)での車修理は、新品を使用するよりも大幅なCO2の排出削減ができることをアピールするのが目的です。日付は4月2日(402)で「シーオーツー」と読む語呂合わせから。
・クラシックカーの日:11月3日
日本で最も古いクラシックカークラブである日本クラシックカークラブが制定した記念日。同クラブは自動車を美学的な見地から論評した、浜徳太郎氏の元に集った愛好家により、1956年に誕生。日本におけるクラシックカーの研究と保存、文化価値の啓蒙と次世代への継承を目指す同クラブの活動を通じて、クラシックカー文化を育んでいくことが目的。日付は同クラブの設立記念日である1956年11月3日から。
***
4月5日は「オープンカーの日」です。爽やかな風を受け、桜舞い散る道を走るオープンカーは、さぞ気持ちがよいことでしょう! 颯爽と走る勇姿を見かけたら、さり気なく「オープンカー」の雑学ネタを周囲にご披露してみてはいかがでしょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『プログレッシブ和英中辞典』(小学館) /日本オープンカー協会(https://www.jp-ca.net) /一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp) :