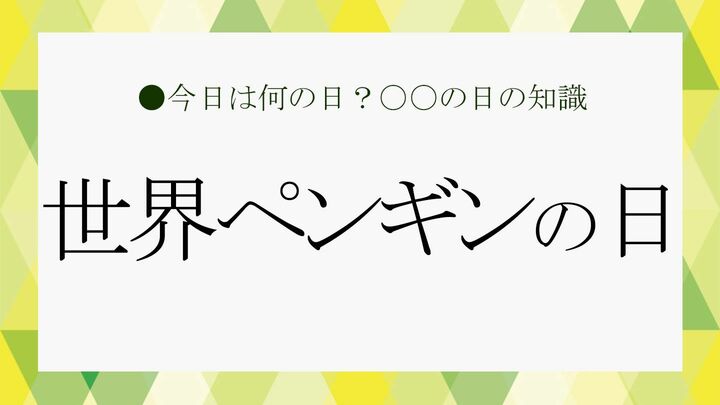【目次】
【「世界ペンギンの日」とは?】
「世界ペンギンの日」と聞いて、すぐにピンとくる人はすくないかもしれませんね。詳しく解説します!
■「いつ」?「英語表記」は?
「世界ペンギンの日」は4月25日。英語表記は[World Penguin Day]です。
■日付の「由来」は?「誰が」決めた?
「世界ペンギンの日」は、南極にあるアメリカの観測基地、「マクマード基地」に、アデリーペンギンが毎年4月25日前後に姿を見せることから、基地の科学者たちが「ペンギンの日」として祝ったことが始まりといわれています。
■「目的」は?
そして現在、「世界ペンギンの日」は絶滅の恐れのあるペンギンたちの保護や環境問題について、みんなで考える日とされています。
【ビジネス雑談に役立つ「ペンギン」の雑学】
■「北半球にペンギンはいない」って知ってた?
「ペンギン」は鳥綱「ペンギン目ペンギン科」に属する海鳥の総称です。生息地は南半球のみ。南極および亜南極圏の島々でペンギンが繁殖しない所はなく、多くのペンギンが繁殖しています。同じく極寒の地である北極には大型の肉食獣・ホッキョクグマがおり、ペンギンの繁殖には適しません。
南極大陸で繁殖するのは、主にコウテイペンギンとアデリーペンギンの2種。


ちなみに、南極は1959年に締結された「南極条約」により、「南極は世界共有の財産である」ことが確認されました。従って、どこかの国が主権を主張することはできません。現在、アメリカやイギリス・ニュージーランド・中国・ロシア・南アフリカといった世界の国々が基地を置き、宇宙や気象、生物などを対象に、平和的に調査を実施しています。
■「ペンギン」の種類は? 実は絶滅の危機
分類方法により若干の違いはありますが、ペンギンは現在、18種とされていて、その約半数が絶滅の危機にあるそうです。原因は環境汚染や生息地の破壊、漁業、地球温暖化など。世界規模での対応が急務とされています。
■ペンギンの大きさは?
ペンギンの大きさは、種類によって実にさまざま。最大といわれる「コウテイペンギン」は身長100~130cm、体重約30kgといわれる一方、最少の「コガタペンギン」は体長30~40cm、体重約1kgくらいです。数字だけ見ると、同じ種族とは思えない程、大きさが違うんですね。
■鳥なのにはぜ飛べないの?
実は、ペンギンの祖先は飛ぶことができました。しかし、泳ぐことが得意な体に進化したことで空を飛ぶための翼が退化したと考えられています。
ペンギンが海中を自在に泳ぎ回る様子は、「水中を飛ぶ」とも形容されます。羽と尾、そして足は短いのがペンギンの特徴。翼の代わりにフリッパーと呼ばれるヒレと足の間の水かきが発達し、水中を進みやすい流線型の体型になっています。
頸 (くび) から上を水から出して遊泳し、すばやく潜水して水中を高速で進むこともできますが、ちょうどイルカのように水中から空中に飛び出し、空気を吸い込んで着水し、また勢いをつけて水から飛び出すことを繰り返して、移動することもあるそうです。
一般的なペンギンが泳ぐ速度は、時速約11kmといわれ、ペンギン界最速といわれるジェンツーペンギンは、時速約35kmで泳げるそうです!潜水に適応した鳥なので、地上ではお世辞にも敏捷 (びんしょう)とは言えません。直立姿勢をとり、歩いたり跳ねたりして移動します。氷上では胸腹部をつけて、滑るようにはうことも。可愛いですよね!

■寒い場所でしか生きられないの?
南極半島と南極大陸の沿岸には多くのペンギンが生息していますが、そのほかにも、オーストラリア、ニュージーランド、南アメリカ、南アフリカ、ガラパゴス諸島など、温暖な地域に住むペンギンもいます。
日本で最も多く飼育されているフンボルトペンギンは、日本から地球のちょうど真裏あたりにある、南米のチリ・ペルーなどに住んでいます。気温や気候が日本とほぼ変わらないため、水族館や動物園の屋外で散歩するイベントが行われていたり、夏でも元気な様子を見ることができるのですね。

■ペンギンには歯がない!
ペンギンの口を開けると、舌と上あごから奥に向かってギザギザのトゲ(突起)がありますが、これは歯ではありません。魚などの獲物をくちばしでくわえるとスルリを奥に入りますが、うろこがひっかかり逃がさない構造です。これにより、水中でしっかりに魚をキャッチできるのです。また、なるべく早く多く、スムーズに食べられるよう、獲物を頭から飲み込んでいくそうです。
■ペンギンは短足ではない!
短い脚でよちよちと歩く姿がキュートなペンギンですが、実は普段見えているのは足のほんの一部。人間でいうと、かかとから足の甲にあたる部分にあたる「ふしょ骨」が足として見えており、ふしょ骨から上の部分は体内に隠れています。鳥のなかでもペンギンは特にふしょ骨が短く、これは体外に出ている末端の部分を少なくして熱を逃げにくくするためなのだそうです。
■日本では11種類のペンギンが見られます
ペンギンをモチーフとしたキャラクターがたくさんあることからもわかるように、日本は世界でも有数の「ペンギン好きの国」なのだそうです。18種類いるペンギンのうち、11種類が飼育されているといわれていますが、あなたは何種類知っているでしょうか?
コウテイペンギン
世界最大のペンギン。耳や胸に黄色の筋模様が入っているのが特徴です。
オウサマペンギン
外見はコウテイペンギンに似ていますが、サイズは一回り小さめ。喉のあたりのオレンジ味が強いのも見分けるポイントのひとつです。
アデリーペンギン
さまざまなキャラクターのベースになっているので、ペンギンといえば「アデリーペンギン」を思い浮かべる人も多いでしょう。顔が黒く、目の周りが白いのが特徴で、尾羽が長く、若鳥はアゴの下が白くなっています。実はやや荒っぽい気性なのだとか。
イワトビペンギン
名前の由来は、このペンギンが岩場をぴょんぴょん跳び回ることにちなんでいます。
金色の冠羽(かんう・かんむりばね)と赤い目が特徴で、性格は攻撃的です。
コガタペンギン
「フェアリーペンギン」とも呼ばれる最小のペンギンです。
ただし縄張り意識が強く、見かけによらず攻撃的な性格をしています。
フンボルトペンギン
胸に伸びる、太く黒いラインが特徴。日本の気候と相性がよく、日本で飼育されているペンギンの約1割は、フンボルトペンギンです。
そのほか、ケープペンギン、マゼランペンギン、ジェンツーペンギン、ヒゲペンギン、マカロニペンギンが日本で飼育されています。
■コウテイペンギンの雄はイクメン
基本的にペンギンは、卵が生まれるとオスとメスが交代で卵を温めます。ただし、たとえば「キングペンギンは立ったまま」「ジェンツーペンギンは腹ばいで」など、そのスタイルは種類によってさまざま。 また、南極に住むコウテイペンギンは、卵を温めるのはオスの役割となっています。卵を産んだメスはエサを求めて海に行き、3か月近くも帰ってきません。オスはメスが食べ物を持って帰ってくるまで、気温-60℃の極寒で強風が吹く中、飲まず食わずで卵を温め続けます。なかなか過酷な育卵です!
■年に一度、羽毛が生え変わる
鳥の羽毛は、汚れたり破損しても自己修復はしません。時間の経過とともに撥水性も保温性も低下していくため、ペンギンは1年に1度古い羽毛を脱ぎ捨て、新しい羽毛を身にまとう「換羽(かんう)」を行います。換羽の期間は2〜3週間ほど。換羽中は新旧の羽毛が混じった中途の状態にあるため撥水性、保存性が完全には維持されず、海に入ってしまうと体温を奪われて死んでしまうそうです。そのため、陸上にとどまったまま、換羽が終わるのをじっと待ちます。
換羽期間の野生のペンギンは食事を摂れなくなるので、絶食して過ごすことになります。換羽自体でもエネルギーを消費するため、あらかじめたくさん食べて脂肪を蓄積し、換羽中はなるべく動かないで過ごします。動物園や水族館で羽が抜けてボサボサになっているペンギンがいたら、それは換羽期に入っているせいなのかもしれません。
***
世界ペンギンの日である4月25日前後から5月の連休にかけて、毎年ペンギンのいる水族館や動物園ではさまざまなイベントが行われます。ショーではペンギンの可愛い勇姿が見られますよ。お出掛けしてみてはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所(https://www.nipr.ac.jp) :