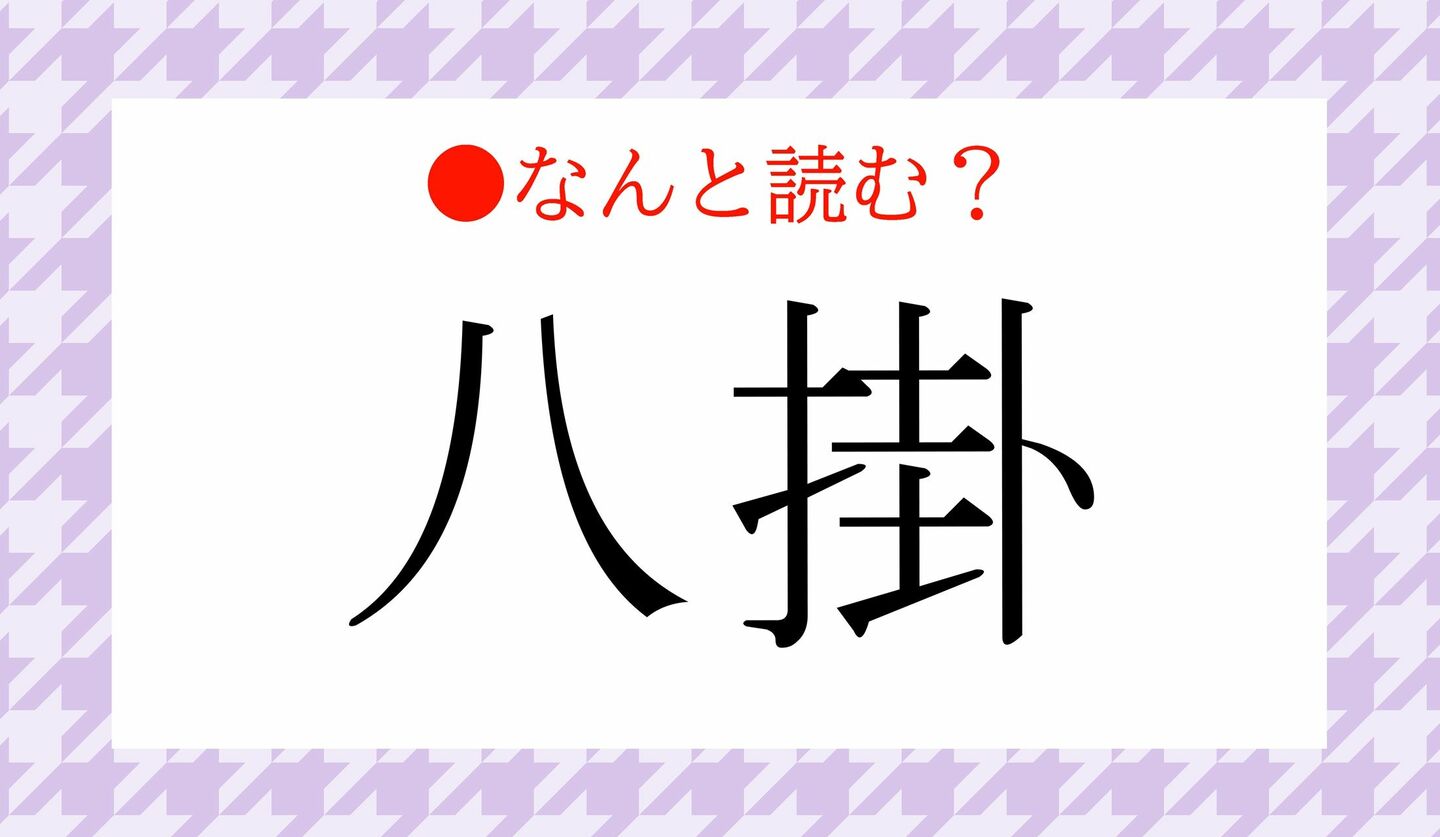「久方振」ってなんと読む?「きゅうほうしん」ではないですよ!
明日・5月6日は『ふりかけの日』です。大正時代に、当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として、魚の骨を砕いてご飯にかける「ふりかけ」の基礎となる食べ方を考案した薬剤師・吉丸末吉氏の生誕日にちなんで記念日で、ふりかけという食文化の発展を目的としています。「ふりかけ」を漢字で書くと「振掛」ですので、本日は「振」「掛」という字の入った日本語クイズをお送りします。
【問題1】「久方振」ってなんと読む?
「久方振」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「前にそのことを経験してから、再びそうなるまでに長い日数が過ぎているさま」です。
<使用例>
「この連休に、久方振に同窓会があって、旧交を温めることができました」
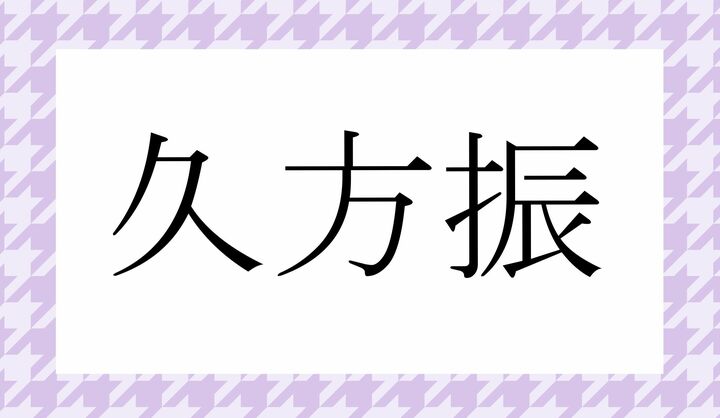
…さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。
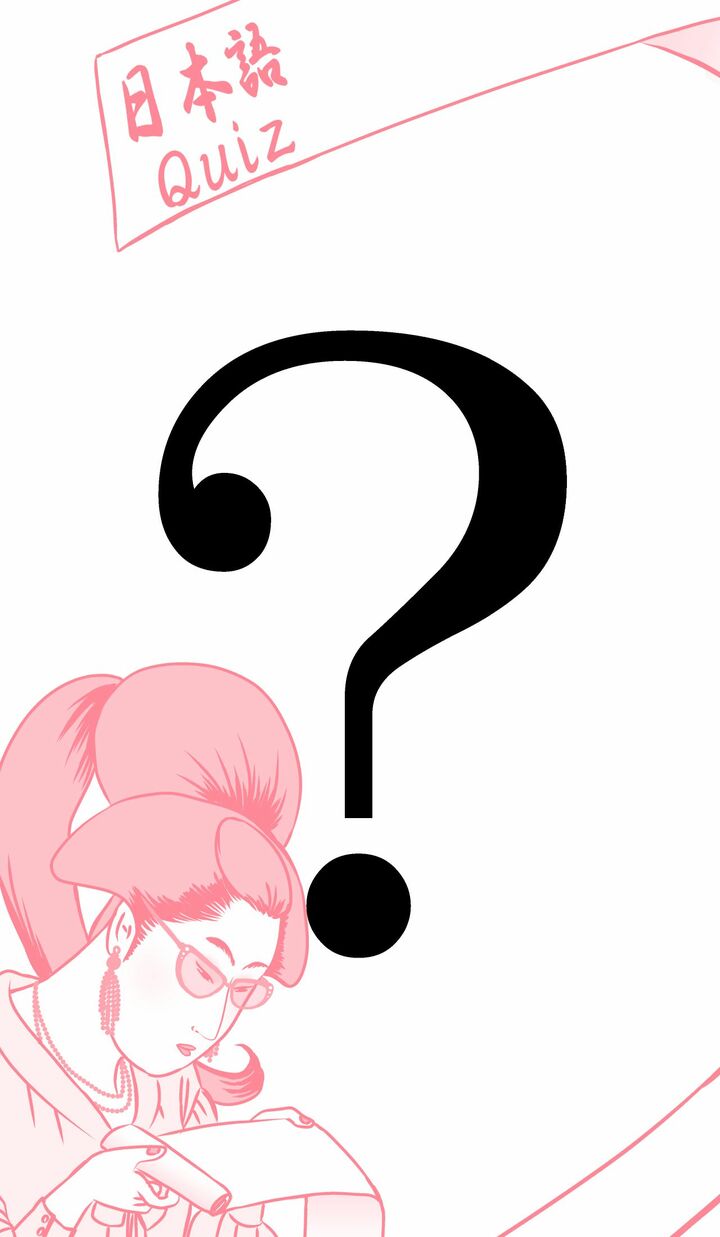
正解は… 久方振(ひさかたぶり) です。
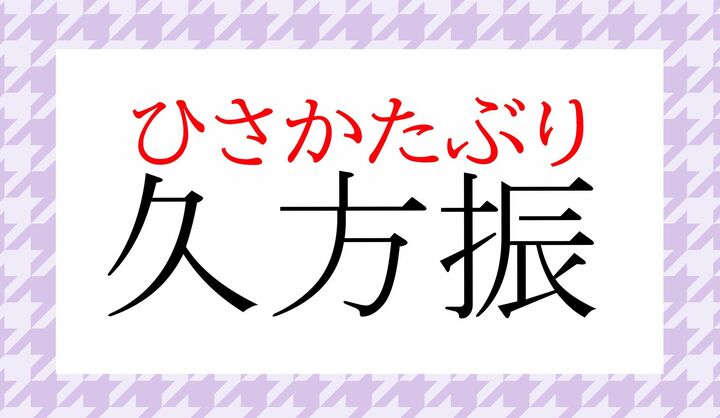
ちなみに「ひさしぶり」の漢字表記は「久し振り」です。
さて、2問目は「掛」という字の入ったクイズです。
【問題2】「八掛」ってなんと読む?
「八掛」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「袷(あわせ)の着物(夏以外のシーズンに着る、裏地のついた着物)の裏すそに用いる布」の名称です。
<使用例>
「この着物、春先に着たくて、八掛を軽やかな色にしたのよ」

…さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 八掛(はっかけ) です。
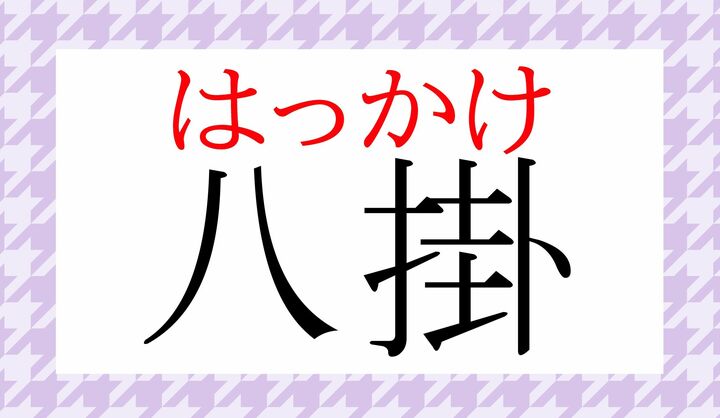

和装用語ではありますが、「襦袢(じゅばん)」くらいポピュラーな名称なので、大人の一般常識として知っておきたい言葉です。「八掛(はっかけ)」は袖口や裾など、合計八か所につける裏地なので、この名称で呼ばれるようになりました。袖や裾など、着物の傷みやすい部分を保護することも兼ねており、1~2mmほど着物から出るように仕立てるので、外からはちらりと見える程度ではありますが、着物と同系色にする場合と、反対色にする場合では印象が変わります。和装の、上級者的おしゃれポイントにもなる布です。
***
本日は、5月6日が『ふりかけの日』にちなんで、「振」「掛」という字の入った日本語から、
・久方振(ひさかたぶり)
・八掛(はっかけ)
の読み方、言葉の背景などをおさらいいたしました。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- BY :
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/日本記念日協会ホームページ/『きものと』ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)/photo AC
- ILLUSTRATION :
- 小出 真朱