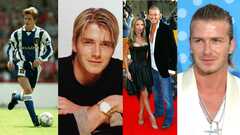【目次】
【前回のあらすじ】
前々回の「招かれざる客」では、蔦重(横浜流星さん)と歌麿(染谷将太さん)の関係に見えざる亀裂が入る経緯が描かれました。
そして前回、「裏切りの恋歌」で状況はさらに悪化。とうとう決別の時を迎えます。
先に別れを決めたのは、歌麿でした。
「この仕事が終わったら、もう蔦重とは終わりにします」。
歌麿は、かねてより歌麿に憧れ、ぜひとも一緒に仕事をしたいと企画を持ちかけてきた、地本問屋・西村屋の2代目、万次郎(中村莟玉さん)にこう告げます。このセリフ、ビジネスについて話しているようには聞こえませんね。蔦重に対する自分の気持ちに終止符を打つために、歌麿は蔦重とビジネス上のタッグを解消する決心をしたのでした。
「これが蔦重との最後の仕事」と心に決めて、吉原で花魁たちのスケッチを進める歌麿。「花魁、間夫(遊女の情夫)を想って歌を詠んでるふうにしてくれないか」と、花魁が恋する人を想う一瞬を写し取ろうとろうと試みます。ふと視線を移せば、かつての恋人をしみじみと懐かしむ遣り手(遊女を監督し、あれこれと手配をする年配の女性)にも、なんとも言えない風情が。茶屋に入れば、愛しい人を待つ少女の姿が、歌麿の目を惹きつけます。
今回、歌麿がこのうえなく優しい視線を送り、その絵に写し取った相手は、みな恋心を胸に秘めた女性ばかりなんですね。人の心の機微に敏感で、誰より繊細な心をもつ歌麿だからこそ、恋する女性たちにまるで自分の姿を重ねるように、恋心を絵に閉じ込めようと思いついたのでしょう。しかし残念なことに、そういう方面にはめっぽう疎い蔦重に、歌麿の思いはまったく伝わりません。
想いを込めたスケッチを蔦重に差し出して、「俺が恋をしていたから、恋心を描いたのさ」と話す歌麿。これはもう、蔦重への告白も同然。にもかかわらず、蔦重は亡くなったおきよさん(藤間爽子さん)の名前までもち出して、歌にもやっと好きな女性ができたのかと無邪気に喜んでしまいます。この無神経ぶりに、思わずテレビの前で「蔦重、そういうところだよ!」と叫んでしまったのは、筆者ばかりではないはずです。
しかもですよ、改めて振り返ってみると、歌麿にはおきよさんの梅毒はうつらなかったのですよね…。ということは、ふたりには男女の関係はなかったのかもしれず…絶望的な瞳で蔦重を見つめる歌麿が…つらい。
とはいえ、ドラマの初回、私たちも目撃したはずです。江戸を焼き尽くさんばかりに燃え広がる火事のさなか、炎にふらふらと近づいていく少年(歌麿)を「べらぼうめ!」と叱り飛ばし、腕をつかんで一緒に走って逃げた蔦重を。蔦重からしてみれば、歌麿は可愛くて大切な弟分。歌麿が男だからという以前に、弟同然の歌麿が恋愛対象にならないのは、むしろ当然のことなんですよね。さらに、「女郎との色恋沙汰は死罪」という吉原で育った蔦重が「色恋に滅法疎い」のも仕方ないこと。だから蔦重に、本来落ち度はないのです。
それにしても、常に「吉原のため」「世のため」を思って行動している蔦重なのに、自分の近くにいる人の気持ちに限っては、果てしなく鈍感なのはどうしたことでしょう。この矛盾にどうにも納得がいかず、気か付けばすっかり歌麿に感情移入して、蔦重がどんなに無神経で残酷か、腹を立ててしまう…ゴメンよ、蔦重。ドラマの主役はあなたなのにねぇ。
「もう一緒に仕事をしない」と一方的に宣言されてしまった蔦重は、歌麿への文を残します。
「悪かった。あの日から20年。俺についてきてくれてありがとな。とびきりの夢を見させてもらった。ありがと。体を大事にしろよ。お前は江戸っ子の自慢。当代一の絵師なんだから」
蔦重からの手紙を読む歌麿に、かすかに落胆の色を感じたのは、筆者だけでしょうか? 「今は顔を見るのもつらい。この状況から逃げ出したい…」と自ら別れを告げたものの、そこには蔦重に対する甘えもあって。「逃げ出したい。でも引き留めてほしい」という未練が感じられはしませんでしたか?
蔦重の手元に残ったのは、歌麿が自分の恋心を描いたスケッチの数々。これらはいずれ、『歌撰恋之部(かせんこいのぶ)』として世に出て、「喜多川歌麿の最高傑作」と謳われることとなる傑作です。
蔦重と歌麿。果たしてふたりが歩む道は、このまま離れていってしまうのでしょうか。
【江戸の出産は命懸け】
歌麿が、蔦重への恋心に終止符を打った一方で、てい(橋本愛さん)は蔦重に献身的な愛を捧げます。
「生まれてくる子どもの名前は“つよ吉”ではいかがでしょう?」。今は亡き蔦重の母・つよ(高岡早紀さん)の名前を子どもに付けようとするなんて、つよさん、愛されていましたね。おなかの子へ本を読み聞かせる蔦重も、幸せそう! でも、その幸せも長くは続きませんでした。
ある日突然、ていを襲ったおなかの痛みに、駆けつけた産婆(榊原郁恵さん)は母体優先の対応を即決します。「今生まれたら、この子は生きてはいけませんよね」「この子を旦那さまに差し上げたいのです。子を育てるよろこびを旦那さまに…!」と懇願するていの涙が、胸を打ちます。誰よりも賢いていには、今の「蔦重に欠けているもの」が何なのか、きっとわかっていたのでしょう。
歌麿の、蔦重に対する想いを知っているのは、現状おそらく、ていひとり。同じ人を愛する者として、ていは歌麿を深く思いやっていますが、現実として、蔦重とていにとってかけがえのない新しい命は、歌麿にとっては「招かざる客」でもありました。そして今回、その「招かれざる客」が、ていを苦しめているのです…あな恐ろしや、森下脚本…!
■現代から見れば、江戸は短命・早婚・子だくさん
『べらぼう』で描かれている11代将軍・徳川家斉(城桧吏さん)は、徳川将軍歴代最長の、実に50年という在位期間を誇る将軍です。ちなみに、今回、家斉が『べらぼう』に登場したことにより、大河ドラマの歴史に15代の徳川将軍がすべて出揃ったそうです。
さて、将軍退位後も「大御所」と呼ばれ、長きにわたり君臨した家斉ですが、彼は少なくとも16人の妻妾(さいしょう)をもち、歴代徳川将軍の中で最多となる53人の子女(息子26人・娘27人。諸説あり)をもうけたことでも知られています。
とはいえ、成人できたのは、約半数の28人。もっとも注意深く、多くの目配りがかけられ、何かあれば万全を尽くされていたに違いない「徳川将軍の子」であっても、生存率はわずかに50%程度なのです。そう、当時の日本は「7歳になる前の子は神の子」と言われるほど、乳幼児の死亡率が高かったのです。
女性にとっても、出産は想像を絶するほどに過酷なものでした。妊娠期間中にも体調を崩して亡くなってしまうことも多く、それが当時の女性の死亡率を引き上げる要因にもなっていました。
しかも、「ひとりの女性が生涯に生むであろう子どもの数」を意味する合計特殊出生率は、17世紀末期(徳川綱吉の時代)で6または7人。18世紀中ごろ(徳川吉宗・家重の時代)までには低下したとはいえ、「5人生む」という慣行はその後も長く続きます。減少し始めるのは大正生まれの女性からだったそうです。
当然、長子出生から、末子が成人するまでの養育扶養期間も非常に長いものでした。現代では、子どもが成人し巣立ったのち、夫婦だけになる期間が30年以上あるといわれていますが、江戸時代にはほとんど存在しなかったとか。当時、女性の結婚適齢期は町人で16歳から18歳くらい。寿命は、男性52歳、女性50歳くらいですから、5人も子育てしていたら、確かに「老後ゆっくり」過ごす時間なんて、ほとんどないに等しいですね。
■再び、あの手袋が表舞台に…!
さて、江戸城では、将軍補佐で老中の松平定信(井上祐貴さん)が定信を疎ましく思う将軍・家斉や徳川治済(生田斗真さん)の罠にかかり、失脚します。
「これで倹約の世は終わり」と狂喜乱舞する江戸の人々。そんななか、元大奥総取締の高岳(冨永愛さん)が、徳川家基が鷹狩りの際に身につけていた手袋を携え、定信を訪ねてきます。そうです! その親指に、家基を毒殺するための毒が仕込まれ、平賀源内を死に追いやる一因ともなった、あの手袋です! こちらも新たな展開がありそうですね。見逃せません!
【次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』 第44回「空飛ぶ源内」のあらすじ】
蔦重(横浜流星さん)の前に、耕書堂で本を書かせて欲しいと、駿府生まれの貞一(井上芳雄さん)と名乗る男が現れる。貞一は源内(安田顕さん)がつくったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白(山中聡さん)や南畝(桐谷健太さん)、重政(橋本淳さん)らと会い、源内の謎を追い続ける。
一方、歌麿(染谷将太さん)は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第43回「裏切りの恋歌」のNHK ONE配信期間は2025年11日16日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- WRITING :
- 河西真紀
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 完結編』(NHK出版)/人生40 年の世界:江戸時代の出生と死亡(https://minato.sip21c.org/humeco/anthro2000/kito.pdf) /『お江戸の結婚』(三省堂) :