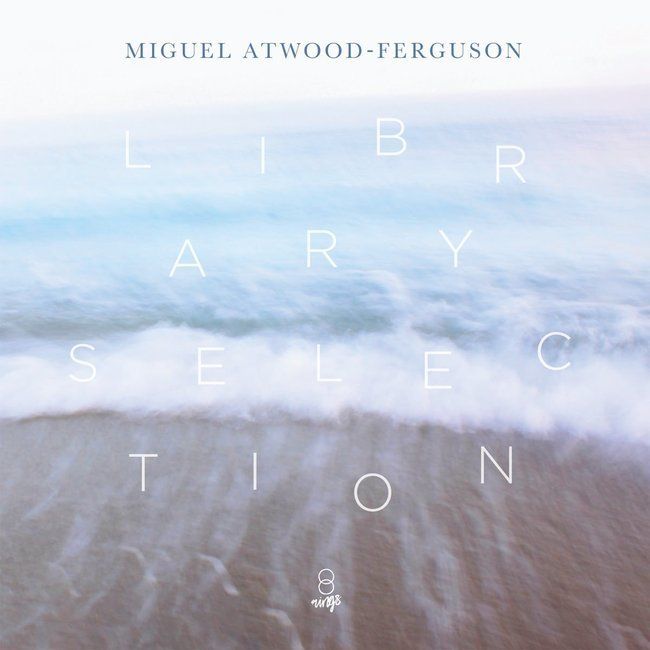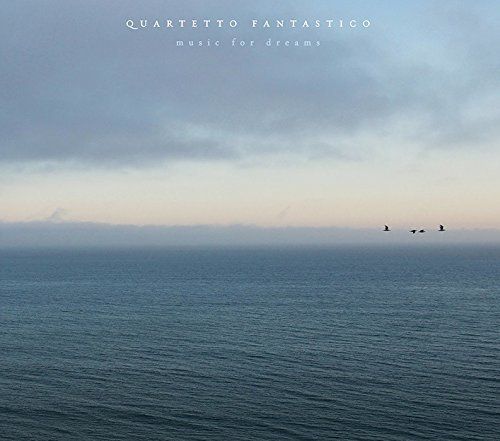意外な場所で出合った、現代的な弦楽の妙味。
夜10時を過ぎて、遅い夕食を摂ろうとすると、選択肢はぐっと少なくなる。食事の後でもう少し仕事をしたいと思うから、居酒屋やワインバルに行くのはちょっと躊躇ってしまう。結局、深夜まで開いている(店によっては24時間だ)スーパー「成城石井」に立ち寄って、ちょっとした惣菜を買いつつ、家路につくことになる。
ミゲル・アトウッド・ファーガソンは、以前この連載でも取り上げたMockyのアルバムにも参加している、マルチ器楽奏者だ。彼のホームページを見ると関わったアルバムのジャケットがずらりと並んでいるが、その幅広さにまず驚かされる。バリー・マニロウからレイ・チャールズ、さらにはコモンやフライング・ロータスのようなヒップホップマナーのアーティスト、そして数々の映画音楽。彼は作曲やストリングスアレンジ、ヴィオラやヴァイオリン等の演奏で、クラシック畑ではなくポップスフィールドで長らく活動してきた。
ピアニストの父を持ち、幼い頃からヴァイオリンを演奏していたミゲルは、南カリフォルニア大学のクラシック学科に進む。CDに付属している原雅明氏のライナーノーツによれば、大学進学時に既にプロの演奏家だった彼は、大学を卒業する際にはクラシック音楽の世界で活動するつもりがなかったという。
「僕は当時オーケストラのスタジオ・ミュージシャンの世界ではAリストのヴィオラ奏者だった。でも、そういう仕事の世界が嫌になって、辞めたんだ。多くのストリングス奏者のスタジオ・ミュージシャンは、僕のようにクリエイティブなプロジェクトに関わっていない。彼らの多くは天才なのに、その才能を活かしきれていない。いいギャラはもらっているけど、オーケストラの中で好きでもない音楽を演奏しないといけないから、いつも機嫌が悪いんだ」(『ミュージック・フォー・ドリームス』カルテット・ファンタスティコのライナーノーツより引用)
クラシック音楽を演奏すること自体は十分クリエイティブな行為だと思うが、クラシック音楽をめぐる環境は、決してそうとはいえない側面もあるのかもしれない。さらに、オリジナルの音楽を生み出すことは、クラシック音楽の演奏とは創造性の質が異なるともいえる。ミゲルの感性は、自身の音楽を生み出すことに向いていたということなのだろう。
ミゲル・アトウッド・ファーガソンの名を知らしめたのは、カルロス・ニーニョと協同で行った、ヒップホップのトラックメーカー&MCとして活躍した故J・ディラへオマージュを捧げた、オーケストラのプロジェクト「スイート・フォー・マ・デュークス(マ・デュークスはJ・ディラの母親のこと)」だった。ヒップホップチューンとオーケストレーション、その意外な取り合わせは、LA音楽シーンの重要人物であるカルロスの貢献も大きいが、ミゲルの音楽的感性と素養なくしては実現しなかっただろう。
さて、成城石井で私の耳が捉えたのは、ミゲルの2015年リリースのアルバム『ライブラリー・セレクション』に収められている「Do The Astral Plane」だった。ストリングスの旋律が印象的なこの曲は、フライング・ロータスのアルバムに収録された同名曲のストリングスバージョンという。太いビートに乗ったフライング・ロータス版も佳曲として印象的だったが、ミゲル版はよりアンサンブルの妙と構成の美しさが際立っている。この『ライブラリー・セレクション』は、ミゲルの幅広い音楽性を端的に表した作品といえるだろう。カルロス・ニーニョによる、フィールドレコーディング音源のエフェクトがブレンドしたそのサウンドは、一聴ニューエイジ的なフィーリングがありながらも、聴き進めるほどに音楽的なストラクチャーがしっかりと耳を捉え、決して「流れて」しまうことはない。エレクトロニックなビートがリードする曲、ストリングスを中心に構成される曲、ピアノ曲、内容はバラエティに富むが、いずれにおいても、美しい旋律が印象に残る。それはヒップホップ的ループに慣れた時代の耳にこそ、フレッシュに響く生音ともいえるかもしれない。
さらに、ミゲルが2007年より取り組んでいる弦楽四重奏楽団「カルテット・ファンタスティコ」は、現代におけるフレッシュなアコースティックアンサンブルのありようを、よりにシンプルに追求した形といえるかもしれない。全編即興演奏という彼らのアルバム『ミュージック・フォー・ドリームス』は、古典的なフーガ調あり、アブストラクトな弦の響きの連なりありとこれまた多彩な内容で、そこには即興演奏が陥りがちな単調さはなく、むしろナラティブな展開の妙が感じられる。その様子から感じられるのは、演奏し表現することへのポジティブな姿勢だ。クラシック音楽から発展した、ロジカルな、いわば因数分解的な現代音楽のテンション(それはそれで魅力的ではあるが)とは一線を画す、楽器同士の有機的な相関から立ち上る音楽。それは例えばアートにおける、抽象の後に訪れた具象の価値の再発見のような、新鮮な存在感ともいえる。ぜひライブで体験してみたいサウンドだ。もちろん、深夜のスーパーで流れていても十分素敵なのだが。
- TEXT :
- 菅原幸裕 編集者