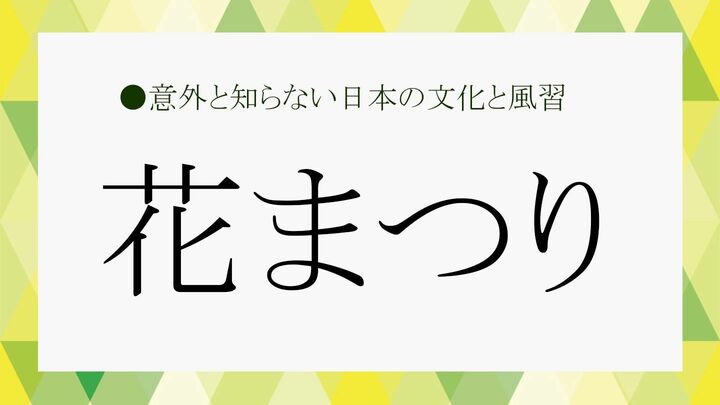【目次】
【「花まつり」とは?知っておきたい「基礎知識」】
■「花まつり」とは?
「花まつり」は仏教の創始者、ゴータマ・シッダールダ(お釈迦さま)の誕生を祝う行事のこと。正式な名称は「灌仏会(かんぶつえ)」で、「仏生会(ぶっしょうえ)」「降誕会(ごうたんえ)」「浴仏会(よくぶつえ)」「龍華会(りゅうげえ)」「花会式(はなえしき)」といった別名もあります。「花まつり」もそのひとつ。この言い方が一般に知られるようになったのは、明治時代末ごろからとされています。「花まつり」と呼ばれるようになった理由としては、お釈迦さまの誕生日である4月8日が桜をはじめ、春の花が咲き誇る季節と重なるから、という説や、お釈迦さまの生まれたインドのルンビニーの花園では美しい花々が咲いていたからという説など、諸説あります。
■由来・歴史
「花まつり」の由来は、お釈迦さまの誕生秘話にあります。
お釈迦さまは、生まれてすぐに立ち上がって7歩歩き、一方の手で天を指し「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と言ったという伝説が伝えられています。「天上天下唯我独尊」は、人気漫画『呪術廻戦』で子どもたちにも知られるようになりましたが、「個の世界に自分よりも尊いものはない」、つまり「人間は生きているだけで価値がある、ということに気付き、自分を慈しみましょう」「同じように他人を尊重しましょう」という意味で、広く人間の尊厳を言い表しています。「花まつり」は、そんなすばらしい言葉が生まれたお釈迦さまの誕生日を祝い、これからもお釈迦さまに守っていただけるように願うおまつりです。
「花まつり」では、たくさんの花で華やかにお飾りした花御堂をつくり、その中心にお釈迦さまの誕生時の姿を表す小さなお像、「誕生仏」を安置します。「誕生仏」は右手で天を、左手で地を指しています。
【「花まつり」には「どこ」で「何が」行われる?】
仏教にはさまざまな宗派があります。お釈迦さまの誕生を祝う「花まつり」は、宗派を問わず全国各地の寺院行われますが、日蓮正宗など、「花まつり」を行わない宗派もあります。では「花まつり」では、どんな行事が行われているのでしょうか。
■誕生仏に甘茶を注ぐ
「花まつり」では、参拝者は用意された甘茶をひしゃくですくい、花御堂の誕生仏に優しくかけて拝みます。これは、かつてお釈迦さまが誕生したときの、「9匹の龍が天から現れ、甘露(かんろ)の雨を降らせた」という伝説にちなみます。
「甘露」とは、不老不死になるとされた神の飲み物。「花まつり」では甘露を甘茶にたとえ、お像にかけることでお釈迦さまの霊力を保ち、この先も長く守り助けていただけるよう願うのです。実は「花まつり」本来の名称である「灌仏会」の「灌」には、「そそぐ」という意味があるんですよ。
■稚児行列(ちごぎょうれつ)
「花まつり」は、お釈迦さまの誕生を祝いつつ、子どもたちの健康を祈る行事でもあります。そのため、寺院のほか、仏教系の保育園や幼稚園では、「稚児行列」を行うことも。「稚児行列」では、子どもたちはお釈迦さままに仕える身として、平安装束を模した伝統衣装をまとい化粧を施され、列になって街を行進し、無病息災と成長を願います。
■白象の模型を引いての巡行
お釈迦さまの生母である摩耶王妃は、お釈迦さまを身ごもった際に、体の中に6本の牙をもつ白い象が入ってくる夢を見た、という逸話があります。この言い伝えにより「花まつり」では白い象は神聖な動物として親しまれています。
【どうして「甘茶」が用いられるの?】
■小さな子どもや妊婦の方でも安心
甘茶とは、ユキノシタ科の「アマチャ」という木の葉を蒸して揉み、乾燥させてから煎じてつくったお茶のことです。黄褐色の色合いで、名前のとおり強い甘味があるのが特徴。ほんのり甘く、カロリーはゼロで、漢方薬としても使用されています。アンチエイジング作用や鎮静作用のほか、花粉症やアレルギーなどの軽減も期待できる抗アレルギー作用など、さまざまな効能があるとされています。さらにカフェインやタンニンを含まないため、小さな子どもや妊婦の方でも飲むことができます。
■甘茶を飲むと無病息災が叶うという言い伝えから
「花まつり」には、子どもたちの健康を願う行事としての一面もあります。古くから、「甘茶をすくった手で赤ちゃんの頭をなでると、元気で丈夫な子どもに育つ」「甘茶を飲むと無病息災に過ごせる」という言い伝えがあることから、人々にふるまわれるようになったといわれています。
【有名な「花まつり」のイベントは?】
「花まつり」のイベントをいくつかご紹介します。詳細はHPにてご確認ください。
■築地本願寺(東京)
日時・場所/2025年4月5日(土)10:00~16:00、築地本願寺本堂・境内
やきそば、わたあめ、カレーなどの飲食、わなげやスーパーボールすくいといった縁日的なコンテンツのほか、ステージではインド大使館・スリランカ大使館による古典舞踏、大道芸や太鼓演奏などのショーも。
■真言宗智山派総本山 智積院(京都)
日時・場所/毎年4月8日 10:00~、智積院金堂にて
上述の日時の法要は一般の人も参加可能。毎年4月8日前後の日曜日には、午前11時から智積院金堂にて子どもたちの健やかな成長を祈り、「子ども花まつり」が開催されます。スクリーン紙芝居を楽しんだのち、子どもたち、ひとりひとりにお加持をし、額にお釈迦さまの梵字の判子を押していただけます。誕生仏に甘茶をそそいだあとは、お加持された「うでわ念珠」と「こどもお守り」を授けてもらえます。くじ引きやお土産などもありますよ。
***
「花まつり」は4月8日前後に全国で行われ、甘茶をふるまってくださる寺院もあります。感謝と共にいただきたいですね。宗派には関係なく開催されますが、すべてのお寺で行わるわけではありません。ご縁のあるお寺、行ってみたいお寺などのホームページを事前にチェックしてからお出掛けくださいね。ほっこりと心温まる1日になりそうです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /築地本願寺HP「花まつり開催のお知らせ」(https://tsukijihongwanji.jp/news/8599/) /法眞山 妙昌寺HP(https://www.myoushoujitemple.website/花まつり/) /総本山 智積院HP(https://chisan.or.jp/chishakuin/event/schedule/子ども花まつり#:~:text=花まつりとは、お釈迦様,によるスクリーン紙芝居があります%E3%80%82) :