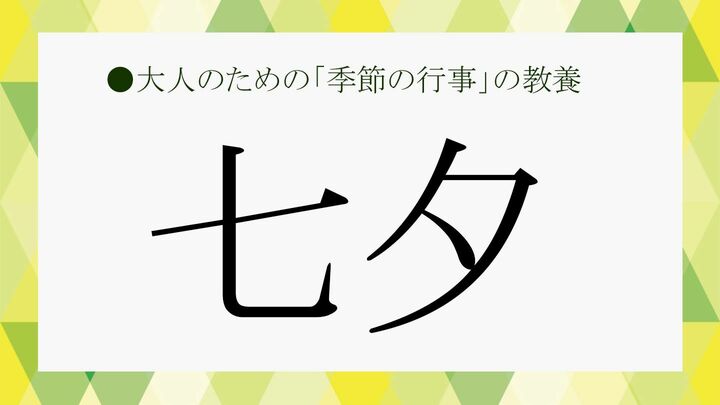【目次】
【「七夕」とは?「読み方」「漢字のなりたち」など「基礎知識」】
■「七夕」とはいつ?何の日?
「七夕」は一般に「たなばた」と読み、五節供(五節句とも。桃の節句、端午の節句など、1年にある5つの節句のこと)のひとつです。「しちせき」「しっせき」とも読み、陰暦7月7日の夜を意味します。
■どうして「七夕」を「たなばた」と読む?
「たなばた」という読み方は、日本に古くから伝わる伝承に由来します。その伝承では、乙女は神を迎え祀るために、水辺の棚に設けた機屋 (はたや) にこもり、神の降臨を待って一夜を過ごしたとされています。ここから棚機つ女 (たなばたつめ) 、乙棚機 (おとたなばた) 、さらに「たなばた」と呼ぶようになったといわれています、また、「たなばた」はもともとお盆行事の一環でもあり、お盆の一週間前にあたる旧暦7月7日の夜、巫女(棚機つ女)が神聖な機織り小屋の中で、農作をもたらす神の衣を織りながら待つ、という風習があったそうです。ここから、「7日の夕」で「七夕」と書くようになったともいわれています。ちなみに「棚機月 (たなばたづき)」は、旧暦7月の異称のひとつです。
【「七夕」の物語とは?】
■「物語概要」
「七夕」にまつわる伝説といえば、織姫と彦星が登場する物語が有名ですね! このストーリーは、奈良時代に中国から伝わりました。
天の神さまには、美しいを織物を織る「織姫」という娘がいました。天の神さまは、化粧もせず仕事に精を出す娘を不憫に思い、牛の世話を行う「彦星」を引き合わせました。ふたりはすぐに恋に落ち、結婚することになりましたが、ふたり共、結婚すると仕事をせず、遊んでばかりの生活を送るようになったのです。織姫が機織りをしなくなったために天の衣類は廃れ、彦星が放っておいた牛もやせ細るばかりです。
それに怒った天の神さまは、ふたりを天の川の、東と西に引き離してしまいました。すると、ふたりは悲しみに暮れ、ますます働こうとしなかったため、天の神さまは真面目に働くことを条件に、年に1度だけふたりが会うことを許したのです。それ以来、毎年7月7日の夜は、織姫と彦星は天の川を渡り、会いに行くようになりました。
■「織姫」「彦星」の正式な名前と星は?
中国で「彦星」と「織姫」に相当する星は、「牽牛(けんぎゅう)星(わし座のα 星アルタイル)」と「織女星(こと座のα星ベガ)」の二星です。「牽牛星」は農時を知る基準となり、「織女星」はその名が示すように養蚕や裁縫を司る星とされていました。陰暦7月の初めごろは、この二星が北東から南西に横たわる天の川を挟んで、人々の頭上に明るく見えることから、擬人化されて、二星の相会う伝説が生まれたものと考えられています。
【「七夕」の「由来」と「歴史」】
現在の「七夕」は、中国伝来の行事と日本古来の伝承、さらに盆行事の一環としての行事など、さまざまな要素が入り混じり、伝承されたものだといわれています。「由来」とされる、ふたつの行事をご紹介しましょう。
■中国の「乞巧奠(きっこうでん)」
「七夕」の由来のひとつは、中国で7月7日の夜に行われる行事「乞巧奠(きっこうでん)」です。もともと「乞巧奠」は、手芸などに携わる仕事に就く女性が、より優れた技術を授かることができるよう、あるいは針仕事がもっと上達するよう、星空に祈りを捧げる日でした。奈良時代に、この「乞巧奠」が日本に伝わると、機織りなどの仕事に限らず、書道や芸事などの上達も祈願するようになったといわれています。
■日本に伝わる「棚機女(棚機津女:たなばたつめ)」
日本に古くからある「棚機(たなばた)」という行事も、七夕の由来のひとつです。「棚機」とは、秋の豊作を願い着物を織って棚に供える行事のこと。このとき、機屋(はたや)にこもり神さまへ供える着物を織るのが、「棚機つ女」と呼ばれる選ばれた女性です。この行事は、お盆を迎える準備としても行われ、旧暦の7月6~7日に実施されていました。そこから、現代の七夕につながっていったと考えられています。
日本の「七夕」は、これらの伝説や行事が長い歴史のなかで入り交じり、現在に伝えられた行事です。本来は陰暦(現歴の8月)で行っていましたが、現在では陽暦(現在の暦)の7月7日に行うところが多いですね。東北地方や北海道などでは今も月遅れの8月7日に行っており、有名な「仙台七夕まつり」も8月の開催です。「織女祭 (しょくじょさい)」 、「星祭 (ほしまつり)」 などとも呼ばれます。
■「七夕」の「歴史」
日本における「七夕」の歴史は奈良時代に遡ります。陰暦7月7日に上でも紹介した中国伝来の「乞巧奠(きっこうでん)」 が、宮中の行事として行われていました。桃や梨 、茄子 、瓜 、大豆 、干鯛 (ひだい) 、薄鮑 (うすあわび) などを清涼殿の東庭に供え、牽牛と織女の二星を祀 (まつ) ったそうです。一方で、錦(にしき)や綾などを織り、染め物を司った織部司 (おりべのつかさ) の行事として、7月7日に織女祭が行われたとも伝えられています。いずれも宮廷や貴族の習俗でした。
室町時代になると、「七夕」に歌を供える風習が伝わり、7という数にあやかって、7種の遊びを行ったとされています。さらに江戸時代には、武家の年中行事としても定着し、五節供のひとつに定められました。笹竹に五色の紙や糸を吊るして軒端に立てる風習も、江戸市中に見られるようになり、今日に近い七夕風景となっていきます。実はこれには寺子屋の普及が関係しているといわれています。寺子屋が広く定着し、庶民が読み書きや書道、そろばんなどの「手習い」ができるようになったことで、願いごとを書いた短冊を竹や笹に飾る習慣が、一斉に庶民の間で広がったのです。ちなみに、当時の願いごとは、手習いに関するものが多かったようです。
一方で、長野県松本地方では、同じく江戸時代より、各家々の軒端に「七夕人形」といって、板の人形 (ひとがた) に子どもの着物を着せて吊るし、その年に生まれた子どもの無病息災を祈願する風習が伝えられています。また、小さな紙の人形を紐に連ねて吊るしているところもあり、現在でも行われています。同じ七夕行事とはいっても、農民層には貴族・武家階級とは異なった習俗が伝承されているのが「七夕」の特徴でもあります。
【「七夕」の「食べ物」素麺を食べるのはなぜ?】
■そうめん(素麺)を「天の川」に見立てていました!
七夕にいただく食事としては、そうめんが有名ですね。そうめんは天の川に見立てて食べられることから、広く人々の間に浸透しました。また、7月7日は機織り技術の向上を願う日であったことから、そうめんが白い糸と似ていることも関連しているといわれています。実は全国乾麺協同組合連合会は、7月7日を「そうめんの日」と制定していますよ。
■中国のお菓子「索餅(さくべい)」がルーツ?
「七夕」にそうめんを食べるようになったのは、中国がルーツだともいわれています。中国では、7月7日に「索餅(さくべい)」と呼ばれるお菓子が食べられていました。「索餅」は小麦粉を練り、縄のようにねじってつくったお菓子で、この日に索餅を食べると無病息災で過ごせると考えられていたのです。これが日本に伝わったときに、素麺に変化していったとも言われています。
【「七夕」を「英語」で言うと?】
日本では広く行われている「七夕」ですが、欧米などでは知られていないため、ぴたりと当てはまる英語表現はありません。[the Tanabata Festival]、あるいは[the Star Festival]と称して、その後に「七夕」についての説明が必要です。例えば…
Tanabata is an annual event held on the evening of July 7th, commemorating the story of Hikoboshi and Orihime, who are separated on opposite sides of the Milky Way and reunite only once a year. On this day, it is customary to plant bamboo and decorate them with tanzaku (small pieces of paper on which wishes are written).
七夕は、天の川の反対で引き離され、年に一度だけ再会する彦星と織姫の物語にちなんだ7月7日の夜に行われる年中行事です。この日には、竹を立て、短冊(願い事を書いた小さな紙)を飾る風習があります。
***
現在では新暦7月7日に行われることが多い「七夕」ですが、この頃はちょうど梅雨の時季にあたります。そのため、織姫と彦星の再会は叶わないことも多いのですが、国立天文台では旧暦の7月7日を「伝統的七夕」と呼び、その日付を広く公開しています。
2025年の「伝統的七夕」は、8月29日。年によって日付がかなり前後しますが、日本の梅雨明けは平年7月19日ごろですから、「伝統的七夕」の晴天率は高く、月は夜半前には沈み、その後は天の川がくっきりと見える観察条件となります。20時ごろには織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)が空高く輝いているのが見られますよ。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /『プログレッシブ和英中辞典』(小学館) //国立天文台「伝統的七夕について教えて」(https://www.nao.ac.jp/faq/a0310.html) :