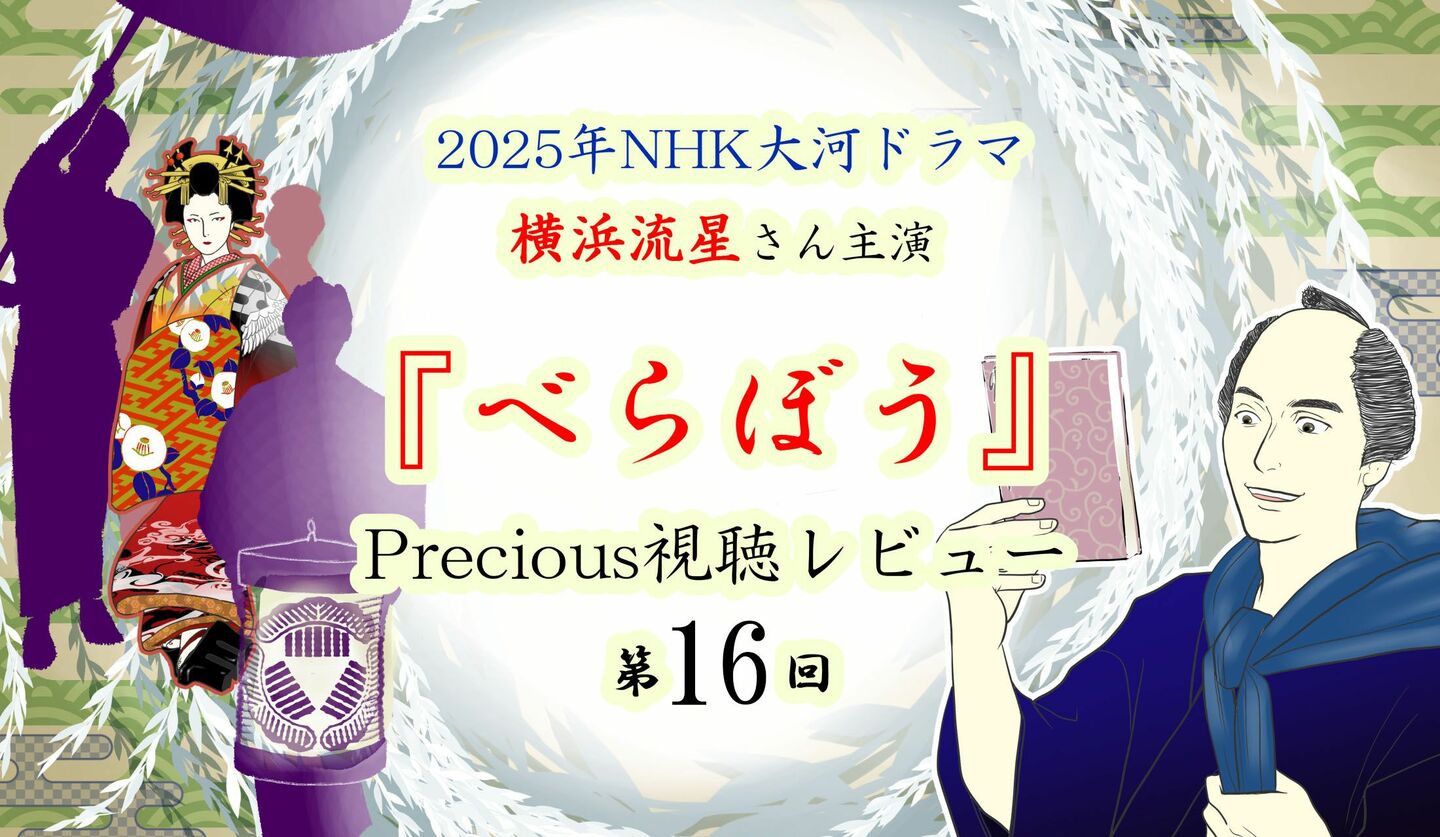【目次】
【前回のあらすじ】
第15回「死を呼ぶ手袋」、そして第16回「さらば源内、見立ては蓬莱(ほうらい)」と2週続けてきな臭さが漂った『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』。大河ドラマファンなら「これよこれ、大河はこうでなくっちゃ」と膝を打ったかもしれませんね。
第15回の終盤で殺された老中首座の「白眉毛」こと松平武元(石坂浩二さん)の死と、将軍徳川家治の嫡男・家基(奥智哉さん)の暗殺を企てたと噂される田沼意次(渡辺謙さん)。意次は、身に覚えのないこととはいえ、これ以上の深入りは危険が及ぶやもと、平賀源内(安田顕さん)に「この件は終わったのだ、忘れろ。それがお前のためでもある。ご苦労であった」と金を渡しますが源内は拒否。薬草、鉱山、エレキテル…意次の金と源内の知恵で持ちつ持たれつの関係だったふたりでしたが、ついに決裂!?
そして、発明したエレキテルはインチキ、平賀源内はいかさま師だと言われ、信用も金もなく、源内は自暴自棄になります。そんな源内に再起の道を与えた(に見えた)のは、果たして意次か蔦重(横浜流星さん)か、それとも…。
第15回での石坂浩二さんと渡辺謙さん、そして第16回での安田顕さんと渡辺謙さんの怪演。大物俳優を惜しみなく登用するNHKの大河ドラマらしい2話でした。
【東京国立博物館「蔦屋重三郎」展もいよいよ開催!】
さて、今回の連載は、少々趣を変えてお届けします。2025年4月22日(金)から上野の東京国立博物館 平成館で始まったのが、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」。2025年は浮世絵の展覧会や蔦重関連のイベントが目白押しですが、その大本命ともいえるのが本展です。
大河ドラマ『べらぼう』の数々のシーンでわかる通り、蔦重が商売したのは木版画による摺りもの、市中の人々の楽しみとなる本や一枚ものの浮世絵です。これらは、作家や戯作者が物語をつくり、絵師が絵を描き、それを彫師が板木に彫り、摺師(すりし)が奉書(和紙)に摺るという共同作業によって完成する商品です。絵だけのものもありますね。それらは蔦重のような版元が企画し、絵師は誰、彫師は、摺師は…とキャスティングして制作されます。
今までの大河ドラマ『べらぼう』の放送のなかでも、すでに『吉原細見』や『一目千本』、『雛形若菜の初模様』『青楼美人合姿鏡』、そして大人向けの絵本(青本)など、数々の版本や一枚ものの浮世絵を企画制作、販売してきた蔦重。ドラマの中で蔦重や花魁たちが手にするそれらは小道具として再現製作されたものですが、江戸時代につくられた実物を鑑賞できるのが本展なのです。

※取材許可のもと撮影しています。展示室は一部を除いて撮影禁止です。

【ドラマで見たあの浮世絵も!実物のクオリティにびっくり!】
■サイズ感にびっくり、その細かさにもびっくり
大河ドラマ『べらぼう』で蔦重がプロデュースして出版した最初の版本は『一目千本』でしたね。「ツーンとしている女郎は、わさびの花」「夜冴えないのは昼顔」というように蔦重が知恵を絞り、入銀(お客にスポンサーになってもらってお金を集めること)した女郎を花に見立てて描くよう絵師の北尾重政(橋本淳さん)に依頼。120人の女郎が生け花として描かれた、花図鑑のような美しい一冊ができ上がりました。
吉原で生まれ育ち、女郎の性格や好みも知り尽くした蔦重にしか企画できないこの版本、展示室で江戸時代につくられた実物を見ると…小さい! 吉原のガイドブック的な『吉原細見』はもっと小さく、見たら驚くかもしれませんが、これは着物の懐(たもと)や袂に入れて持ち歩くのによいサイズ、というわけなのです。
木版画の浮世絵は、現代のように縮小や拡大ができるわけではないので小さいものは小さく、原寸大の板木をつくります。絵師はまだしも彫師は大変です。絵師が描いた下絵を木の板に反転させて貼り、その上から小刀や鑿(のみ)などさまざまな道具を使って板木を彫るのですが、例えば文字が途切れず続く蓮面体(れんめんたい)で、しかも反転している仮名や漢字を彫る…精一杯想像してみても、にわかには信じられません。
■浮世絵ってこういうもの!
この展覧会での鑑賞ポイントでもあるのが、この「江戸庶民が楽しんだ浮世絵は木版画である」ということ。浮世絵は字のごとく「浮世(当世・現代)を写す絵」、江戸時代初期に成立した絵画のいちジャンルです。それ以前の日本の絵画は、公家や大名が屋敷を飾るためや贈りものとして絵師に描かせたり、仏画のように礼拝の対象としてのものだったりと、いわゆる特権階級のものでした。
彼らの庇護にあった伝統的な絵を描く絵師集団ではなく、庶民階級の絵師による風俗画が源流となって生まれたのが浮世絵です。初めは版画ではなく肉筆画、いわゆる一点ものでした。ちなみに…通常の絵画は「肉筆」とは言いません。浮世絵だけが版画ものと区別するため肉筆という呼び方をします。版画でも実際に描いたものでも、浮世を描いたものが浮世絵。本展覧会では肉筆の浮世絵も展示されています。
肉筆ではなく木版画がつくられるようになったのは、大量につくって安く庶民に届けるため。一枚ものの浮世絵はアートピースではありません。人気役者や力士、評判の遊女や町娘などのブロマイドであったり、芝居や相撲の取組といった興行、花魁の襲名、役者の訃報を知らせる瓦版的なものであったり。現代の感覚で一枚数百円から買えるものもあり、「襖の破れ隠しに浮世絵を貼った」なんて話もあるくらい、庶民の生活に溶け込んだものだったのです。
■浮世絵鑑賞は上質なものに限ります
人気作は重版を重ねるわけですが、木版画ですから摺れば摺るほど板木に表現された繊細な線などは曖昧になったり欠けてしまったりすることも。また、初版は色や摺り具合にも絵師の意向が反映されたはずですが、そのうちチェックがおろそかになったりすることもあったでしょう。そのため、同じ作品なのに色が違ったり、ぼかし具合がうまくなかったり、また摺師によって違いが出てくることも。
今回の展覧会は、多くは東京国立博物館の所蔵品で構成されていますが、太田記念美術館や公益財団法人平木浮世絵財団、千葉市美術館(ラヴィッツ・コレクション)、江戸東京博物館などの所蔵品から選りすぐられた浮世絵も展示されています。同じ作品でも、摺りや保存状態によって美術的価値が異なるのが浮世絵版画の宿命。大河ドラマ『べらぼう』で浮世絵や江戸時代の風俗に興味をもったなら、ぜひこの東京国立博物館の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」で、上質な浮世絵を鑑賞することをおすすめします!
【大門が!桜が!耕書堂が! 『べらぼう』の世界が出現する展覧会】
■ドラマのあのシーンに入り込んだよう…展示室は吉原だった!

東京国立博物館でのこの蔦重展、浮世絵を見る前にまず圧倒されるのは、展示室の入口に設えられた大門(おおもん)です。大河ドラマ『べらぼう』では、市中と吉原の人々の往来を象徴する場所であり、鳥山検校(市原隼人さん)に身請けされた瀬川(小芝風花さん)が花嫁道中の末に出て行くのも大門、うつせみ(小野花梨さん)と小田新之助(井之脇海さん)が手に手を取って消えていくのも大門でしたね。その板葺き屋根の冠木門(かぶきもん)という造りの大きな門が、本展覧会でお出迎えしてくれるのです! これ、なんと大河ドラマ『べらぼう』のセットをそのまま持ってきたのだとか!
さらにその門をくぐると…そこには桜の季節の吉原のメインストリート、仲之町が!

吉原は桜の名所といわれますが、満開の桜を大門の中で楽しむという趣向として、期間限定で移植された桜なのです。

その期間は通常出入りが制限されていた女性や子どもも、花見がてら吉原散策することができた――を再現しているというわけ。大門といい桜といい、『べらぼう』ファンなら浮世絵鑑賞の直前にテンション爆上がり間違いなしです。
■最後の展示室では蔦重の「耕書堂」も営業!?
浮世絵自体の見方や見どころなどは後日の配信のレポート後編で解説しますが、今回お届けしたいのは展示室での楽しい仕掛け。最初の大門と桜にもびっくりしましたが、最後の展示室にはなんと蔦重の「耕書堂」が! 第16回の終盤シーン、新年に10冊の新刊青本を店頭に並べた蔦重でしたが、その店舗が再現されているのです。
しかもここには、瀬川や源内先生のあのシーンのパネル展示なども。また、夜が明けてから空に花火が上がるまでを映像で体験できるのですが、これはNHKの番組『歴史探偵』のチームが制作したVRコンテンツ。この「附章 天明寛政、江戸の街」と題して『べらぼう』の世界観を体験する空間は撮影OK! 多くの人とワクワクを共有することも可能です。


■ワクワクな蔦重展は6月15日まで開催!
上野公園の一角にある東京国立博物館の平成館で、4月22日(火)から6月15日(日)まで開催される特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」。月曜日は休館ですが、4月28日と5月5日は開館。通常9時30分から17時までの開館ですが、毎週金曜日と土曜日、5月4日(日・祝)と5月5日(月・祝)は午後8時まで開館(全日入場は開館の30分前まで)。観覧料2,100円で、表慶館で同時期開催の展覧会「浮世絵現代」も見応えがあってとてもおもしろい! 平成館と表慶館あわせての新旧浮世絵鑑賞、ぜひお楽しみあれ!
※詳細は東京国立博物館の公式サイトをご確認ください。
【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第17回 「乱れ咲き往来の桜」のあらすじ】
蔦重(横浜流星さん)は青本など10冊もの新作を一挙に刊行し、耕書堂の認知度は急上昇する。そんななか、うつせみ(小野花梨さん)と足抜けした新之助(井之脇海さん)と再会し、話の中で、子どもが読み書きを覚えるための往来物と呼ばれる手習い本に目を付ける。
一方、意次(渡辺謙さん)は、相良城が落成し、視察のため三浦(原田泰造さん)と共にお国入りする。そして、繁栄する城下町を見て、ある考えを思いつく。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回「さらば源内、見立ては蓬莱(ほうらい)」のNHKプラス配信期間は2025年4月27日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書) :