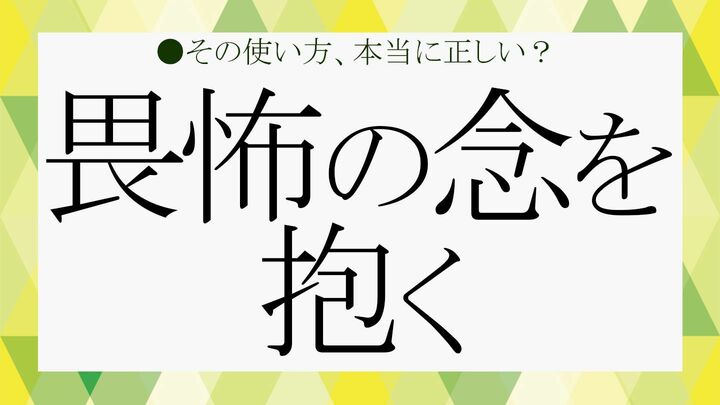【目次】
【「畏怖の念を抱く」とは?】
■読み方
「畏怖の念を抱く」の「畏怖」は「いふ」、「念」は「ねん」。「抱く」の「抱」は「いだ」と読みます。
■意味
「畏怖」とは「畏(おそ)れ慄(おのの)く」こと。単に怖がるというだけでなく、自然や神仏など、人間の力が遠く及ばない存在から不気味な威圧感などを感じ取り、恐れおののく様子を指します。
熟語を紐解くと、「畏」には「怖がること、敬うこと」という意味があり、一説によると、幽鬼や虎に似た恐ろしいものを恐れ憎むことを表しているそうです。「怖」にも「恐れる、怖がる」という意味があり、恐れの感情が迫ってくるさまを表します。「畏怖」は似た意味をもつ語をふたつ重ねることで強い恐れを表し、さらにそこに尊敬や崇拝の念が加わった言葉と言えます。
「念」は「思いや気持ち」を表す言葉で、「尊敬の念を表す」のように使われますね。
「畏怖の念を抱く」は、「恐れや敬いの気持ちをもつ」という意味で使われる、改まった印象を与える書き言葉。「畏怖の念を抱いたのよ」などと、通常の会話で使われることはあまりありません。
「畏怖の念を抱く」は強調した言い方なので、多少の誇張も含みつつ「恐怖心を覚えるほど素晴らしい」というニュアンスでも使われます。
【ビジネスでそのまま使える「例文」】
「畏怖」は本来、自然や神仏など、人間の力が遠く及ばない存在に対する恐れや敬いの気持ちを表す言葉ですが、「畏怖の念を抱く」は、自分の心情を誇張する表現として、尊敬すべき人や物に対しても使用されます。例文を見てみましょう。
■1:「古代の人々は自然のなかに神を見い出し、畏怖の念を抱いていた」
■2:「あまりにも大きな、災害が残した爪痕に、畏怖の念を抱いた」
■3:「歴史上の偉大な人物に対し、畏怖の念を抱いた」
■4:「素晴らしい演奏に心打たれると同時に畏怖の念を抱いた」
■5:△「理路整然とした彼の素晴らしい答弁に畏怖の念を抱いた」
「畏怖の念を抱く」は、畏れ、敬う気持ちが込められた表現です。そのため、同僚や友だちなど対等な関係の相手に対して使うことはあまりありません。その場合には「理路整然とした彼の素晴らしい答弁に尊敬の念を抱いた」など、理由をもって語るのにふさわしい言葉です。
【「類語」「言い換え」表現】
■「畏怖」の類語
・恐怖(きょうふ):恐れること、怖いと思うこと。また、その気持ち。「恐怖にかられる」「恐怖心」
・崇敬(すうけい):神仏や立派な人などを崇(あが)め敬うこと。「生き仏として崇敬する」「崇敬の念」
・畏敬(いけい):崇高なものや偉大な人を、恐れ敬うこと。「畏敬の念を抱く」
「畏怖」と「畏敬」はとてもよく似た意味をもつ「類語」ですが、「畏怖」が自然や神仏など人間の力が遠く及ばない存在に対する恐れや敬いの気持ちを表す言葉であるのに対し、「畏敬」は神仏だけでなく「尊敬すべき目上の人や偉大な人物」など、人を対象としても使われます。「畏敬」のほうが一般的であり、日常的には使いやすい言葉だと言えるでしょう。
・怯む(ひる-む):怖気づいて尻込みすること、気後れすること。「相手の剣幕に怯む」
・怯える(おび-える):物事を怖がってびくびくする。恐れ驚く。恐れ縮む。「不安に怯える」
上記ふたつは動詞ですが、「畏怖」の感情に近い表現と言えます。
■「畏怖の念を抱く」の使いやすい言い換え
・畏敬の念を抱く
・尊敬の念を抱く
・敬意を表する
・崇敬の念を抱く
・神聖な気持ちになる
・厳粛な気持ちになる
【「英語」で言うと?】
「畏怖」や「恐れ」は[awe]もしくは[fear]で表現することができます。「〜を畏怖している」は、[be in awe of]と表現します。
[awe]と[fear]の違いは、[awe]は相手への畏敬の念によるものであり、[fear]は自分に危害の及ぶのを恐れる気持ちを表しています。
・People were in awe of the big Tsunami.(人々は大津波に畏怖の念を抱いた)
・He arouses fear (awe)in others.(彼は人々に畏怖の念を起こさせる)
***
「畏怖」は、自然や神仏に対する恐れや敬いを表す言葉です。音楽や絵画などの芸術や、偉大な人物についても「畏怖の念を抱く」は使われることがありますが、あまり日常的な表現ではありません。「畏敬」や「尊敬」「崇拝」などの類語を頭に入れておき、状況に応じて使い分けましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『プログレッシブ英和中辞典』(小学館) /『使い方の分かる 類語例解辞典』(小学館) :