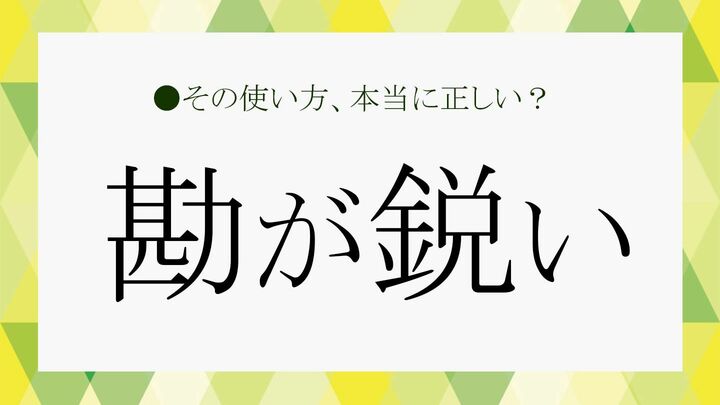【目次】
【「頭がいい」っていうこと?「勘が鋭い」とは?「意味」】
■読み方
「勘が鋭い」は「かんがするどい」と読みます。
■意味
「勘」とは、直観的に事柄を感知したり、判断したり、行動したりする心のはたらきを指します。「視覚」「聴覚」「嗅覚」「味覚」「触覚」といった人間の五感を超えた能力を第六感といいますが、「勘」も第六感のひとつ。「鋭い」にはさまざまな意味がありますが、この場合は感覚が鋭敏、細やか、素早く的確に本質を捉えるさまを表します。つまり、「勘が鋭い」とは、「物事のよし悪しなどを直感的に判断する能力に長けている」ということなのです。
■「頭がいい」とはどう違う?
「勘が鋭い」はあくまで直感的な判断力に秀でていることを意味します。熟考を経た判断力や、学力の高さ、知識の豊富さなど、広く「頭がいい」とされる判断基準とは異なります。「頭がいい」といわれる人は、一般的に感覚よりも思考を優先するタイプです。
【「勘が鋭い」人の特徴】
■具体的な特徴
・観察力や洞察力に優れている ・頭の回転が速い
・危機回避能力が高い ・相手の心中を見透かすような発言をする ・人のウソを見抜く
■「勘が鋭い人」のメリット
「勘が鋭い人」は、無意識に周囲の人や状況を細かく観察しています。ですから例えば、当人が何も言っていないのに、「〇〇さん、もしかして体調悪い? 無理しないでね」といった気遣いができるのです。こちらが説明しようとしていることを先回りして理解していることも、「勘が鋭い」人の特徴です。「ビジネスでは、指示されなくても先回りして仕事を進めたり、気を利かせることができる」のは高く評価されますので、「仕事ができる人」と言われることも多いはずです。
■「勘が鋭い人」のデメリット
「直感」が当たるときはよいのですが、「100%的中」させるのは、どんな人でも難しいものです。そのため、「勘が鋭い人」の中には、自分の直感を過信するあまり、「思い込みが激しい」という烙印を押されてしまうケースも。また、せっかちな人、短気な人も少なくないため、他者と歩調を合わせるのが苦手、という人もいるようです。特技であるはずの「先回り」が裏目に出ることもあるので、「勘が鋭い人」が必ずしもいつでも歓迎されるとは限りません。
また、「勘」はよいことばかりにはたらくわけではありません。「勘が鋭い人」は悪い予感も当たりがち。早めに心構えや対処ができる、トラブルを未然に防ぐことができるなどのメリットはありますが、難しい事柄だと精神面に負担がかかる時間が長い、というデメリットも…。いずれにしてもひとりで先走るのは危険です。お仕事シーンでは、やはり「報告」「連絡」「相談」の“ホウレンソウ”を欠かさないことが大切です。
【「類語」「言い換え」表現】
■類語
・察しがいい:「察し」とは推し量ること。「勘」と同様に、第六感を使います。
■言い換え表現
・勘がはたらく ・勘がいい ・勘が当たる ・理解が早い ・インスピレーションがはたらく
・のみ込みが早い ・物わかりがいい ・ピンと来る ・ひらめく
■関連語
・一を聞いて十を知る:物事の一部を聞いただけで全体を理解すること。賢明で察しのいいことのたとえです。『論語』で知られる孔子(こうし)の弟子の子貢(しこう)が「一を聞いて十を知る」と言い、孔子もその意見に賛成しました。また、同じく思想家の荀子(じゅんし)は「一を以(もっ)て万を知る」と言いました。どちらも「勘が鋭い」ことを表現しています。
【「反対語」は鈍感?】
「反対語」の候補をあげようと思ったら、「勘が鋭い」であれば「鋭い」の反対語を考えてみるのが簡単です。
・勘が鈍い ・勘が悪い ・勘がはたらかない
熟語の「鈍感」は「感じ方が鈍いこと。気が利かないこと」を意味する熟語ですから、こちらも「勘が鋭い」の反対語と言っていいでしょう。
【「英語」で言うと?】
「勘」を英語で表現すると、[intuition](直観)となります。また、「第六感」に相当する[sixth sense]を使うのも適切ですね。
・I have good intuition.(私は勘が鋭い)
・She have a good sixth sense.(彼女は勘が鋭い)
***
「勘が鋭い」人には気配り上手な人も多いので、よいビジネスパートナーになってくれそうです。とはいえ、「言いたくないことでもなぜかバレてしまう」鋭い洞察力の持ち主なので、常に緊張感は必要かも。プライベートでは、「勘が鋭い人」は「自分とは合わない」と感じたら、す〜っと離れていく傾向にあるので、もし避けられていると感じたら、関係を親密にするのはなかなか難しいかもしれませんね。どう向き合っていくのが適切なのか……これを判断するのも、「勘」次第と言えそうです!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『角川類似新語辞典』(KADOKAWA)/『プログレッシブ英和中辞典』(小学館) :