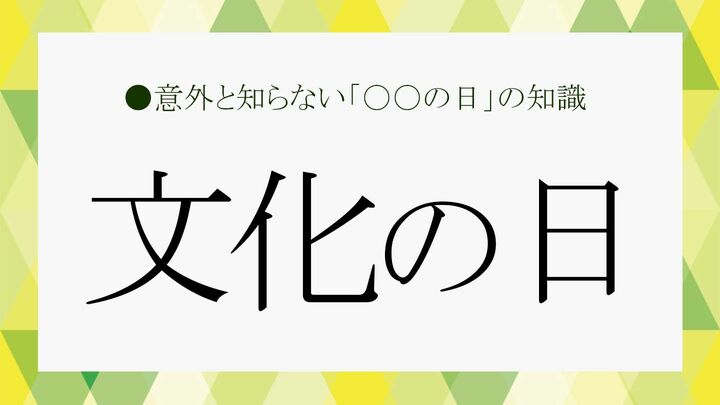【目次】
■「文化の日」とは?「意味」
11月3日は「文化の日」で祝日ですが、その意味を正しく言えるでしょうか?
「文化の日」とは、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とした国民の祝日です。1948(昭和23)年に制定されたので、生まれてからず~っと11月3日は祝日、という方が多いのではないでしょうか。
■日付
2025年の11月3日は月曜日なので土曜日から3連休という人もいるでしょう。11月のもうひとつの国民の祝日「勤労感謝の日」の23日は日曜日にあたるため、翌月曜日が振替休日となります。2025年の11月は3連休が2回あることになります。
【なぜ11月3日?「文化の日」にまつわる雑学】
■なぜ11月3日?「由来」
「文化の日」が制定される2年前、1946(昭和21)年の11月3日は、日本国憲法が公布された日です。平和と文化を謳った新憲法の精神に基づいて制定されたため「平和と文化」が強調され、1948(昭和23)年にこの日を「文化の日」として定めました。
■「文化の日」の名称にはどんな意味が?
日本国憲法では“戦争放棄”という重大な宣言をしているため、この「文化の日」は国際的にもとても重要な日として認識されています。平和を図り、文化を進める――戦争など争いごとがない平和な社会であるだけでなく、文化的な生活や、文化を愛で発展させるという意味から、「文化の日」と名付けられたのだとか。
■何をする日?
「文化の日」には皇居で文化勲章の親授式が行われます。文化勲章は、科学や芸術などの分野において日本の文化の発展に貢献した人々に贈られる勲章です。ほかの勲章のような等級はなく、称号にも結びついていません。受章者の選定には、法令に明確な規定がなく、文部科学省の関係機関が選考委員会を設けて候補者を推薦し、閣議で決定されます。授与式では、皇居の宮殿「松の間」で天皇陛下から受章者へ文化勲章が授与され、内閣総理大臣から勲記が伝達されます。
2025年の文化勲章は下記の方などが受賞されました。
・王貞治さん:元プロ野球選手・監督で、現在は福岡ソフトバンクホークスの球団会長。1952(昭和27)年に本塁打の世界記録を達成、初の国民栄誉賞を受賞。スポーツの振興に貢献。
・片岡仁左衛門さん:歌舞伎俳優。人間国宝に認定され、後進の育成にも尽力。
・コシノジュンコさん:ファッションデザイナー。業界の枠を超えた活躍で諸外国との文化交流に貢献。
・辻惟雄さん:美術史家、東京大名誉教授。日本の文化や歴史を国際的な連携の下で研究し、芸術文化の普及に貢献。伊藤若冲をはじめ、江戸時代の知られざる画家たちの魅力を世に示した『奇想の系譜』(美術出版社、1970年)は、従来の日本美術史のとらえ方を刷新。
■晴天に恵まれる日
また、この時期は統計的に天候が落ち着いていて、11月3日は晴天に恵まれる“気象上の特異日”であるため、学校や自治体などでは文化祭や学園祭、芸術祭といった各種催しが開催されることの多い日でもあります。
■昔は「文化の日」ではなく「明治節」だった!
11月3日が「文化の日」になる以前、この日は「明治節」と呼ばれる祝日でした。11月3日は明治天皇の誕生日。昭和前期に明治天皇の遺徳を偲び、明治時代を追慕する目的でこの日を「明治節」として制定していたのです。
明治天皇の在位期間(1867~1912年)は、日本が近代国家として発展した時期。それゆえ明治天皇は国家の威信を高めた英明な天皇として賛美され、「明治節」は国家主義と天皇崇拝を高めるための記念日となりました。明治天皇は旧江戸城を皇居とした天皇ですね。「明治神宮も明治天皇がつくったの?」と思った人、いいセンいっていますが違います。明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀るため、明治天皇の崩御後に創建されたものです。
■「文化の日」といえば日章旗!
「文化の日」に、公共施設やバスなどの公共交通機関、商店街や民家などにも日章旗(日の丸の旗)が掲げられているのを見たことがあるでしょう。これは、平和な日本に感謝し、より豊かで幸せな生活を送るためにこの日を祝う、という意味を込めて掲げるもの。「文化の日」に限らず、国民の祝日には掲げられることが多いようです。休日を「旗日(たはび)」とも呼ぶのはそういった理由からなのでしょう。
■「文化の日」には美術展へ!
学校や職場でのイベントがない人は特に「文化の日」として意識することはないかもしれませんが、せっかくの国民の祝日ですから、文化的な一日を過ごしてみてはいかがでしょう。音楽コンサートやスポーツ観戦などチケットが必要なものは直前では入手が難しいかもしれませんが、比較的気軽に体験できるアート鑑賞がおすすめです。2025年の「文化の日」に鑑賞できる、国立の美術館・博物館で開催される展覧会は下記の通りです。
・東京国立博物館:特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」 本館 特別5室にて11月30日(日)まで開催
・国立西洋美術館 :「フルーニング美術館・国立西洋美術館所蔵 フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会”」 本館展示室にて2026年5月10日(日)まで開催
・国立新美術館:「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」 企画展示室1Eにて12月8日(月)まで開催
・京都国立博物館:特別展「宋元仏画─蒼海(うみ)を越えたほとけたち」 平成知新館にて11月16日(日)まで開催
・奈良国立博物館:「第77回 正倉院展」 東新館・西新館にて11月10日(月)まで開催
・九州国立博物館:特別展「法然と極楽浄土」 11月30日(日)まで開催
【憲法記念日との違い】
■「憲法記念日」とは?
拳法記念日とは、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」という趣旨の国民の祝日です。
日本国憲法は1946(昭和21)年11月3日に公布され、半年後の1947(昭和22)年5月3日に施行が開始されました。「憲法記念日」を、公布された11月3日にするか、施行された5月3日にするかについては、当時相当な議論がなされたようです。
■「文化の日」と「憲法記念日」の違い
「憲法記念日」の趣旨は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」こと。一方の「文化の日」は「憲法の制定にあたり、平和や自由・文化を重んじる日」です。国の成長を願うのが「憲法記念日」、平和や文化を重んじるのが「文化の日」と言えそうです。
【ビジネス雑談に使える令和の日本を象徴する「文化」とは?】
現代社会にはさまざまな「文化」が存在し、また「文化」の定義も多様化しています。ちょっとした会話に使えそうな“現代の文化”についてご紹介しましょう。
■そもそも「文化」って?
『デジタル大辞泉』では下記のように説明されています。
1. 人間の生活様式の全体。人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体。「日本の文化」「東西の文化の交流」
2. 1のうち、特に、哲学・芸術・科学・宗教などの精神的活動、およびその所産。
3. 世の中が開けて生活内容が高まること。文明開化。多く他の語の上に付いて、便利・モダン・新式などの意を表す。「文化的な生活」「文化住宅」
ちょっと難しいでしょうか。一般的に会話のなかで使用される「文化」は、3の意味が多いようです。
次に、「令和を象徴する文化」をご紹介しましょう。
■推し文化
「推し」という単語がこれほどまでに脚光を浴びるとは! という感じですが、今やなんでもかんでも「推し」のひと言で表わせる時代です。
そもそも「推し」とは「ほかの人に勧めること」を意味します。そこから発展して「人に勧めたいほど気に入っている人や物」を指す言葉に。音楽グループやアイドルグループのなかで最も応援しているメンバーを意味する語「推しメン」、グループ全体を応援することを「箱推し」というフレーズが流行したことから、好きなアイドルや俳優などを表す言葉として定着しました。「推しの主演ドラマ」や、「推しの好み」「推し活」というように使いますが、そういった表現や活動をまとめて「推し文化」と表現します。
■「多様性」「共生」「サステナブル」も「文化」です!
現代は、時代を象徴するキーワードが産む事柄が「文化」として認識され、発展しやすい時代です。特にビジネス会話でもよく使われる文化的なキーワードをおさらいしておきましょう。
・多様性:「いろいろな種類や傾向のものがあること」や「変化に富むこと」を表す言葉。「生物の多様性を保つ」というように使います。現代では「性の多様性」について語られることも多く、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(身体的な性別と、本人が認識する性別が異なる人)の頭文字を組み合わせた「LGBT」も覚えておきたいワードです。
・共生:「共に同じ所で生活すること」「異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること」を指します。「ペット共生マンション」をご存知ですか? これは人間とペットが、ともに快適かつ安全に暮らせるような設備や配慮がなされたマンションのこと。ペット専用の出入口や足洗い場があったり、ペットによる汚れや音に配慮した内装が施されているようです。
・サステナブル:英語で[sustainable]なので「サステイナブル」とも。「持続可能であるさま」を表す単語で、特に地球環境を保全しつつ持続が可能な産業や開発などについて言います。「サステナブルな社会づくり」や「サステナブルな取り組み」のように使いますね。
***
「文化の日」は「国民の祝日」ですが、「国民の休日」というフレーズもありますよね。「国民の祝日=休日」なのですが、「祝日法第3条」では「ふたつの祝日に挟まれた平日は休日とする」ことが規定されていて、これが「国民の休日」です。ただし祝日法には「国民の休日」という文言の記載はないので、「国民の休日」は俗称ということになるのだとか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『現代用語の基礎知識』(自由国民社)/『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館) /内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/ :