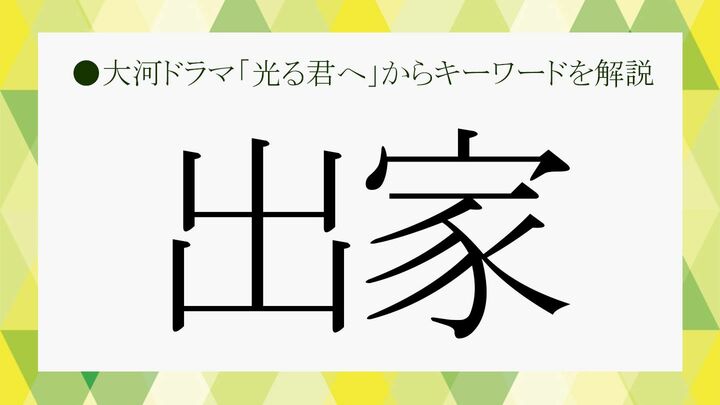【目次】
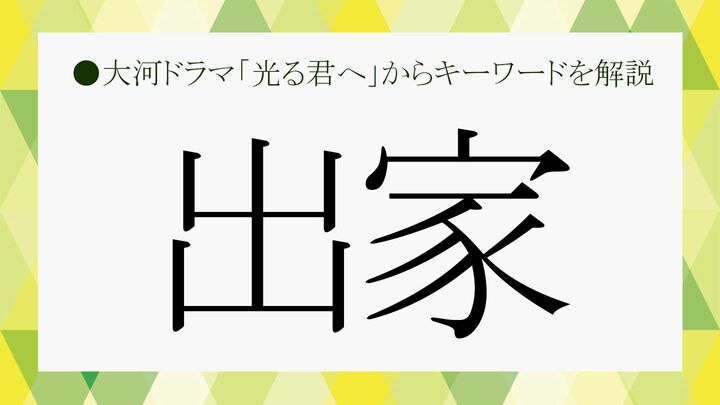
【大河ドラマ『光る君へ』にも登場した「出家」とは?「読み方」「意味」】
■「読み方」
「出家」は「しゅっけ」、あるいは「しゅけ」と読み、「すけ」とも発音します。
■簡単に言うと…「意味」
俗世(俗世)と呼ばれる通常の社会生活を捨てて、仏道修行の生活に入ることを「出家」と言います。
【出家するには?】
現代では、それぞれの宗派の定めに従って、僧侶の資格を得ることを「出家」と表現することが多いようです。
■お寺で修行を積む
まずは仏教の知識を深める必要があります。信頼できる僧侶から基本的なことを学んだうえで、その宗門の修行ができるお寺に入り、修行を積むという方法です。お寺によっては、仏教に入門するためのコースを設けていたり、出家者を募集していることもあるようです。
■専門学校や仏教系大学へ入る
現代では僧侶を目指せる学校もあります。よく知られているのは、仏教系の大学や、総合大学の中の仏教を専門で学べる学部への進学です。例えば、曹洞宗であれば駒澤大学(東京)、浄土真宗であれば龍谷大学(京都)、日蓮宗であれば立正大学(東京・埼玉)、真言宗であれば高野山大学(和歌山・大阪)などが有名。そのほか、専門学校や通信教育でも学べる仕組みがあります。
■「得度(とくど)」という儀式を受ける
「得度」とは僧侶入門の儀式のこと。宗派により内容は異なりますが、この時点で髪を剃り、寺院で生活を送り、肉や魚を食べられない俗世から離れた厳しい修行を行い、布教活動に励みます。
【出家するとどうなる?】
NHK大河ドラマ『光る君へ』でも、主要登場人物の多くが「出家」を選択しています。花山天皇(本郷奏多さん)、藤原兼家(段田安則さん)、中宮定子(高畑充希さん)、藤原為時(岸谷五朗さん)そして藤原道長(柄本佑さん)。道長と源明子(瀧内公美さん)の三男、藤原顕信(あきのぶ:百瀬朔さん)が出家したシーンでは、「顕信を返せー!」と、悲しみと怒りを爆発させる明子の姿が印象的でした。
■平安時代の「出家」の意味は?
平安時代、王朝人たちが信じていたのは、浄土信仰でした。浄土信仰とは、現世の苦しみから逃れて極楽浄土に往生することを目的とし、念仏などを実践する教えです。藤原兼家や道隆、道長など、身分の高い貴族たちの多くが、現世だけでなく来世の幸せを願うようになっていたのです。そのための方法のひとつが出家です。
■具体的に禁じられることは?
平安時代は、仏道修行の生活に入ることの象徴として、「飾り」である髪を切ったり剃ったりすることから、「落飾(らくしょく)」あるいは「剃髪(ていはつ)」とも言いました。出家後は具体的には、男女の交わりや肉食・飲酒・殺生を禁じられる身となります。平安の人々にとって「出家」は、一種の死と見なされていたため、誰かが出家を希望すると、家や親戚、家来が全力で引き留め、ついに出家となったあかつきには、一同悲泣するのが通例でした。『光る君へ』でも、道長の妻・倫子(黒木華さん)が、夫の出家を必死に止める場面がありましたね。娘たちが入内したのち、夫婦ふたりでゆっくりと過ごしたいと望んでいた倫子にとって、夫の出家はさぞかし辛いものだったことでしょう。
■「出家」のパターンはふたつ
・お寺に入り、現世を捨てる
ひとつめは、藤原顕信のように、世をはかなんで突如、山寺に篭もってしまう「出家」のパターンです。生きることが困難な現世、現世に関わるすべてを振り捨ててしまうため、自分の家に戻ることはありません。
・現世にいながら「出家」する(在家出家)
もうひとつ、世間の雑事から離れ、家の中で仏道に励むことも「出家」と言いました。兼家や道長のパターンですね。彼らは、別邸を寺院にした在宅出家でした。ただし、そのときも髪の毛は剃りました。剃髪については、懇意のお寺からお坊さんが出向き、行うこともあったようです。女性の場合は、背中の辺りで揃えました。それを「尼削ぎ」といったのです。一条朝期には、中宮定子が自ら髪を切って出家したにもかかわらず、天皇に愛され続け子を産むという大スキャンダルが起きました。
【ビジネス雑談に役立つ「出家」にまつわる「雑学」】
■現在の僧侶が結婚しているのはなぜ?
私たちが日常お目にかかるお寺の住職さんは、結婚して妻や子どもがいる方がほとんどですよね。実は僧侶が婚姻届けを提出し結婚できるようになったのは、明治以降です。
仏教が国家の庇護と規制のもとに置かれたのは8世紀頃。『僧尼令(そうにりょう)』が制定され、当時、僧尼の出家には朝廷の許可が必要でした。今で言う国家公務員のような身分が与えられ、試験もありました。試験に合格すると剃髪し、正式な僧侶となるための儀式(授戒)が行われました。合計250もの戒律があり、それらを守ることはかなり厳しかったようです。当然、僧侶として戒律を守る以上は、独身でいなければなりません。江戸時代に入っても、寺院と僧侶は厳しく統制されました。
明治維新を迎えると、政府は神道国教化政策により、1872(明治5)年「僧侶の肉食(にくじき)妻帯蓄髪(さいたいちくはつ)は勝手たるべきこと」と太政官布告を出します。要するに、「僧侶は鳥や豚、牛のお肉を食べようが結婚しようが、髪の毛を伸ばそうが自由にしてよい」という許可が出たのです。これは「僧侶として守らなければならない戒律を放棄することを国家が認めた」という意味ではありません。単純に、国家として仏教を統制することを止めたということです。現在、多くの寺院は夫婦単位でお寺を守り、子どもが仏教の大学などへ進学し、跡を取ることが多いようですね。
■「尼僧(出家して仏道に入った女性)」は結婚できるの?
結論から言えば、可能です。前述の通り、日本の仏教では結婚が認められており、もちろん男女平等。従って、住職さんが結婚して子どもをもっているように、尼さんが結婚し、子どもを育てることに制限はありません。お寺によっては、産後休暇・育児休暇などの制度も整えているところもあるそうです。ただし、実際のところは、結婚して子どもを育てている尼僧は非常に少ないのが現状です。
■「プチ出家」って知ってる?
現代の京都のお寺には、静かな空間で自分自身と向き合いながら、日常生活で必要なエネルギーのチャージができる1泊2日程度の「プチ出家体験」を行っているところがあるそうです。宿泊するのはお寺の宿坊。もともとは寺の僧や参詣人が泊まる施設でしたが、現在では日本人はもちろん、海外の観光客にも解放されています。座禅や読経、お経を書き写す「写経」体験などができるお寺が人気を集めているそうです。
■「出家」に年齢制限はある?
ありません。天台宗の尼僧となった故・瀬戸内寂聴さんが出家したのは51歳のときでした。
***
『光る君へ』では、わが身の不幸を嘆いた中宮・定子が、自ら髪を切るシーンが印象的でした。現代を生きる私たちの目には、「あんなちょっとだけ髪を切って、出家したことになるの?」と感じた人も多かったのでは? 平安時代の女性は夫に先立たれると、死後の極楽浄土を願って出家するのが普通のことでもあったようです。一方で藤原道長は、出家後は「禅閤(ぜんこう)」と呼ばれ、政治的な力を行使し続けていたようです。平等院鳳凰堂は、藤原頼通が父道長の別荘を寺院に改めたもの。現世での繁栄に加え、彼らが願った極楽浄土への夢とは、なんと荘厳で華麗なものだったことでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『全文全訳古語辞典』(小学館) /NHK大河ドラマ・ガイド『光る君へ 完結編』(NHK出版) /『平安 もの こと ひと 事典』(朝日新聞出版) /『平安貴族とは何か 三つの日記で読む実像』(NHK出版新書) /『はじめての王朝文化辞典』(角川文庫) :