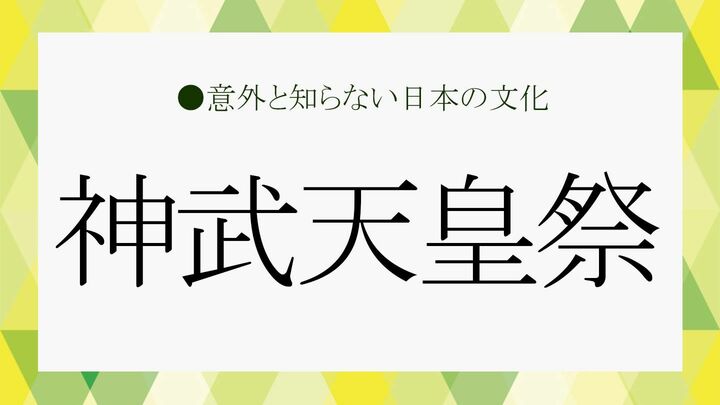「神武天皇祭」は、日本の初代天皇とされている神武天皇の崩御日である、4月に行われる大祭です。以前は祝祭日でしたが、現在では宮中祭祀として存続しています。今回は「神武天皇祭」の正確な意味やその経緯、知っているとちょっと話したくなる雑学をご紹介します。ビジネス雑談での小ネタとして、ご活用ください。
【目次】
【「神武天皇祭」とは?】
■「意味」は?
「神武天皇祭」は、国や皇室が執り行う大祭日(たいさいじつ)のひとつです。『日本書紀』によれば、日本の初代天皇である神武天皇の崩御日は、紀元前586(神武天皇76)年の3月11日とされていますが、これを現在の新暦に換算すると4月3日になるため、この日に「神武天皇祭」が行われることになりました。毎年4月3日には、宮中の皇霊殿と神武天皇陵に治定される奈良県橿原市の畝傍山東北陵で儀式が行われ、天皇がその霊を祭ります。
■「いつ」からある?
「神武天皇祭」は江戸の幕末の孝明天皇の時代、神武天皇の御陵祭として始まり、1871(明治4)年に、皇室の祭祀に関する規則である「四時祭典定則」で規則化されました。その後、1908(明治41)年に「皇室祭祀令」で改めて法制化されましたが、1947(昭和22)年に廃止。以降は宮中祭祀として存続しています。1874(明治7)年から1948(昭和23)年までは祝祭日(休日)でした。
【何をした人?卑弥呼との関係は?ビジネス雑談に役立つ神武天皇の雑学】
■今さら聞けない!神武天皇の基礎知識
神武天皇は『古事記』と『日本書紀』において、日本の初代天皇とされています。天皇に即位する前は、神日本磐余彦尊 (かんやまといわれひこのみこと)と呼ばれました。桓武天皇は、もともとは日向国(現在の宮崎県)に住んでいましたが、45歳のときに、東方に美しい土地があることを聞き、天下を治めるためにそこに都をつくることを宣言します。そして一族を率いて東征を開始し、幾多の戦いを経て、52歳のときに大和を平定。紀元前660年橿原宮(かしはらのみや)で即位し日本国を建国したといわれる、伝説上の人物です。
神武天皇は太陽神である天照大神(あまてらす)をはじめとする天津神の直系で、山・海といった大自然の神々の系譜、さらに国津神の末裔と婚姻を果たし、あらゆる神々を合一化したといわれています。その存在は、国家安寧や安泰を象徴し、「建国記念の日」においては、その即位を祝う紀元節が祝われてきました。
■「建国記念の日」と神武天皇の関係を知ってる?
「建国記念の日」は2月11日。「建国をしのび、国を愛する心を養う」ことを趣旨として制定された、国民の祝日です。そしてこの2月11日という日付は、神武天皇に由来します。
神武天皇の即位は紀元前660年1月1日。この日付を現在の新暦に換算すると2月11日にあたるため、この日が「建国記念の日」に定められました。神武天皇は伝説上の人物ですから、1776年7月4日に新たな独立国家を形成したアメリカのように、何年何月何日に建国したのかについて、明確な根拠はありません。これが、「建国記念の日」が「建国記念日」という名称でない理由。「日本が建国された記念日」ではなく、「日本が建国されたことを祝う日」なのです。古代の建国説話に基づき「建国の日」が制定されているのは、世界的にも非常に珍しい事例だそうですよ。
■卑弥呼は神武天皇の子孫なの?
卑弥呼は、3世紀頃に邪馬台国(やまたいこく)を治めた女王だとされています。卑弥呼が中国の魏(ぎ)という国と交流をもち、「親魏倭王(しんぎわおう)」という称号をもらったことは、中国の歴史書『魏志倭人伝』に書かれています。
一方で、紀元前660年に即位されたとする神武天皇については、伝説上の人物であるという説が一般的。さらに、「卑弥呼の時代の日本」と「神武天皇がつくったとされる大和朝廷」の時代は、800年以上も離れています。さらに『日本書紀』に卑弥呼は登場しないため、卑弥呼と神武天皇に血縁関係があったのか、あるいは対立関係にあったのかなど、確かな資料はありません。
■神武天皇は天下を治めるために「飴」をつくった?
日本で初めて編纂された歴史書である『日本書紀』の「神武紀」には、「飴をつくった」人物についての記載があります。「われ今まさに八十平瓮(やそひらか=たくさんの平らな皿)をもちて、水無しに飴(たがね)をつくろうと思う。飴ができたならばわれは武力を用いずに天下を治めることができるだろう」。つまり、「飴をつくって皆にふるまえば、武力を行使することなしに天下を治められるだろう」と言っているのですね。神武天皇がつくったのは、米を原料とする水飴状の飴だったと言われていますよ。
■「神武天皇祭」が行われる神社は?
神武天皇は紀元前660年に、畝傍山(うねびやま)の東南に位置する「橿原宮かしはらのみや)」で即位したといわれています。明治に入り、「橿原宮址(かしはらのみやあと)」に神宮創建を望む、民間有志からの請願を受け、明治天皇によって1890(明治23)年4月2日に創建されたのが、「橿原神宮」です。
古くから「神武さん」と親しまれ、神武天皇が崩御された4月3日に行われる「神武天皇祭」には、地元はもとより近郷、他府県からの参拝者で賑わいます。「神武天皇祭」は、橿原神宮(奈良県)や宮崎神宮(宮崎県)など、神武天皇を祀る神社はもとより、日本全国の神社のほとんどで、遙拝式や祭典が行なわれます。
***
初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年(紀元)とする「皇紀」では、今年(2025年)は2685年にあたります。皇統については伝承による部分もあり、実質の建国は古墳時代(6世紀ごろ)ではともいわれていますが、いずれにせよ、ひとつの皇統が続き、他国に支配されたこともない日本は、世界に現存する国家では最も古い国です。「神武天皇祭」を迎えるこの時期、桜が満開となった地域も多いですね。近くの神社にお出掛けしてみてはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /橿原神宮(https://kashiharajingu.or.jp) /カンロ株式会社『Sweeten the Future』(https://www.kanro.co.jp/sweeten/detail/id=694) :