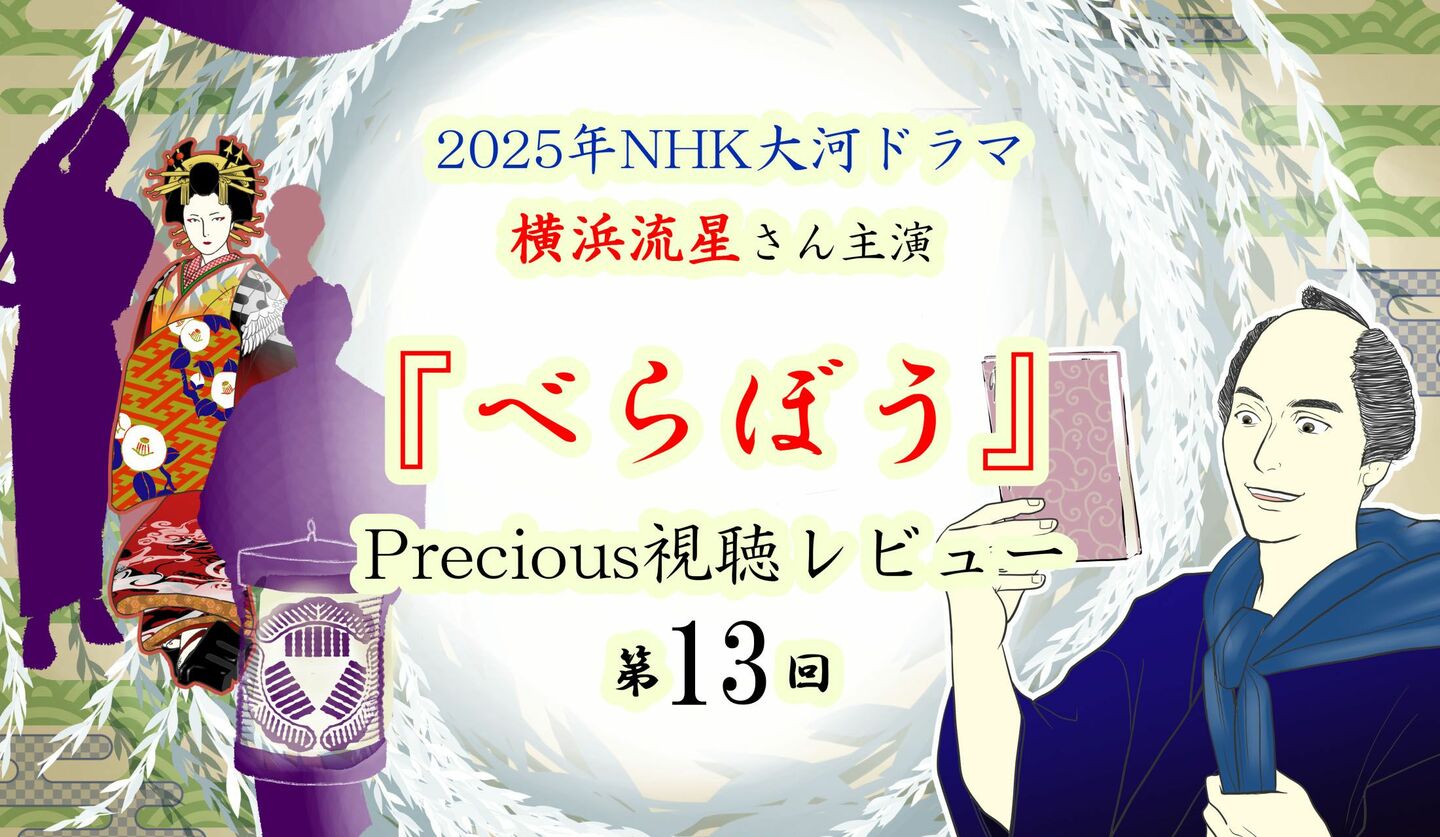【目次】
- これまでのあらすじ
- 実在した五代目瀬川の値打ちは1億4000万円!
- 『べらぼう』での五代目瀬川の幸せはどこに?
- 身請けされて幸せになった遊女はいるのか?
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第14回「蔦重瀬川夫婦道中」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
体は己のもとにあっても、瀬川改め瀬以(小芝風花さん)の心は吉原の蔦重(横浜流星さん)のもとにある、と疑う鳥山検校(市原隼人さん)。回を重ねるごとにすごみが増し、「瀬以危ない!」「ヤバいこのオトコ!」とハラハラさせられます。某住宅メーカーのCMでの市原さんの演技がどんどん検校寄りになってる…と感じているのは筆者だけでしょうか?
さて、五代目瀬川は1400両というべらぼうな大金で鳥山検校に身請けされて吉原を去り、蔦重はよりおもしろい本を出版して吉原を盛り立てたいと知恵を絞って企画を練る。吉原の親父衆は江戸っ子らしく見栄を張り合い、祭りや花見でみな楽し気――というわけにはいかないのが『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』です。
第13話では、再び鱗形屋の偽板本が出回り、鳥山検校をトップとする当道座(とうどうざ/盲人の組織)の座頭金(ざとうがね/高利貸し営業)は市中だけでなく旗本や大名のなかにも手を出す者が続出。そして、嫉妬に駆られた鳥山検校は瀬以を監禁…と、あちこちで問題が勃発しました。
『べらぼう』は、江戸時代に実在した人物や事件、エピソードをふんだんに盛り込んだ、蔦屋重三郎というひとりの出版人を軸とした物語。今回は、実在した伝説の花魁“五代目瀬川”に注目します。
【実在した五代目瀬川の値打ちは1億4000万円!】
唯一の幕府公認遊郭だった吉原。そこでしか生きられない遊女たちの多くは幸せな生涯だったとはいえませんが、250年近く経ってドラマの主役級に描かれるほど人々を魅了した花魁がいました。それが、五代目瀬川。大河ドラマ『べらぼう』で小芝風花さんが演じるあの花魁は、実在する人物なのです。
■五代目瀬川は最上級店のトップ花魁
実在した五代目瀬川が吉原を賑わしたのは、江戸時代中期の安永年間(1772~81年)。江戸の町が経済的にも文化的にも繁栄した時期で、吉原をはじめとする遊里文化は成熟期を迎えていました。
瀬川がいた松葉屋のような「大見世」と呼ばれる高級店が10軒、準高級店の「中見世」が29軒、大衆店の「小見世」が22軒。加えてさらに大衆的な「切見世」や「河岸見世」も数軒ありました。1796(寛政8)年発行の『吉原細見』が、ほぼ正確な数を教えてくれます。
彼女の生涯については明確な記録が少なく、生没年すら不明ですが、1775(安永4)年に、盲人の高利貸しで大金持ちの鳥山検校に身請けされたのは事実。1400両という身請け金が本当なら、瀬川は約1億4000万円で吉原を出たことになります。
これは吉原どころか江戸中を揺るがす金額で、その後検校が逮捕されたこともあって大事件として語られ、当時の世相や遊里文化に大きな影響を与えたのだとか。内容は創作されていますが、この瀬川を題材にした洒落本(絵入りの読み物)『契情買虎之巻(けいせいかいとらのまき)』という吉原文学も大ヒット。ちなみに作者は洒落本で活躍した田螺金魚(たにしきんぎょ)。明らかにペンネームですが、こうしたふざけた名前は江戸っ子の粋(いき)。貧乏武士が副業する際によく使われました。
【『べらぼう』での五代目瀬川の幸せはどこに?】
■花の井(小芝風花さん)が五代目瀬川を継いだわけ
吉原には、「高尾」「玉菊」「吉野」「薄雲」など、代々引き継がれる名跡(みょうせき)がいくつも存在しました。名跡とは名字や師匠の仕事を受け継ぐことで、転じて「名を残すこと」や「後世に残した名」を指します。
吉原の名跡のなかでも特に重んじられたのが「瀬川」。大見世の松葉屋の看板遊女の名跡ですが、『べらぼう』では四代目瀬川が自害したため20年近く欠番状態だったとされていましたね。実在した四代目瀬川は実際に28歳という若さで亡くなっていますが、その死因ははっきりしていません。ドラマのなかは花の井が蔦重の力になるべく、縁起の悪い名跡を継いだ、という展開でした。
こうして『べらぼう』では鳴り物入り的に襲名された五代目瀬川。ガンガン稼いで吉原を、松葉屋を盛り立てるのかと思いきや、意外にもあっさり鳥山検校の求めに応じて身請けされていきました。襲名も身請けも、しょせん結ばれない蔦重への想いを押し殺してのもの。吉原に生きる男と遊女が結ばれるのは、ご法度だったのです。
■「五代目瀬川」から検校の妻「瀬以」へ
晴れて検校の妻「瀬以」となった瀬川。検校にめちゃくちゃ大事にされて幸せなはずですが、想いいはやはり…。そんな妻の気配を感じ取っているような不穏な様子の検校は、美しい絹織物や高価なくしやかんざしなど「好きなものを好きなだけ」お買い与えるという夢のような大盤振る舞いで妻を喜ばせようとします。「これを吉原の娘たちに」という瀬以の申し出まで叶え、読書好きの彼女のために図書室のような部屋も設えるのですが…。
第13回の放送での小芝さんの演技に涙した人も多いのでは? 子どものころから自分の光であり続けた重三(じゅうざ、蔦重のこと/横浜流星さん)への想いを胸に秘め、懸命に検校の愛に報おうとするも蔦重との仲を疑われ…「けんど、この世にないのは四角い卵と女郎のまこと、どうして己の心ばかりはだませぬのでありんしょ」と胸の内を検校に吐露してしまうのです。切なすぎる…そして残酷すぎる!
【身請けされて幸せになった遊女はいるのか?】
次回放送以降の瀬川も気になるところですが、最後に「身請けされた遊女」について少々。
■あの「見返り美人」のモデルは…
蔦重が出版プロデューサーとして活躍する時期からさらに100年ほど前の時代に活躍した江戸の絵師・菱川師宣(ひしかわもろのぶ)。吉原を舞台にした艶本(えんぽん)や枕絵(まくらえ)と呼ばれる大人向き商品をたくさん描き、あの浮世絵「見返り美人」(東京国立博物館所蔵)を制作して浮世絵の祖ともいわれます。師宣の初婚、再婚の相手はいずれも遊女。「見返り美人図」のモデルになったのは、身請けした22歳も年下の再婚相手だといわれています。
■身請けされて妾に…も珍しくない
御家人であり、戯作や随筆、狂歌などに文才を発揮した大田南畝(おおたなんぽ)。家庭をもつ身でありながら松葉屋の美保崎(三保崎とも)という遊女にのめり込み、妾として身請けしました。彼女に語らせ書いた随筆『松楼私語(しょうろうしご)』には、遊女屋での風習などが仔細に記されています。
■年季が明けるまで…
戯作者で絵師の山東京伝は19歳のときに吉原の扇屋の菊園に惚れて通い続け、年季が明けてから夫婦に、という純愛パターン。京伝30歳、菊園27歳でした。しかし菊園は30歳で亡くなってしまうので、幸せな時間は長くなかったというわけです。遊女はカラダを張って生きてきたわけで、早死にすることも少なくありませんでした。
人気作家になった京伝は再び吉原通いをし、40歳で弥八玉屋の高級遊女・玉の井を身請け。『作者胎内十月図(さくしゃたいないとつきのず)』に京伝の隣で裁縫をする彼女の姿が描かれています。
次回第14話放送では、不当な高利貸しや非道な取り立ての罪で検校と瀬以が捕らええられ、蔦重も巻き込まれ――というくだりから始まります。小芝風花さんの熱演と市原隼人さんの怪演による妙味もクライマックスを迎えそうな予感。ますます日曜日が楽しみです!
【次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第14回「蔦重瀬川夫婦道中」のあらすじ】
幕府による当道座の取り締まりで、検校(市原隼人さん)と瀬以(小芝風花さん)は捕らえられ、蔦重(横浜流星さん)までも同心に連行されてしまう。その後釈放された蔦重は、大文字屋(伊藤淳史さん)から五十間道に空き店舗が出ると聞き、独立して自分の店を持てないかと考える。そんななか、いね(水野美紀)からエレキテルが効果のない代物だと聞き、源内(安田顕さん)を訪ねる。源内はエレキテルが売れないのは、弥七(片桐仁さん)のせいだと訴える。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第13回 「お江戸揺るがす座頭金(がね)」のNHKプラス配信期間は2025年4月6日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『精選版 日本国語大辞典』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『250年前にタイム・スリップ! 見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春出版社)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社) :