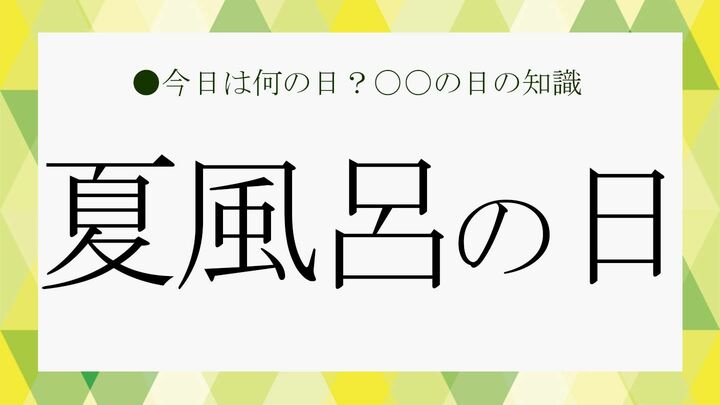【目次】
【「夏風呂の日」とは?由来】
「夏風呂の日」は、「な(7)つ ふ(2)ろ(6)」(夏風呂)と読む語呂合わせから、7月26日に制定された記念日です。夏にお風呂に入ることの爽快さを、もっと多くの人に知ってもらうことが目的。夏風呂の愛好家らが制定したといわれています。
【ビジネス雑談に役立つ「お風呂」と「入浴」の雑学】
■「夏こそお風呂」が爽快な理由は?
夏場は日中の暑さに疲れて、「お風呂はめんどうだからシャワーでとサッと汗を流したい」と思いがちな季節。でも実は、しっかり湯船に浸かることで心身のリラックス効果が得られ、ぐっすり眠れることで、この時期特有の体の不調が改善できるといわれています。また、入浴によってからだを温めることは、エアコンなどが原因で起こる夏の冷え性、たとえば足先の冷えやだるさ、肩こりなどの症状の改善も期待できますよ。
■ぬるめのお湯と水分補給が鍵
夏場の入浴は、少しぬるめのお湯(36℃~38℃)にゆっくり浸かることがポイントです。ぬるめのお湯に浸かることで副交感神経のはたらきが促され、ぐっすり眠ることができますよ。そして、たとえ10分から15分の短い入浴であっても、からだからは約800mlの水分が失われてしまうといわれています。ですから入浴後はミネラルウォーターや白湯、麦茶などのカフェインレスの飲み物でしっかり水分補給することが大切です。「お風呂上がりにはキンキンに冷えたビール!」を楽しみにしている人も多いかもしれませんが、入浴効果を求めるなら、冷たい飲み物よりも、からだを冷やさない、常温に近い飲み物がおすすめ。できれば、入浴前と後、両方で水分補給を行うと“健康的な入浴タイム”を実現できますよ。
■「お風呂」ってどうして「風呂」?
「お風呂」という言葉の語源については諸説あります。有力なのは「ムロ(室)」という言葉が訛って「フロ」になったという説。「ムロ」は、窟 (いわや) や岩室を意味します。
日本には、奈良時代ごろから風呂文化があったといわれています。当時の風呂は、石を焼き、その水蒸気でからだを温める「蒸し風呂」、つまりサウナのようなもの。狭い空間に溜めた蒸気を浴びてからだの汚れをふやかし、こすり落としてからだをキレイにしていました。そして、「風呂」は、古来より寄港した船乗りのための憩いの場所として風呂文化が根付いていた瀬戸内海湾岸の港町から、交易の活発化によって周辺から全国へと広がっていったようです。
■お湯に浸かる「お風呂」はいつから?
現在のように、お湯に浸かる入浴スタイルが確立されたのは、江戸時代中期以降。こちらは「(蒸し)風呂」に対し、「湯」と呼ばれていました。
「湯」とは、本来、からだにかけるもの(=行水という行為)を表すものでしたが、これが次第に「全身で湯に浸かるもの」に変化していきました。温湯浴の設備を示す「湯屋(ゆや)」や「湯殿(ゆどの)」の普及により、時代を経るに従って、もともとの蒸し風呂は日常生活で見られなくなっていきました。その結果、「風呂」と「湯」は混同して用いられるようになったのです。
■日本初の銭湯が登場したのは鎌倉時代
有料の入浴場がいつからあったのかについては、定かではありません。史実としては、鎌倉時代末、京都・八坂神社社内に銭湯があったという記録が残っています。江戸と大阪では、大阪のほうが早く、1590 (天正18)年に銭湯ができたようです。
江戸の銭湯の始まりは、徳川家康入府の翌年、1591(天正19)年に、伊勢の人、与市という人が現在も千代田区大手町にある常盤橋と呉服橋の間にあった銭瓶橋という橋のほとりに銭湯風呂をつくり、永楽一銭(永楽通宝という室町時代から江戸時代にかけて流通した銅銭。現代の価格に換算すると200円程度)で入浴させたのが最初とされていますよ。
そして、慶長年間の終わり(17世紀初頭)になると、銭湯は「町ごとに風呂あり」と言われる程に広まりました。当時の銭湯は蒸し風呂で、江戸時代後期にあたる文化年間(1804~1818年)には、江戸中に銭湯が約600軒あったと言われています。
■銭湯は「混浴が普通」でした!
江戸時代の銭湯は「入込湯(いりこみゆ)」と言われ、男女混浴。風紀の乱れという観点からたびたび問題視され、幕府から何度か禁止令も出されましたが、効果は上がりませんでした。天保の改革(1841~1843年)では、さらなる厳しく取り締まりが行なわれ、銭湯では男女が別々に入れるよう浴槽の中央に仕切りを取り付けたり、男女の入浴日時を分けたりという施策がされました。また、男湯だけ、女湯だけという銭湯も登場したようです。
明治になると、政府によって混浴は特に厳しく禁止され、たびたび通達が出されます。しかし、長年の風習がそう簡単に改まることはなく、実際に男女別浴となったのは、明治のなかごろまでかかったといわれています。
■「風呂敷」もお風呂が語源だって知ってた?
布でものを包む習慣は古くからありましたが、そうした布をまとめて「風呂敷」と呼ぶようになったのは、銭湯が普及した江戸時代からだとされています。銭湯では、人々は自分の着替えを布で包んだり、その布を敷物にして身繕いをするなど、布を使う機会がとても多かったのです。銭湯が普及し、人々の布の利用が増えたことによって、最初は布自体を「風呂敷」と呼ぶようになり、やがて細分化され、ものを包む布だけが「風呂敷」と呼ばれるようになった考えられています。
■「お風呂」に関連する記念日はほかにもある?
・「お風呂の日」
「お風呂の日」は「一般社団法人HOT JAPAN」より制定されました。温泉や銭湯、家庭風呂など、日本独自のお風呂文化の魅力をさらに多くの人に知らせることを目的とし、日付は2と6で「風呂」と読む語呂合わせから、2月6日です。
・「よい風呂の日」
4月26日は「よい風呂の日(正式名称「日本入浴協会・よい風呂の日)」です。日本入浴協会はお風呂に特化した専門団体で、日本初で唯一のお風呂の検定「入浴検定」を開催しています。
・「給湯の日」
9月10日は「給湯の日」。大阪府大阪市に本社を置く関西電力株式会社が制定しました。家庭で最もエネルギーを使う「給湯」を見直し、省エネ電気給湯器の「エコキュート」を多くの人に知ってもらうのが目的です。
***
梅雨のない北海道を除き、日本でいちばん梅雨明けが遅いのは東北地方です。例年7月19日ころですから、7月26日の「夏風呂の日」には、日本全国が夏の暑さ全開の日々を迎えていることになります。クーラーによる冷え性に悩む人ほど、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かる「夏風呂」の恩恵を感じやすいもの。のんびりとお風呂タイムを楽しんで、心と体をリフレッシュしてくださいね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『江戸のきものと衣生活』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『日本髪の描き方』(ポーラ文化研究所)/『お江戸ファッション図鑑』(マール社)/『見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春文庫)/『江戸の衣装と暮らし解剖図鑑』(X-Knowledge)/『一日江戸人』(新潮文庫)/『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書) :