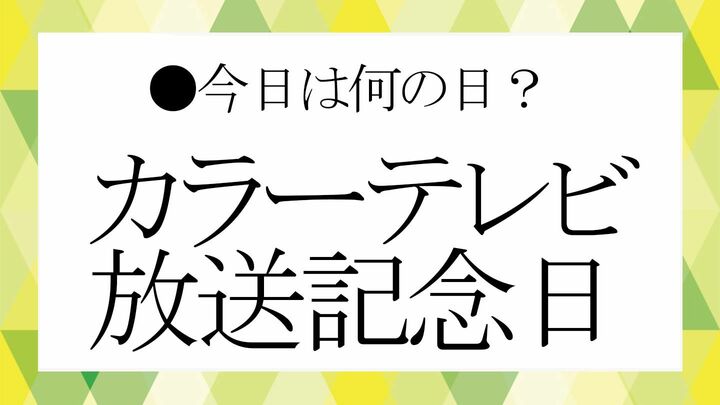【目次】
【「カラーテレビ放送記念日」とは?由来】
9月10日は「カラーテレビ放送記念日」です。日付は1960(昭和35)年のこの日、東京と大阪で、NHK、日本テレビ、ラジオ東京テレビ(現:TBS)、朝日放送、そして読売テレビの5局が、カラーテレビの本放送を開始したことにちなみます。1960年にカラー放送をしたのは、アメリカに次いで世界で2番目となる快挙でした。
【ビジネス雑談に役立つ「テレビ」の雑学】
■「テレビ」とは?
テレビとは、[テレビジョン]の略。映像と音声を離れた場所に送って再生する仕組みや装置(受像機)のこと。放送そのものや放送される番組を指すこともあります。
■「テレビ」という名前の由来は?
「テレビ」の正式名称「テレビジョン(television)」。この言葉の由来のひとつは、ギリシア語で「離れて」を意味する[tele]だといわれています。この[tele]にラテン語の「見る」を意味する[vision]が合成され、[television]に、そしてそれを略して「TV」という表現が誕生しました。
■世界で初めてブラウン管に映像を映した国は?
答えは「日本」です! ご存知でしたか?
ときは1926(昭和元)年、場所は、浜松高等工業(現在の静岡大学工学部)の実験室でした。今では日本の「テレビの父」と呼ばれている高柳健次郎博士が、石英版に書いた「イ」の字の映像を、機械式の円形撮像装置で読み取って電子式のブラウン管に送り、映像を映し出すことに成功しました。
その後、高柳博士は1940年にはNHK(日本放送協会)技術研究所のチームを率いて、テレビの実験放送に成功。第二次世界大戦後も日本のテレビ開発を指揮し、1953年のテレビ放送開始や日本初のテレビ開発、VTRやビデオディスクの開発にも関わりました。
■1950年代、テレビは庶民の「三種の神器」のひとつでした
NHKがテレビ放送を開始したのは1953(昭和28)年2月。8月には民放もこれに続きました。国産初となる14型、17型白黒テレビが発売されると、白黒テレビは洗濯機、冷蔵庫と並び、「三種の神器」と呼ばれるようになりました。サラリーマンの月給が3万円といわれた時代に、テレビのお値段は1台30万円前後だったと言いますから、まさに高嶺の花だったのですね。
ちなみに、1960年代に入ると、庶民の憧れの対象はカラーテレビ(Color television)、クーラー(Cooler)、自動車(Car)となり、この3つの頭文字をとった「3C」が「新・三種の神器」と呼ばれたそうです。
■テレビ放送が始まった当時の人気番組は?
テレビ放送開始直後、テレビはとても高価だったため、なかなか一般家庭には普及せず、人々は繁華街に置かれた街頭テレビに群がりました。人気があった番組は、プロレス・大相撲、プロ野球。スポーツ番組が中心だったのですね。人気プロレス選手だった力道山の得意技は、空手チョップ。野球といえば、「巨人」でした。川上哲治さんなどが活躍し、ミスターこと長嶋茂雄さんが入団するのは1958年です。国民的な人気を表す流行語、「巨人・大鵬・卵焼き」が生まれたのは1960年代ですが、大鵬の初土俵は1956年の9月場所です。
■カラーテレビ普及のきっかけは?
国産初のカラーテレビが発売されたのは、1957(昭和32)年。ですが、日本でカラーテレビの本放送が開始されたのは、その3年後の1960年で、白黒テレビじたいの世帯普及率も、29.1%に過ぎませんでした。
しかし、 1959(昭和34)年には、皇太子殿下(現在の上皇陛下)のご成婚の模様がテレビで放映され、美智子妃殿下(現在の上皇后陛下)のお美しさに「ミッチーブーム」の旋風が吹き荒れます。
そして、カラーテレビが一気に普及するきっかけとなったのは、1964年の東京オリンピックです。開会式や競技の一部がカラー放送で中継されたことにより、カラーテレビの需要が白黒テレビを上回ったのです。とはいえ、当初は外国の映画やスポーツ中継などが中心。NHKの場合、1日1時間ほどしか放送されなかったといわれています。そして、大量生産が可能となり、カラーテレビの価格が下がっていくにしたがって、カラーテレビの所有率は高まり、1975年には90%以上になりました。
■リモコン付きテレビが発売されたのはいつ?
かつてのテレビにはリモコンなどなく、チャンネルは「まわす」ものでした…覚えていますか? 本体から着脱できるリモコン付きテレビが発売されたのは1979(昭和54)年ですから、チャンネルを変えるたびに席を立たなければならない不便さを知っているのは、現在の50代以降ということになります。1979年はタイトーの固定画面のシューティングゲーム『スペースインベーダー』に端を発した「インベーダーゲーム)」が爆発的に流行した年。隔世の感がありますね。
■現在の「家庭テレビのサイズ」の主流は?
高柳博士がけん引したテレビの開発で生まれたブラウン管テレビは、昭和のテレビとしての地位を確立、その後、液晶ディスプレイなどを用いた軽量な薄型テレビが登場し、日本では2015年に生産が終了しました。電子情報技術産業協会のデータによると、2022年の1年間で出荷された薄型テレビの約40%が50インチ以上で、現在、家庭用テレビとして主流になっているのは、50、もしくは55インチのテレビだといわれています。
テレビのインチ数は、本体背面や保証書に記載されている「形名(型番)」を見ればわかりますよ。たとえば「TH-37PX300」なら「37インチ」。「KDL-○○EX720」などの「○○」の部分がインチ数です。
1インチは約2.54cmで、画面の対角線の長さを表しています。従って、50インチのテレビなら、画面の左下から右上までの対角線の長さが約127cmということになります。これはディスプレイ部分のみのサイズで、テレビ全体の外寸とは異なります。覚えておいてくださいね。
■部屋の広さと適切なテレビサイズの関係は?
テレビを快適に見るために必要な視聴距離は、画面高さの3倍程度が理想とされています。
6畳未満 … 32~40インチ
6~8畳 … 40~50インチ
8~10畳 … 50~60インチ
10畳以上 … 65インチ以上
視聴距離が近すぎると画素が目立ち、遠すぎると迫力が失われてしまうそうですよ。
■テレビにまつわるほかの記念日は?
・テレビ放送記念日…2月1日
「テレビ放送記念日」は、1953(昭和28)年の 2月1日 、NHKが日本初のテレビ本放送を行ったことに由来した記念日です。当日は、東京・千代田区内幸町にあった放送会館第1スタジオ(現在の日比谷シティ)から、歌舞伎の一座、菊五郎劇団の「道行初音旅」や映画などが放送されたそうです。当時の受信契約数は868件、受信料は月額200円でした。
・ケーブルテレビの日…6月16日
1972(昭和47)年の6月16日 、有線テレビジョン放送法が成立したことを記念して、ケーブルテレビ事業者などが制定した記念日です。
***
「テレビ離れ」という言葉を耳にしてから久しいですが、最新の調査によると、10代のテレビ視聴時間は、1日たったの39分、20代でもわずか53分。中高年の視聴時間も、軒並み減少しているとか。テレビ離れの原因はいろいろ考えられますが、大きな要因のひとつは「メディアの主役交代」でしょう。インターネットの発達によって、YouTubeやTikTokを初めとした動画共有サイトや、SNSなどの「パーソナルメディア」がメディアの中心となっているのです。この変化はほんの20年程度のなかで起きているんですよね。20年後、メディア界隈はどうなっているんでしょうね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /一般社団法人 家庭電気文化会「家電の昭和史」(https://www.kdb.or.jp/syouwasiterebi.html#:~:text=昭和32(1957)年に,が発売されました%E3%80%82) /電子情報技術産業協会(https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/shipment/2022/index2.htm) :