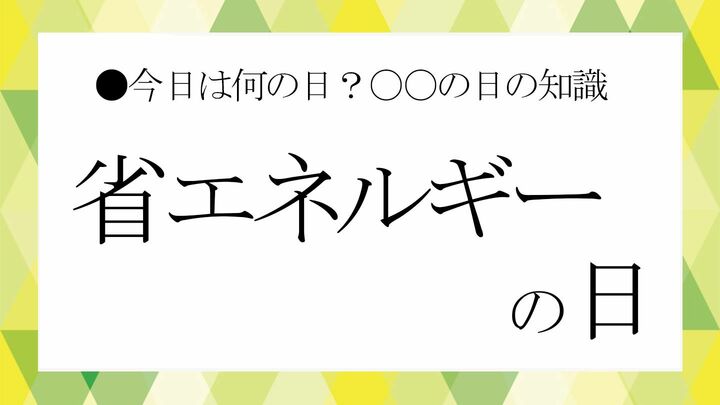【目次】
【「省エネルギーの日」とは?由来】
■「何日」?
「省エネルギーの日」は、毎月1日です。
■「いつ」「誰が」決めた?
1980(昭和55)年3月25日に、省エネルギー・省資源対策推進会議が制定し、4月1日から資源エネルギー庁が実施している記念日です。
■「由来」は?
日本では、毎年2月が「省エネルギー月間」と定められています。これは1977年に「資源とエネルギーを大切にする運動本部」が、国民の省エネルギーへの意識を高め定着を図るために制定したものです。
2月が選ばれたのは、冬季のエネルギー需要期であることから。そして、この「省エネルギー月間」の初日(2月1日)を「省エネルギーの日」としていたものをさらに拡大し、より身近に省エネルギー行動を振り返る機会として生まれたのが、毎月1日の「省エネルギーの日」なのです。地球の化石資源節約のためにエネルギーを大切に使って節約することを促すことが目的となっていて、今日では地方公共団体・企業・家庭などが「省エネルギーの日」「省エネルギー月間」を通じてさまざまな啓発活動を展開しています。
■「省エネルギーの日」に関連する記念日はほかにもある?
前述の通り、毎年2月は「省エネルギー月間」として、国民に省エネルギーの意識を高めてもらう期間とされています。
さらに、8月1日は「夏の省エネ総点検の日」、12月1日は「冬の省エネ総点検の日」として定められています。これらは、冷房・暖房などによってエネルギー使用量が増える時期に合わせて、家庭や職場で省エネルギーの見直しを促すためのものです。
いずれも、生活の中で省エネを意識し、地球環境や資源の大切さについて考えるきっかけとなることを目的としています。
【今日からできる「省エネ」と「効果」の豆知識】
■家電製品で消費電力が高いものは何?
夏期・冬季ともに電力消費が特に大きい機器として、エアコン、冷蔵庫、照明器具が挙げられます。例えば、関西電力のデータでは「エアコン14.7%、冷蔵庫14.3%、照明13.5%」と、これら3つだけで家庭全体の電力消費の半分以上(約52%)を占めているという結果があります。
つまり、節電を進めるうえでは、これら3大家電の使い方を見直すことが大きなポイントです。効率良く消費エネルギーを抑えることで、おサイフと地球環境にやさしい省エネライフを始めましょう。
■エアコンの省エネレッスン
冷房時の工夫
・ドア・窓の開閉は少なく。
・レースのカーテンやすだれなどで日差しをカット。
・外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的。
・扇風機を併用。風がカラダにあたると涼しく感じます。
暖房時の工夫
・冬の暖房時の室温は20℃を目安に。毎日、設定温度を1℃下げるだけで、ひと冬で、約1,430円の節約に!
・ドア・窓の開閉は少なく。
・厚手のカーテンを使用。床まで届く長いカーテンの方が効果的。
・扇風機を併用。暖まった空気を循環させましょう。
※適宜、換気をしましょう
室外機のまわりに物を置かない。
・室外機の吹出口にものを置くと、冷暖房の効果が下がります。
月に1回か2回、フィルターを清掃。
■冷蔵庫の省エネレッスン
熱いものはさましてから保存する!
麦茶やカレー、シチューなど、温かいものをそのまま冷蔵庫に入れていませんか? 庫内の温度が上がって、冷やすのに余分なエネルギーが消費されてしまいます。
庫内の温度設定は適切に
庫内の温度を控えめに設定すると消費電力が小さくなります。設定が「強」になっていたら「中」にして、しばらくの間は食品の傷みぐらいなど、様子を観察しながら調整して。
冷蔵庫の中は整理整頓を
期限切れのものや食べ残した食品が、冷蔵庫の奥で眠っていませんか?「とりあえず保存」は、結局、捨てられることも多いようです。また、缶詰、びん詰や調味料のなかには、常温保存可能なものもあります。常温保存できるものを冷蔵庫に入れるのは、電気の無駄使いにつながります。冷蔵庫に、物を詰め込んだ場合と、半分にした場合では、年間の電気代が約1,360円程、違うそうです!
冷蔵庫の扉の階へ時間はできるだけ短く。
無駄な開閉はしない。
冷蔵庫は、壁から適切な間隔を置いて設置する。
冷蔵庫の上と両側が壁に接している場合と、片側が壁に接している場合の比較では、年間1400円も電気代が違います。環境省では、隙間の目安は5センチとしています。
■ガスコンロの省エネレッスン
鍋をコンロにかけるときは、水滴をふき取ってから
底が濡れたままだと、水を蒸発させるのに、余分なエネルギーが必要になります。
鍋は平たい底が省エネ
鍋ややかんは丸い底のものより、平たい底の方が熱効率が良く、省エネにつながります。
点火のタイミング、気をつけてる?
コンロに点火するのは、鍋ややかんをのせてからにしましょう。
■食器洗い乾燥機の省エネレッスン
条件次第ですが、手洗いよりも食器洗い乾燥機のほうが、省エネにつながりやすいという試算があります。
たとえば、給湯器を使用して40 ℃のお湯で洗い、1回あたり約65 Lを使用する手洗い(冷房期間は給湯器を使わない想定)と、給水接続タイプの食器洗い乾燥機を標準モードで使用した場合を比較すると、年間で約6,000円以上光熱費が節約できるという報告も出ています。
※手洗い・食器洗い乾燥機ともに1日に2回使用するという条件による試算です。
乾燥は余熱で!
洗浄終了後、扉を開けて余熱だけで乾燥させれば省エネにつながります。
コースを上手に使い分けて
食器の点数が少ないときは、「少量コース」等を選びましょう。
洗剤の適量、守ってる?
少なすぎると洗浄力は落ちますが、洗剤を多く入れすぎても洗浄性能はほとんど変わりません。
ちょっとひと手間で洗い上手に
食器の残菜を丁寧に捨てるなど、あらかじめ前処理をしておくと汚れ落ちがよくなります。
■エアコンは「つけっぱなし」がお得?
エアコンはこまめに切るより、つけっぱなしの方がお得だと聞いたことはありませんか? 温度調整や節電を意識してスイッチのONOFFを繰り返すと、エアコンの運転開始時は電気を多く使うので、かえって電気を消費してしまう、というのがその理由です。この件について、空調事業を展開する「ダイキン」が、同社で行った実験結果から、エアコンの上手な運転方法を提案しています。
結果:外気温が高く設定温度との差が大きい時間帯では、つけっぱなしのほうが消費電力量が少なくなる
・日中(9:00~18:00)は、35分までの外出であれば、エアコンを「つけっぱなし」の方が安い。
・夜間(18:00~23:00)であれば、18分までの外出であれば、エアコンを「つけっぱなし」の方が安い。
日中は30分程度の外出ならエアコンをつけっぱなしにして、夜間はこまめに停止させるといった調整を行うことで、お得な運転ができるようです。
■野菜の下ごしらえ。茹でるのと電子レンジ、どちらがお得?
実は、野菜の下ごしらえには電子レンジの方が省エネでお得なケースが多いんです! たとえば、100gの食材を1Lの水(約27℃)に入れて茹でるのと、電子レンジで加熱するのとを比べると、年間でおよそ1,000円近く節約できるという試算もあります(1日1回使用を想定)。
もちろん、食材の量や加熱方法によって差はありますが、「下ごしらえに電子レンジを使う」というちょっとした工夫が、毎日の省エネにつながるんですね。
■ごはんは炊飯器で保温するのと電子レンジで温め直し。どちらが省エネ?
答えは、電子レンジでチン! ごはんを炊飯器で保温する目安は、4時間まで。これ以上の時間だと、保温のためのエネルギーより、電子レンジで温め直すエネルギーの方が少なくなります。
■PC(パソコン)の電気代節約に有効なのは?
PCは「起動するときがいちばん電気を使う」といわれていますが、使わないときは電源をおとしたほうがいいのか、スリープ状態にしておいた方がいいのか…。迷いますよね。 Microsoftの調査によると、ボーダーラインは「90分」なのだそう。つまり、90分以上使わないならシャットダウン、90分以内ならスリープの方が省エネになるそうです。「一日中、スリープ状態」だった人は、さっそく今日から実戦してくださいね。
***
毎日の「省エネ」を心掛けていますか? あまり厳密にマイルールを設けると疲れてしまいますが、電子レンジや食器洗い乾燥機など、文明の利器を効率的に使うことで、思わぬ省エネにつながるケースは少なくありません。上手に活用して、省エネ&快適に、毎日を過ごしたいですね!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /経済産業省 資源エネルギー庁(https://www.enecho.meti.go.jp) /東京電力パワーグリッド(https://pgservice1.tepco.co.jp/2022/12/01/environment/#:~:text=月01日-,12月1日は「冬の省エネ総点検,コラムを紹介します!) /東京ガス暮らし情報メデイア「ウチコト」(https://uchi.tokyo-gas.co.jp/categories/saving) /ダイキン(https://www.daikin.co.jp/air/life/issue/mission05) :