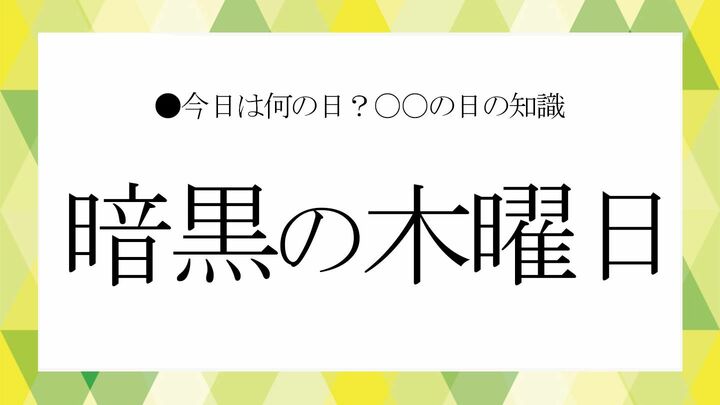【目次】
【「暗黒の木曜日」とは?概要】
「株」や「投資」に興味のある人や仕事で関連のある人なら「暗黒の木曜日」というフレーズを聞いたことがあるでしょう。一方「株」とは無縁の人には「Amazonのブラックフライデーなら知っているけど…」などと、なんのことか全くわからないかもしれません。
1929年10月24日木曜日、米国ニューヨーク株式市場で記録的な大暴落が起こった日を指します。通常、この暴落の始まりを象徴する出来事として扱われ、[Black Thursday]、日本語では「暗黒の木曜日」と呼ばれ、「世界恐慌の伏線」ともされています。
当日、株式売買量は約1,290万株に達し、パニック的な売りが始まりました。株価だけでなく、銀行の倒産、生産能力の低下、貿易の縮小など幅広く影響を及ぼしました。この暴落は世界経済の中心地であったウォール街で発生したことから、「ウォール街大暴落」と呼ばれることもあります。
【ビジネス雑談に役立つ「暗黒の木曜日」にまつわる雑学】
■イケイケ経済から「暗黒の木曜日」へ
1914年~1918年の第一次世界大戦後、主戦場となったヨーロッパ諸国では戦後処理に追われましたが、ダメージが少なかったアメリカの経済は急成長を遂げました。それまで世界経済の中心だったイギリスを追い抜く勢いでアメリカは世界最大の経済大国に躍進しました。
富裕層や特権階級が豊かになるだけでなく、自動車や家電製品といった日用品から、ラジオやテレビ、映画など大衆の生活も文化も発展。その繁栄は永遠に続くかに見えていたので、1929年10月24日の株価大暴落は「暗黒の木曜日」と呼ばれるほどの衝撃だったのです。
■なぜ「暗黒の木曜日」は起こった?
この1929年のウォール街株価大暴落(いわゆる「暗黒の木曜日」などを含む株価大暴落)の原因は、100年近く経った現在もはっきりとは解明されていません。ただし、以下のような複数の要因が重なったと考えられています。
・好景気の裏で進んでいたゆがみ:第一次世界大戦後のアメリカは著しい経済発展を続けていましたが、1920年も後半になると大量生産による商品の飽和が起こります。これは戦時中に拡大した農業にも及び、戦後は需要が落ち着いたにもかかわらず生産量は減らず、余剰在庫があふれる結果に。さらに自国の生産力を守るためにヨーロッパ諸国がアメリカからの輸入関税を引き上げたことで、農業も大不況となったのです。そして1929年の大豊作が農産物の価格を引き下げ、生産者の利益が薄い「豊作貧乏」を生みました。
・投機的な株式市場の膨張: 第一次世界大戦後のアメリカの好景気は、「株を買えば儲かる」という過熱した投資ブームを起こしました。しかし、1929年には過熱しすぎた投資を抑制するための利上げなどが起こります。そして一部の投資家が株の投げ売りを始める事態に。
・信用・金融システムの脆弱性:銀行・持株会社・投資信託が大量の負債を抱え、さらに中央銀行(連邦準備制度理事会)による信用引き締め(例:利上げ・割引率の引上げ)が市場の流動性を圧迫しました。
これらの要因が複雑に絡み合い、10月24日からの株価下落・売りの連鎖を誘発したと考えられています。
■「悲劇の火曜日」も!
ウォール街で最初に株価大暴落が起きたのは10月24日(木)でしたが、その後の週明け、28日(月)と29日(火)にも壊滅的な大暴落が続きました。
週末の間に「暗黒の木曜日」の衝撃を全米各紙が大々的に報じたことによって、市場には不安の混乱が広がります。投資家は追加証拠金が必要となり、手持ち株の現金化を迫られて売り注文が殺到。特に29日(火)には前場のみでダウは12%下げ、市場が閉鎖されるという緊急事態に発展しました。
当然のことながら多くの投資家はパニックに陥り、その損失を埋めるため資金は回収され、アメリカ経済に依存していた他国の経済も連鎖的に破綻。これを[Tragedy Tuesday]、「悲劇の火曜日」と言います。アメリカの株価大暴落は約1か月間続いたため、世界の株式市場まで大きく揺るがす事態となったのです。
■「暗黒の木曜日」を上回った「ブラック・マンデー」
「暗黒の木曜日」から約60年後の1987年10月19日(月)、ニューヨーク株式市場を襲った歴史的な暴落が[Bluck Monday]です。日本語でも「暗黒の月曜日」より「ブラック・マンデー」という呼び方が一般的に使われています。
この日、ダウ平均株価は過去最大の下落率を記録し、1日で約22.6%も暴落。これは1929年の「暗黒の木曜日」をも上回る急落でした。しかし、各国が迅速に協調して金融政策や経済対策を実施したことで、「世界恐慌」のような長期にわたる大不況には至りませんでした。
ブラック・マンデーは、現代の金融市場のリスク管理や国際的な連携の重要性を浮き彫りにした出来事として、今なお語り継がれています。
■記憶に新しい「リーマン・ショック」
いわゆる「リーマン・ショック」は、アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが、2008年9月15日に経営破綻したことで引き起こされた世界的な金融危機です。
背景には、2000年代初頭から続いた、アメリカの住宅バブルがありました。信用力の低い層(サブプライム層)への住宅ローン=「サブプライムローン」が大量に供給され、これが証券化されて世界中の金融機関に販売さrていたのです。
バブル崩壊とともに住宅価格が下落し、多くのローンが不良債権化します。世界有数の投資銀行であったリーマン・ブラザーズは巨額の損失を抱え、最終的に破綻。これにより信用不安が連鎖的に広がり、株価は下落。世界的な大不況を引き起こしたのです。
***
「株」も「投資」もぐんとカジュアルになった現代。むしろ個人資産の運用は当たり前という時代ですね。「暗黒の木曜日」や「ブラック・マンデー」のような、経済パニックを振り返り、その教訓に学ぶことが大切です。再び同じような混乱が起こらないことを祈りつつ、冷静な判断力と情報リテラシーを持って投資と向き合っていきたいものですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『ブリタニカ国際大百科事典』(ブリタニカ・ジャパン)/『共同通信ニュース用語解説』(共同通信社)/『現代用語の基礎知識』(自由国民社) :