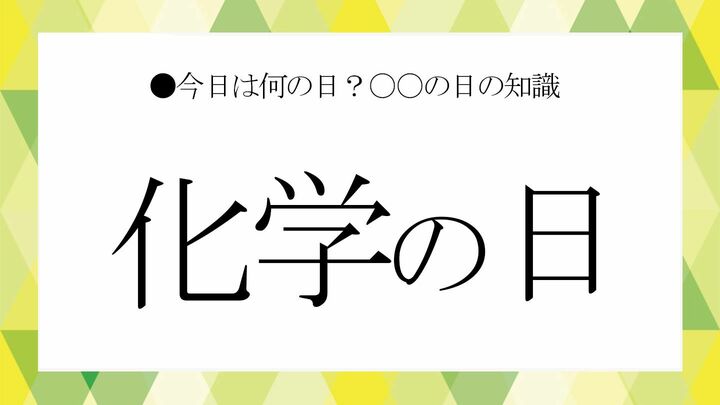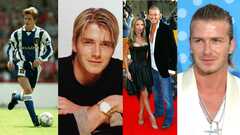【目次】
【「化学の日」とは?由来】
■「何日」?
「化学の日」は10月23日です。
■「いつ」?「誰が」? どんな 「目的」で決めた?
おの記念日は2013年に、日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会、日本化学工業協会の4団体によって制定されました。
目的は、化学と化学産業の魅力や社会への貢献を、より多くの人に知ってもらうこと。10月23日を「化学の日」とし、この日を中心に、「化学の日」を含む月曜日から日曜日までの1週間は「化学週間」としても設定され、小学生から一般の人までを対象とした化学実験の教室や講演会、研究発表会、フォーラムなど、さまざまなイベントが開催されています。
■日付の「由来」は?
10月23日という日付は、アボガドロ定数(6.02×10の23乗)にちなんでいます。
アボガドロ定数は、物質の基本単位である「1mol(モル)」あたりに含まれる粒子(原子や分子)の数がを表したもの。この数字にちなみ、「10月23日=6.02×10²³」という語呂合わせ的な要素で選ばれました。
【ビジネス雑談に役立つ「化学」の雑学】
■そもそも「化学」って何? 「アボガドロ定数」って?
化学は自然科学のひとつで、「物質」を扱う学問です。原子や分子といった小さな構成要素を単位として、宇宙や地球に存在するあらゆる物質の構造や性質を探る学問分野。実験や実習が多い学問としても知られています。
「mol(モル)」は、メートルやキログラムなどと同じく、物質量を表す国際単位系(SI)の基本単位のひとつです。
アボガドロ定数とは、物質量 1 mol に含まれる基本的粒子(原子・分子・イオンなど)の数を示す定数で、値は 6.022140 76 × 10²³ mol⁻¹ と定められています。
この概念の起源は、イタリアの科学者アメデオ・アボガドロ(1776‑1856)が「同一の温度・圧力・体積条件下では、すべての気体に同じ数の分子が含まれる」という仮説(アボガドロの法則)を提唱したことにあります。
■日本のノーベル化学賞受賞者とその功績
2025年のノーベル章は、生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文氏が、化学賞に京都大学特別教授の北川進氏が、それぞれ共同研究者と共に選ばれました。北川氏は気体を自由に出し入れできる「金属有機構造体(MOF)の開発」が評価され、環境・エネルギー問題や新素材開発など広範な分野での応用が期待されています。
日本人がノーベル化学賞を受賞するのは久しぶりのことであり、過去には吉野彰氏(2019年/リチウムイオン電池の開発)、根岸英一氏・鈴木章氏(2010年/パラジウム触媒を用いた有機合成)などが受賞しています。
以下に日本のノーベル化学賞受賞者とその功績を簡単に紹介します。
受賞年:2025年
受賞者:北川進 博士(京都大学特別教授)
受賞理由:金属有機構造体の開発
受賞年:2019年
受賞者:吉野彰 博士(旭化成株式会社名誉フェロー)
受賞理由:リチウムイオン電池の開発
受賞年:2010年
受賞者:根岸英一 博士(米国パデュー大学特別教授)
受賞理由:有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング
受賞年:2010年
受賞者:鈴木章 博士(北海道大学名誉教授)、根岸英一 博士(岡山大学名誉教授)
受賞理由:有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング
受賞年:2008年
受賞者:下村脩 博士(米国ボストン大学名誉教授)
受賞理由:緑色蛍光タンパク質の発見とその応用
受賞年:2002年
受賞者:田中耕一 氏(株式会社島津製作所フェロー)
受賞理由:生体高分子質量分析のソフトデソープションイオン化法の開発
受賞年:2001年
受賞者:野依良治 博士(独立行政法人理化学研究所理事長)
受賞理由:不斉触媒による水素化反応の研究
受賞年:2000年
受賞者:白川英樹 博士(筑波大学名誉教授)
受賞理由:導電性高分子の発見と開発
受賞年:1981年
受賞者:福井謙一 博士(京都大学名誉教授)
受賞理由:化学反応過程の理論的研究
■2025年のノーベル化学賞「金属有機構造体(MOF)の開発」ってどんなこと?
北川進博士が開発した金属有機構造体(MOF)とは、無数に開いた極小の穴に、狙った気体を取り込んで、分離・貯蔵ができる新しい材料です。金属イオンと有機物の組み合わせから成り、ナノサイズ(ナノは10億分の1)の骨組みの中に無数の穴が開いているという構造をもち、表面積が非常に大きいことが特徴。
MOFは、わずか1グラムあたり、実にサッカー場1面に相当する表面積をもつものもあります。大きさや性質を自由に設計することが可能で、特定の気体を穴の中に閉じ込めることができるのです。工場や商業施設での臭い除去や精密機器の保護などの実証実験、応用研究が増えつつある段階にあり、今後は地球温暖化問題の解決など、地球環境、エネルギー、資源といった、幅広い分野での活用が期待されています。
ただし、実用化段階には課題も残っており、私たちの暮らしに広く浸透するには今後のさらなる技術進化とコスト低減が鍵となります。
■あれも化学、これも化学。その1。「ファンデーションの化学」って?
女性が肌を美しく見せるためにおしろい(白粉)を塗り始めたのは、世界では紀元前に遡るといわれていますが、それが日本に伝わったのは7世紀ごろ。当時、おしろいに使われていたのは鉛を含む化合物があり、庶民から貴族までがこぞって使用していたとか。
しかし、鉛化合物が有毒であることがわかるにつれ、江戸時代後期以降からおしろいで肌を白くする化粧はすたれていき、素肌をきれいに見せるための薄化粧にシフトしていきました。
色付きの白粉=肌色のファンデーションが登場した背景には、真っ白な肌よりも「自分の肌色に近づけて自然に見せたい」という美意識の変化があります。こうして、自分の肌色に合わせて選ぶ肌色のファンデーションが開発されるようになりました。
では現在、私たちが日常使っているファンデーションには、どのような物質が配合されているか、ご存知ですか?
まず、肌を明るく見せたり、紫外線を遮る目的で使われるのが酸化チタンです。これは日焼け止めにも使われる顔料、遮光剤です。
ただ、酸化チタンだけでは真っ白な印象になってしまうため、赤色顔料や黄色顔料をバランスよく配合することで「肌色」を調整します。
そして厚塗り感を防ぐためには、細かな粉体(ふんたい)を使って光の散乱を利用して“透明感”を演出する設計がなされています。粉体の粒子による微細な凹凸は光を拡散させ、自然な肌映りを生み出すだけでなく、撥水性、撥油性も高め、汗や皮脂に強くなるといった役割も果たします。
最近では、ファンデーションの“密着感”を向上させるため、ポリマー(高分子)による膜形成技術が用いられる処方も増えています。ただし、その分クレンジングで落ちにくいという課題もあり、肌に残留して炎症を引き起こさないよう、「クレンジングでの落としやすさ」に注目して開発された処方や、「ミネラルファンデーション」として、無機顔料主体の処方も多く見られます。
こうしたファンデーション一つをとっても、化学の知見が“肌を美しく見せる”という目的に深く関わっているのがわかるでしょう。
■あれも化学、これも化学。その2。香水の化学
人間はもちろん、生物が「匂い」を感じるためには、鼻腔の受容体が物質をキャッチし、刺激が伝わる必要があります。液体や固体のままでは鼻腔まで届かないので、香りを発する物質には、揮発性が必須なんですね。
香水といえば、「トップノート」「ミドルノート」「ラストノート」という3段階の香りの変化があることは広く知られています。
・トップノート:つけた直後~5~15分程度
・ミドルノート:30分~3〜4時間程度
・ラストノート:4時間~半日程度
このように、ひとつの香水でも時間差で異なる香りを楽しむことができるのは、香りの成分となる化合物の揮発性が異なるからです。
たとえば、トップノートは比較的軽い成分で構成されており、すぐに空気中へと揮発して最初の印象を与えます。ミドルノートでは、少し重めの香りが中心になり、香水の“個性”が際立ちます。ラストノートはさらに揮発しにくい成分によって構成され、肌に残る落ち着いた香りを長く楽しめます。香水をデザインする調香師は、化合物を絶妙なバランスで混合し、香りが立つ時間までも計算していることになります。香水は単なるファッションアイテムなだけでなく、化学の知の結晶だったのです。
■あれも化学、これも化学。その3。保湿の化学
一般的に、スキンケアの流れは「洗顔→化粧水→乳液→クリーム」とされています。これは科学的にも理にかなった順番です。まず、化粧水で角質層を水分を補給します。ところが水はすぐ蒸散してしまうため、そのあとに乳液やクリームで油分を補い、まるでふたをするように水分を閉じ込める必要があります。
では、乳液とクリームの化学的な違いは何だかわかりですか?
いちばん大きな違いは、油分と水分のバランスです。乳液やクリームは、油分と水分が混ざっている状態です。本来、水と油はお互いに不溶で分離してしまうものですが、界面活性剤という親水部と親油部をもつものを入れて撹拌することで、お互いに混ざり合った白く濁った状態になるのです。この乳化した状態において、水分を多く含んでいるのが乳液、油分を多く含んでいるのがクリームです。
スキンケアのひとつひとつに「なぜこの順番なのか」「この成分がどうはたらくのか」を理解すると、より効果的に肌を守ることが可能です。化粧品は“美しさ”だけではなく、化学の知識に支えられた技術の結晶なのです。
■あれも化学、これも化学。その4。シャンプーの化学
毎日、何気なく使っているシャンプーですが、「どうして汚れが落ちるの?」と不思議に思ったことはありませんか?
シャンプーには、頭皮の汚れの除去のために界面活性剤が配合されています。頭皮の汚れは主に油分ですが、それを水で洗い流そうとしても油と水は分離してしまうためになかなか汚れは落ちません。ところが、界面活性剤を使うと、頭皮の汚れの油分と界面活性剤の親油部がくっついて、界面活性剤の親水部の周りに水が集まります。こうなると、界面活性剤が媒体となるかたちで汚れの油分が水中に取り込まれ、浮かせて洗い流すことができるのです。
多くのシャンプーはアニオン性界面活性剤(負電荷をもつもの)が主成分として使われることが多く、油汚れを落とすのに特化しています。また、髪の毛はアニオン性のタンパク質。アニオンとアニオン同士は静電的に反発することから、アニオン性界面活性剤は洗い残しが発生しづらいといったメリットもあるそうです。だたし、シャンプーには、アニオン性界面活性剤のみならず、両性界面活性剤・ノニオン界面活性剤・ポリマー・シリコーンなども併用されています。
ですから、髪の「洗い残し」を防ぐためには、すすぎ工程も重要です。しっかりと水ですすぎ、界面活性剤や洗浄残留物が頭皮・髪に残らないようにすることで、かゆみ・ごわつき・べたつきなどを防ぐことができます。
“シャンプー=キレイにする”というシンプルなイメージの裏に、化学的な知見がきちんと活かされていることがわかると、日々のケアも少し新鮮に感じられるかもしれません。
***
いかがでしたか? 化学とは、原子や分子といった小さな物質を単位に、宇宙や地球に存在するあらゆる物質の構造や性質を研究する学問です。研究室や白衣といったイメージから、「自分たちの日常とは縁遠いもの」と感じる人もいるかもしれませんが、実は香り・スキンケア・シャンプー・お洗濯など、私たちの暮らしの中にあるさまざまな製品は、化学の知識がなければ生まれなかったものばかりです。「化学の日」をきっかけに、化学が少しでも身近な存在として感じられるといいですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社)/公益財団法人 日本化学会(https://www.chemistry.or.jp/know/molday.html) /一般社団法人 日本化学工業組合「10月23日は化学の日 コラム 」(https://www2.nikkakyo.org/system/files/column332.pdf) /理科・科学の雑学(https://www.kyoushi1.net/column/? :