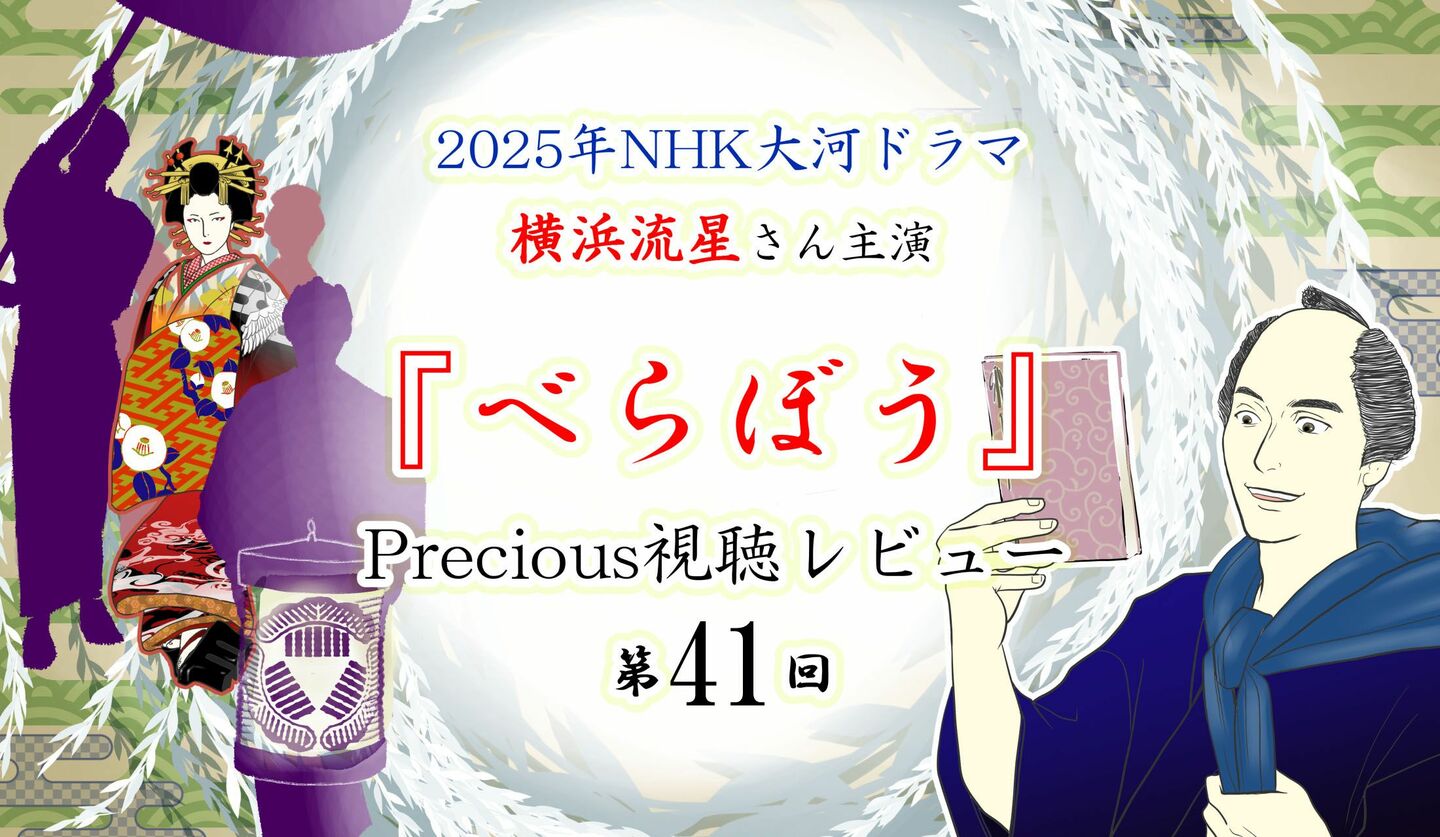【目次】
【前回のあらすじ】
「江戸の出版王」や「敏腕出版プロデューサー」などと呼ばれる蔦屋重三郎(横浜流星さん)の実力が、遺憾なく発揮された第41回放送「歌麿筆美人大首絵」。感心しきり、泣きどころ満載、切なさで胸いっぱいな回でしたね。出版関連のエピソードをざっとおさらいしてみると…。
オロシャ(ロシア)が江戸を攻めてくる可能性について書かれた本を出版して身上半減となった須原屋(里見浩太朗さん)は、高齢ということもあって引退を決意。浮かれて華やいだ江戸の町よ再び…という思いを蔦重に託します。
同時に須原屋は、知らないのは怖いこと、本屋には正しい世の中のためなることを知らせる役目があるのだと改めて説きます。平賀源内(安田顕さん)風に言えば、それは「書をもって世を耕す」――蔦重の「耕書堂」という店名の由来でしたね。蔦重は本屋としての誇りとプライドをもって、世のためにという決意を新たにしたようです。
幕府による規制や懲罰にもへこたれず、何度でもよみがる。耕書堂は娯楽本を扱う地本問屋でしたが、蔦重はお堅い教科書的な本(書物)を扱う書物問屋の株も手に入れたため、これからは書物の新刊もバンバン出していくと宣言。お堅い書物に通じている妻のてい(橋本愛さん)に「企画案30本提出!」と命じ、「無理です無理です無理です無理です」と固辞していた彼女も見事に蔦重の期待に応えました。それが、高名な書家で和学者の加藤千蔭(ちがげ/中山秀征さん)に依頼してでき上がった法帖(ほうじょう/書の手本帖のこと)『ゆきかひふり』です。
美しい「書」は眺めるだけでも楽しく、そんな「書」を書きたい女性は大勢いるはず。法帖を扱う書物問屋に女性は入りにくいけれど、地本問屋だが書物も扱う耕書堂なら気兼ねなく店に入って手に取ることができる――と考えたわけですね。
しかも内容は『源氏物語』からの抜粋という超女子好み! さらに、黒地に白抜き文字という美しさ! この 『ゆきかひふり』は後摺(重版・再販)も多く残っていて、ヒット作だったことがうかがえます。加藤千蔭の美しい連綿体は「千蔭流」と呼ばれ、明治期になっても歌人の間で流行、樋口一葉も千蔭流の書を学んだそうです。
でき上がった『ゆきかひふり』や黄表紙の再印本(再販本)などを持って尾張出張へ出かける蔦重の髪を、実母のつよ(高岡早紀さん)が結うシーンも胸アツでした。
親に捨てられ、吉原の駿河屋夫妻(高橋克実さんと飯島直子さん)に育てられた蔦重でしたが、その真相が初めて明かされ、母子の素直な情が交わされましたね。「ババァ」「あんた」と呼び合っていたふたりが、「重三郎」「おっかさん」って――(泣)。
歌麿にも母のような気遣いを見せるつよ。蔦重への想いを封印し、「きれいな抜け殻だけが残ることが望み」だと語る歌麿とのやりとりは、緑いっぱいの庭を背景にふたりのシルエットが浮かび上がる、まるで絵画のような素敵なシーン、見事な演出でした。
【手元で楽しむ浮世絵版画、ここに極まる!】
前々回「尽きせぬは欲の泉」で蔦重&歌麿が制作に取り掛かった「婦人相学十躰」は、「浮気之相」「おもしろキ相」」「浄(きよ)キ相」の3作の試し摺りが上がってきました。出来は悪くないのに蔦重は「地味じゃねぇか」と今ひとつな様子でしたが、手に取って眺めているうちに背景を雲母摺(きらずり)にすることを思いつきます。
人物の周りがキラキラすれば淡く地味な色もおもしろく見えるんじゃないか、贅沢な気分にもなれるし、雲母(うんも)は金や銀より安価で、何より「見たこともない錦絵」になる! 通例や常識にとらわれずに人を喜ばせるものをつくりたいと願う、蔦重会心の思いつきでした。
これは浮世絵版画が壁に飾って鑑賞するものではなく、手に取って間近で楽しむものだったことに由来するもの。手に取るのであれば、正面からだけでなくさまざまな角度から見ることができます。蔦重も、平らに持ち上げて見ていましたよね。
雲母摺は金銀箔や金銀泥のようなパッとした華やかさはありませんが、じっくりいろいろな角度から眺めると、雲母が明るさや光の当たり具合によってキラキラっとします。暗くなれば蝋燭が主な光源だった江戸時代、ゆらゆらと揺れるろうそくの灯りで見ると、描かれた人物が浮き上がって見えたりも。蔦重、やっぱり天才です!
しかもその売り出し方もすごかった。そもそも『南北相法』という人相学の本をヒントにした「婦人相学十躰」です。売れっ子人相見(人相占い師)の大当開運(おおあたりかいうん/太田光さん)を耕書堂に呼び込み、占い目当てで来店した人相学に興味のある客に「婦人相学十躰」を売ろうという魂胆です。
しかもそこへやって来た歌麿を担いで「今日は特別に歌麿先生が名入をしてくださいます!」と、急きょサイン会を催す始末。あきれるほどの商魂ですね。
■庶民の楽しみからアート作品へ
「錦絵(にしきえ)」と呼ばれる多色摺りの浮世絵版画は、ヒット作は何度も重版されて江戸市中のみならず全国に広まったため、現在も古書店などで販売されていることもあります。初版はもちろん、摺りや保存状態のいい作品のなかには美術館級、古美術級のものも少なくありません。
2025年は『べらぼう』にあやかってか、蔦重や浮世絵関連の美術展が目白押し。そんななかでも話題となったのが、今年の4月から6月にかけて東京国立博物館で開催された特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」で、「婦人相学十躰」の「浄キ相」(のちに「ポッピンを吹く娘」と呼ばれる作)の最初期ものが公開されたことです。
そもそも東京国立博物館は、途中でシリーズ名が「婦女人相十品」に変わってからの「ポッピンを吹く娘」を所蔵しています。しかしこの展覧会で「新発見!」として後期に公開されたのは、パリの画商エルンスト・ル・ヴェールがかつて所有していた「婦女人相十躰」の「ポッピンを吹く娘」(寛政4~5年、1792~93年ごろ)。エルンスト・ル・ヴェールは、19世紀末から20世紀初頭にヨーロッパでジャポニスムが流行した影響で浮世絵を愛好し、明治期に数回来日して数百枚もの浮世絵を購入したと伝わる人物です。
ややこしいのですが、最初期の「婦女人相十躰 ポッピンを吹く娘」が確認されていたのはハワイのホノルル美術館所蔵の1点のみでしたが、それが日本国内でも発見されて話題になったのです。
今でいえば雑誌1冊程度の金額で買えた、庶民の手頃なお楽しみだった浮世絵版画。美術館級に保存状態のよい作品は線がシャープで、色出しも絵師や版元の意向がしっかり反映されています(後摺りになるほど板木は摩耗してシャープではなくなり、色合いも変化していくことがありました)。美術展で展示されるものは、やはりわざわざ見に出かける価値があるというわけです。
■蔦重が仕掛けた写楽の衝撃デビュー作にも雲母!
さて、「歌麿の美人大首絵」は間違いなく出版プロデューサー蔦屋重三郎の仕事を代表するものですが、もうひとつ…そうです、「東洲斎写楽」という絵師も、蔦重の仕事の代表作です。
放送開始前から「『べらぼう』では写楽を誰が演じるのか」「その正体はどう描かれる?」「そもそも写楽は登場するのか」などと話題になっていましたね。写楽の正体は実は北斎だとか、いや蔦重なんだとか、ぶっ飛んだ推測もありますが、最近は阿波徳島藩お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛であるという説に落ち着きつつあるようです。放送があと7回となった『べらぼう』では、ドラマガイド本を探っても斎藤十郎兵衛の登場はなく、ほかの方法で東洲斎写楽をつくり上げています。脚本家の森下佳子さんがどんなロジックで“べらぼうでの写楽誕生”を描くのか楽しみです!
写楽といえば、まったくの新人絵師が大判錦絵28作の役者絵で衝撃デビューし、正体を明かさないままわずか10か月でこつ然と消えた――というエピソードが先行しがちですが、そのデビュー作にも背景に雲母が使用されています。わかりやすいのは「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」という作品。懐からパッと開いた手を出し「金を出せ!」と迫る、目つきの悪いあのオトコです。真っ暗な舞台上の役者にスポットライトが当たっている様子を、漆黒の背景に雲母を使用して表現しました。
歌舞伎の人気役者や、人気演目のシーンを描いた役者絵はブロマイドやポスターなのですから、見て美しく、すてきであることが大前提。多少(かなりの場合も?)いいオトコ方向への修正や加工は当たり前なのです。しかし写楽の役者絵がウケたのは、その役者の必ずしもすてきではない特徴まで誇張したことにありました。人物画としておもしろいことが重要で、歌舞伎を見たことがなくても、その役者のファンでなくても「おもしろいから買う」と購買層を広げたところに勝算あり!なのです。 当然ながら、 役者本人や一部のファンには不評だったようですが…。
【次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第42回「招かれざる客」のあらすじ】
歌麿(染谷将太さん)の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重(横浜流星さん)は、年が明けて身上半減から店を立て直した。歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。そんななか、てい(橋本愛さん)は蔦重に“子ができた”と告げる。
一方、定信(井上祐貴さん)は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第41回「歌麿筆美人大首絵」のNHK ONE配信期間は2025年11日2日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 完結編』(NHK出版)/『江戸の人気浮世絵師 俗とアートを極めた15人』(幻冬舎新書)/『浮世絵の歴史 美人絵・役者絵の世界』(講談社学術文庫)/『教えてコバチュウ先生! 浮世絵超入門』(小学館) :