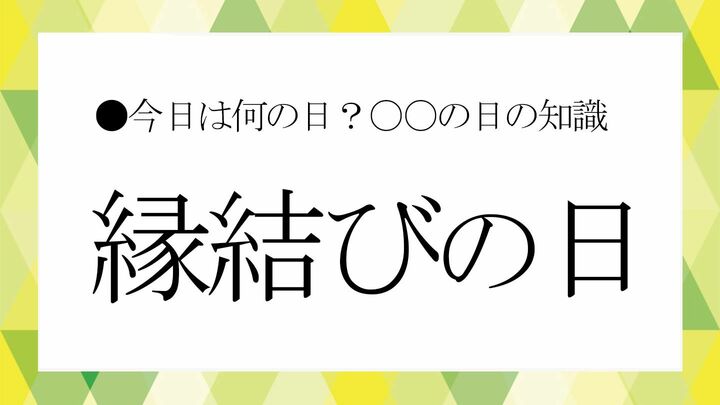【目次】
【11月5日は「縁結びの日」由来は?】
■「縁結びの日」とは?
「縁結びの日」は、神話の国 縁結び観光協会が制定し、現在では公益社団法人島根県観光連盟が継承している記念日です。
■なぜ11月5日?
日付は「11(いい)」「ご(5)縁」という語呂合わせから。「いい」と読める11月は記念日も多く、22日の「いい夫婦の日」や29日の「いい肉の日」なども知られているところですね。
■「縁結びの日」の由来
「縁結びの日」は、島根県出雲市に鎮座する出雲大社が、古くから縁結びのお社として信仰されてきたことに由来します。日本では「和風月名(わふうげつめい)」と呼ばれる旧暦の月の呼び名(異称)がありますね。いくつかおさらいしてみましょう。
・1月「睦月(むつき)」:親類や仲間が集まる機会の多い正月は、睦び(親しくすること)の月。
・5月「皐月(さつき)」:「早月(さつき)とも言います」。早苗(若い苗)を植える月。
・6月「水無月(みなづき)」:「無」は「の」を意味するので「水の月」となります。田んぼに水を引く月です。
・7月「文月(ふみづき)」:稲の穂が実る月。「穂含月(ほふみづき)」とも。
・10月「神無月(かんなづき)」:全国の神さまが出雲大社に集まるため「神さまがいない月」という意味。しかし出雲地方だけは「神在月(かみありづき)」と呼びます。
・12月「師走(しわす)」:師匠といえども走り回るほど忙しい、という意味です。
特に10月は出雲地方にとって特別な日です。全国の八百万(やおよろづ)の神々が日本全国から出雲大社に集まり、さまざまな「縁」を取り決めるとされるため、一般的には「神無月」ですが、出雲地方では「神在月(かみみありづき)」と呼ばれています。そして、この縁とは、伴侶の縁、親子の縁、仕事の縁、友人の縁など、人と人の縁だけでなく、人生におけるあらゆる結びつきのこと。神々が集まるこの神聖な月に、人々の良縁を祈る文化が今も息づいています。
【“恋愛”だけじゃない!人生を豊かにする大人の「ご縁」】
「縁」や「縁結び」と聞くと“恋愛”や“結婚”を連想する人もいると思いますが、あらゆる事柄は「縁」で結ばれていると言ってもいいかもしれません。「縁」のバリエーションを挙げてみましょう。
■人との縁
恋愛関係のほか、親子、兄弟、友人、師弟関係、仕事関係、趣味の仲間、スポーツの仲間、思想や信仰を同じくする同志など、私たちは日々、誰かと出会い、関係を築いています。仕事や趣味・スポーツの仲間、師弟関係など、自分で選んだように思える関係もありますが、出会いの瞬間はやはり「縁」に導かれているのかもしれません。
■物との縁
ふと「これもご縁かな」とつぶやくこと、ありませんか? 熱望して手に入れた物、意図せず迎えた物、人から贈られた物、旅行先で見つけた品など、どんなものであっても、その瞬間に自分のもとへやってきたのは「縁」があったからこそ。たとえ一時的なものであっても、その関わりには意味があります。
■場所との縁
生まれた場所は、人生に大きな意味をもつことがあります。また、住まいがある(あった)場所や、旅先として選んだ場所や土地――そこに惹かれることも、そこになんらかの「縁」を感じずにはいられません。
■事柄との縁
たとえば本との出合いは、物との「縁」のようでいて、それに書かれていた言葉や、ふれたときにこみ上げる思いとの縁。また、ふと耳にした音楽や、誰かの何気ないひとこと――それらも自分のなかに「何か」を残す「事柄との縁」といえるでしょう。趣味やスポーツに出会うことも、知識や経験、人間関係といった新たな「縁」をもたらしてくれますね。旅はまさにその象徴。場所や土地との縁だけでなく、旅先で出会う人や物、体験など、さまざまな「縁」の宝庫です。
【ご縁を育てる大人の習慣】
「縁」とは仏教の教えでもあります。辞書を引くと仏語としての「縁」は、「結果を生じさせる間接的な原因、条件や事情」などとあります。また、「そのようになるめぐりあわせ」や「関係をつくるきっかけ」とも。
物事にはすべて始まりである「因」があり、そこに「縁」が働き、なんらかの結果が生じます。これが「因縁」です。また、「縁」が起きることを「縁起」と言いますね。「縁」を呼び込み「縁」を育むために、日常的な心掛けや習慣を身につけてはいかがでしょう。
■ポジティブ思考でいる
何事もポジティブに捉えられる人は、一緒にいてとてもラク。ポジティブ思考の人のところには、人も物も情報も集まるるので、「縁」も生まれやすいといえるでしょう。ただし、同じように他人にもポジティブ思考を強要するのはNGです。
■朗らかでいる
いつも愛想よくする必要はありませんが、適度な親しみやすさや、前向きな雰囲気をまとうことで、人は安心して近づくことができます。
もちろん、世の中にはさまざまな考え方をもつ人がおり、ビジネスや人間関係の距離感も文化や場面によって異なります。過剰なフレンドリーさが誤解を生んだり、時にはリスクを招く可能性もあるでしょう。しかし、だからといって常に構えてばかりでは、よいご縁すら遠ざけてしまうかもしれません。
大切なのは、しなやかな心で朗らかに接しながらも、自分の軸はしっかりと保つこと。笑顔や柔らかな表情、肯定的な言葉は、信頼や共感の土台となり、「この人ともっと話してみたい」と思わせる空気を生み出します。
■人の話をよく聴く
「話を聴く」とは、単に耳を傾けるだけではありません。相手の言葉の奥にある感情や背景にも関心をもち、自分とは異なる視点にも心を開くこと。そうしたオープンな心構えが、「この人なら理解してくれそう」「もっと話してみたい」と思わせる安心感を生み、自然と人を惹きつけていきます。
一方で、現代は情報過多で人間関係にも慎重さが求められる時代。無理に話しかける、興味のなさそうな相手に過度に関わろうとすることは、警戒心を招きかねません。だからこそ、自分自身が“聴く姿勢”を持ち続けることが、ご縁を引き寄せる静かな力となるのです。
■興味の範囲を広くもつ
これは、「縁」を呼び込む間口を広げる、ということです。
■希望や願いを口にする
「こうなりたい」「こんなことをやってみたい」「こんな物を探している」――そんな何気ないひと言が、ふとしたタイミングで誰かの記憶に残り、思いがけないご縁を呼び込んでくれることがあります。
すぐに実現しなくても、伝えることで“共鳴”が起き、自分の想いに共感してくれる人、あるいはサポートしてくれる“誰か”が現れる可能性がぐっと高まります。また、自分の願いを素直に、品よく表現することは、自分自身の意思を確認する意味でも有効です。
■否定的な発言を控える、他人を否定しない
何でもかんでも受け入れるという意味ではなく、「そういう考えもある」といったん飲み込むのが大人の選択。相容れない人の悪口を口にするのではなく、関わらない方向に働く方が建設的です。人に対してのネガティブな感情は「縁」を遠ざけると心得て。
【「縁結び」にまつわる雑学」】
■全国の縁結びスポット
・出雲大社(島根県出雲市):全国から神さまが集まる10月の出雲大社は最強ですが、そのほかの月でももちろん強力な縁結びスポットです。
・猿田彦神社(和歌山県伊勢市):猿田彦大神は、物事の始めに出現して万事最もよい方へ“おみちびき”になる神さま。「みちひらきの神さま」とも言われています。また、境内には佐瑠女(さるめ)神社というお社もあり、祀られている天宇受売命(あめのうずめのみこと)は神楽や技芸、鎮魂の祖神とされるほか、縁結びの神さまでもあります。天上の神さまと地上の神さまとの縁を取り持ったことから、さまざまな縁を結ぶ良縁の神さまとして信仰されています。
・東京大神宮(東京都千代田区):「東京のお伊勢さま」とも呼ばれています。江戸時代「一生に一度はお伊勢参り」と言われ、伊勢神宮への参拝は人々の生涯かけての願いでした。明治の新国家が誕生し、伊勢神宮の遥拝殿として明治13年に創建されたのが東京大神宮。神前式の結婚式を始めた神社だというのも、良縁をもたらすとして人気の所以です。
・川越氷川神社(埼玉県川越市):お祀りしている五柱の神々に二組の夫婦が含まれていることから、縁結びの神さまとして信仰されています。身を清めた巫女が拾い集めた境内の小石を神職がお祓いをし、奉製した授与品「縁結び玉」も人気。
■カップルで縁結びの神社にお参りするのはNG!
都市伝説…の域を出ませんが、神さまがふたりに嫉妬して別れさせてしまう、ということのようです。気になる人は、境内では別行動をしてみては?
■護摩や絵馬に何を書く?
人との出会いや良縁を求めるなら、護摩や絵馬には正しく書いて祈願すべきですね。
・出会いを求める場合は「良縁祈願」
・好きな人と付き合いたい場合は「恋愛成就」
・すでに付き合っている人がいて結婚などの関係に発展させたい場合は「縁結び」
***
「縁結びの日」をきっかけに、さまざまな「縁」に思いを馳せてみたいもの。すべての事柄に「縁」を感じられれば、日々の小さな出来事さえありがたく、大切にしようと思うかもしれません。
もちろん、「望まない縁」もあるもの。ですが、そこに何かしらの意味があると受け止めてみると、不思議と少し気持ちが楽になる――そんなふうに感じられるといいですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『デジタル大辞泉』(小学館) /一般社団法人 日本記念日協会HP(https://www.kinenbi.gr.jp)/『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社) :