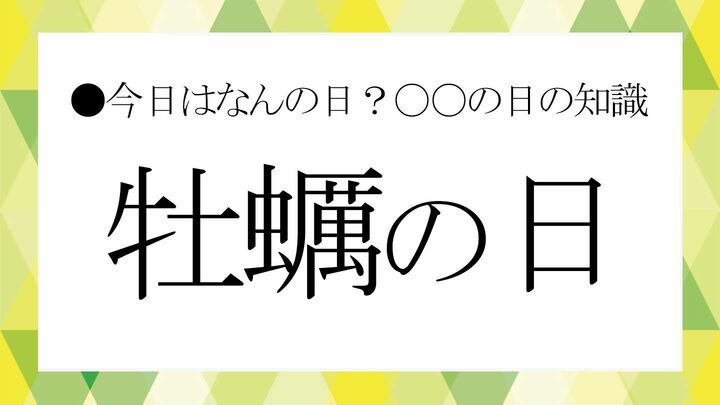【目次】
【「牡蠣の日」とは?由来】
■11月23日は「牡蠣の日」!
11月に話題となる旬の魚介といえば、日本海沿岸地域で毎年11月6日に漁が解禁されるズワイガニ、そして…牡蠣! 実は1年中食べられる食材ですが、やっぱり冬に旬を迎える真牡蠣の美味しさは格別!――ということで、そのピークを迎える11月23日が「牡蠣の日」なのです。「牡蠣フェア」などを行う飲食店や販売店などもあり、牡蠣好きには無視できない一日もしれませんね。
■どこが制定?
2003年(平成15)年6月に、全国漁業協同組合連合会(JF全漁連)が制定しました。おいしさのピークを迎える時期であること、鍋物などの食材や贈答用などの需要が12月にピークを迎えることから、その直前の祝日である「勤労感謝の日」が日付として選ばれました。「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日」である「勤労感謝の日」に、滋養食材である牡蠣を食べて日々の疲れを癒そうという思いが込められているのだとか。
【ビジネス雑談に役立つ「牡蠣」の雑学】
牡蠣好きにはたまらないシーズンです。好き嫌いが分かれる食材かもしれませんが、この時期のビジネス雑談にはもってこいの話題では? そんな時に役立てたい、牡蠣の雑学をご紹介します。
■「加熱用」と「生食用」何が違う?
「今夜は牡蠣フライ!」と買い物に行き、売り場で「生食用のほうが新鮮なはずだからこれを揚げよう」と思ったことはありませんか? 牡蠣の「生食用」と「加熱用」は鮮度の違いなのでしょうか? 農林水産省のホームページで確認してみると、両者の違いは「鮮度」ではなく、採取海域・浄化処理・出荷時の衛生管理という規定の違いがあるのです。
食品衛生法に基づき、「1.海水中の大腸菌数が定められた基準を満たした海域で採取されたもの、あるいは同等の基準を満たした海水または人工塩水で浄化したもの」「2.洗浄殺菌した器具を用いて衛生的な場所で加工したもの」などの基準を満たしたものが「生食用牡蠣」。鮮度に関わらず生食用か否かを明示することが義務づけられています。
加熱調理して食べる場合は「生食用」でも「加熱用」でも構いませんが、生で食べることを前提にするなら、必ず「生食用」を選んでくださいね。
■「真牡蠣」と「岩牡蠣」どっちが好み?
日本の牡蠣は、冬が旬の「真牡蠣」と夏が旬の「岩牡蠣」の2種類に分けられます。一般的に牡蠣=冬のイメージが強いため、夏が旬の岩牡蠣は全国的な知名度がまだ高いとは言えません。
真牡蠣は浅瀬で養殖され、岩牡蠣は深い岩場でじっくり育つなど、育つ環境が大きく異なるため、旬も味わいもまったく違います。それぞれの特徴を見てみましょう。
・真牡蠣:餌となるプランクトンや太陽の恵みが豊富な、海面下50cm~6mの浅瀬で養殖されます。11月上旬から出荷が始まり、産卵前の冬の時期に旬を迎えます。旨味が凝縮されクリーミーな味わいが特徴。産卵に向けて養分を蓄える春から初夏にかけては、冬とは違った味わいが楽しめます。
・岩牡蠣:海面下5m〜10mの岩場で3年から5年ほどかけてじっくり育つ天然のものが多く、外敵から身を守るため殻が大きく頑丈です。養分をたっぷり蓄えた産卵期にあたる6月から8月中旬の夏季が旬ですが、近年は養殖技術の発達によって早春から楽しめるものも。真牡蠣に比べて身が大きくプリッとした食感が特徴で、濃厚でクリーミーな味わいから「海のチーズ」と呼ばれます。
■「牡蠣県」はやっぱり広島!世界で見ると?
都道府県別の牡蠣の養殖生産量(2021年)では、最も多いのが広島県の92,827tで圧倒的1位。2位は宮城県(22,335t)、3位岡山県、4位兵庫県、5位岩手県が続きます。
生産量を世界全体で見てみると、2021年のデータでは中国の3,357,000tが桁違いでトップ! 2位は中国の10分の1以下の韓国で201t、3位がアゼルバイジャンの192t、日本は188tで4位です。消費量でも中国が1位で、日本は2位。この2カ国だけで世界の牡蠣の半分を消費しているといわれています。
■「かきおこ」を知っていますか?
フライや鍋の具材としても人気の牡蠣ですが、広島の郷土料理として親しまれているのが「牡蠣の土手鍋」です。その最大の特徴は、白みそと赤みそ、酒、みりん、砂糖などを混ぜた調味みそを土鍋の縁に土手になるように塗り付けること。野菜などの具材を盛り込み、牡蠣をトッピングしたらだし汁を加えて煮立て、土手の味噌を崩しながら各々好みの味にしていただくという、ちょっとしたイベント性があるところも人気なのでしょう。
そのほか、牡蠣は「牡蠣フライ」はもちろんのこと、「牡蠣めし(炊き込みご飯)」にしてもおいしいのですが、「かきおこ」はご存知でしょうか? 「牡蠣のお好み焼き」の略である「かきおこ」は、岡山県備前市の漁師町日生(ひなせ)で、漁師の妻たちが考案したもの。身が小さかったり傷ついいたりしたため売り物にならない牡蠣を、お好み焼きに入れて食べたのが始まりとされています。山盛りの千切りキャベツとカキをたっぷりのせて焼く「かきおこ」は、この地域から広まり、今では備前市の郷土料理のひとつとして人気を博しているようです。
■牡蠣からも真珠が!?
真珠といえばアコヤ貝ですが、実は牡蠣からもごく稀に真珠ができます。
真珠は貝の体内でつくられる「生体鉱物(バイオミネラル)」という宝石。
アコヤ貝の真珠は宝飾品として美しい輝きを持ちますが、殻の内側が白い牡蠣の場合、できた真珠には光沢が乏しく、宝石としての価値はほとんどありません。
とはいえ「牡蠣を食べたら真珠が出てきた!」というレアな体験は、ごく稀に起こるようです。
***
海の恵みである牡蠣は、その季節ごとの味わいや地域の食文化を楽しめる、日本が誇る食材のひとつです。近年、一部海域での大量死など環境変化のニュースも耳にしますが、これは“海の状況を知るきっかけ”として受け止めたいところ。私たちが安心して旬を味わえる背景には、日々の養殖管理や衛生基準づくりに携わる多くの人々の努力があります。
だからこそ、「牡蠣の日」は、ただおいしくいただくだけでなく、海と生産者へのリスペクトを込めて楽しみたい日。冬は真牡蠣、夏は岩牡蠣、土地ごとの料理――その奥に広がる物語を知るほど、味わいは豊かになります。
今日はぜひ、あなたの“お気に入りの牡蠣”を楽しんでみてください。食を通して季節と地域を感じる、ささやかな贅沢はわたしたちの暮らしを豊かにしてくれるはずです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/農林水産省( https://www.maff.go.jp/index.html )/日本かきセンター( https://www.oyster-center.com/ )全国漁業協同組合連合会( https://www.zengyoren.or.jp/ )/岡山観光WEB( https://www.okayama-kanko.jp/index.html ) :