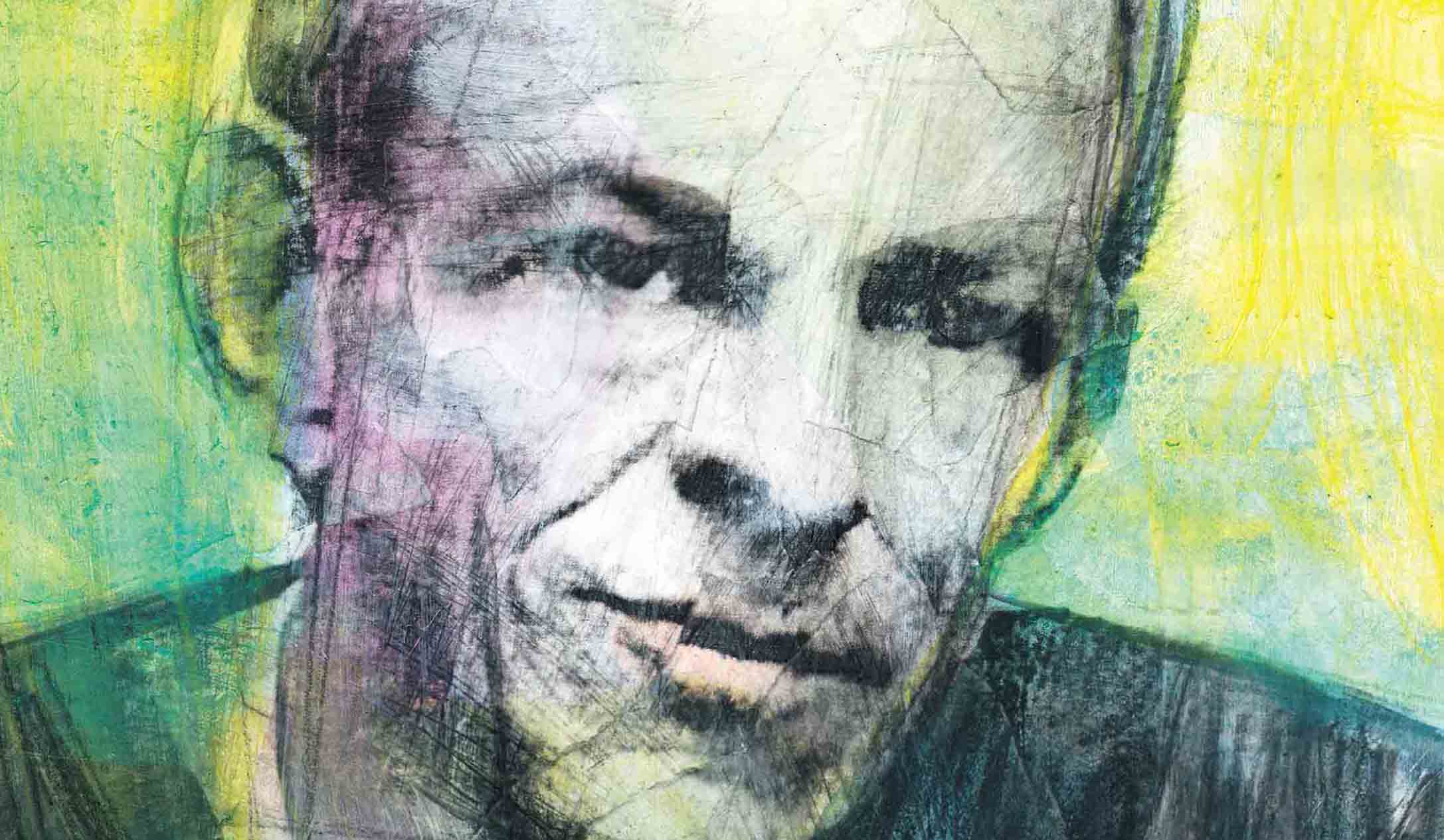1960年代から'90年代にかけて世界の現代アートファンにとてつもない衝撃を与えたひとりのアメリカ人写真家/アーティストがいた。彼の名はピーター・ビアード。ニューヨーク出身で、イエール大学で古典絵画論を学ぶ。両親とも大富豪の家系という恵まれた出自のこの作家のいったい何が衝撃だったのか?
ゴシップと恋愛が絶えなかった伝説のカメラマン
ピーター・ビアード
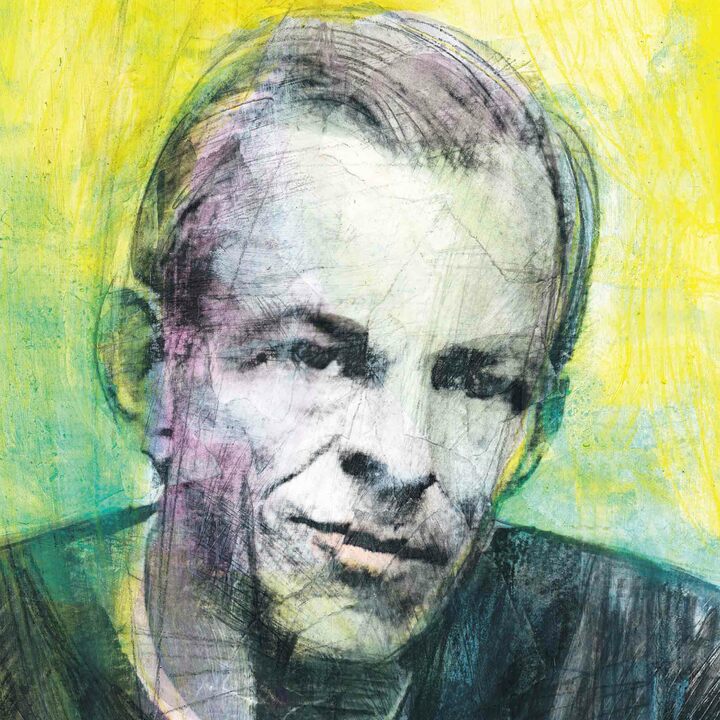
ビアードの主な作品は、彼が撮影した写真に私的なメモや新聞や雑誌の切り抜きを貼り、その上にスケッチやドローイングを重ねて一冊の英国レッツ社製日記帳にまとめたダイアリー形式だったからである。
個人の日記が文芸作品ではなく、アートとして他者の鑑賞の対象になる、これが当時のアート界に衝撃を与えたわけである。
しかも、ビアードの写真は被写体も撮影場所も見る者の想像をはるかに超えていた。撮影場所は1961年に移住したビアード第二の故郷、東アフリカのケニア。被写体はそこに生き、死んでゆく人間や動物の野生の姿である。ことに1965年に出版した『ジ・エンド・オブ・ザ・ゲーム』(日本では1993年刊行)は、1964年から'65年にかけてツァヴォ国立公園で乱獲された何千ものアフリカ象の屍の写真を核心に据え、資料写真や白人入植者たちの歴史文献をアッサンブラージュし、環境変化により死にゆくアフリカを記録したもので、フォトグラフィーとして、アーティスティックなドキュメントとして最高の評価を受けるのである。「エコロジー」などという言葉が人の口にのぼる、はるか以前のことである。
その後、ケニアとエチオピアにまたがるルドルフ湖での、人とクロコダイルの壮絶な共生の姿を記録したフォトコラージュ・ブック『夜明けの瞼』(1973年)を著すと、ビアードは生活の拠点をニューヨーク州の東端、ロングアイランド島のモントークに移す。そこで待っていたのは、めくるめくような、セレブ生活である。
'70年代のニューヨークの社交界は新しい血を求めていた。それまでは東海岸の新旧富豪たちを中心に、有力政治家や、ハリウッドの俳優や歌手といった面子が集う閉鎖社会だったが、人権意識の高まりや、カウンターカルチャーの登場で、社交界も話題の作家やジャーナリスト、アーティストなどを受け入れることで活性化を図っていたのだろう。
そこに鉄道とタバコで財をなした立志伝中のファミリー出身で話題のアーティストが遠い東アフリカから帰ってきた。ビアードは一躍'70年代ニューヨークの社交場「スタジオ54」のメインテーブルの主あるじになったのである。
ビアードは彼の作品の熱烈な礼らい賛さん者であったアンディ・ウォーホールやルーマン・カポーティ、ミック・ジャガーやジャッキー・オナシスとすぐに意気投合。彼らのポートレートや、ストーンズのツアーの撮影をし、『ヴォーグ』誌ではファッションシューティングまで手がけるようになる。画家フランシス・ベーコンとはお互いのポートレートを描きあう仲になるほどだ。
ハンサムな顔にスレンダーな体軀。サファリジャケット姿の彼は「優雅で野蛮なダンディ」として若き日のトミー・ヒルフィガーやマイケル・コースらデザイナーたちにも影響を与える。まさにファッションアイコンだ。
しかし、何不自由なく育ったという生い立ちのせいか。青年時代を過ごしたアフリカのおおらかさのせいか。彼には金銭感覚というものがまるっきり欠けていた。そして当時のニューヨークにありがちな、ドラッグと女性関係の乱れがそれを増幅する。
その間も彼の作品の評価はうなぎのぼりで、日本を含む世界の美術館やギャラリーで展示、コレクションもされ、『Diary』(1993年)、『50Years of Portraits』(1999年)と重要な著作も次々に刊行されるが、作品を気軽に他人にあげてしまう癖のせいで、本人の手もとに残る作品は多くなく、モントークの家は未払いの請求書だらけになっていたという、影の目撃者まで現れる始末。
現在は散逸するコレクションを妻のネジーマが再収集しているという。それでも自らの仕事、作品を「アート」だとは決して呼ばないビアードの頑固さは、ダンディズムの残光だろうか
- TEXT :
- 林 信朗 服飾評論家
- BY :
- MEN'S Precious2016年冬号ダンディズム烈伝より
- クレジット :
- 文/林 信朗 イラスト/木村タカヒロ