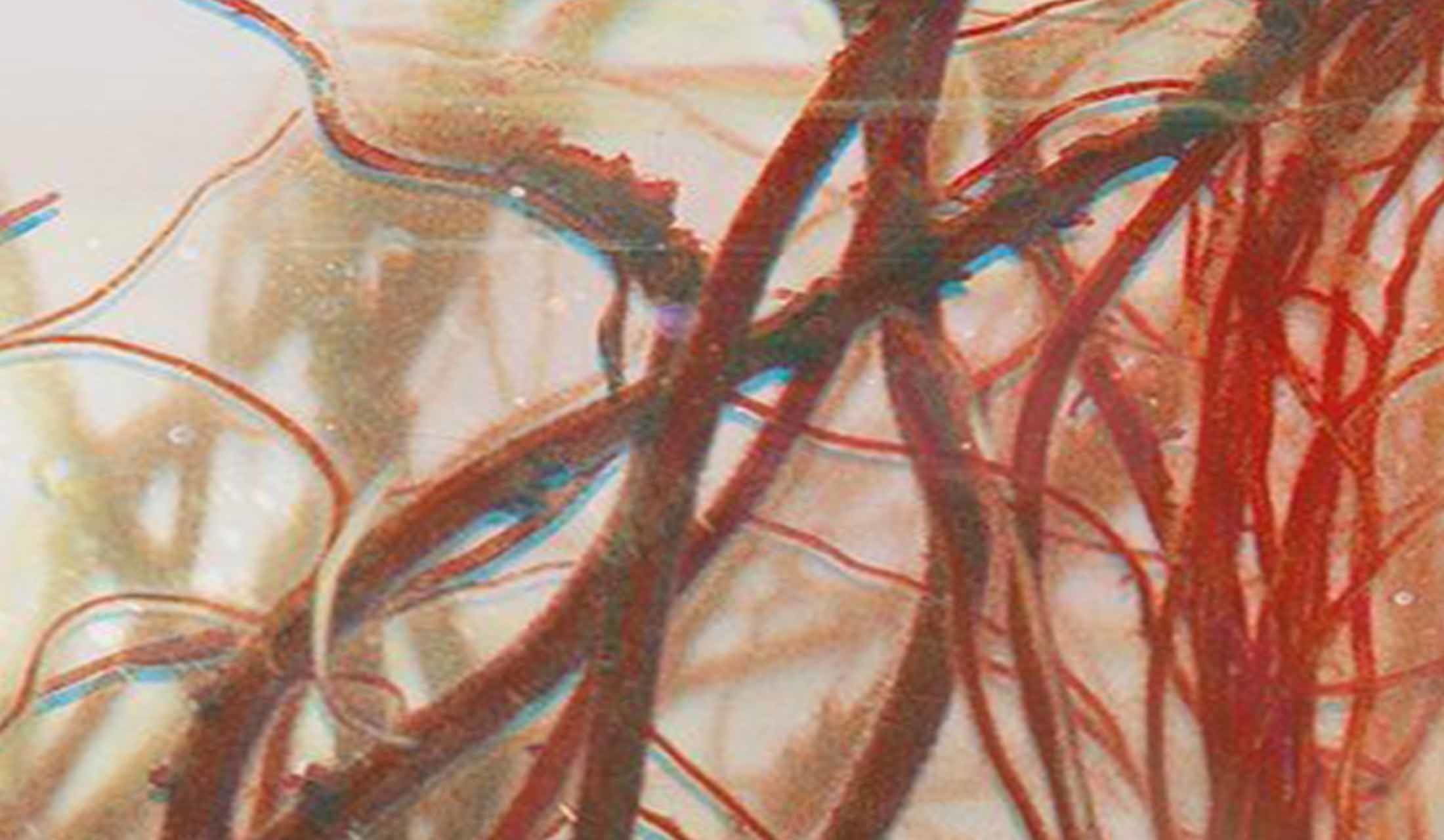怪しげで所在なげな名は、彼らのスタンスを表象する
yahyel(ヤイエル)の音楽に出合ったのは、幸か不幸か、いきなりライブだった。現在は改装中の渋谷PARCO Part1の6Fにあった、「2.5D Studio」というスペース。知人の知人が参加しているバンドといわれ、ちょっと年不相応かなとも思いつつ、覗いたのだった。ステージには大きく投影されたヴィジュアルの前で、マイクを両手で握るヴォーカリストと、ラップトップを操作する人影がまず目に入った。打ち込みと楽器によるサウンドに、オートチューンを通したソリッドな質感のヴォーカルが絡むその演奏にフロアで触れるうち、なんだか懐かしいような、奇妙な感興を得た。音楽が過去のものに似ている、ということではない。サウンドとしては、むしろ近年のエレクトロニック・ミュージックのマナーに沿ったものともいえる。
演奏を聴きながら頭をよぎったのは、自分がかつて親しんでいた、当時「ニューウェーヴ」と呼ばれた、1980年代の一連の音楽だった。例えばソフト・セルやデペッシュ・モード、またはD.A.F.、そしてコクトーズ......ヤイエルの音楽を語る際によく引き合いに出されるジェイムズ・ブレイクを連想したのはもっとずっと後、彼らの音楽をライブではなく音源として聴いた時だった。それは単に彼らのサウンドにニューウェーヴ風の音感が含まれていたからだろうか。そう思ってかつて聴いたニューウェーヴのアルバムをいくつか参照してみて、それらは音楽性やサウンドの関連というより、むしろ音楽を生み出すマインドの領域で、似た美意識めいたものを感じたからだとわかった。それは、最近あまり感じることがなかった、ある種の「洗練された、ソリッドなダークネス」とでもいえるだろうか。ディストピア、という語をあるインタビューでメンバーの篠田ミルは持ち出しているが、確かにそうかもしれない。ニューウェーヴの背景には、当時映画化もされたジョージ・オーウェル『1984』にも繋がるような世界観が横たわっていた。「NO FUTURE」なパンクの刹那主義は、暗澹たる未来像を愛玩するような感覚(同時にそれはロマンティシズムとして、過去に向かうケースもあった)と、そのコインの表側である乱痴気騒ぎへと変化したのだった。
もっとも、ヤイエルの音楽はディストピアというには、むしろヴァイタルな魅力がある。ヴォーカルの池貝峻はもともとブルーズなどにも親しんでいたそうで、ファルセットを駆使するヴォーカルマナーにはR&B感が強い。その点はまさにジェイムズ・ブレイクにも通じるところだろう。サウンドのプロダクションも、ノイズすれすれの音感で辛くも音楽を成立させるというよりは、既視感(既聴感?)を承知の上で、あえて「テクノっぽい」音感を基調にしつつ、ところどころ日常音からのサンプリングなどを巧みに織り交ぜた、グルーヴミュージックとなっている。
このように文字にしてしまうと、なんだか月並みな音楽のように映るかもしれない。そこは私の筆力の乏しさをご容赦いただくとして、彼らの音楽は、細部や構造の新しさとは別のところに、魅力というか、新鮮さがあるようにも思える。「デジタルネイティヴ」という言葉があるが、彼らの音楽づくりにおいては、オートチューンもサンプリングも楽器演奏も等価であり、所与のもの、すでに手元にあるものだった。テクノロジーの進歩を紀年法的に体験してきた人間は、とかく新しいもの優先になりがちだ。しかし「デジタルネイティヴ」にとって各テクノロジーは、その登場順に縛られることなくフラットに使いわけ、組み合わせできる素材となる。ヤイエルのサウンドにはそんな「ポスト・ラップトップミュージック」なスタンスが感じられる。その「ポスト〜」感は全編英語で歌われるヴォーカルにもいえるだろう。インターネット時代においては音楽の発表の場は最初からグローバルであり、それを踏まえれば各国語よりも英語のほうが自然な選択だろう。
ところで、これはごく私的な印象だが、音楽においてグルーヴを得やすい、というか、私たち聴き手がグルーヴ感を認知しやすいのは、やっぱり英語の詞なのかもなと彼らの音楽を聴いているうちに感じてしまった。いまやポップスやロックに限らず、ヒップホップにおいても、日本語の詞と英語の詞、音楽的にはいずれも遜色ないかもしれない。ただ、やはり英語のほうが裏の拍をとりやすいのではないだろうか。そもそも「ワン、ツー」と「いち、に」からして、拍感が異なっている。そこに抗して、あえて「日本語の」グルーヴミュージックを追求するのはもちろん尊い挑戦的行為だ。だが、彼らのように英語での表現を選ぶのも、現代においてはしなやかな態度だなと、妙に納得したのだった。
ちなみに彼らの最新アルバムは昨年11月にリリースされた『Flesh And Blood』。Youtubeで音楽とともに彼らの重要な表現でもあるヴィジュアルを見れば、その世界観はよりわかりやすいかもしれない。
- TEXT :
- 菅原幸裕 編集者