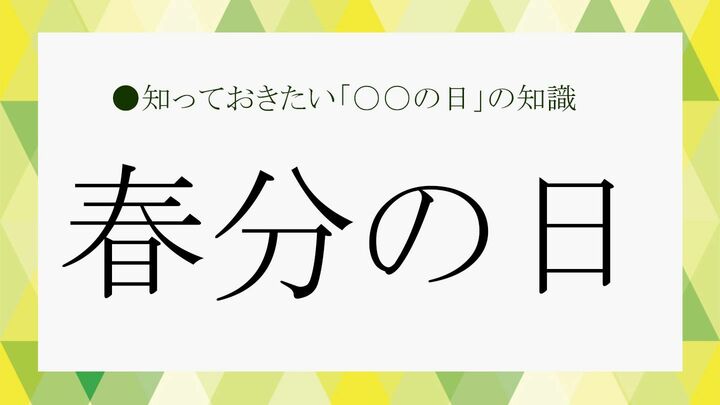「春分の日」に対して、なんとなく「これから暖かくなっていく日…?」というイメージをもっている人は多いのではないでしょうか? でも、「春分の日」に、どんな意味があって、どうやって決まるのか、何をする日?と聞かれたら、よくわからないですよね。この記事では2024年の「春分の日」はいつなのか、何をする日なのかなど、押さえておきたい基礎知識をご紹介します。
【目次】
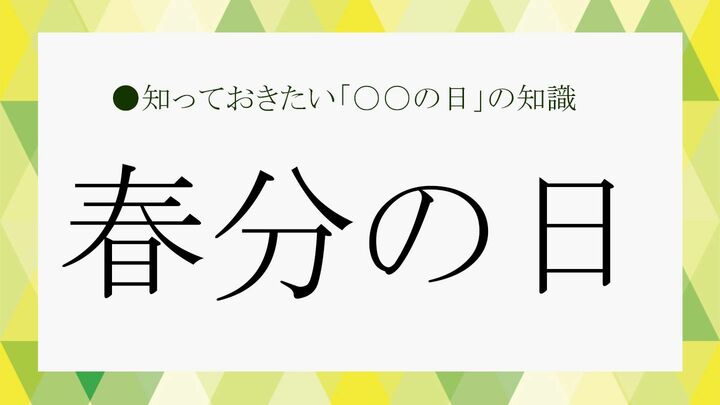
【「春分の日」って何?正しく理解するための「基礎知識」】
■「春分の日」って具体的にどんな日なの?
「春分の日」とは、その年の太陽が黄経0度の春分点を通過する日を指します。この日、太陽は真東から出て、真西に沈みます。昼と夜の長さがほぼ等しくなる日として知られ、二十四節気のひとつでもあります。ご存じのように、冬の間は夜の時間が長く、春に向けて少しずつ太陽が昇る時間が早くなり、日が暮れる時間が遅くなることで昼の時間が長くなっていきます。その課程で、昼と夜の時間の長さがほぼ同じになる日、それが「春分の日」なのです。そのため、私たちは「春分の日」を迎えると、「春の訪れ」を感じるのです。ちなみに、「秋分の日」とは、太陽が黄経180度の秋分点を通る日のこと。「春分の日」とは反対に、それまで長かった昼の時間が短くなる冬に向け、昼と夜の時間とほぼ同じになる日が「秋分の日」です。
■「春分の日」と「お彼岸」は関係は?
「春分の日」は「お彼岸 (ひがん) の中日(ちゅうにち)」でもあります。「彼岸」とは、「春分の日」と「秋分の日」、それぞれを中日とした前後3日間、合計7日間の期間です。お彼岸は年に2回あり、それぞれを「春の彼岸」「秋の彼岸」と呼びます。つまり、「春分の日」は「春のお彼岸の中日」というわけです。また、彼岸の最初の日は「お彼岸の入り」、最終日は「お彼岸のあけ」と呼ばれます。
■2024年の「春分の日」は「いつ」?どうやって決まるの?
結論から言えば、2024年の「春分の日」は3月20日です。しかし、年によっては「春分の日」が3月21日なることは、ご存じですか? 「春分の日」とはその年の太陽が春分点を通過する日。国立天文台が毎年2月に公表する暦要項(れきようこう)に、翌年の「春分の日」と「秋分の日」を記載することにより、日にちが正式に決定されます。逆に言えば、歴要項が更新される前は、「春分の日」は「まだ正式には決まっていない」ということになります。3月21日になる年がある理由は、地球が太陽の周りを公転する周期は365日ちょうどではなく、365日と6時間程かかるため。ですから、太陽が春分点を通過する「春分日」が変わることがあるのです。これは「秋分の日」も同様です。
【なぜ「祝日」?なぜ「休日」?】
■「春分の日」は「自然をたたえ、生物を慈しむ」日
「春分の日」も「秋分の日」も、1948年の施行された祝日法「国民の祝日に関する法律」により、「国民の祝日」と定められています。祝日法の制定時の記録には、「この日は、昼夜の長さが等しく、"自然のあらゆる生命が若々しく盛り上がるとき"であるため、異議なく採用された」とあります。ちなみに、現在、「祝日法」により定められた「国民の祝日」は16日ありますが、制定当初は9日でした。
■なぜ「休日」なの?
上でも触れましたが、「祝日法」により、日本には年間16日の「国民の祝日」が設けられています。「国民の祝日」とは、美しい風習を育てつつ、よりよい社会、より豊かな生活を築きあげるために定められた「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。そして、同法第3条により、「『国民の祝日』は、休日とする」と定められているのです。
【「春分の日」に「すること」は?「食べ物」は?「風習」】
■「春分の日」「秋分の日」は「先祖を敬い、故人を偲ぶ日」
前述の通り、「春分の日」と「秋分の日」、それぞれを中日とした前後3日間、合計7日間の期間は、「お彼岸」とされています。「お彼岸」という言葉の由来は、インドのサンスクリット語の「paramita(パーラミター)」。「波羅蜜多(はらみた)」と表記され、さらにこの「波羅蜜多」を漢訳した「到彼岸」を略して「彼岸」と用いられるようになりました。仏教では「彼岸」には「向こう岸」という意味があり、ご先祖さまがいる極楽浄土の世界を指します。「春分の日」と「秋分の日」は、昼と夜の長さがちょうど同じになる日。同時に「此岸(現世)と彼岸(極楽浄土)が最も近づく日」とされ、極楽浄土があるとされる真西に沈む太陽に手を合わせ、死者や来世を偲ぶ日となりました。
■「お彼岸」には何をする?
・お仏壇を掃除してお供えをする
お彼岸には、仏壇・仏具の掃除を行います。掃除方法は(1)飾ってある仏具を外す(2)仏壇の内側・外側の埃を「毛払い」という道具で払う(3)柔らかい布で乾拭きする(4)仏具を元に戻すという流れが基本。あとから飾り方がわからなくなってしまわないように、掃除前に仏壇の写真を撮っておくと安心です。
・「墓参り」でご先祖さまを供養する
「お彼岸」は仏教に由来しますが、仏教を信仰していない人でも、お彼岸にお墓参りをするのは日本の一般的な習慣です。日本では古くから暮らしの中で、春には豊作を願い、秋には収穫を自然の神々に感謝する慣習が根付いていました。「お墓参り」ではお墓の掃除も行いましょう。
■「食べ物」は?
「春分の日」の食べ物といえば、「ぼたもち」が有名ですね!「おはぎ」とも言いますが、実は昔は、春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」と呼び分けていました。どちらも、もち米とあんこを使った和菓子ですが、漢字では「ぼたもち」は「牡丹餅」。春に咲く牡丹の花を由来とします。「おはぎ」は「お萩」で、秋に咲く萩の花に由来します。そのため、「ぼたもち」と「おはぎ」は見た目や形にも違いがあり、以前は「ぼたもち」は牡丹の花のように大きな丸い形でつくられ、「おはぎ」は萩の花のように、やや俵型で小ぶりにつくられていたそうです。また、使用されるあんこは、秋のお彼岸には収穫したばかりの柔らかい小豆を使うことができるため、「おはぎ」には粒あんが、一方、春のお彼岸では冬を越して少し固くなった小豆を使わなければならないため、「ぼたもち」には皮を取り除いた小豆でつくったこしあんが使われていたとか。とはいえ、現代では小豆の保存技術が発達したことや小豆の品種改良が進んだことなどから、「ぼたもち」と「おはぎ」で、違いはほとんどなくなりました。中日となる「春分の日」や「秋分の日」にお供えしたら、その日のうちにお下がりをいただくのが正式と言われていますよ。「ぼたもち」「おはぎ」以外のお彼岸のお供え物としては、故人が好きだった和菓子や焼き菓子、洋菓子などがおすすめです。
***
毎年「春分の日」を迎えると、「いよいよ本格的な春が来る!」と、気持ちが明るく前向きになるものです。たとえお墓参りは無理だとしても、ぼたもちを食べながら、亡くなった親族や友人など、故人を思う日としてみてはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /内閣府HP「国民の祝日について」 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html :