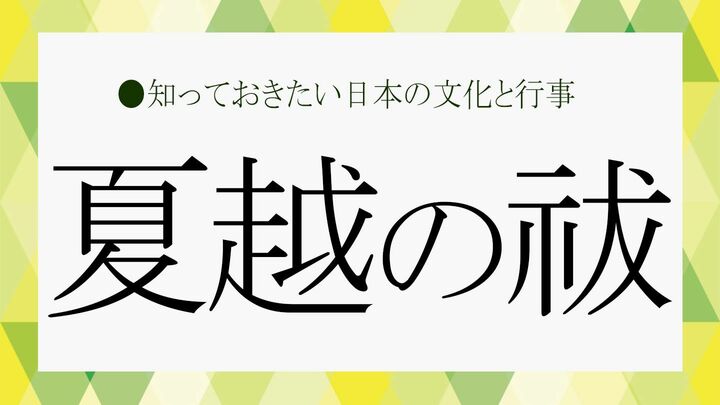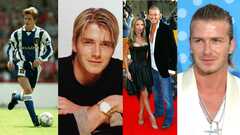【目次】
【「夏越の祓」とは?「読み方」と「意味」、「由来」】
■「読み方」
「夏越の祓」の「夏越」は「なごし」、「祓」は「はらえ」と読みます。
■「意味」
「夏越の祓」は、6月の晦日(みそか=月の最終日)、すなわち6月30日に行う「大祓(おおはらえ)」の行事です。
「大祓」とは古代律令体制下で行なわれた民俗信仰に基づく年中行事のひとつで、毎年6月と12月の晦日に、諸人の罪や穢れを祓い清めるため、宮中や神社で行われる神事です。このうち6月の神事が「夏越の祓」です。「夏祓」、「水無月(みなづき)祓」などとも呼ばれます。
平安期には6月と12月の晦日に朱雀門において、中臣が祝詞を読んで祭事を行っていましたが、律令体制の崩壊と供に次第に崩れ、応仁の乱で絶えてしまいます。一方で、この行事は民間にも伝えられ、宮中大祓の途絶えたあとも発達しました。ことに6月の祓は夏季の悪疫除去の意を含めて盛んに行われるようになり、「夏越の祓」として残ったといわれています。
■「由来」
上述の通り、「夏越の祓」の由来は、年に2回ある神事「大祓」にあります。大祓は、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の禊祓(みそぎはらい)をルーツとする神事で、心身の穢れや厄災を祓い清める儀式でした。最古の資料としては、『古事記』に仲哀 (ちゅうあい) 天皇が崩御のとき国の大祓をしたとの記載があります。
【2025年の「夏越の祓」はいつ?】
「夏越の祓」は、毎年6月晦日(みそか=月の最終日)、つまり6月30日に行われる神事です。基本的に日にちが変わることはなく、2025年も6月30日に行われます。
【「夏越の祓」では何をする?「行事」と「食べ物」】
■行事
「夏越の祓」に行われる代表的な行事に、「茅の輪くぐり」と「人形流し」という風習があります。それぞれの内容と方法を詳しく見ていきましょう。
・茅の輪くぐり
「茅の輪」とは、チガヤなどの植物でつくられた、人の背丈よりも大きな輪のこと。神社の鳥居や境内に茅の輪を設け、そこをくぐることで1年の前半の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災や厄除け、家内安全を祈願するのが「茅の輪くぐり」です。神主や巫女だけでなく、参拝者もくぐることができます。一般的な「茅の輪くぐり」の作法をご紹介しましょう。基本は、唱え詞(ことば)を唱えながら八の字に3回茅の輪をくぐりぬけるのが作法です。
1周目、正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで左回りで正面に戻ります。
2周目、正面でお辞儀をし、右足で茅の輪をまたいで右回りで正面に戻ります。
3周目、正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで左回りで正面に戻ります。
最後は正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたいで参拝します。
茅の輪を3周する際には、唱え詞を声に出さずに唱えます。
「祓へ給ひ 清め給へ 守り給ひ 幸え給へ(はらえたまい きよめたまえ まもりたまい さきわえたまえ)」
神社によっては、茅の輪くぐりの作法が異なる場合があるので、それぞれの神社の作法に従ってくださいね。
・人形(ひとがた)流し
「人形流し」とは、神社から授与された人形で体をなでたりして罪穢(つみけがれ)を祓う行事です。人形に自分自身の罪や穢れを移し、身代わりとして神社に納めるのです。身代わりとなった人形は、神事で川や海に流したり、篝火(かがりび)で焚いたりして清めてもらいます。
ちなみに「人形」は、紙ではなく、藁(わら)などでつくるところもあるそうです。「人形流し」の一般的な方法は、人形に自分の名前、年齢を書き、その人形で体をなでて息を3回吹きかけます。そして、神社に納めます。 「人形流し」も神社によってやり方が異なる場合があるので、そちらに従ってください。
■食べ物
「夏越の祓」に食べるとよいとされる食べ物をご紹介します。厄除けや暑気払いにぴったりです。
・水無月
「夏越の祓」に欠かせないのが、ういろうの生地に小豆を散らして三角に切った「水無月」というお菓子です。古来、宮中などでは、この日に氷を口にして暑気払いをしていました。当時の氷はとても貴重。氷が食べられない庶民がお菓子を氷に見立てて食べたのが「水無月」のはじまりといわれています。白い生地が定番ですが、黒糖や抹茶の入ったタイプもありますよ。
・夏越ごはん
公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構では、「夏越の祓」に合わせた「夏越ごはん」を提唱しています。
2025年は、東京都内140社の神社が協力。参拝者に「夏越ごはん」のリーフレットと雑穀米が配布されています。
昔から日本人にとって、米は最も重要な穀物で、宮中や全国各地の神社などで行われる豊穣祈願や新嘗の行事には欠かせません。「夏越ごはん」は、雑穀ごはんの上に夏野菜を使って、「茅の輪」をイメージした丸い食材をのせた行事食です。その昔、蘇民将来(そみんしょうらい)が素戔嗚尊(すさのおのみこと)を「粟飯」でもてなした伝承に由来しています。
【「夏越の祓」が行われている場所は?】
記事の最後に、「夏越の祓」が行われている神社をいくつかご紹介しましょう。
■東京「東京大神宮」(東京都千代田区富士見)
「東京大神宮」は、東京の「お伊勢さま」と呼ばれ、多くの人に親しまれている神社で、格式高い「東京五社」のひとつでもあります。昨今では、恋愛のパワースポットとしても注目されています。「夏越の祓」は6月30日 の午後2時と4時の2回、行われます。茅でつくった大きな輪をくぐる「茅の輪くぐり」や、人の形に切り抜いた紙に名前と年齢を書いた「形代(かたしろ)」に自分の罪や穢れを移し、我が身の代わりに清める行事も行われます。「茅の輪」は6月30日まで設置されています。ただし、30日午後1時頃から午後5時ごろまで、祭典の関係で「茅の輪」をくぐれませんのでご注意を。
■東京「神田明神」(東京都千代田区外神田)
東京の中心にある「神田明神」は、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場、築地魚市場ー、108町会の氏神さまです。「明神さま」の名で親しまれています。神田明神では「夏越の祓」を「夏越大祓式」と呼び、毎年6月30日に斎行されます。2025年も午前11時と午後3時の2回行われ、人形を大海原のはるか彼方へ流す「流却神事」や、神職と供に参拝者が茅の輪をくぐり、穢れや災いを祓う「茅の輪くぐり」が行われます。
■京都「平安神宮」(京都府京都市左京区岡崎)
平安神宮は1895(明治28)年に、平安遷都1100年を記念して創建された神社です。国の名勝庭園にも指定されている「神苑」や、重要文化財でもある大極殿、丹塗りの応天門もあり、見どころがたくさんある神社でもあります。平安神宮では、「夏越大祓式」として、6月30日午後4時より夏越の祓が執り行われています。茅の輪をくぐることによって、半年間の汚れを祓い清めて無病息災を祈願する行事です。
■京都「北野天満宮」(京都府京都市上京区馬喰町)
梅と紅葉で有名な京都の神社「北野天満宮」は、菅原道真公をご祭神としてお祀りする、全国約1万2000社の天満宮、天神社の総本社です。北野天満宮の「夏越の大祓」は、6月30日の午後4時より神事を執り行います。本殿正面にて、神職と供に「茅の輪くぐり」を行い、日常無意識のうちに心身に付着した罪や穢れを祓い浄め、無病息災を祈願します。社殿では直径7~8cmの小型の「茅の輪」を授与していますよ。
■福岡「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市宰府)
太宰府天満宮は、菅原道真公の墓所の上に社殿を造営し、その神霊を祀る神社です。また、「学問・至誠しせい・厄除けの神さま」として、年間に約1000万人の参拝者が訪れています。こちらでは「大祓式」として、楼門前にて午後4時より執り行われます。神職が「大祓詞」を唱えたあと、人の形をした「形代」に半年間の罪穢をかえし、浄火にてお焚き上げをします。 個人のお祓いとしてはもちろん、広く地域や社会を祓い清める公の神事としても親しまれています。
***
「夏越の祓」は6月30日に全国の神社で行われます。有名な神社を訪ねるのもいいですが、地元の神社を訪れて、「茅の輪くぐり」や「人形流し」を行い、半年間の穢れを祓い、残り半年の無病息災を願いましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) 「夏越ごはん」オフィシャルサイト(https://www.komenet.jp/nagoshigohan/) :