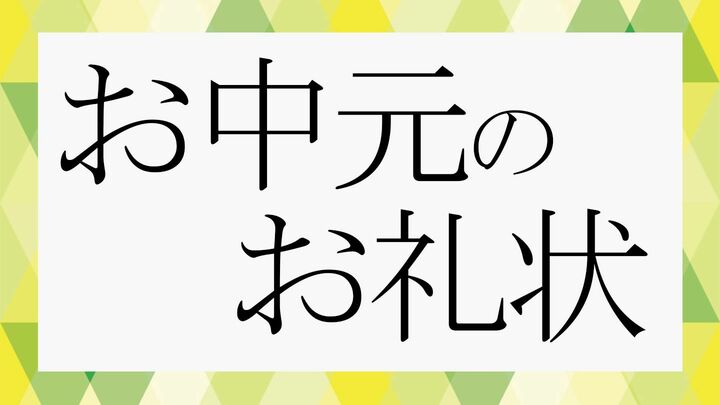【目次】
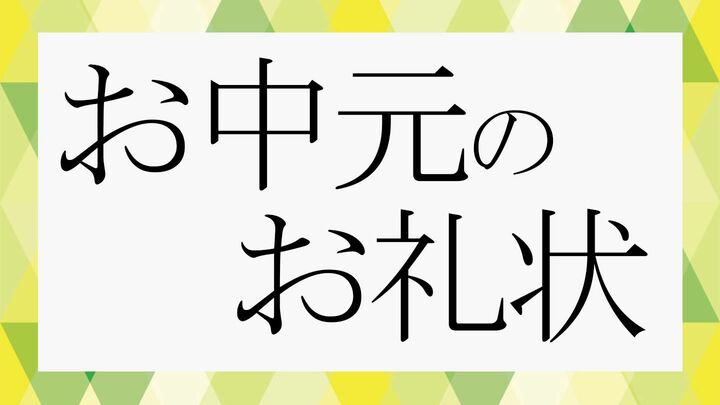
【そもそも「お中元」って? お中元の基礎知識】
まずは「お中元」について解説しておきましょう。
■お中元とは?
日ごろお世話になっている人に、お付き合いに対するお礼を品物に託して届ける季節のあいさつです。今後も変わらずお付き合いさせていただきたいことや、相手の健康・発展を祈る気持ちを込めて贈ります。年末にも同様に「お歳暮」という習慣がありますね。
■誰に贈る?
離れて暮らしている両親や親戚、勤め先の上司や取引先、友人、知人など、「お世話になっている、これからもよい関係を保ちたい」と考える相手へ贈るもの。一度きりではなく、毎年継続して贈ります。一度きりのお礼ということなら、お中元としてではなく贈るのがよいでしょう。
■いつ贈る?
お中元は夏のあいさつなので、7月初旬から15日ごろまでに(旧盆の地域では7月末から8月中旬ごろまでに)、先方が受け取れるよう届けます。お歳暮は、12月初旬から20日までに届くようにしたいものです。なお、お中元とお歳暮のどちらかだけなら、お歳暮を贈るのがマナーです。
■起源
ルーツは中国古来の「道教」と日本の「お盆」にあるといわれています。中国では1月15日、7月15日、10月15日を「三元」として祝う習慣があり、7月15日を「中元」として半年の無事を祝い、祖先の供養をしたのだとか。日本の仏教では、夏の時期に先祖の霊を家に迎えて供養する「盂蘭盆(うらぼん)=お盆」という行事があります。お盆には親類や知人などが集まって無事を確かめ合うわけですが、その際にお互いに贈りものをするようになりました。その贈り物の習慣が「お世話になっている人や目上の人に、感謝の気持ちを込めて贈りものをする」というお中元の文化に発展したのです。
【「お中元」のお礼状の送り方とマナー】
■いつ送る?
受け取ったらすぐにお礼状を、がマナーです。中身を確認し、3日以内を目安にお礼状を送りましょう。食品であればすぐにいただき、ひと言でも感想を述べたいものですね。
■何で送る?
お中元のお礼状を何で送るかは、相手との関係によって考えたいもの。目上の方からいただいたお中元に対してのお礼状なら、白地(無地・無罫)の便箋に、白地の封筒が格式が高いので向いているでしょう。もう少し砕けた間柄の親戚や知人であれば、季節の絵柄の便箋・封筒を使用したり、はがきでもいいでしょう。ちなみに、縦書きは格式が高く、横書きはカジュアルな印象になります。
■手紙でないとNG?メールや電話は?
お礼の形態も時代とともに変化…という訳にいくでしょうか。そもそもSNSやメールでのコミュニケーションが主流な世代には、お中元やお歳暮という習慣はないかもしれませんが…。まずは「受け取りました、ありがとうございます」という第一報をメールやLINEで送り、改めてお礼状を郵送するのがいいかもしれませんね。よく電話がかかって来る相手なら、その人にとっては電話が負担にならないコミュニケーションツールということなので、電話でお礼を述べてもいいでしょう。
【ビジネス、個人、親戚など…相手別「お中元のお礼状」例文】
■「取り引き先」からいただいたお中元に対するお礼状
部署や会社を代表してお礼状を差し上げる際には、「頭語」「時候や季節の挨拶」「お中元をいただいたことへのお礼」「日頃の感謝」「健康への気遣い」「結びの言葉」「日付と差出人名」と、お礼状の決まり事をしっかり踏襲したいものです。
-----------------------------------------------------------
〇〇〇〇株式会社
〇〇〇〇部 〇〇〇〇様
拝啓 盛夏の候、貴殿におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度は、心のこもったお品を頂戴し、誠にありがとうございました。
平素よりのご支援に加え、過分のお心遣いに恐縮しております。
弊社一同心より感謝を申し上げますとともに、以後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
暑さ厳しい時節柄、皆様のご健康と貴社の一層のご繁栄をお祈り申し上げます。
略儀ながら書中にてお礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
〇〇部 〇〇〇〇(名前)
■職場の「上司」から個人的にいただいたお中元に対するお礼状
お世話になった人に贈るのがお中元。下の者から上位の相手に贈るのが一般的ですが、上司から自宅に届いてしまった…ということもあるでしょう。大変親しく思ってくれている相手からの品ですから、あまりかしこまらず手紙文のマナーにこだわりすぎず、自分の言葉で感謝を述べたほうが気持ちが伝わるでしょう。
-----------------------------------------------------------
前略ごめんください。
日頃よりご指導いただきありがとうございます。
本日は上等な品をちょうだいし、恐縮しながらも大変うれしく思っております。
先日お話をうかがいました部長の故郷の特産品ですね。
とても瑞々しく香りも甘みも豊かで、「こんなおいしい〇〇食べたことない!」と言いながら、
夕食後に家族でおいしくいただきました。ありがとうございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇(自分の名前)
〇〇〇〇様(相手の名前)
■「親戚」からのお中元に対するお礼状の例文
世話好きの親戚のおばさんからのお中元…はよくあることかもしれませんね。こちらの近況や、相手の健康を気遣う気持ちを込めた手紙は、きっと喜ばれるはずです。
-----------------------------------------------------------
〇〇おじさん、〇〇おばさん、元気でお過ごしですか。
昨日〇〇を受け取りました。毎年送っていただき、ありがとうございます。
小学4年生になった息子も大喜びでさっそく朝食にいただき、元気に登校していきました。
家族3人何とかこの猛暑の日々を過ごしていますが、おふたりも熱中症には十分気を付けてくださいね。
のどの渇きを感じていなくても、30分おきに二口三口程度の水分補給をするのがいいようですよ。
久しぶりに秋のお彼岸には帰郷する予定なのでお会いできると思います。楽しみです。
寝苦しい夜が続きますが、どうぞご自愛くださいませ。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇(自分の名前)
【お中元の豆知識】
■妥当な金額は?
お中元のギフトの相場は3000円から5000円くらいのようです。お中元は関係を続けていく限り継続するものと考えたいので、お互いにあまり負担にならないようにすることが肝心です。
■時期を逃してしまったら?
お中元期間を逃してしまったら、「残暑見舞い」や「暑気払い」「おうかがい」などの名目で贈るといいでしょう。
■商品券や現金は失礼?
相手の好みや家族構成がわからない場合や、趣向を変えたい場合は、商品券や現金でも。「お好きなものをどうぞ」などと添えましょう。
■お返しは必要?
お中元やお歳暮に「お返しの品」は不要ですが、いただきっぱなしにせず、必ずお礼状などで感謝を伝えましょう。
■喪中の人へは?
お中元はお祝いごとではないので喪中の方へ届けても問題はありません。しかし、49日が過ぎるまでは控えたほうがいいかもしれません。その間にお中元の時期が過ぎてしまうのであれば、別の名目で贈ればいいのです。
■毎年贈るのがしんどい…
そろそろお中元やお歳暮をやめたい、ということもあるでしょう。お中元とお歳暮を贈っていた相手なら、まずはお中元をやめてお歳暮だけにし、翌年はお歳暮もやめるなどと、段階を踏んでみては? また、贈り合っている相手であれば、お礼状に「来年からはどうぞお気遣いくださいませんよう」と添え、「今回でおしまいにします」という気持ちをやんわり伝える、という方法も。
■贈ってはいけない職種も
たとえお世話になっていたとしても、お中元を贈らないほうがいい職種もあります。政治家や公務員(公立学校の教員や、役所の職員)への贈り物はNGと考えたほうがいいでしょう。当人同士の関係性に関わらず「収賄」と捉えられてしまう場合があるのです。恩師が公立学校の先生という場合や、親戚が公務員ということは珍しくないと思いますが気を付けたいものです。また、職場の上司や先輩などへ贈る場合、お中元やお歳暮などを含む贈り物のやり取りを禁止している会社もあるので、事前に確認したほうがいいでしょう。
***
お中元もお歳暮も、気持ちを形に替えて届ける日本独特の文化です。贈るか否かは個人の自由ですが、いただいた場合にはしっかり大人としてのマナーを発揮してくださいね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『マナーと常識事典』(自由国民社『現代用語の基礎知識』2007年版付録)/『デジタル大辞泉』(小学館) :