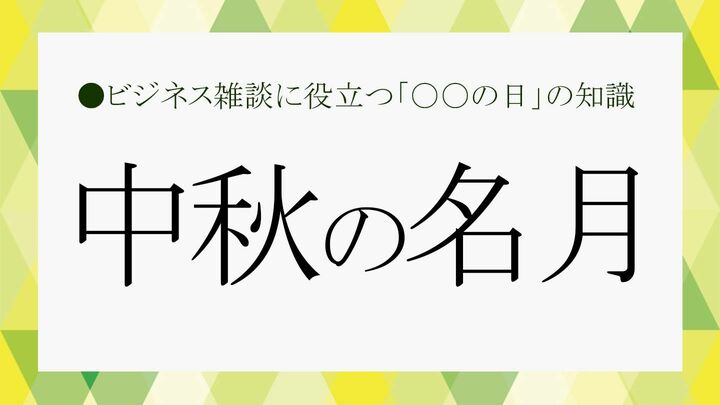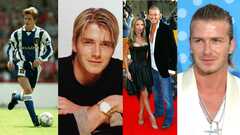【目次】
【「中秋の名月」とは?「読み方」と「意味」】
■「読み方」
「中秋の名月」は「ちゅうしゅうのめいげつ」と読みます。
■「意味」
「中秋の名月」とは、「旧暦で8月15日に見える月」を指します。また、「十五夜(じゅうごや)」は「旧暦15日の夜」のことで、特に旧暦8月15日の夜のことを表すので、「中秋の名月」のことでもあるわけです。一年で最も美しい月とされ、古くからお月見の習慣が残っています。
■「由来」は?
「中秋(ちゅうしゅう)」は、旧暦の「秋の真ん中」を意味します。旧暦における「秋」は7月から9月の3か月間で、7月を「孟秋(もうしゅう)」、8月を「中秋」、9月を「季秋(きしゅう)」と呼んでいました。このことから、「中秋の名月」は、旧暦8月15日に見える月を指しているといえるのです。
■「歴史」は?
「お月見」の習慣は中国から伝わったといわれています。平安時代には貴族の間で盛んに行われ、美しい月を眺めながら、お酒を酌み交わしたり楽器を奏でたりして、宴を楽しんでいました。江戸時代になると、この習慣が一般庶民にも広まり、秋の収穫に感謝するお祭りのようになっていきました。現代にも、「中秋の名月」にはお月見をする習わしが残っていますね。
■「十五夜」との違いは?
「中秋の名月」は、「旧暦8月15日の月」であるとご紹介しました。そして「十五夜」とは、本来、旧暦で「15日の夜」を指します。従って、たとえ1月であっても7月であっても、厳密には15日であれば「十五夜」なのです。
「旧暦」は「太陽太陰暦」とも言われ、は月の満ち欠けを用いてつくられた暦で、明治5年までは日本でも使われていました。旧暦に対して、現在私たちが使っているのが「新暦(太陽暦)」ですね。
旧暦の基本となるのは新月です。月の満ち欠けの周期は多少変化するものの、平均して約29.5日。新月から数えて14日目から17日目が満月にあたるため、旧暦で15日の月は、毎月、満月か、もしくは満月に近い月ということになります。
とりわけ、秋は空気が澄んで月がとてもきれいに見えることから、古くから旧暦8月15日の「十五夜」は、一年のなかでも特別な「十五夜」と捉えられてきました。このような経緯で、「十五夜」は「中秋の名月」を指す言葉となったのです。
■実は「満月」でないこともある「中秋の名月」
多くの方が、「中秋の名月は満月」だと思っていることでしょう。でも実は、「中秋の名月」は必ずしも満月とは限りません。むしろ満月とはならない年のほうが多いのです。前述の通り、旧暦は月の満ち欠けを元にした暦で、新月で月がまったく見えない状態の日を毎月1日と数え、毎月15日に満月を迎えるとされていました。
しかしながら、「天文学的な意味での満月」は、地球から見て太陽と反対方向になった瞬間の月のこと。そして月の満ち欠けの周期はぴったり15日ではなく、およそ14.8日です。このわずかなズレのせいで、「中秋の名月」よりあとに、天文学的な意味での満月を迎えることが多いのです。
【2025年の「中秋の名月」はいつ?】
■2025年の「中秋の名月」はいつ?「満月」なの?
2025年の「中秋の名月」は、10月6日です。そして、翌7日が「満月」になり、日付が1日ずれます。次に「中秋の名月」と「満月」が同じ日付になるのは、2030年です。
■今後の「中秋の名月」は?
「中秋の名月」は毎年日付が変わります。2024年は9月17日でした。今年は10月6日ですから、想像以上にその日付には幅があるのですね。
2025年 中秋の名月:10月6日 満月:10月7日
2026年 中秋の名月:9月25日 満月:9月27日
2027年 中秋の名月:9月15日 満月:9月16日
2028年 中秋の名月:10月3日 満月:10月4日
2029年 中秋の名月:9月22日 満月:9月23日
2030年 中秋の名月:9月12日 満月:9月12日
【「食べ物」など「中秋の名月」にまつわる「雑学」】
■秋に「お月見」をするのはなぜ?
「満月」はだいたい月に1度は見られるものですが、なぜ「お月見」の行事は秋に行われるのでしょうか。その理由は、「空が澄んでいて、月の高さがちょうどいいから」といわれています。ご存知の通り、満月は夏に低く、冬に高く、空に昇ります。春と秋は満月が低すぎず高すぎずで、眺めるのにちょうどいい高さにあるのですが、「おぼろ月」という言葉もあるように、春は空気がかすんでいるため、月はくっきりとは見えず、かすんでいることが多いのです。
これに対して、秋の満月は、空に昇る高さがちょうどよく、空気も澄んでいるため、月がきれいに見えます。真冬の「お月見」は寒いですし、夏の暑さがひと段落し、過ごしやすい気候となる秋は、月を眺めるベストシーズンということになった理由のひとつといえるでしょう。
ちなみに、歳時記によると「月見」とは、旧暦の8月15日と9月13日の月を眺めて楽しむこと。「中秋の名月」に対して、9月13日のほうは「後(のち)の月見」と呼ばれます。つまり、お月見は2度行うもので、どちらか一方だけの月見をすることは「片月見」といって避ける地方もあるのだそう。旧暦9月13日を新暦になおすと、2025年は11月2日。10月6日にお月見をしたら、11月2日の月も鑑賞するのが、昔ながらの習わし通りなのですね。
■月見団子だけじゃない!中秋の名月にお供えするもの
・とはいえ、代表選手はやはり「お団子」
お月見といえば、月見団子が欠かせません。「中秋の名月」にちなみ、お団子を満月のような丸い形にしてお供えします。数は、十五夜ということもあり15個用意し、ピラミッド状に重ねていきます。頂上部分に置かれた一番上の団子は、霊界との架け橋になると考えられていたそうです。
・ススキなどの秋の七草
ススキも、「中秋の名月」にはマストなお供え物ですね。昔は農作物を収穫できたことに感謝し、芋や豆などもお供えしていましたが、稲はまだ収穫前だったことから、稲と似たススキを飾るようになったといわれています。また、ススキには魔除けの意味もあり、災いから家族や農作物を守るために飾られていた習慣が、現代にも残っているのです。
現代では「お月見といえば、お団子とススキ」というイメージが定着していますが、実は「中秋の名月」には、ススキをはじめ、「秋の七草」を飾るのがいいとされています。萩に尾花(おばな/ススキの穂)、撫子(なでしこ)、葛(くず)、女郎花(おみなえし)、桔梗(ききょう)、藤袴(ふじばかま)。これが「秋の七草」です。
・里芋など芋類
「お月見」でお団子を供えるようになったのは、中国で月餅を供える習慣が日本に伝わり、月見団子となったとされています。また、農家では稲の豊作を祈願するだけでなく、芋類の収穫祭としても「お月見」が行われていました。これは昔の主食が米ではなく、里芋などの芋類が食べられていた頃の名残。人々は団子と共に収穫したばかりの芋を供えたため、「中秋の名月」は別名「芋名月」といわれています。
■世界の「中秋の名月」
夜空に浮かぶ美しい月は、なんだか不思議なパワーに満ちているように感じられます。そのためか、「中秋の名月」には、世界各国でさまざまな行事が行われています。
・中国の「中秋節」
中国で中秋の名月に行われる伝統行事が「中秋節」と呼ばれるもの。中国では旧正月を祝う「春節」の時期に連休となり、多くの方が旅行に出掛けたり家族と一緒に過ごしたりします。中秋節にも同じように連休となり、中秋節は春節に次ぐ大きな祝日なのです。月餅や提灯などを飾り、お月見を楽しんだりする習慣もあるそうです。
・韓国の「秋夕(チュソク)」
韓国にも「中秋の名月」に関連した行事があります。それが「秋夕(チュソク)」で、「ハンガウィ」とも呼ばれます。旧暦の8月15日の前後1日を含めた3日間が祝日となり、親戚が集まってご先祖様のお墓参りに出掛けたり、秋の収穫をお祝いしたりします。日本では、お盆の時期になると里帰りしてお墓参りをしたり、家族で集まって食事を楽しんだりしますが、韓国にも、それと同じような風習として「秋夕」があるのです。
・アメリカの「ハーベストムーン」
アメリカでは、それぞれの月の満月に「〇〇ムーン」と呼び名が付けられています。例えば、2月は「Snow Moon(スノームーン)」、6月は「Strawberry Moon(ストロベリームーン)」という具合。そして9月の満月は、おおむね「Harvest Moon(ハーベストムーン:収穫月)」と呼ばれますが、「秋分の日」に最も近い満月を指すため、年により9月だったり10月だったりします。2025年のハーベストムーンは9月8日。作物の収穫を迎える繁忙期に、夜遅くまで作業を行う人たちを月明かりが照らしていたことに由来し、名付けられたそうです。
***
今年は例年以上に暑く長い夏が続いていますが、それを乗り越え、ようやく涼しい風が感じられるようになると、夜空の月も澄んで見えてきます。「中秋の名月」には「秋の七草」を飾り、美しい月を愛でながらゆっくりグラスを傾ける…そんな時間が叶わないなら、せめてビルの合間から覗く、まん丸な月を探してみてください。わけもなく胸がキュッとする…秋の月夜は、そんな美しさに満ちているはずです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社)/国立天文台(https://www.nao.ac.jp/) :