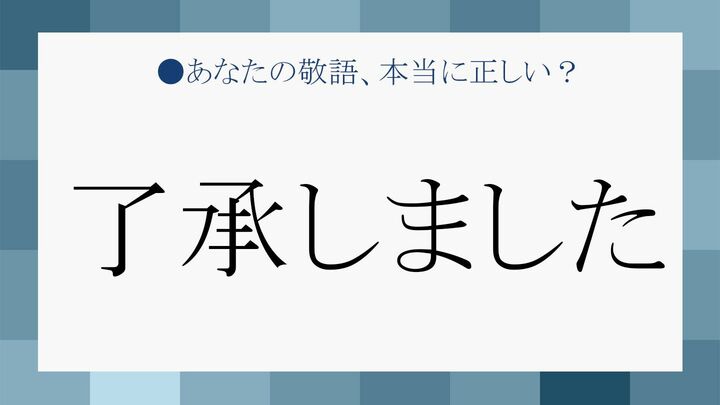【目次】
【「了承しました」の「了承」とは?意味】
■「意味」
「明日正午までの確認、了承しました」「あらかじめご了承ください」など、ビジネスの内外で目にする「了承しました」ですが、「了承」の意味をしっかり理解していますか? 『デジタル大辞泉』には、【事情を汲んで納得すること。承知すること。承諾。「了承を得る」「申し入れを了承する」「了承済み」】とあります。終了や完結を意味する「了」と、受け入れる動作を表す「承」の組み合わせである「了承」は、ある事柄を受け止めるだけではなく「納得して承知、承諾すること」なのです。
■「了解」「承知」との違い
似たような言葉の「了解」や「承知」はどうでしょうか。いずれもビジネスメールや電話でも頻繁に使いますね。「了解」と「了承」はどちらも「事情や内容を理解して受け入れること」と、はっきりと意思を感じさせる言葉。それに比べると「承知」は少々あいまいな表現で、「知っている」「理解している」くらいのニュアンスです。
【「了承しました」は正しい「敬語」?】
■「正しい敬語」といえる?
敬語には、以下の3種類があります。
・敬う気持ちを表現する「尊敬語」(お話しくださる、ご利用なさる、〇〇様、〇〇先生、など)
・へりくだって敬意を表す「謙譲語」(いただく、申す、うかがう、拝見する、など)
・丁寧な言い方で敬意を表す「丁寧語」(です、ます、ございまます、など)
「了承しました」は丁寧語にあたるので、これも立派な敬語です。ただし、相手の依頼やお願いごとに対して「OKですよ」と受け入れるニュアンスなので、目上の人に対して使うのはふさわしくありません。上司には「了承しました」ではなく「承知しました」が正解。「承知する」は「わかる(=了解する)」の謙譲語だからです。「了承」は、同僚や部下、後輩など、自分と同等以下の相手に使用するべきと心得て。
■「了承です」は失礼?
「了承」は名詞ですし、「了承する」の形で動詞としても使えます。 「です」は丁寧な断定の助動詞で名詞に付くのが本則ですから、「了承です」は文法的に誤りではありません。とはいえ、違和感のある表現ですね。少なくとも、上司や取引先に対し使う言葉ではありません。
■「了承いたしました」は間違い?
「了承いたしました」は「いたす」という謙譲語が含まれているため文法的には正しい敬語表現です。ただし、繰り返しになりますが、「了承」という言葉には相手の依頼やお願いごとを「OKですよ」と受け入れるニュアンスがあるため、ほとんどの場合、目上の人が目下に対して使います。丁寧な印象はあるものの、「了承」という言葉の印象を考慮すると、少々違和感のある表現でしょう。あえて使わずとも、「承知しました」「うけたまわりました」でいいのでは。
【そのまま使える「例文」】
■同僚や部下に対して…「了承」の例文
「了承」とは場合によっては少しカジュアルなニュアンスも含む「丁寧語」。従って、同僚や部下、後輩といった立場の人に対して使える「例文」を見てみましょう。
(1)「○○社へのプレゼンの件、了承しました」
(2)「時間がかかる旨、了承しておりますのでご安心ください」
(3)「昨日の提案、皆さん了承済みでしょうか?」
■意味を正しく理解して…「了承」を使った定型文
「了承」とは「事情や内容を理解して受け入れること」。その意味をしっかり把握した上で使いたい、丁寧な印象を与える「例文」を見てみましょう。
(1)「ご了承のうえご利用くださいますようお願いいたします」
(2)「大変ご不便をおかけしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます」
【「かしこまりました」など「言い換え」表現とそれぞれの意味の違い】
■「言い換え」表現
・了解
「了解」に関しては、事情が少々複雑です。もともと「了解」は「はっきりとよくわかること。よく理解すること」という意味の言葉で、「了解いたしました」と使えば、「承知いたしました」同様、目上の方にも失礼な要素はありません。しかしながら、ネットなどでは「『了解』という言葉を目上の方に使うのは失礼だ」といった論調が強く、その感覚は次第に定着しつつあります。「了解しました」を不快に思う人が一定数いるのがわかっているのであれば、あえて目上の人に使う必要はありませんね。
・承諾
「相手の意見や希望、要求などを聞いて、受け入れること」の意味で使われます。法律の分野では「申し込みに応じて契約を成立させる意思表示」となり、「一定の事実の承認、または同意の意」に用いられることもあります。
・承(うけたまわ)る
「承る」は「受ける」「聞く」「伝え聞く」「引き受ける」の謙譲語です。「了承」が多くの場合、目上の人が目下に対して使う言葉であるのに対し、「承る」は「ご依頼の件、承りました」のように、目下から目上の人に対して使われます。
■「かしこまりました」との違い
「かしこまりました」と「承りました」は、どちらも謙譲語で、ほぼ同じシーンや相手に使用できます。ただし、「かしこまる」は漢字で「畏まる」と表記することからもわかるように、相手を恐れ敬う気持ちを表す言葉です。相手への敬意は「かしこまりました」のほうがより強く、より丁寧です。そのため、接客サービスなどの現場では「かしこまりました」が頻繁に使われているのです。
■「承知しました」との違い
「承知」は「相手の申し入れや頼みをききいれること」。相手の頼みを「了承」するのは目上の人ですが、「承知」するのは目下の人、と、使い方の違いを覚えておきましょう。
***
「了承しました」「承知しました」といった言いまわしは、ビジネスの現場では同じように使われがちなフレーズですが、使っては失礼にあたる相手や、ふさわしくないシーンがあることがわかりました。敬語である「丁寧語」「謙譲語」「尊敬語」の使い分けは難しいものですが、相手によってとっさに使い分けできるようにしたいものですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『精選版日本国語大辞典』(小学館)/『とっさに使える敬語手帳』(新星出版社)/『すぐに使えて、きちんと伝わる敬語サクッとノート』(永岡書店)/『印象が飛躍的にアップする大人の「言い方」練習帳』(総合法令出版)/『心理学的に正しい!人に必ず好かれる言葉づかいの図鑑』(宝島社) :