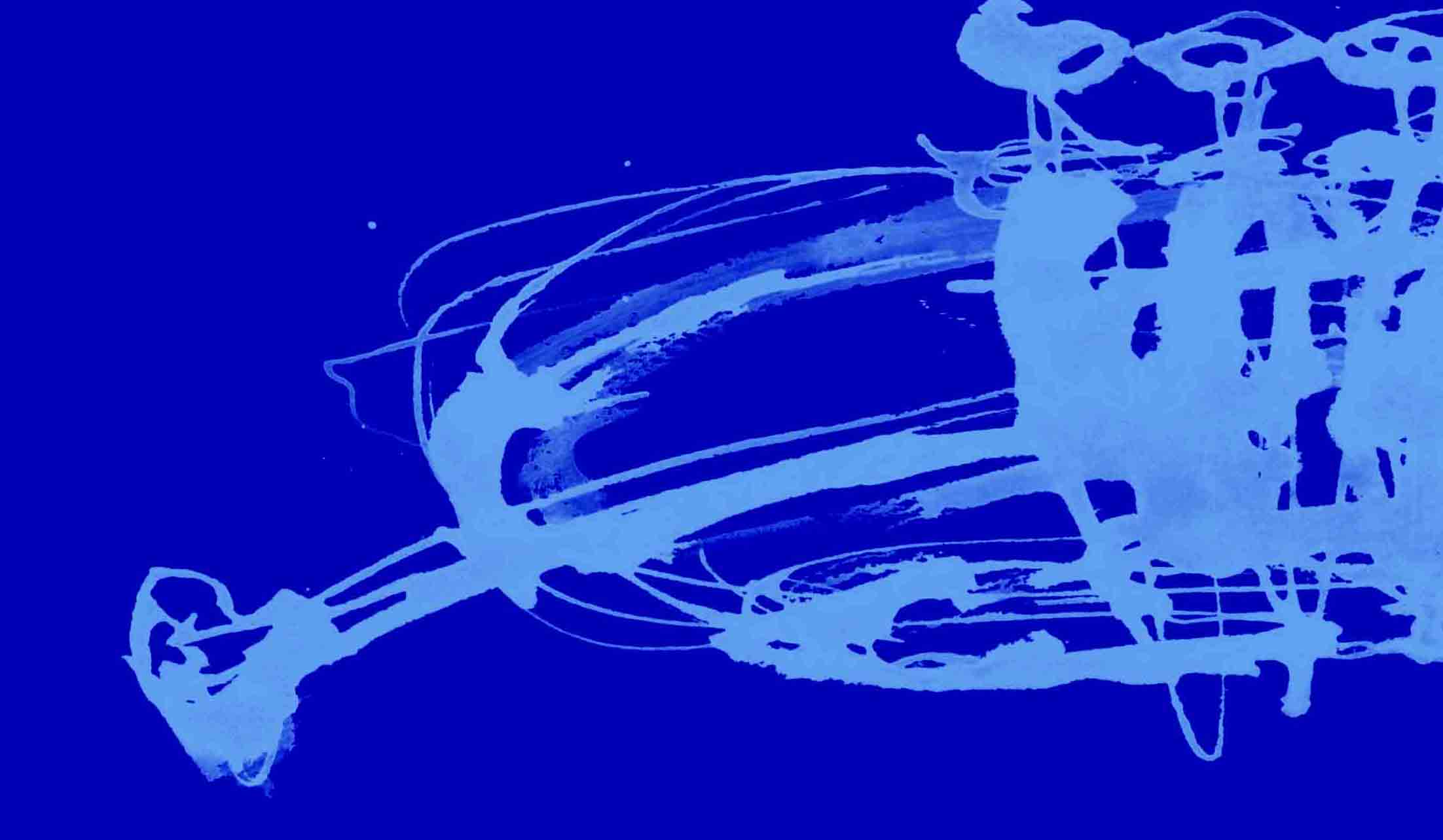「この曲は青い」と作曲家が発した言葉がタイトルになったという『ラプソディー・イン・ブルー(青の狂詩曲)』。その演奏を聴けばわかる通り、ここでのブルーには、ジャズの含意がある。
ジョージ・ガーシュインの頭の中で、黒人霊歌〜ブルーズ〜ジャズという流れが成立していたかは不明だが、ジャズ・エイジからハーレム・ルネサンスへと推移する1920年代のニューヨークにおいて、それは体感されていたのではなかろうか。そしてハーレムから遠く、ミッドタウンのエオリアンホールで初演された『ラプソディー・イン・ブルー』は、現在から見れば、ダンス音楽から音楽芸術へと発展するジャズの歩みを先んじたものだった。
コードとインプロヴァイズ(即興)、そしてインタープレイがジャズの真骨頂とすれば、明確にスコア化された音楽は、ジャズとはやや異質かもしれない。その一方で、音楽がエスタブリッシュされる手段として、当時楽譜は欠かせないものだった。白人音楽家によるスコアリング、その事実こそ、ジャズの普遍化の証明に他ならない。音楽という芸術が行き渡りはじめた20世紀初頭の大衆に、ジャズはこうして、「青」という色とともに、紹介されたのだった。
それから35年後、大戦が終わり、ジャズ、なかでもビ・バップやハード・バップがポピュラー音楽を席巻する中、1枚のアルバムが出現する。『カインド・オブ・ブルー』、作者はマイルス・デイヴィス。
既にジャズ界のスターだった彼は、このアルバムで自らのジャズをコード進行に支配されるバップから、スケール(音列)をベースとした「モード・ジャズ」へと大きく舵を切った。
ジャズの音楽理論上革新的な出来事であった一方、リスナーたちは、そこで提示されていたミニマルでリニアな音の肌触りを新しいサウンドとして支持した。この作品における、モード・ジャズの共同制作者ビル・エヴァンスは、ライナーノーツで日本の水墨画に言及している。かくして聴き手の脳裏には、青い墨で描かれた線画のヴィジョンが現れたに違いない。
ところで、現代の私たちは、マイルス・デイヴィスが、ジャズの範疇を超え、常に自身にとってオリジナルな音楽を求め続けた求道者であったことを知っている。その視座から見たとき、この『カインド・オブ・ブルー』は、マイルスの生涯続く音楽的冒険のスタートだったのではないか。『ビッチェズ・ブリュー』も『オン・ザ・コーナー』も『ドゥー・バップ』も、このアルバムを起点として、導かれたのだ。
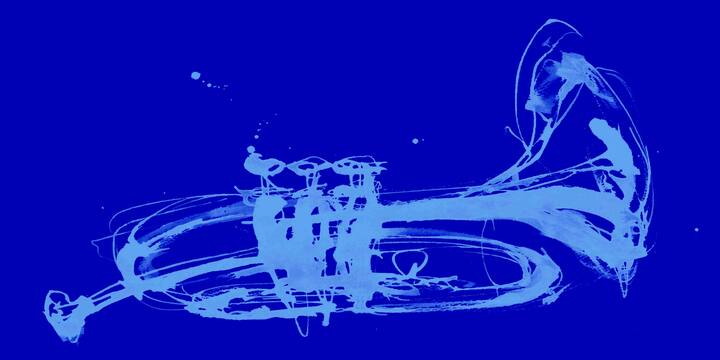
自身の音楽的更新に「青」を冠したマイルスと対照的に、ひとつの「結び」に「青」と題したアーティストがいる。ジョニ・ミッチェル。カナダ出身のフォークシンガーとして、ディヴィッド・クロスビーのプロデュースでアルバムデビューし、「ビッグ・イエロー・タクシー」などのヒット、さらには「青春の光と影」「サークル・ゲーム」「ウッドストック」の作者として、フラワームーヴメントで盛り上がる時代を彩る女性シンガーソングライターとなった。
しかし、ウッドストックを経験しなかった彼女が参加したワイト島ロックフェスティヴァルは、混乱の中で幕を閉じ、皮肉にもラヴ&ピースの時代の終焉を象徴することとなった。その翌年に発表されたアルバム『ブルー』。
タイトル曲は、カナダ出身のシンガーソングライター、ディヴィッド・ブルーとの恋を歌ったものだが、アルバムタイトルとしての「ブルー」の意味合いは、パーソナルな逸話だけに帰結されるものではないだろう。シンガーソングライターとしての魅力が十二分に盛り込まれたその音楽には、彼女がワイト島ロックフェスにて、暴れる観客に対し発した「頭冷やして、考えるべき時じゃない?」という問いかけが、通奏低音よろしく、横たわっているようだ。この後アルバム『バラにおくる』を経て、彼女は自身の音楽をがらりと変える。ウエストコーストのジャズ&フュージョンミュージシャンたちと生み出した『コート・アンド・スパーク』から、ジョニの音楽性はフォークやロックなどのカテゴリーを軽々と超え、新たな次元へと進む。彼女にとって、青は過ぎ去りゆく青春の色、そして決意の色となった。
1990年代以降、ポピュラー音楽は安易なジャンル分けを許さないほど混沌としたものになった。音楽の場としてクラブやレイヴ等が重要度を増すなか、コンピュータライズやターンテーブライズが加速した。そんな時代を先駆けたサウンドが、マッシヴ・アタックのデビューアルバム『ブルー・ラインズ』である。そのタイトルはクラブカルチャーの影の部分である、ドラッグを含意しているといわれるが、当時リスナーを驚かせたのは、音楽の全編に漂うメランコリックでヘビーなムードだった。
ブレイクビーツやヒップホップなど、クラブサウンドに端を発しながら、フロアのスポットライトが当たる部分ではない、むしろ、その周縁の闇を表したかのような音楽。その「オフ/クラブ」的な存在感が、英国のみならず、世界中で支持されたのだった。彼らがこのアルバムで提示した音楽は後に「トリップ・ホップ」と名付けられた。クラブライフの陰画として日常をブルーに、感覚的に描写するそのスタンスは、例えばFKAツイッグスのサウンドなどに、今なお受け継がれている。
時代もジャンルも異なるこれらの作品を聴くと、共通点というか、ある言葉が頭をよぎる。それは「孤高」の二文字だ。いずれの音楽も、自身の美意識に拠って、時の趨勢に対し屹立している。その表現は決して声高ではなく、あえて抑制的に、ゆえに強く、聴く者に迫る。それは「青」という色の存在感とオーバーラップする。彼らはタイトルに選んだ青について、そこまで意識はしていなかったかも知れない。しかし、これらの音楽と出合い、心打たれたリスナーは、そこに青の導きを感じずにはいられないのだ。
- TEXT :
- 菅原幸裕 編集者
- BY :
- MEN'S Precious2015年春号 男たちを魅了した「青」の記憶
- クレジット :
- アートワーク/FRANERO(HUESPACE) 構成/菅原幸裕