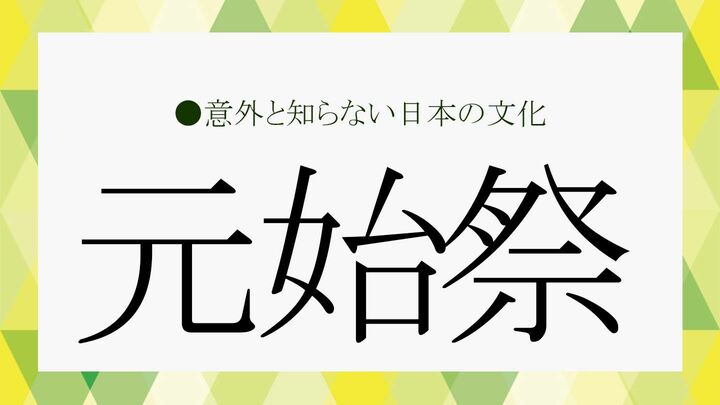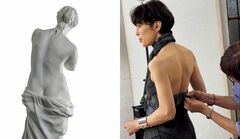【目次】
- 元始祭とは?2026年1月3日に行われる皇室行事の意味と由来
- 元始祭の歴史|明治から続く皇位のはじまりを祝う祭祀
- 元始祭にまつわる豆知識3選(皇室祭祀、祝詞、伊勢神宮)
- 2026年の初詣、いつまでOK?元始祭と関連づけて考える
- 【2026年版】恵方はどっち?運気アップの参拝豆知識
- 参拝マナーの基礎|大人が知っておきたい神社の作法
【元始祭とは?2026年1月3日に行われる皇室行事の意味と由来】
■読み方
「元始祭」と書いて「げんしさい」と読みます。
■意味
「元始祭」は、1872(明治5)年に制定された皇室祭祀のひとつで、天皇陛下が御自ら、皇位の始まりを祝います。毎年1月3日に皇位の元始を寿(ことほ)ぎ、賢所(かしこどころ)、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)の宮中三殿で行われ、1947(昭和22)年の皇室祭祀令廃止後も、皇室の私事として施行されています。
■何をする?
宮中では、宮中三殿において天皇陛下が国家国民の繁栄を祈りご親祭されます。また全国の神社でも、皇室の繁栄と国家の平安を祈る元始祭が執り行われています。例えば伊勢神宮では、1月3日の早朝4時から外宮(豊受大神宮)にて、7時から内宮(皇大神宮)にて諸宮社へ祭りを奉仕します。
1月3日に初詣に出かけたら、「今日は元始祭だな」と思い出してみてください。
【元始祭の歴史|明治から続く皇位のはじまりを祝う祭祀】
「元始祭」の起源は1870(明治3)年1月3日、神祇官八神殿(じんぎかんはっしんでん)に八神、天神地祇 (てんじんちぎ) 、そして歴代皇霊を鎮祭したことに始まります。「元始祭」という名称は『古事記』にある「元始綿邈(げんしめんばく)」からとられました。
「元始祭」は1908(明治41)年制定の「皇室祭祀令」で大祭に編入され、1927(昭和2)年の公布で「祭日および祝日」と定められました。第二次世界大戦後に国民の祝日からは外れましたが、宮中では旧来どおりの方式で祭儀が営まれています。
【元始祭の歴史概要】
起源:1870年1月3日、神祇官八神殿で行われた鎮祭がはじまり
名称の由来:『古事記』にある「元始綿邈(げんしめんばく)」から
法的な変遷:
・1908年:皇室祭祀令で「大祭」に指定
・1927年:「祭日および祝日」に制定される
・1947年:祝日から外れるも、宮中祭祀として継続
【元始祭にまつわる豆知識3選(皇室祭祀、祝詞、伊勢神宮)】
■祝詞に込められた意味
祭祀に祝詞(のりと/神前に奏上する言葉)はつきもの。「元始祭」の祝詞で詠み上げられる「元始(もとつはじめ)」は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を天上の高天原(たかまのはら)から地上の豊葦原中国(とよあしはらのなかつくに/日本の別名)に遣わされたことが「元始」であると述べています。
この瓊瓊杵尊の血統を継ぐ初代神武天皇から、現在の第126代天皇に至るまで、万世一系(ばんせいいっけい/永久にひとつの系統が続くこと)の血脈が継承されてきたことが、国土を治める由来でもあると言っているのです。
■皇室祭祀とは?
皇室で執り行われる祭祀は主に神道的儀式を基本としています。そのなかには「新嘗祭(にいなめさい)」など古代からの祭祀を継承したものや、「元始祭」のように明治維新後の神道国教化政策や、神仏分離政策の影響を受けて新たに定められた神道祭祀なども。
年間さまざまな皇室祭祀が行われていて、宮内庁ホームページでは「主要祭儀一覧」として24の祭祀を紹介。例えば、元日には「四方拝(しほうはい)」と「歳旦祭(さいたんさい)」、1月3日の「元始祭」、1月4日の「奏事始(そうじはじめ)」と、年明けは祭祀が目白押し。1月2日には新年祝賀と一般参賀があるので、皇室の方々は新年から連日大忙しなのです。
■伊勢神宮の元始祭(2026年)
伊勢神宮では2026年1月3日も、以下のように元始祭が奉仕されます。
外宮(豊受大神宮):午前4時〜
内宮(皇大神宮):午前7時〜
全国の主要な神社でも元始祭が行われます。初詣がてら訪れる際は、「今日は元始祭だな」と意識すると、より意味深い参拝になります。
2026年の初詣、いつまでOK?元始祭と関連づけて考える
1月3日の「元始祭」にちなみ、初詣についても触れておきましょう。
初詣とは、新年最初に神仏に参詣することを指します。古くは、大晦日の夜から元日にかけては地域の氏神にこもって年を越すことを言いました。初詣は「恵方参り」とも言い、その年の恵方にある社寺に参詣する例も多いです。そこで初日の出を拝んだり、「初詣が済むまでは途中で人に会っても言葉を交わさない」などの習慣がある地域も。
初詣は松の内の期間に…と言われることが多いですね。松の内とは年神様の依代である松を飾っておく期間のこと。先祖である年神様をお迎えして、一年の安寧と無病息災を願って祝う日本古来の行事です。その期間は地域によって異なり、関東では1月1日から7日までが一般的ですが、1月15日までという地域もあります。2025年にかかわらず、松の内は毎年1月7日までか15日までと覚えておきましょう。
けれど、新年最初に神仏に参詣することが初詣です。松の内を過ぎても安心して参拝してくださいね。
【2026年版】恵方はどっち?運気アップの参拝豆知識
■2025年の恵方は西南西
自宅や職場など、日常的にいる場所から西南西の方向にある寺社にお参りするといいかもしれません。
参拝マナーの基礎|大人が知っておきたい神社の作法
鳥居をくぐる際にはその手前で一礼を。参道の中央は神様の通り道といわれているので、歩くのを避けるといいでしょう。帰りも同様です。
手水舎で手や口を清めますが、コロナ過以降、手水を使えないようにしたり廃止している神社も少なくないようです。その場合はハンカチやウエットティッシュなどでぬぐう、あるいは気持ちだけでも心を静めて清らかに…を心掛けて。
本殿や拝殿では、賽銭箱に賽銭を入れ(よっぽど混雑していない限り、投げ入れるのではなくそっと落とし入れるのが大人のマナーです!)、鈴があれば振り動かして鳴らします。これは「本坪鈴(ほんつぼすず)」と言い、その清々しい音色で参拝者を敬虔な気持ちにする共に、参拝者を祓い清め神霊の発動を促すのだとか。
そして二礼二拍手ののち合掌して祈願や感謝などを唱え、一礼して終了です。
ちなみに、寺院参拝では拍手(かしわで)は打たないので気を付けて!
***
「元始祭」は、ニュースで取り上げられることも少ない皇室行事ですが、知っているとちょっと差がつく教養のひとつ。年始のご挨拶や初詣の話題が飛び交うこの時期、「1月3日は元始祭なんですよ」とさらりと話せたら、知的で品のある印象を与えられるはず。歴史や文化をさりげなく語れる大人の女性は、社内外の信頼感にもつながります。忙しい新年こそ、少し立ち止まって“日本らしさ”に触れてみてはいかがでしょうか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/宮内庁・神社本庁・伊勢神宮・東京都神宮庁ホームページ :