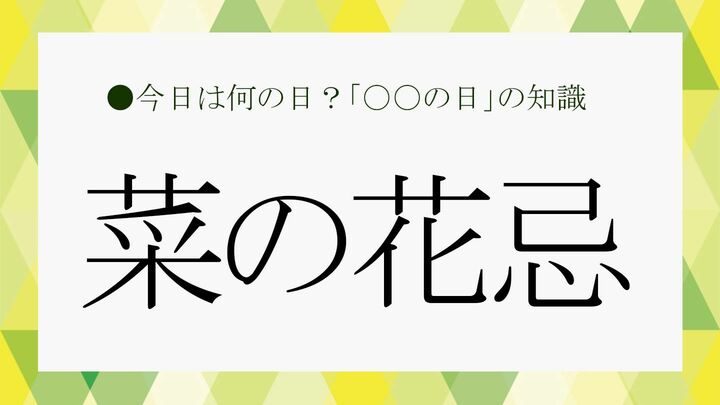2月12日の「菜の花忌」は、小説家 司馬遼太郎の忌日名です。今回は「忌日」の意味や「菜の花忌」にまつわる雑学をご紹介します。
【目次】
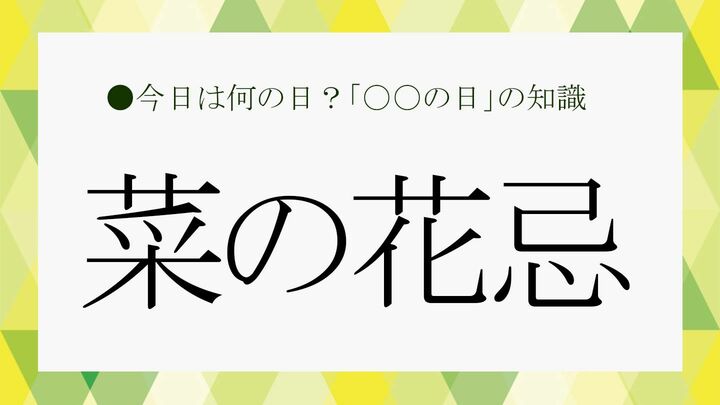
【「菜の花忌」の「読み方」「意味」「由来」】
■「読み方」
「菜の花忌」は「なのはなき」と読みます。
■「意味」
「菜の花忌」は、小説家、司馬遼太郎の忌日として知られ、日付は2月12日です。「忌」の文字があることから、人の死に関わる神聖な事柄であると推測できますね。
■「由来」
司馬遼太郎が菜の花を好んだこと、また、作品『菜の花の沖』があることに由来します。
【ビジネス雑談に役立つ「菜の花忌」の雑学】
■「忌日」って何?
「忌日」は「きにち」もしくは「きじつ」と読みます。その人が「亡くなった日にあたる日」を意味し、「命日」とほぼ同義で使われます。「初七日」や「一周忌」、「二十三回忌」など、「忌日」を基準とした忌日法要は皆さんご存知ですね。「忌日」も同様に、毎年または毎月、成仏を願う仏事供養である法要が行われます。
「忌日」は「いみび」とも読みますが、こちらは「けがれを避けて慎むべき日、物忌みの日、縁起の悪い日」という意味になります。「きじつ」とは区別して使いましょう。
■司馬遼太郎著『菜の花の沖』
司馬遼太郎の小説に『菜の花の沖』という作品があります。主人公は、江戸後期の豪商・高田屋嘉兵衛。淡路島に生まれ、貧しい境遇から海の男として身を起こし、たったひとりで大国ロシアと外交を繰り広げ、数奇な運命を生き抜いた快男児の生涯が、雄大なスケールで描かれています。文春文庫版で全6巻。司馬作品のなかでは『翔ぶが如く』(10巻)、『竜馬がゆく』(8巻)、『坂の上の雲』(8巻)に次ぐ大長編です。
■司馬遼太郎は黄色好き
司馬遼太郎は野に咲く花、とりわけタンポポや菜の花などの、黄色い花が好きだったそうです。大阪府東大阪市の住宅街の一画にある司馬遼太郎記念館は、司馬遼太郎の自宅と隣接地に建つ安藤忠雄さん設計のコンクリート打ちっ放しの建物で構成されています。司馬遼太郎は書斎の前に菜の花を植えて、春の開花を楽しみにしていました。現在でもボランティアの方々により、毎年可愛らしい菜の花が見られます。司馬遼太郎記念館では毎年、菜の花忌シンポジウムが開催されています(2025年の申し込み受け付けは終了しました)。
■「忌日」を「菜の花忌」とする著名人はほかにもいます
実は「菜の花忌」を忌日名としているのは、司馬遼太郎だけではありません。ひとりは浪漫派の詩人、伊東静雄。こちらは3月12日です。そして歌人、前田夕暮(ゆうぐれ)の忌日も「菜の花忌」と呼ばれており、4月20日です。
詩人・伊東 静雄は1906(明治39)年12月10日生まれ。 命日は1953(昭和28)年3月12日。現在の長崎県諫早(いさはや)市出身で、京都帝国大学文学部国文科在学中の1928年に懸賞募集児童映画脚本の童話『美しき朋輩達』が一等当選となり、映画化されています。
生涯にわたり教職を離れなかった伊藤静雄は、友人と同人雑誌「呂(ろ)」を創刊し、毎号詩を発表していました。その詩を萩原朔太郎が激賞しています。作品に『わがひとに与ふる哀歌』(1935年)、『夏花』(1940年)など。諫早市では、諫早市美術・歴史館にて、伊東静雄を偲び功績を顕彰する「菜の花忌」が、毎年3月の最終日曜日(2025年は3月30日)に開催されています。
前田夕暮は1883(明治16)年、神奈川県大住郡南矢名村(現在の秦野市南矢名)生まれ。1910(明治43)年、処女歌集『収穫』を刊行し、同時期に『別離』を出した若山牧水と共に自然主義の代表歌人として注目され「夕暮・牧水時代」と称される一時代を築きました。白日社を興し、短歌雑誌「詩歌」を毎月発行。三木露風、山村暮鳥、斎藤茂吉、室生犀星、萩原朔太郎、高村光太郎など、たくさんの詩人や歌人に活躍の場を与え、多くの歌人たちを育てています。1951(昭和26)年4月20日に、67歳で逝去しました。
***
司馬遼太郎の長編小説『菜の花の沖』は、 2013年12月にNHK「放送開始75周年記念番組」としてドラマ化されています。主演は竹中直人さん。DVDが発売されています。一方、小説は文庫版で全6巻と大作ですが、菜の花忌をきっかけに、挑戦してみるのもいいかもしれません。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:/『デジタル大辞泉』(小学館) /『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /司馬遼太郎記念館(https://www.shibazaidan.or.jp) :