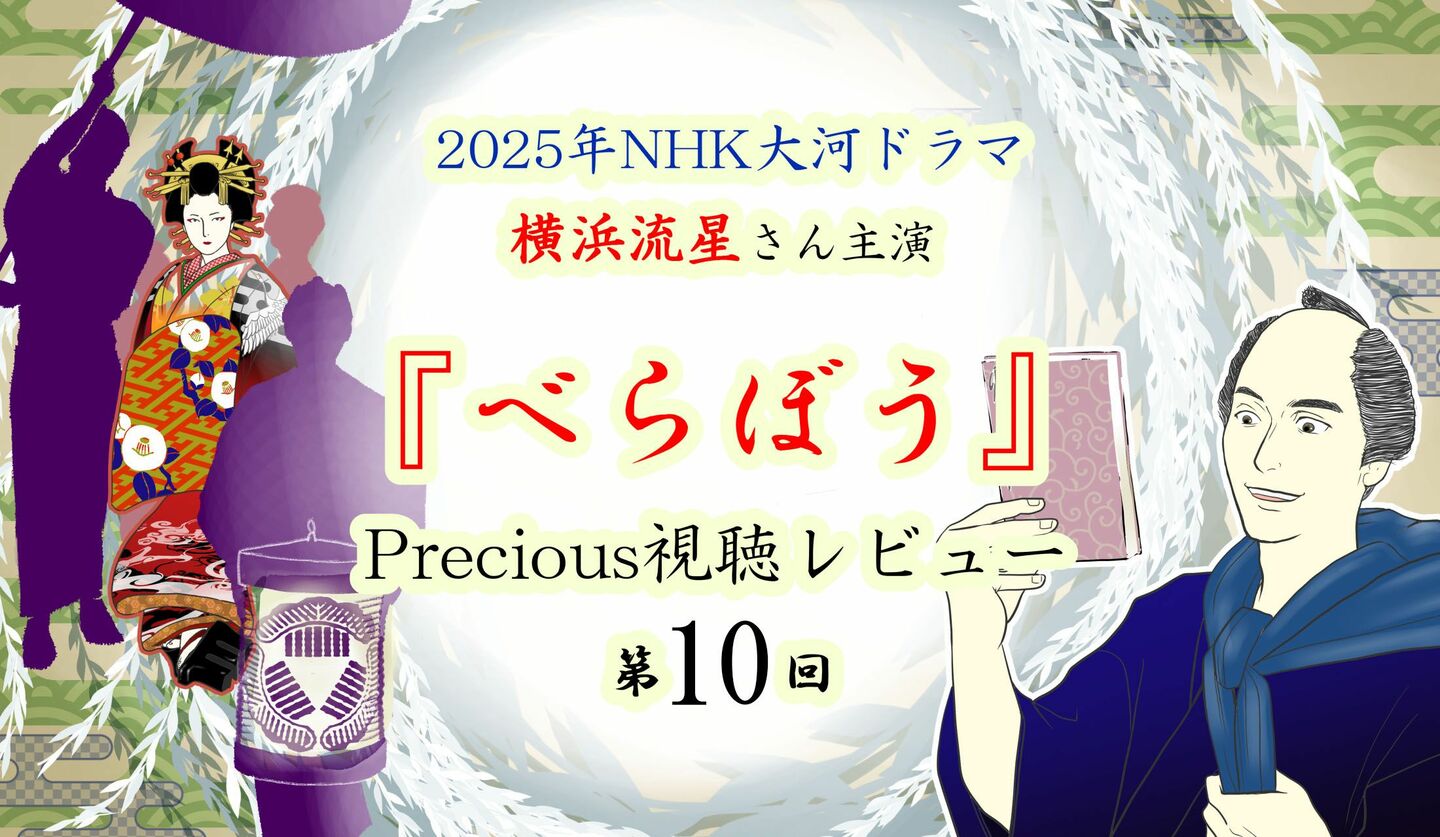【目次】
【これまでのあらすじ】
江戸時代中期の吉原を舞台に、喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽といった才能あふれる浮世絵師を世に送り出し、「江戸のメディア王」として名を馳せた版元、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星さん)の人生をエンターテインメントの要素たっぷりに描く『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。第10回は、烏山検校(市原隼人さん)に身請けされた瀬川(小芝風花さん)が吉原を出るタイミングに合わせ、次に人気にさせたい女郎たちを紹介する錦絵本をつくるため、蔦重が奔走するというお話。
この錦絵本は、1776(安永5)年に初版が売り出された『青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)』のこと。瀬川が身請けされたのが1775(安永4)年ですから、忘八衆の最初のターンで「(瀬川の)最後の花魁道中は暮れだっけ?」「正月なら、そこで細見もさばけたのにね」「暮れに売っちまいやいいじゃないか」云々、といった年をまたぐかどうか、といったやりとりは、史実との辻褄もグラデーションにする絶妙な演出です。
『青楼美人合姿鏡』とは
『青楼美人合姿鏡』は、『べらぼう』第3回で『一目千本』を手掛けた北尾重政(橋本淳さん)とドラマでは「家も近所だし」という設定の勝川春章(前野朋哉さん)というふたりの浮世絵師による、女郎たちのプライベート(風)な姿を描いた錦絵本で、蔦屋重三郎が山崎屋金兵衛という地本問屋との共販として出版されました。
当時、本は株仲間である地本問屋がからんでいないと流通経路が断たれ、出版できないことになっていた、というのは、第4回で思い知ったわけですが、いきなり出てきた山崎屋金兵衛という人物。え? 誰?となりますが、今回の物語にはさほど関係ないのか、『青楼美人合姿鏡』の奥付に名前があったのみ。当然実在する人物で実績もあります。きっと蔦重の人柄による人脈でつながり、彼の英知に惚れて味方になってくれたのでしょう。
さて、書籍のタイトルをひも解いていきましょう。「青楼」とは遊郭の別称。「美人」というのは、各店の美人どころ、つまりトップの女郎たち、という意味と推測できます。そして「合姿鏡」というのは、豪華で美しい色彩と、リアルなその画風から、絵本を開けば向かい合わせで姿鏡を覗いているかのように、彼女たちの日常の姿が楽しめる、といったところでしょうか。
実際、東京国立博物館のウェブサイトで閲覧できる内容を見てみると、美しく、高級そうな衣装をまとった女郎たちが、晴れやかな庭やモダンな室内で読書や書き物をしたり、鳥を愛でたり、花を生けたり、投扇興(とうせんきょう/扇を投げて蝶の的に当てる遊び)や囲碁、楽器の練習をしたりといった、優雅な姿が。蔦重の「吉原を江戸っ子が憧れる町にしてぇのよ」「俺はここを楽しいばかりのとこにしようと思ってんのよ。売られてきた女郎がいい思い出いっぱいもって、大門を出ていけるようにしたくてよ」というセリフ通りの、煌びやかな夢を見させる一冊であったことがうかがえます。
【白無垢の花魁道中って本当にあったの?】
そして瀬川は白無垢姿で最後の花魁道中に臨みます。その美しさはSNSを大いに沸かせました。「蔦重といるときのかわいらしさと、色気のギャップがすごい」「(小芝風花さんの)演技力に飲まれた」「ありがた山です」「べらぼうじゃなくてブラボー!」とベタぼめ。実際、瀬川が歩いた道中を上から撮影したシーンで土の道に残る、完璧な外八文字の美しさは、見事としか言いようがありません。
とはいうものの、映画『吉原炎上』(1987年)での名取裕子さんを筆頭に、映画やドラマで数々の花魁道中を見てきた人たちも、「身請けのときは白無垢を着て花魁道中をするの?」と疑問に思ったのではないでしょうか。ネットには瀬川ラストの花魁道中を花嫁道中としている向きも散見されますが、「花嫁道中」とは、ドラマ『ゆとりですがなにか』(2016年、日本テレビ系)を観ていた人などは思い出せるかもしれません、地方に今も残る、新郎新婦が結婚式場などに向かう昔ながらのパレード的なもの。ちょっと違う気がします。
ただし、1822(文政5)年から1823(文政6)年ごろの初代歌川国貞(くにさだ)の作品として「江戸新吉原八朔(はっさく)白無垢の図」という3人の花魁を描いた浮世絵があります。その説明によると、毎年8月1日、徳川家康が江戸に入府したことを記念し、幕府では白帷子(しろかたびら)に長袴で待つ大名たちのもとに、同じ格好で将軍がお目見えする、という行事が行われていて、吉原ではそれをまねて、その日になると、女郎たちが白無垢を着て花魁道中をした、とのこと。つまり少なくとも、年に1回は白無垢の花魁道中があったということです。イレギュラーではあるかもしれませんが「瀬川烏山事件」と語り継がれるほど高額(1400両!)で身請けされた瀬川の最後の花魁道中なら、そうだったかも…と思わせるところがありました。
とはいえ、筆者には、この「江戸新吉原八朔白無垢の図」のお着物が、どうしても白無垢には見えないのです。だって柄なんです。華やかにするためにデフォルメしたということなのでしょうか…。気になる人は、東京都立図書館のデジタルアーカイブや神奈川県立歴史博物館のサイトで見られるので、ご自身の目で確かめてみてください。そしてぜひ感想を教えてください。
とにもかくにも第10回は、視聴者が瀬川(小芝風花さん)を温かく送り出すための回だったと感じました。心を通わせたのに初恋叶わず、裕福だとはいえ、かなり厳しい取り立てを行う金貸し業で財をなしたという烏山検校に金で買われて嫁ぐのが果たして幸せか、めでたいのか、というのは令和を生きる庶民としてはもやもやします。しかし、当時の、しかも吉原では、シンデレラストーリー(というのも現代でははばかられますが)と言っていいわけで、部外者がケチをつけるのは野暮なだけ。乱暴なし、むしろ気遣いすら見せる忘八衆、出版にあたっての蔦重ピンチなし、西村屋の嫌がらせや嫌味もなし、吉原で苦しい生活を強いられている女郎たちの姿はプレイバックのみという展開は、見る側を優しい気持ちにさせ、瀬川の落籍を心から祝福するモードに入るのに、しっかり機能していました。
気になるのは、瀬川を迎えたときの吉原大門を見る(盲目ですから実際には見てはいませんが)烏山検校の険しい顔、そして、「うちの細見が売れなくなるよ!」と慌てている西村屋から受け取った『青楼美人合姿鏡』をめくりながら「ご案じなく、これは売れませんよ」と言ってニヤリと笑う鶴屋(風間俊介さん)でのエンディング…。穏やな気持ちで見られる回は、まさかこれきり? 蔦重の新たなピンチが始まる予感です。
【次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第11回 「富本、仁義の馬面」のあらすじ】
『青楼美人合姿鏡』が高値で売れず頭を抱える蔦重(横浜流星さん)は、親父たちから俄(にわか)祭りの目玉に浄瑠璃の人気太夫・富本豊志太夫/午之助(寛一郎さん)を招きたいと依頼される。りつ(安達祐実さん)たちと芝居小屋を訪れ、午之助に俄祭りの参加を求めるが、過去に吉原への出入り禁止を言い渡された午之助は、蔦重を門前払いする。そんななか、鳥山検校(市原隼人さん)が浄瑠璃の元締めだと知った蔦重は、瀬川(小芝風花さん)のいる検校の屋敷を訪ねる。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第10回 「『青楼美人』の見る夢は」のNHKプラス配信期間は2025年3月16日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 簗場久美子
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『初めての大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~歴史おもしろBOOK』小学館)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社)/『大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~蔦屋重三郎とその時代』(宝島社)/『デジタル大辞泉』(小学館) :