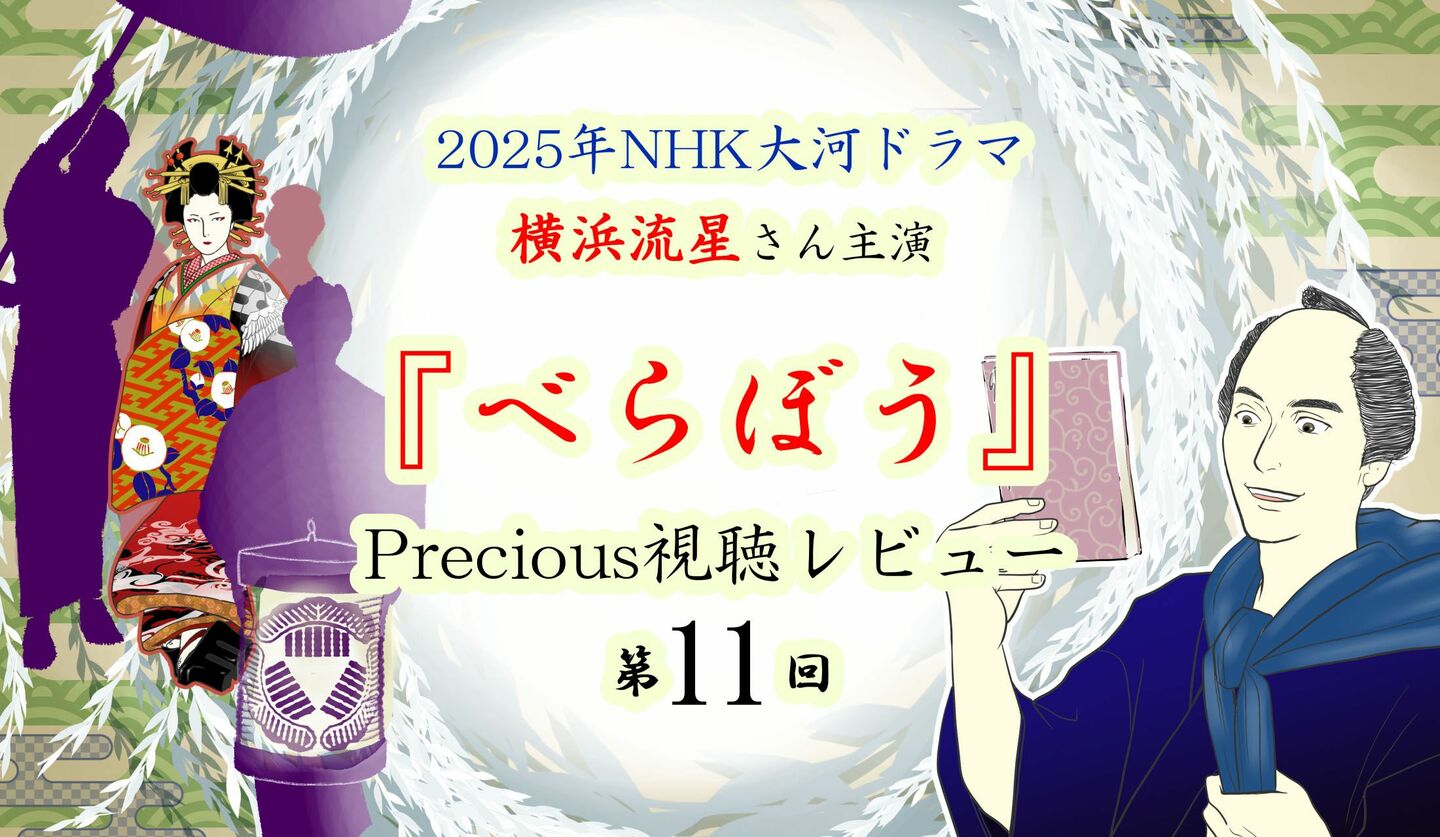【目次】
- これまでのあらすじ
- イベントが盛りだくさん!吉原は江戸のテーマパークだった
- 第11回「富本、仁義の馬面」のキーワード、「俄」とは?
- 「オーミーを探せ?」の謎は解けるのか?
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第12回 「俄なる『明月余情』」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、天下泰平、文化隆盛の江戸時代中期を舞台に、親なし金なしの蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星さん)が、その企画力とプロデュース力で「江戸のメディア王」にのし上がっていく物語です。
ストーリーがますます熱を帯びていくなか、3月14日、主役を演じる横浜流星さんが、映画『正体』で第48回 日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞を受賞されました。檀上で受賞の喜びを語る流星さんは『べらぼう』の蔦重とはまるで別人。誠実さのなかにきらきらとしたオーラと色香が…。筆者などはお顔がアップになるたび、「顔がいい…!」と呟いてしまうのですが、不思議なことに『べらぼう』では、美男なことを忘れさせるほど、「江戸の蔦重」になりきっているんですよね。本当にいい役者さんです。
さて、第10回「『青楼美人』の見る夢は」では、蔦重は女郎たちのバックステージを描いた錦絵本『青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)』を完成させ、平賀源内(安田顕さん)から田沼意次(渡辺謙さん)を通して、10代将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に献上することに成功します。一方、瀬川(小芝風花さん)は白無垢に身を包んだ花魁道中を最後に、吉原を去っていきます。「吉原を江戸っ子が憧れるような場所にしたい」、「瀬川とおれをつなぐものは、この夢しかねえから」と心に誓う蔦重。晴れ晴れとした顔ですれ違う、ふたりの横顔を捉えた演出が見事でしたね!
今回のレビューは、物語の鍵となる「俄(にわか)」をはじめとした、吉原のイベントに着目します!
【イベントが盛りだくさん!吉原は江戸のテーマパークだった】
第11回の「富本、仁義の馬面」は、「これ(『青楼美人合姿鏡』)は売れません。これに金を出すのは、よほどの浮世絵好きか、吉原好きだけじゃないですかね…」と呟く鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)のしたり顔で始まります。彼は「こんなマニアックな本、オタク以外は買わないよ」と言っているのです。その言葉通り、書物問屋を通じて売り出した『青楼美人合姿鏡』は、スタートこそ華々しいものでしたが、豪華本ゆえの高価格のためかさっぱり売れず、吉原への集客にも結びつきませんでした。
『青楼美人合姿鏡』の現物支給で借金返済を頼む蔦重に、三味線でブーイングする忘八たちの絵面から、すでに様式美となった蔦重の階段落ちへ。今回はいささか勢いが過ぎたようで、かなり痛そうでした!
一方そのころ、江戸城では徳川吉宗以来48年ぶりとなる日光社参(にっこうしゃさん)が始まっていました。日光社参とは、将軍が日光東照宮に参拝すること。その長い行列は先頭から最後まで、出立だけで約12時間もかかったといいます。すると、遠くから行列を見物していた大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)が、8月に行われる吉原の祭りである「俄(にわか)」で、老若男女が楽しめるイベントをやって客寄せをしようと言い出します。そして、その幹事を命じられた蔦重に、大黒屋のりつ(安達祐実さん)がリクエストしたのが、浄瑠璃の流派のひとつである富本節(とみもとぶし)の太夫(たゆう)である富本午之助(とみもとうまのすけ/寛一郎さん)の出演でした。
当時、吉原では年中行事が大切にされていました。正月やひな祭り、七夕など、江戸市中と同様のものだけでなく、吉原独特の行事もありました。これらの特別な日を「紋日(もんび)」と言います。
なかでも、3月の「花見」、7月の「玉菊灯籠(たまぎくどうろう)」、8月の「俄(にわか)」は、吉原の三大行事とされ、多くの見物客が集まり賑わったそうです。
■江戸の名物、吉原の夜桜。引手茶屋2階から見下ろす眺めは上客の特権
吉原最大の催しである「花見」は、3月の1日から月末まで。「吉原のどこで桜見物を?」と思うかもしれませんね。おっしゃる通り! そもそも仲の町に桜並木はありません。吉原の桜並木は、毎年、植木屋が開花直前の根付きの桜の木を運び込んで植えていたのです。下草に山吹、周囲には青竹の垣根。桜の高さは、引手茶屋の2階からの眺めを考慮して揃えられました。雪洞(ぼんぼり)に照らされた満開の桜の下、多くの供を引き連れて進む花魁道中は妖艶で、息を飲むほどの美しさだったことでしょう。
夜明けまで灯がともされた吉原は不夜城でした。油が高価だったこの時代、夜桜が楽しめる場所は江戸でも吉原のほかなく、老若男女が押し寄せて夜桜見物を堪能したそうです。見物だけならお金はかかりませんから、私たちがクリスマスイルミネーションを見に名所を訪れるのと、同じような感覚ですね。
現代人の私たちの感覚では、「遊郭としての吉原」は、庶民の生活エリアからは多少なりとも隔離された場所のようにイメージしがちですが、性に関して開放的だった江戸時代、男性の遊郭通いは珍しいことではありませんでした。人気の花魁は女性たちにとってのファッションリーダーであり、アイドル的な存在でもありましたから、女郎の衣装や髪型を見るために、女性も吉原へ出入りしていましたし、地方から江戸に出てきた人々も、どこよりもまず、吉原を見に行きたがったそうです。吉原は江戸文化の中心であり、子ども連れでも楽しめるテーマパークとしての一面ももっていたのです。
■第9回のタイトルにもなった「玉菊灯籠」とは?
「玉菊燈籠」は、実在した女郎「玉菊(たまぎく)」を偲び、仲の町の引手茶屋が軒先に灯籠を吊るす行事です。才色兼備と讃えられ、その人柄も慕われた玉菊でしたが、生来のお酒好きがたたり、わずか25歳の若さで亡くなってしまいます。玉菊を弔い、同時に吉原で亡くなったすべての女郎たちの霊を弔うために行われた「玉菊燈籠」は、最初は小さな催しでしたが、各見世が燈籠に趣向を凝らすようになるに従い、吉原を代表するほどに大きなイベントとなりました。ドラマ第9回「玉菊灯籠恋の地獄」でも、黄昏時、柔らかな灯りを灯す灯籠を眺めて賑わう、多くの見物客が描かれていましたね。
吉原には、飲食物を売る商人や仕立て屋など、普段から一般の女性も多く出入りしていましたが、唯一の出入り口である大門では女性の出入りが監視されていました。そもそも吉原の女郎に与えられた休日は年に2日ほど。しかも、休日といえども自由に大門の外に出ることは許されていませんでした。
そして、一般の女性に変装して逃亡を企てる女郎の足抜け(芸妓や娼妓などが前借り金を清算しないで逃げること)を防ぎ、一般女性と女郎を区別するため、「切手(通行証)」が発行され、女性が吉原から出る際は、切手を出入口の番所(ばんしょ)に見せる必要がありました。最終的に実行に移されることはありませんでしたが、蔦重が瀬川と一緒に吉原から逃げ出そうと夢想したのも、切手を使っての足抜けでしたね。蔦重の「蔦屋」も、その切手を発行できる店だったのです。
【第11回「富本、仁義の馬面」のキーワード、「俄」とは?】
■吉原のお祭りイベント「俄」とは?
「俄(にわか)」とは、もともと吉原で小さく開かれていた催事で、仮装をした幇間(ほうかん/男芸者)や芸者が中心となって、俄(だしぬけ)に歌舞伎の真似事などをしだすという、お座敷芸から始まった即興の寸劇イベント。8月朔日(ついたち)から月末まで行われていました。享保年間(1716~36年)に、歌舞伎好きの引手茶屋や妓楼の主人たちが集まって、思いつきの俄狂言を披露したのが始まりといわれています。やがて大きなイベントとなり、妓楼や引手茶屋の協力のもと、踊りや有名な芝居の真似をしながら練り歩いたり、車の付いた舞台を引いて回ったりするお祭りに発展しました。
ドラマの舞台は1776年ですから、大文字屋市兵衛のアイディアをきっかけとして、一大イベントに成長していったという設定なのかもしれません。
■どうして吉原ではイベントが大事にされたの?
現代の高級クラブやキャバクラでも、豆まきやハロウィン、クリスマスなど、毎月のようにイベントを企画して、集客に努めています。接客を仕事とする女性たちは、その日に向けて馴染みの客に、手裏剣のように営業LINEを送るわけですが、それと同じようなことが、江戸時代の吉原でも行われていたのです。ドラマでも、忘八たちが「老若男女が楽しめる祭りをすれば、吉原の評判も上がり、蔦重の本も売れるはず!」と主張していましたね。
ただし、吉原のイベントがほかと大きく異なるのは、その日は遊女の揚代(あげだい/料金)はもちろん、仕出し料理や祝儀など、すべての値段が倍でした。ですから、イベントデーと知らずに吉原を訪れた客は思わぬ散財を強いられました。ちなみに、そのイベント日程を知るためにも『吉原細見』は重宝されたのです。
さらにイベントデーは遊女にとっても出費のかさむ日でした。花魁たちは華やかなイベントのために、自腹でお付きの新造や禿たちのものも含め衣装を新調したり、妓楼の奉公人などに祝儀をあげたりしなければなりませんでした。しかも、客がつかない遊女は揚代を自分で支払うというルールまであったのです。
妓楼の側はもうけが大きくなるため、イベントをどんどん増やしましたが、やがてそれが災いをして、客足を遠ざける一因になっていきます。幕府からの通達もあり、1797(寛政9)年、それまで80日以上あった紋日を一気に18日まで減らす対策が取られたそうです。
【「オーミーを探せ!」の謎は解けるのか?】
富本午之助の「俄祭り」出演を叶えるため、浄瑠璃の元締めである鳥山検校の協力を得ようと検校を訪ねた蔦重は、瀬川改め瀬以(小芝風花さん)に再会します。上品な勝山髷に文庫結びという、いかにも御新造様(ごしんぞうさま/武家や富裕な町家の妻や新妻に対する尊敬語の呼称)といった風情の瀬以に、蔦重は「別れを決意したのは正解だった」と、瀬以への気持ちにひとつ区切りを付けられたのではないでしょうか。
一方、検校を慕うかに見せる瀬以の芝居は、気配を敏に察する検校には効きません。このあと、検校の嫉妬が瀬以を苦しめることになりはしないか…気になります。
最初は「俄」への出演を断った富本午之助でしたが、生まれて初めて芝居を観た吉原の花魁や振袖新造たちが涙を流して喜んでいるのを見て、二代目市川門之助(濱尾ノリタカさん)とともに、「俄」への出演を快諾します。検校の協力により二代目富本豊前太夫(とみもとぶぜんだゆう)襲名を認める知らせも入り、蔦重は富本節正本の「直伝(じきでん)」出版の権利を手に入れます。
「正本」とは浄瑠璃を嗜む人にとっての譜面、稽古本で、なかでも本元の太夫の許可を得て出されたものが「直伝」と呼ばれました。富本節の人気が高まるなか、「直伝」の「富本正本」は弟子の数だけ確実に売れる、優良商品だったのです。
そして今回も、次郎兵衛兄さん(中村蒼さん)がいい味を出していましたね。前回から何度か、三味線片手に語っていたのが「富本節」だったのですねー。出だしの「たっ」だけで終わる回想シーンに、蔦重同様、「あれがそうだったんだ…」と呟いた人も多かったのでは(笑)。とはいえ、とぼけているようでいて、富本午之助の「正本直伝」出版へのヒントを投げてくれるのだから、なんともありがた山なお方です。
そうそう、ドラマの序盤、鶴屋喜右衛門に「こんなマニアック本は売れない」と言わしめた『青楼美人合姿鏡』を手に取って、「いやぁ、いい本をつくるねぇ」と大興奮して吉原を語るマニアがいたことを覚えていますか? 演じているのは、尾美としのりさん。
実は尾美さんは毎回、オープニングロールに名前が出るものの、あまりに出演時間が短いため、SNSでは人気絵本「ウォーリーをさがせ!」ならぬ「オーミーを探せ!」と話題になっていました。「まるでレアポケモンだ…」という声も。尾美さんのセリフ付きの本格的な登場に加え、蔦重も「どこかでお見かけしているような?」と、今までの伏線回収を予測させるようなセリフを口にします。そして次回予告には「覆面作家を探せ」の文字が…。いよいよ「オーミー」の存在が、キーキャラになっていくのかもしれません!
【次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第12回 「俄なる『明月余情』」のあらすじ】
昨年に続き吉原で行われる『 俄(にわか)』祭り。その企画の覇権を巡り、大文字屋(伊藤淳史さん)と若木屋(本宮泰風さん)らの間で戦いの火ぶたが切られた。蔦重(横浜流星)は、30日間かけて行われる俄祭りの内情をおもしろおかしく書いてほしいと平賀源内(安田顕さん)に執筆を依頼。すると、朋誠堂喜三二はどうかと勧められる。喜三二の正体は、かつて蔦重も会っていた、宝暦の色男とも呼ばれている秋田佐竹家留守居役のあの男だった…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第11回 「富本、仁義の馬面」のNHKプラス配信期間は2025年3月23日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 河西真紀
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館)/『江戸の色町 遊女と吉原の歴史』(KANZEN)/『吉原事典』(朝日文庫)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『日本髪の描き方』(エクスナレッジ)/『お江戸ファッション図鑑』(マール社)/『見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春文庫)/『結うこころ 日本髪の美しさとその型 江戸から明治へ』(ポーラ文化研究所) :