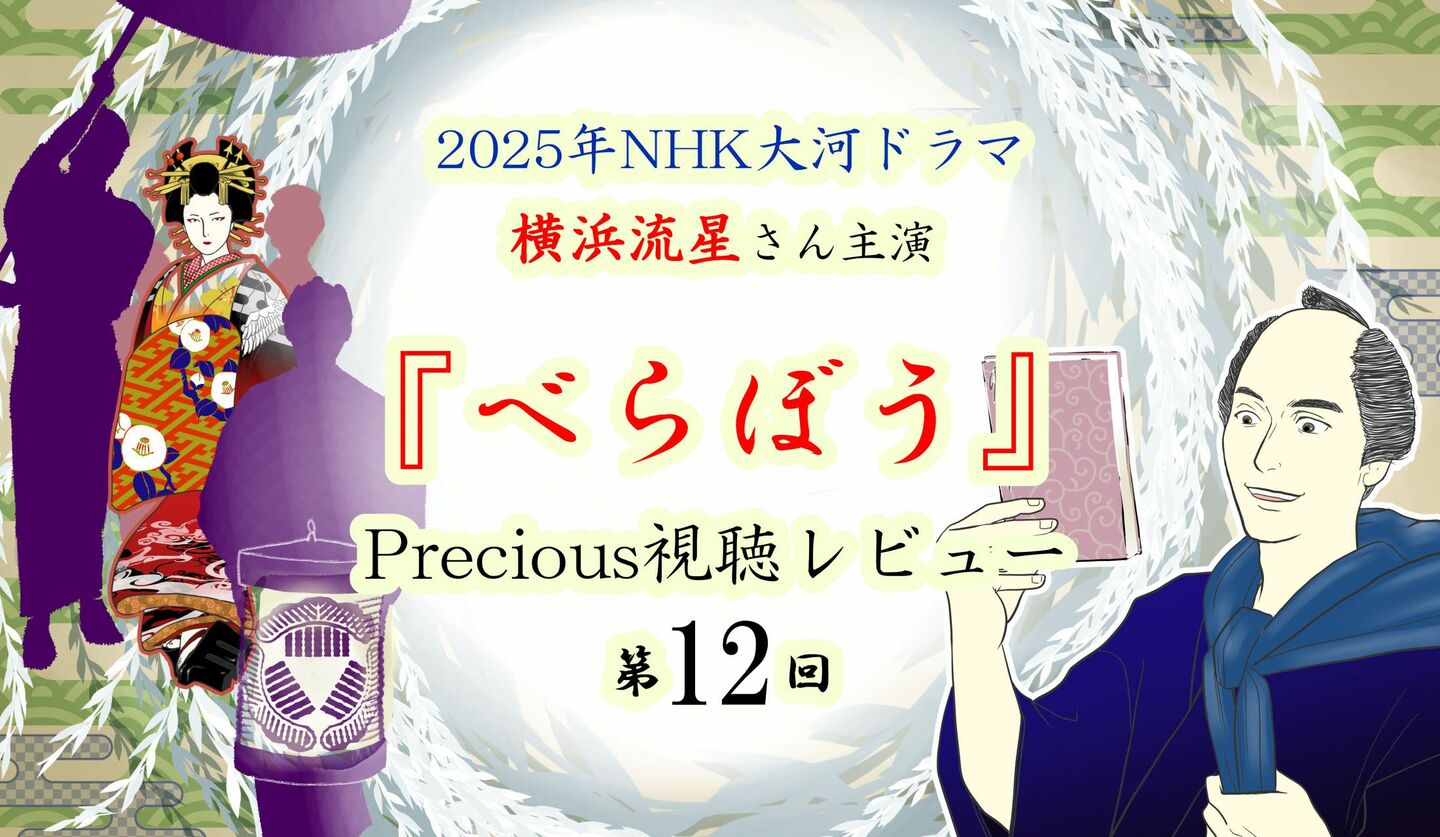【目次】
- これまでのあらすじ
- 大文字屋(伊藤淳史さん)が大暴走
- 『明月余情』とは?
- 『明月余情』の序にならったロマンチックなうつせみと新之助のラストだが…
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第13回 「お江戸揺るがす座頭金(がね)」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
江戸時代中期の吉原を舞台に、喜多川歌麿や葛飾北斎、東洲斎写楽といった才能あふれる浮世絵師を世に送り出し、「江戸のメディア王」として名を馳せた版元、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星さん)の人生をエンターテインメントの要素たっぷりに描く『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。第12回「俄なる『明月余情』」は、吉原で8月に行われていた大イベント「俄(にわか)」祭りの準備からフィナーレまでを舞台に、そこに暮らす人々の千変万化が繰り広げられる内容でした。
【大文字屋(伊藤淳史さん)が大暴走】
まず蔦重。第11回で話がまとまった、浄瑠璃の富本豊前太夫(午之介/寛一郎さん)の「直伝」(富本節正本)の売り上げが軌道に乗り、手堅い収入源を確保。実際の蔦重も、ベストセラーよりも、定期発行のロングセラーを生むのが得意だったそうですよ。
とはいえ、蔦重は市中の本を売らせてもらえない立場。弾が少ないことに変わりなく、「ウリ」になる次のアイディアが必要です。ブームとなっている青本がつくれればと模索しますが、そんなことをすれば青本を一手に扱っている鱗形屋(片岡愛之助さん)との対立は必至です。
一方、錦絵の販売を牛耳っているのが、蔦重の足を引っ張る第二波、西村屋(西村まさ彦さん)。その彼と結託して忘八衆の反対勢力となった若木屋(本宮泰風さん)が総代を名乗り、これまでいまひとつ盛り上がっていなかった「俄(にわか)」祭りを盛大に執り行うという内容を記した廻状(かいじょう/回覧文書)をまきます。さらに、西村屋仕立ての錦絵『青楼俄狂言尽(せいろうにわかきょうげんづくし』を売り出すから、掲載してほしい見世は2両払うべし、とのお知らせも。
これに「同じことを考えてたのに!」と声を荒げたのが大文字屋(伊藤淳史さん)です。怒りに任せて呼びつけた蔦重の頭を何度も叩きます。腹いせに自分より立場の低い人間をいたぶる、という描写はコメディタッチでも心がざわつきますが、大文字屋さんには「いちばんの出し物を見せつけて、正々堂々、総代の座を奪い取りましょう」と言う蔦重の説得を受け入れて頑張るという柔軟さもある、さらに蔦重は聞く耳をもたれる立場である、ということでもやもは相殺しておきましょう。
【『明月余情』とは?】
さて、吉原では1か月にわたる「俄」祭りに向け、その準備が着々と進められます。「俄」は遊郭で女郎の世話をする禿(かむろ)や、芸者たちが仮装して、寸劇をしたり踊ったりしながら仲の町通りを練り歩く、即興要素の強いパレードのようなイベント。江戸市内からも見物客が多くやって来ます。
蔦重はここに目を付けました。その日限りしか見られない「俄」の演目を絵と文章にして、来た人は思い出にできる、見損ねた人や来られない人は臨場感をもって楽しめる、そんな絵本をつくったら売れるのではないか…そうして誕生したのが『明月余情』です。「俄」開催中のちょうど真ん中、8月15日に迎える仲秋の名月からそのタイトルが付けられたようです。風流ですね。蔦重のセンスがうかがえます。
そして、コストを抑えるためか、スピード重視で売ることが必須だったためか、墨摺り『明月余情』は低価格。3冊、各十数ページという薄いつくりで軽く、手にも取りやすい。観光客が持ち帰るお土産としてもちょうどよかったようです。その内容は、国立国会図書館のデジタルコレクションで確認できますが、さすが似顔絵風作画のパイオニア、勝川春章(前野朋哉さん)ならではの見事な出来。大きな山車の上で芸者たちが演奏する絵があったり、男たちがダイナミックなはしご芸をする様子があったり、ドラマのシーンさながらの、三度笠を被った衆が躍る姿も臨場感あふれる筆遣いで描かれています。
『明月余情』の序にならったロマンチックなうつせみと新之助のラストだが…
『明月余情』の序を書いたのが、謎の人気青本作家、朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)。蔦重は喜三二の正体がお役人の平沢常富だと知り、「もう飽きた。ネタもない」と言う喜三二に、「例えば祭りの裏側、大文字屋と若木屋の喧嘩を源平合戦に見立てて書くとか?」とちょうどいい塩梅のアイディアを出したり、喜三二が膨らませた構想を「おもしれえ! 俺、それ読みてぇです!」と本気モードで盛り上げたり、「書き上がったら吉原あげておもてなしします!」と欲望を刺激したりといったシーンは、なるほど上手だなぁ、と蔦重の書籍編集者としての能力の高さに感服です。
しかしながら、鱗形屋の家族総出の芝居じみたともいえる土下座(!)に圧倒され、相談した倉橋格(岡山天音さん)にも半ば反対され、その話はなかったことに。とはいえ喜三二は蔦重のことも気にしていて、その引け目から『明月余情』の序を書くことを承諾した、という流れ。史実かどうかは別として、スムーズです。
「鳥が啼く、東の華街(いろまち)に」から始まるその序は、「人と我との隔てなく 俄の文字が調(ととの)いはべり」と結ばれ、ドラマでは、第9回で足抜けに失敗したうつせみ(小野花梨さん)と新之助(井之脇海さん)の数年ぶりの再会のシーンで流れました。そして、ふたりは人混みに紛れてそっと吉原から去ったのでした…。
「人と我との隔てなく」は誰もが対等である、という意味ですから、身分に縛られた吉原の人々も「俄」のときは、そういったものから解き放たれて自由になるという解釈もでき、そんな夢のような時間のなかにふたりが溶け込んでいくというシーンは美しく、SNSでも「泣いた」「感動した」「お幸せに!」と話題になりました。井之脇海さんも、ドラマ公式のインタビューで「ふたりはどこかでつましく、幸せに暮らしていくと思う」と答えていましたが、心のざわつきが収まりません。当時の吉原はそんなに甘いものでしょうか。逃げ切れるものでしょうか。そして、「愛のために命を捨てる」ことが美化されていた感もあるこの時代、「現世で無理ならあの世で幸せに」という風潮もありました。この逃避行がそんなフラグでないことを祈ります。
一方、瀬以(小芝風花さん)は、夫となった鳥山検校(市原隼人さん)のお屋敷で庭を見ながら憂い顔。吉原を出たとて鳥かごの中の鳥であることには変わりなく。鳥かごが変わっただけなんですよね…。苦しい。そんな瀬以の様子に気付いていそうな検校の無表情にもハラハラします。そしてこの人、来週ヤバそうです。
【次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第13回 「お江戸揺るがす座頭金(がね)」のあらすじ】
蔦重(横浜流星さん)は、留四郎(水沢林太郎さん)から鱗形屋(片岡愛之助さん)が再び偽板の罪で捕まったらしいとの知らせを受ける。そして、鱗形屋が各所に借金を重ね、その証文のひとつが鳥山検校(市原隼人さん)を頭とする金貸しの座頭に流れ、苦し紛れに罪を犯したことを知る。
一方、江戸城内でも旗本の娘が借金のかたに売られていることが問題視され、田沼意次(渡辺謙さん)は、座頭金の実情を明らかにするため、長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)に探るよう命じる。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第12回 「俄なる『明月余情』」のNHKプラス配信期間は2025年3月30日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 簗場久美子
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版) :