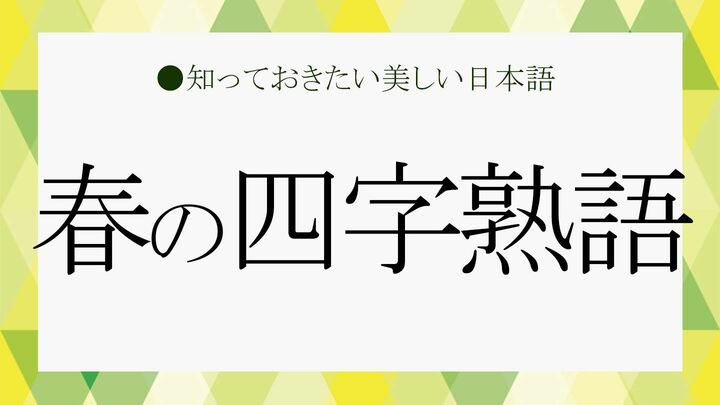桜の開花は心弾む季節の到来を知らせてくれます。新入学や入社、引っ越しなど環境の変化に期待が膨らむ人はもちろん、何も変わらずとも全国の開花ニュースやSNSに投稿される各地の桜にときめく人も多いのでは? 今回はそんな時期に使いたい、春を表す美しい言葉をご紹介します。
【目次】
【『べらぼう』にも登場! 桜咲くころの「四字熟語」】
今すぐに使える季節を表す四字熟語8選! あわせて例文もご紹介しましょう。
■春風満面
「春風満面(しゅんぷうまんめん)」とは、気持ちを抑えきれず、顔中に喜びが溢れ出た様子を言います。「思いがけない贈り物に、彼女は春風満面の笑みを浮かべていた」
■桜花爛漫
「桜花爛漫(「おうからんまん)」は、桜の花が今を盛りに咲き乱れているさま。「今週末には近所の並木も桜花爛漫の予想です。よろしかったら遊びにいらっしゃいませんか?」
■春風駘蕩
春風駘蕩は「しゅんぷうたいとう」と読み、 春の暖かい暖かい風がのどかに吹くさまを表します。「春風駘蕩たる穏やかな日和、いかがお過ごしですか」
また、人が物事に動じず余裕のあるさま、ゆったりとのんびりしているさまも。「春風駘蕩たる大人(だいじん)」といったら、物事に動じない徳のある立派な人、という意味です。
■一目千本
この「一目千本(ひとめせんぼん)」、大河ドラマファンなら覚えがあるかも…『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で横浜流星さん演じる蔦屋重三郎が、吉原の遊女を生け花に見立ててヒットを飛ばした絵本仕立ての本が『一目千本』でしたね。熟語の意味は千本の桜がひと目で見渡せる場所。古くから絶景と親しまれた、奈良の吉野山の桜を見渡すのに絶好の場所を指すことも。
■春日遅遅
春日遅遅は「しゅんじつちち」と読みます。春の日のうららかでのどかなさまや、春の日の暮れるのが遅いさまをいいます。「穏やかな春日遅遅の日々、いかがお過ごしですか」
■柳暗花明
「柳暗花明(りゅうあんかめい)」を直訳すると、柳が茂って辺りはほの暗く、花が咲き匂って明るいさま。転じて、春の景色が美しいことを表します。花柳界のことを指す場合も。
■柳緑花紅
「柳緑花紅(りゅうりょくかこう)」は柳が緑色に茂り、花が紅色に咲くという意味から、春の美しい景色を表す言葉ですが、自然のまま手を加えられていないこと、ものには個性があることのたとえとしても使われます。「日本全国、柳緑花紅の手仕事を残していきたい」
■春暖花開
春暖花開(しゅんしゅんだんかいか)」は花咲くうららかな春、行楽に絶好の季節であることを言う中国語の四字熟語です。手紙のあしらいなどに使えそうですね。
【積極的に使いたい「春の美しい日本語」】
四字熟語以外にも春を表す美しい言葉は数多くあります。天候や時間などによって使い分けられたら素敵です!
■花の雨
桜の花が咲くころに、音もなく降り続く雨を言います。「春雨」と同義ですが、「花の雨」のほうが風情がありますね。
■春暁
「しゅんぎょう」と読み、春の明け方を表します。「春眠暁を覚えず」はご存知でしょう。これは中国唐代を代表する詩人、孟浩然(もうこうねん)の「春暁」という漢詩の第一句なのですよ。
■朧月夜
朧月夜は「おぼろづきよ」と読み、春の夜に月がかすんでいる情景のこと。『源氏物語』に登場する、源氏の恋人の名前としても有名です。「春は朧」は薄曇りのなかぼんやりした景色を指し、「春はあけぼの」は清少納言『枕草子』の出だし、「春おぼろ」は1979(昭和54)年にリリースされた岩崎宏美のシングル曲。
■東風
東風は「とうふう」ではありません「こち」と読みます。春から夏にかけて東から吹く風をいう、春の季語。この風が吹くと寒さがゆるんで本格的な春の到来です。
【四季のなかでも心浮き立つ「春」についてもおさらい!】
3月の夏日、暑すぎる長い夏や、爆弾低気圧など…、異常気象はますます進む一方。日本は特異な地形や環境によって、春、夏、秋、冬と季節で気候が明確に異なっていました。それゆえ暮らしにさまざまな工夫が必要で、知恵を働かせて四季を楽しみながら生活してきたのです。
昔から春夏秋冬の区分は、太陰太陽暦(旧暦)による季節のずれを正すために1年を24等分した中国の二十四節気(にじゅうしせっき)をもとにしています。中国と日本では気候が合わない時期もあるので、日本ではこの二十四節気に「土用」や「八十八夜」などの雑節を取り入れています。
二十四節気の「春」は下記のとおり。季節の挨拶文などに利用できますよ。
・立春(りっしゅん/2月4日ごろ) 春の始まり。梅の花がほころびかける時期で、立春から立夏までを春といいます。
・雨水(うすい/2月19日ごろ) 春一番が吹くころ。雪が雨になり、積もった雪が溶け始めて水になり、植物に栄養を届けます。
・啓蟄(けいちつ/3月5日ごろ) 冬眠していた虫が活動を始めるころ。
・春分(しゅんぶん/3月21日ごろ) 昼と夜の長さが等しくなる日ですが、実際には昼のほうがやや長いとか。お彼岸の中日にあたります。
・清明(せいめい/4月5日ごろ) 春の長雨が続いたり、清く明る空気が満ちて、草木が芽吹き、花咲き乱れるころ。清浄明潔(せいじょうめいけつ)を略した言葉。
・穀雨(こくう/4月20日ごろ) 準備が整った田んぼや畑に栄養を与えるように、春の雨が降るころ。気候が安定してくる時期でもあります。
・立夏(りっか/5月5日ごろ) 田んぼに水が張られ、野山が新緑に包まれる時期。暦のうえではこの日から夏になります。
***
梅も桜も、可憐な姿の花とはらはら花びらを散らす様子は情緒がありますね。満開の桜の下を散歩できるのはほんの数日という少なさも、日本人が桜を愛でる要因かもしれません。今回はそんな季節に使いたい、美しい言葉を並べてみました。ぜひ活用してみてください。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『今日から役に立つ! 使える「語彙力」2726』(西東社)/『決定版 すぐに使える! 教養の「語彙力」3240』(西東社)/『中日辞典 第3版』(小学館) :