古川麦(ふるかわばく)のことを知ったのは、以前本連載で少し触れたことのある「表現(Hyogen)」というバンドのライヴだった。当時はややエキセントリックな印象だったヴォーカル佐藤公哉の脇で、体を丸めて一心不乱にアコースティックギターをかき鳴らす古川の姿が、妙に印象に残った。というのも、そのギターから繰り出されるパッセージが、演奏する姿からはかなり意外な、流麗なものだったからだ。時にラインハルト(訂正:以前の原稿ではトリスターノの名前になっていました。ジャンゴ・ラインハルトの誤りです。失礼いたしました)、時にボサノヴァを連想させるギタープレイは、無国籍なバンドのサウンドにしっかりと独自の色を加えていた。
ボサノヴァからクラシックまで、幅広い音楽性に裏打ちされたギター

その後、何度か古川自身がアーティストとして出演するライヴにも足を運んで、「表現」の時とはまた違った彼の演奏にも触れた。「弾き語り」というとどこかフォーキーな音楽を連想しがちだが、彼の弾き語りは決して一本調子ではなく、器楽演奏と歌声のアンサンブルだ。つまり、それはひき「語り」ではなく、歌もまた演奏といえる。「口笛」を多用することも、彼の音楽をよく物語っているように思える。
ジョアン・ジルベルトを聴いてギター&歌を始めたという古川だが、その音楽性は決してボサノヴァやブラジル音楽だけに依拠してはいない。彼の楽器がナイロン弦のギターであることから、クラシック音楽に関する素養も感じられる。また彼はギター以外にもいくつか楽器を演奏する(彼がサポートメンバーを務めるceroでは管楽器奏者の側面もある)が、そのことは彼自身の音楽が持つスケール感につながっていると思う。
しかし、古川の音楽の魅力をひとことで言い表すとしたら、「素直さ」ではないだろうか。ある種の屈託が音楽づくりの契機となることも多いが、彼の音楽に屈託やコンプレックスが生む影はあまり感じられない。基本的に陽性で、ポジティブな姿勢。そこから生み出される潔い、歪みを感じさせない音楽。もしかしたらその風合いは、ユニバーサルなサウンド、さらに言えばポップネスを彼なりに追求した結果なのかもしれない。

3月にリリースされた古川のアルバム『シースケープ』は、彼らしさをどう広く伝えていくかが、より考慮されているように、彼の音楽を追いかけてきた者には映る。フルアルバムとしては前作にあたる『far/close』は、彼自身の音楽をひとつのアルバムとしてコンパイルすることにフォーカスされた、実にみずみずしい作品だった。英語と日本語の歌が自然に混在し、ストリングスをフィーチャーしながら極上のポップスに仕上げた「Green Turquoise」ほか楽曲も多彩で、まさに古川麦の人となりが感じられるアルバムの音世界だった。
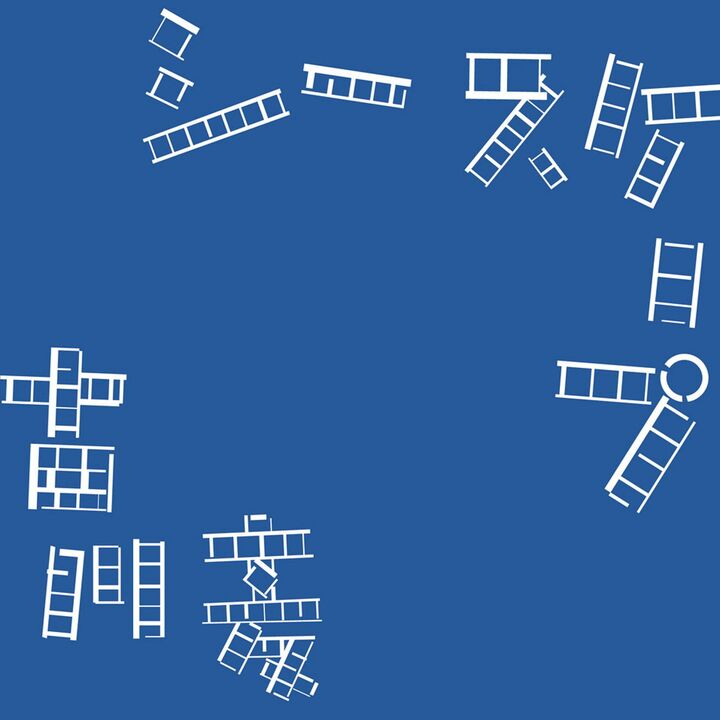
フルアルバム2作目は、P-VINEといういわばメジャーに近いレーベルからのリリース。音楽性の多彩さという彼の持ち味をベースに、それぞれの曲においてさらに一歩突っ込んだサウンドになっているように感じられる。それもあって、最初のアルバムよりもどこか凝縮された、ソリッドな印象だ。タイトルチューンの「シースケープ」は、クラシカルな音節をきっかけに、その後の展開が意外な曲。古川の英語の歌にエレクトロニカ的なサウンド&グルーヴが絡む「Here Lies the Sun」は彼の新機軸といえる。そして後半のうねるリズムと大胆な展開がブラジルの気鋭アントニオ・ロウレイロあたりを連想させる「Frutas」は、より振り切った感じで聴き手を圧倒する。こんな巧妙なグルーヴを生み出すアーティストは、日本でもそう多くはないだろう。
そして、アルバム全体を通じて耳に残るのは、古川のギターとともにその歌声の存在感だ。繊細な男声は確かに美しいが、もしかしたら同時に本作における音楽の可能性を規定してしまっているのかもしれない。女性ヴォーカル優河を迎えた彼の定番曲「Coo Coo」を聴くと、そんな思いが頭をよぎる。しかしそれは古川にとって承知のことだろう。彼はあるがまま、自らの声を軸に音楽を生み出した。バンド「表現」やcero、さらには他の音楽家と絡むことの多い巧者だからこそ、彼は自身の声で歌うことの必然を感じているのかもしれない。それはまた音楽に対する実に率直な姿勢でもあり、その潔さが、強く聴き手の心を捉えるのだ。
- TEXT :
- 菅原幸裕 編集者














