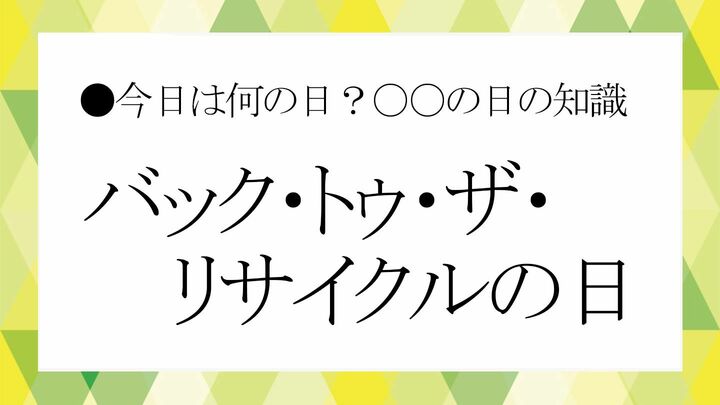【目次】
【「バック・トゥ・ザ・リサイクルの日」とは?由来】
■「いつ」?
「バック・トゥ・ザ・リサイクルの日」は10月21日です。
■「誰が」決めた?
循環型社会を目指し、リサイクル技術の開発やリサイクルの仕組みの提案などを行う株式会社JEPLAN(旧 日本環境設計株式会社)が制定した記念日です。
■「由来」と「目的」は?
日付は、1985年公開のアメリカ映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で、ごみを燃料とする車型のタイムマシーン「デロリアン」が到着する未来が、2015年10月21日であることに由来します。「デロリアン」がゴミを燃料とする夢のタイムマシーンであったように、「ごみがごみでなく、エネルギーに生まれ変わる日に」という願いが込められているのです!
■過去のイベントは?
2015年の第1回の記念日には、映画仕様の「デロリアン」の走行イベントが、映画会社NBCユニバーサルとJEPLANとの共同で開催されました。その際には、古着をリサイクル技術によって糖化しバイオエタノールに変えた、当時最先端の燃料が使用されました。
【ビジネス雑談に役立つ「サステナブル」にまつわる雑学】
■「リサイクル」についておさらい!
「リサイクル」をごく簡単に説明すると、「いらなくなったものやゴミをそのまま捨てずに、もう一度資源として利用すること」。リサイクルと聞いて思い浮かぶのは、ペットボトルやジュース、缶、びん、古紙などでしょうか。
■リサイクルの「3R」って知ってる?
「3R」は、ゴミの削減やリサイクルに関連する3つの単語の頭文字をとったものの総称です。
・リデュース(Reduce)
物を大切に使い、ごみを減らすことです。たとえば、必要ない物は買わない、もらわない。あるいは、買い物にはマイバッグを持参するなど
・リユース(Reuse)
使える物は、繰り返し使うことです。たとえば、詰め替え用の製品を選だり、いらなくなった物を譲り合うなど
・リサイクル(Recycle)
ごみを資源として再利用することです。たとえば、ごみを正しく分別する、ごみを再生して作られた製品を利用するあどがあてはまります。
■「リサイクル」されると何に生まれ変わる?
たとえば紙の場合、新聞紙はもう一度新聞紙にリサイクルされます。コピー用紙はノートやトイレットペーパーに。空き瓶については、実は瓶には洗って繰くり返し使える「リターナル瓶」と、1回しか使えない「ワンウェイ瓶」があります。ワンウェイ瓶であれば、粉々にしてもう一度瓶をつくり直すことが可能です。そしてスチール製の缶は、鉄板などの鉄製品になり、アルミでできたものは自動車の部品になったり。身近なところで再利用されているんですね。
■簡単にできる身近な「リサイクル行動」
以下は、習慣にしたい「リサイクル行動」の例です。「もうやってるわ!」という人も多いのでは? そう、リサイクルって、すごく身近なことなんです!
・分別をきちんとする
プラごみなどの容器は洗って、缶や瓶のラベルも剥がして、自治体ルールに従って出しましょう。
・使い捨てを減らす
実はこれがいちばんの肝! そもそも使い捨てるものを減らすことが最優先です。
・リサイクル製品を選ぶ
同じアイテムならば、再生素材を使った製品をチョイスすれば、リサイクルのサイクルを支えられます。
・リユースも意識する
もう使わないかな…と思ったものは、フリマアプリやリサイクルショップに出すなど、ひと手間掛けて再利用を意識しましょう。
■ゴミの分別は意味がない?
「ごみの分別は当然」と考える人がいる一方、「ごみ分別は意味がない」と感じている人も少なくないようです。その理由を、環境省のデータ(2023年度)から探ってみました。
・ごみの処分方法のうち、もっとも多いのは「焼却」で80.3%
ごみの焼却量は、2014年以降、減少傾向とはいえ、ごみの8割が「燃やされている」とは、衝撃です。
・リサイクル率はわずか19.5%
日本のリサイクル率は、2020年度に微増したものの、2021年度以降は再び微減しています。
「一生懸命分別しても、リサイクルされるものは2割程度で、結局ほとんどのごみは燃やされる」という事実が、「ごみの分別は意味がない」という意見につながっているようです。とはいえ、「分別されていないごみ」には問題があります。
・処理施設での作業効率を低下させる
ごみが分別されていないと、施設の稼働時間が伸び、エネルギー消費量が増加してしまいます。結果として、温室効果ガス排出量が増えるほか、処理コストの上昇を招き、最終的には市民の税負担増加につながる可能も。
・有害物質や危険物が混入する可能性があり、収集作業員や処理施設の従業員の安全を脅かす
分別せずに捨てたごみは、すべてが燃やされてしまいますが、たとえその2割ではあっても、分別したものを再利用すれば資源になります。この視点は忘れたくないですね。
■プラごみの再利用についておさらい!
プラスチックごみのリサイクルには、大きく分けて3種類あります。
1)マテリアルリサイクル
廃棄されたプラごみをそのまま原料とし、新しい製品をつくる技術が、マテリアルリサイクル。破砕・洗浄・乾燥させてフレークにしたプラごみを溶かして粒状のペレットにし、さらに溶かして樹脂材料として再生させます。
2)ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクルは、廃プラを化学的に分解し、製品の原料に変えて再利用するものです。いくつかの方法があり、原料に戻して再利用する手法、製鉄所でコークスの代わりに還元剤として利用する手法、ガスにして化学工業の原料にする手法などがあります。ただし、ケミカルリサイクルを実現するためには、大型の設備を整備する必要があり、それらの設備は既存の製鉄や石油化学コンビナートに隣接させるため、輸送コストが高くなるなど、経済的な側面が課題となっています。
3)サーマルリサイクル
サーマルリサイクルは、プラごみ焼却時に生じる「熱エネルギー」を回収し、それを再利用することで「リサイクルした」と“みなす方法”です。清掃工場で行われている発電や、近隣の温水プールへの熱供給などが該当します。
リサイクル方法の内訳としては、マテリアルリサイクルが21%、ケミカルリサイクルは3%、サーマルリサイクルが62%と、プラスチックは焼却処分される率がかなり高め。しかも、サーマルリサイクルではプラスチックの焼却時にCO2が排出されるので、資源循環のためにも、マテリアルリサイクルの割合を高めていく必要があると言えます。
■スタバが紙ストローを廃止。これって時代の逆行?
スターバックスジャパンは、2020年ごろから、Forest Stewardship Council(森林環境協議会/FSC(R)認証の紙ストローを導入していましたが、「時間が経つとふにゃふにゃになって飲みにくい!」といった声が多く、飲み心地のよさと環境配慮の両立を模索していました。
その結果、2025年3月から導入されたのが、化学メーカーのカネカが開発した、植物油などを主原料とする素材「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet(グリーンプラネット)」。使用後にもし自然界に流出してしまっても、海中や土壌中の微生物によって二酸化炭素と水に生分解される特殊素材です。紙ストローに比べて、生産から廃棄までのライフサイクル全体での二酸化炭素排出量を抑えられ、重さが半分になるため、報道によると、廃棄物を約200t減らせる見込みなのだそうです。
■小泉進次郎元環境大臣「レジ袋有料化に環境効果なし」発言の真意は?
2020年、BSフジの『プライムニュース』に出演した小泉進次郎環境大臣(当時)に、視聴者から「レジ袋有料化で買い物が不便になった」という趣旨の質問が寄せられ、それに対する小泉氏の発言が話題となりました。
番組では、「食料品をマイバックに入れるのは不潔である一方、レジ袋はゴミ捨てに欠かせず、便利で有用。ごみを入れたまま燃やすことにも問題ないのでは」という質問に、小泉氏は「レジ袋を全部なくしたところで、プラスチックごみの問題は解決しない」としたうえで、「この有料化をきっかけに、なぜプラスチック素材が世界中の問題となって取り組まれているのか、そこに問題意識をもって、ひとりひとりが始められる行動につなげてもらいたい」という趣旨を語りました。レジ袋有料化の本当の狙いは“環境問題への意識喚起”にある、というのが当時の小泉氏の立場だったのです。
しかし、この前半の発言だけが切り取られ、「レジ袋有料化には環境効果がない」という言葉だけがひとりあるき状態となり、レジ袋有料化に賛否の声があがりました。
実際、環境庁のデータによれば、レジ袋が全国の自治体のごみに占める割合は、わずか0.4%程度。しかも、当時の質問者の方の言う通り、レジ袋は、石油精製時に生じる副産物であり、焼却しても有害物質が出ることもありません。これらの点を踏まえると、「レジ袋を減らすこと」そのものよりも、「それをきっかけに日常の消費行動を見直してもらうこと」が政策の本質であると言えます。
■江戸時代のリサイクルは?
江戸の町は、物を、可能な限り使い切り、再生利用を常としたリサイクル社会といえる風景がありまた。代表的なものをいくつか挙げてみましょう。
まずは紙屑(くず)屋。江戸時代、紙はとても貴重でしたが、庶民に手が届かなかったわけではありません。紙くずやでは、不要になった帳簿や紙類を買い取り、漉き返して再び紙として流通させていた記録があります。リサイクルられた「漉き返し紙」は、手軽に買えた、まさに“庶民の紙”だったのです。
紙と共に貴重だったのが、灯りです。これは「蝋燭(ろうそく)の流れ買い」が活躍しました。蝋燭からしたたり落ちて燭台に溜まったロウを買い取り、溶かして再び蝋燭に成形していた業者がいたといいます。
そのほか、竈や火鉢などの灰を買い、土壌改良や染め物、肥料として売る「灰買い」や、古い傘の骨組みだけを買い取り再利用する「古骨買い」も存在しました。
女性が長い髪を梳(と)かした抜ける髪を扱う「梳(す)き髪買い」という仕事もありました。これは、買い取った髪を集めて「髢(かもじ/かつら)にしたり、髪を結うときの入れ髪をつくって販売していたそうです。そのほかにも、「古着屋」「湯屋(銭湯)の木拾い」「古樽買い」「肥汲み」などなど、さまざまなリサイクル業が商売として成り立っていました。こうした仕組みがあったため、江戸では「ゴミ」が町中に溢れることが少なかったともいわれ、“日本の循環型社会の源流”としても評価されています。江戸時代の人々は、ものというのは、かたちの残る限り、すべて再生できると考えていたのですね! すごい!
***
み問題を考える際、まず注目したいのは「リサイクル」よりも「ごみを出さない工夫」です。いらないものを買わない、使い捨てを減らす、自然由来の素材を選ぶなど、日々の選択が未来の環境を変えていきます。リサイクルももちろん大切ですが、「最初からごみにしない」意識を持つことが、ごみ削減への第一歩。できることから少しずつ、楽しみながら取り組んでいきましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /JEPLAN(https://www.jeplan.co.jp) /環境省「3R」(https://www.env.go.jp/recycle/3r/campaign/campain.html) /環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和5年度)について」(https://www.env.go.jp/content/000301183.pdf) /『お江戸でござる』(新潮文庫)/The Asahi Shinbun SDGs ACTION!(https://www.asahi.com/sdgs/)/PRESIDENT Online(https://president.jp/articles/-/38058) :