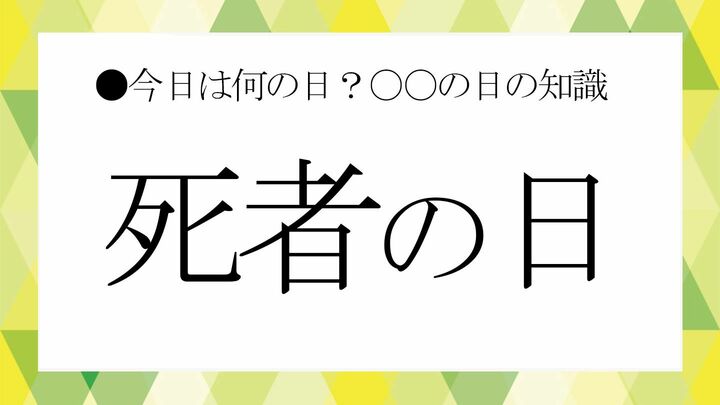【目次】
【「死者の日」とは?起源と変遷】
■「意味」は?「何日」?
「死者の日[Dia de muertos]」はラテンアメリカで「死者(先祖)の魂を迎え、祝う日」とされています。特に、メキシコで11月1日と2日に行われる祭礼が有名ですが、地域により多少違いはあるようで、農村地帯や先住民たちの間では、10月31日~11月1日は子どもの魂を迎えるための日、11月1日~2日は大人の魂を迎える日とされています。2003年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。
■「起源」は?
「死者の日」は、もともと先住民たちの間で、トウモロコシや豆など農作物の収穫期に合わせ、8月に行われていました。しかし16世紀、スペイン侵略後のカトリック教への改宗により、日程が変えられて現在の日にちになったそうです。
さらに、そのルーツは14世紀から16世紀にかけてメキシコ中央部で栄えたアステカ文明の時代までさかのぼるともいわれており、さまざまな歴史的背景が色濃く宿る行事です。
現在行われている「死者の日」の直接のルーツはキリスト教です。キリスト教では11月1日を万聖節、翌日11月2日を万霊節(または死者の日)と呼び、亡くなった聖人と信者の方のために祈りをささげる日とされています。つまり、キリスト教を信仰する国や地域ではどこでも「死者の日」が行われているとも言えますね。
メキシコ独特の「死者の日」は、キリスト教の行事に古代アステカ暦の「死の小祝宴」という祭祀が合わさって、独特の行事に発展したものです。アステカの祭祀では、人間を神にささげる生贄の儀式が行われたり、「骸骨(ガイコツ)」を並べて祀ったりと、かなり血なまぐさいものであったようです。メキシコの「死者の日」のシンボルといえばガイコツですが、街中にガイコツを飾るのには、こんな理由があったのですね。
【「死者の日」の主要な儀式と象徴的モチーフは?】
■「何をする」?
メキシコでは、「死者の日」である11月1日の夜から2日にかけて、盛大にパーティーが催されます。家族で集まり、オフレンダという祭壇を囲って団らんをするのです。
■象徴的なモチーフは?
・ガイコツ
街中に飾られるガイコツは「死者の日」のアイコンアイテム。「人は亡くなってもあの世でガイコツとなって生きている。だからご先祖様を敬いつつ、一緒にいるときはガイコツであっても一緒に楽しもう!」という思いが込められているのでしょうか。

・マリーゴールド(センパスチル)
10月の終わりから、街の至る所でマリーゴールドが売られ始めます。メキシコでは、鮮やかな色の花びらや強い方香が、死者の魂をこの世へと導く道しるべとなると言われているのです。
・パン・デ・ムエルト(死者の日のパン)
「死者の日」のひと月前くらいから、街では「死者の日のパン」が売られるようになります。これは特別な形状をした甘いパンで、おもてなしの精神と大地の恵を表しています。十字の棒が骨、真ん中の丸が頭蓋骨を表しているとされています。
・祭壇(オフレンダ)
街の人目につくところや家の中心部となる場所に、祭壇が設置されます。「死者の日」の祭壇は、思いを故人に捧げるという目的はもちろんのこと、生きる者が集まり飲食を楽しみながら故人の思い出話に花を咲かせる「集いの場」としても機能しています。親族や友人、近所の人々など様々な世代での交流がなされ、絆がさらに深まるのです。
祭壇には通常、「パペル・ピカド」と呼ばれるメキシコの伝統的な切り紙の飾りのほか、死者の魂が安全に戻ってこられるよう場を浄化する「塩とお香」、装飾された砂糖菓子でつくられた「カラベリタ(どくろ)の飾り」、死者の魂の行き帰りの道を照らす「ろうそく」、死者たちの段の渇きを癒す「水」、死者の魂を喜ばせ、彼らをもてなすための「飾りやおもちゃ」、そして「供え物の飲食物」などが飾られます。豪華ですね!

【「死者の日」の祭りとは?見どころ】
「死者の日」は、観光客でも十分に楽しむことができますよ。
■祭壇(オフレンダ)を見て楽しむ
祭りの最中は、街の至る所に祭壇が飾られます。日本人の感覚だと、他人のお墓を見に行くというのは、ちょっとイメージしにくいものですが、思い思いに美しく飾られた祭壇は、見る人を楽しませてくれます。
■パレードに参加して楽しむ
「死者の日」である11月1日から2日にかけては、街の中心地などでパレードなどが開催されるところがあります。
■フェイスペインティングをして楽しむ
髑髏メイクは「死者の日」のアイコンです。伝統行事ではありませんが、「死者の日」にはレストランのウェイターさんなど、骸骨メイクをした人を多く見かけます。有料ですが、誰でも気軽にやってもらえるようです。

■「死者の日」のイベントで有名な街は?
ミチョアカン
伝統的な「ザ・死者の日」を楽しめるのがミチョアカンです。特にミチョアカンにあるパツクアロ地域のハニッツィオという湖は、「死者の日」の有名なスポット。毎年多くの観光客が訪れます。
メキシコシティ
メキシコ合衆国の首都であり、最大の都市がメキシコシティ。成田から直行便で行ける「最も遠い都市」としても知られています。ここでの「死者の日」は現代っぽいパレードがメインで、伝統的というより観光よりですが、手軽に楽しみたい人や初心者の人にはおすすめ。
【日本のお盆との違いと共通点】
「死者の日」を祝う文化は、メキシコを代表する伝統文化で、メキシコ人にとってとても大切な行事です。「先祖の魂が帰ってくるのをお迎えする行事」という意味では日本のお盆に似ていますが、メキシコの「死者の日」はとてもカラフルで明るく、楽しいイベントです。死を悲しむのではなく、故人との絆を祝福し、命の美しさと短さを称えたり、一年に一度先祖に会える日として、盛大に祝われます。
***
「死者の日」は「先祖の霊を敬い、感謝を捧げる日」という意味合いでは日本の「お盆」と似ていますが、それを「明るく楽しもう!」とするのは、いかにもラテンアメリカならではの行事のように思われます。日本からは成田発の直行便で「死者の日」を楽しむ、添乗員同行のツアーもあるようです。安全第一に、楽しんできてはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- PHOTO&MOVIE :
- AC
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /在日メキシコ大使館(https://note.com/embamexjp/n/n085f2c5aaf32) :