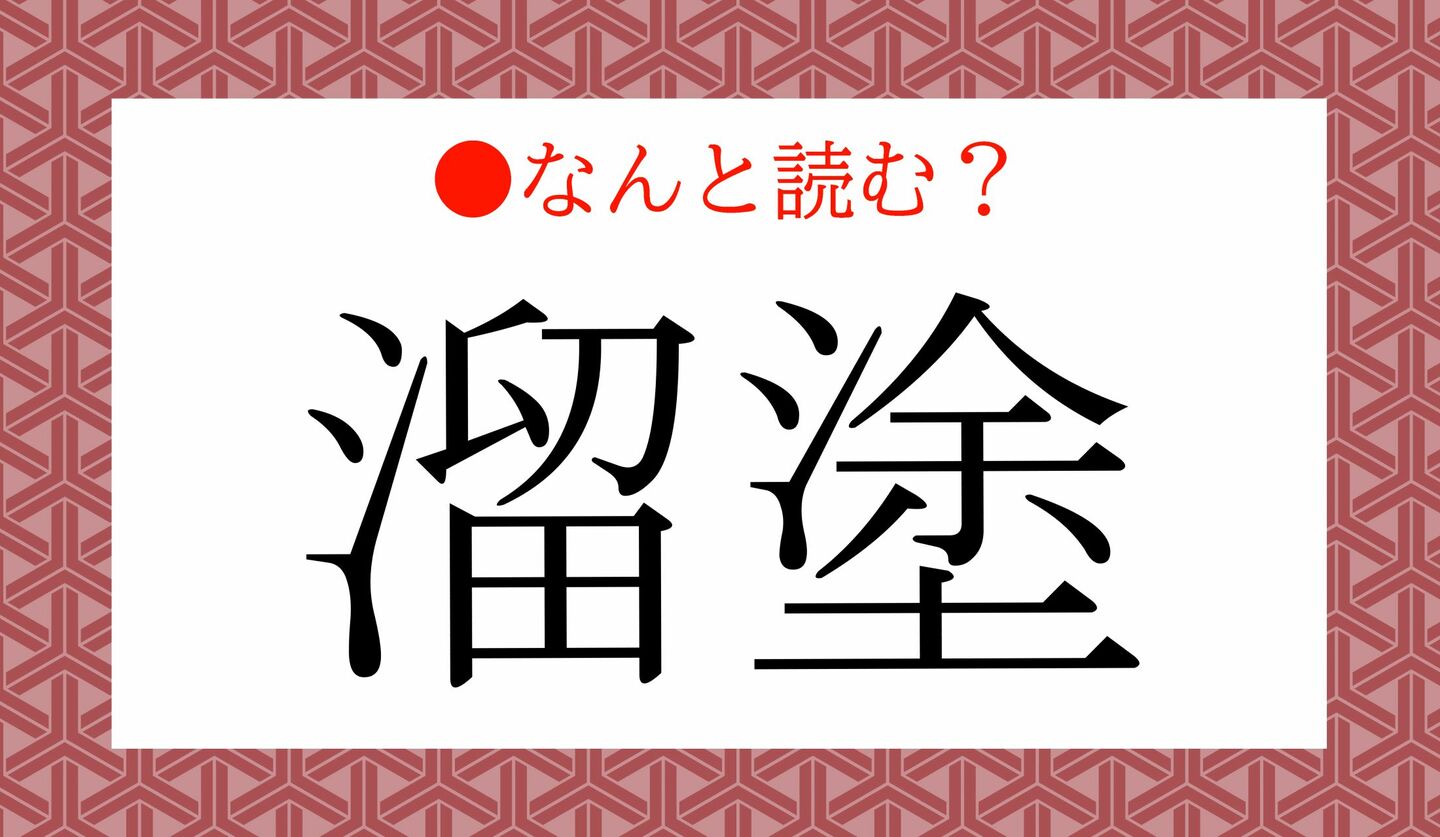明日、11月13日は『うるしの日』です。汁椀や重箱など、生活道具の美しさと強度を上げるため、日本古来から用いられてきた漆器ですが、その製造方法は「文徳天皇の第一皇子・惟喬親王(これたかしんのう)が、京都嵐山法輪寺に参籠(さんろう/一定期間、神社や仏閣にこもり、世間との交際を絶って祈願や修行を行うこと)された際、本尊虚空蔵(こくうぞう)菩薩から伝授・教示されて完成した」という伝説があります。
その参籠の満願日であったとされる11月13日は、漆工関係者の間で古くから大切に考えられてきた日で、改めて1985(昭和60)年に本漆工協会がこの日を『うるしの日』と定め、漆文化を幅広い層に広める取り組みなどをしています。
それを踏まえ、本日は「漆(うるし)」をキーワードにした日本語クイズをお送りします。
【問題1】「漆黒」ってなんと読む?
「漆黒」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「黒うるしを塗ったように黒くて艶があること。また、そのさまやその色。真っ黒」を言う言葉です。
<使用例>
「あなたの、サラサラで漆黒のストレートロングヘア、憧れちゃうわ」
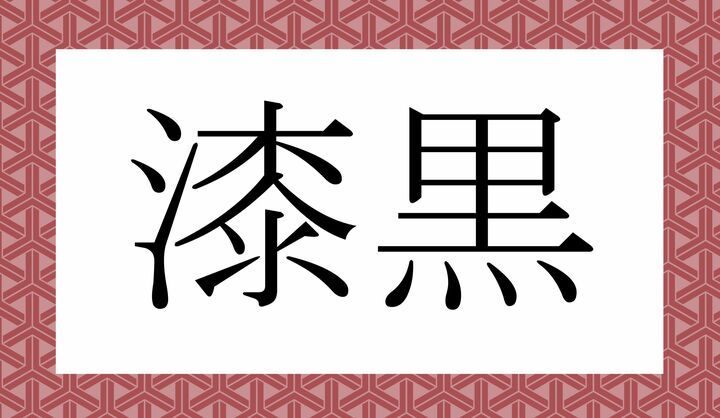
…さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。
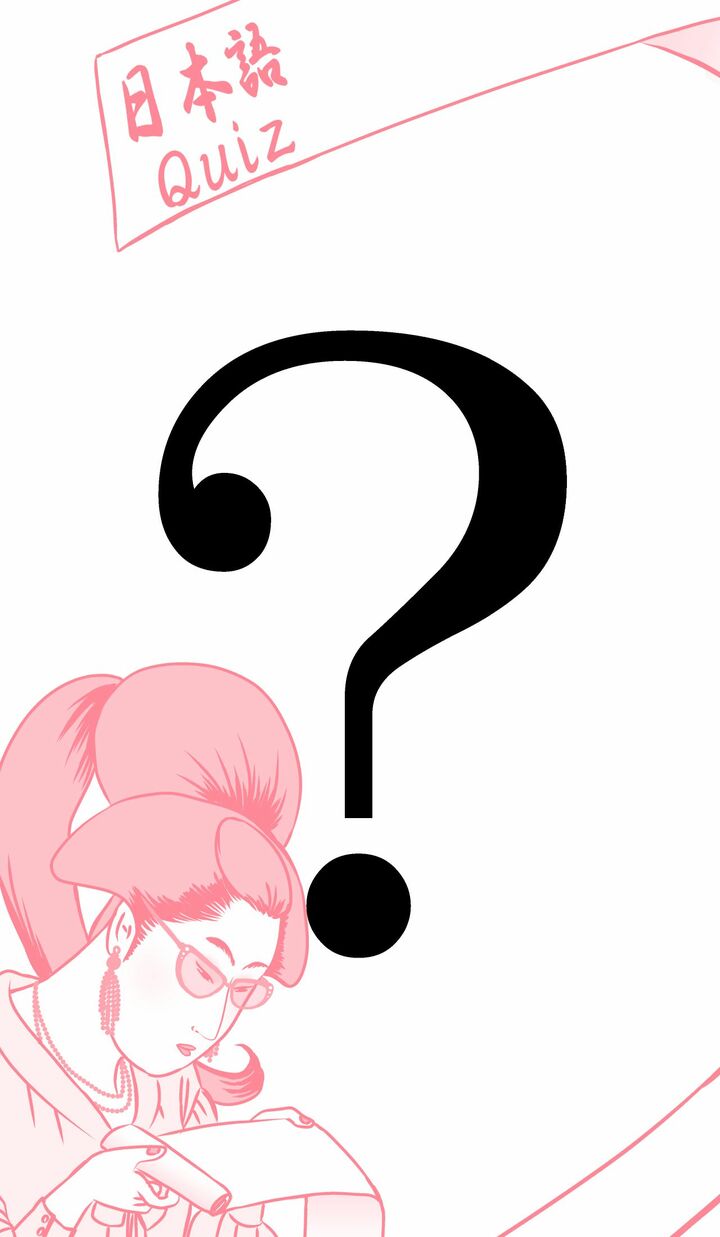
正解は… 漆黒(しっこく) です。

「漆黒の髪」「漆黒の闇」など「趣きを感じる黒」「真っ黒」の表現としてよく用いられますが、「漆の黒」にたとえた言葉です。「漆器(しっき)」と言うように「漆」の音読みは「シツ」です。
では、二問目にまいりましょう。
【問題2】「溜塗」ってなんと読む?
「溜塗」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント: 「漆芸の塗り技法のひとつで、色漆をつくる際にベースとなる褐色みの強い透明な漆を厚めに塗り仕上げること。また、そのように仕上げられたもの」を言う言葉で、下の色(朱や、木の素地など)がほんのりと透けて見えます。
<使用例>
「ついに、憧れだった本漆・溜塗の三段重をお正月用に買ってしまったわ!」
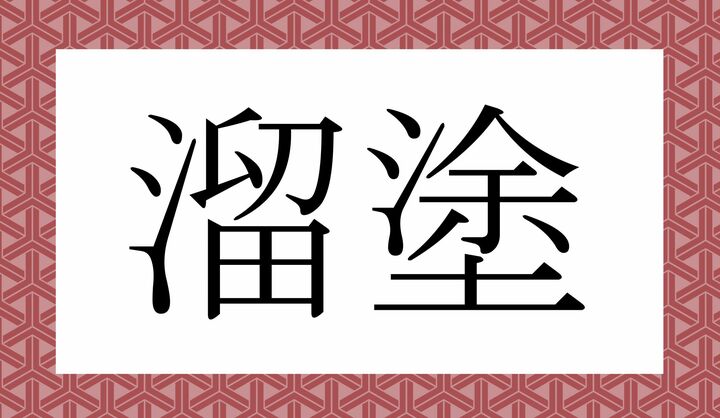
さて、正解は?
※画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 溜塗(ためぬり) です。
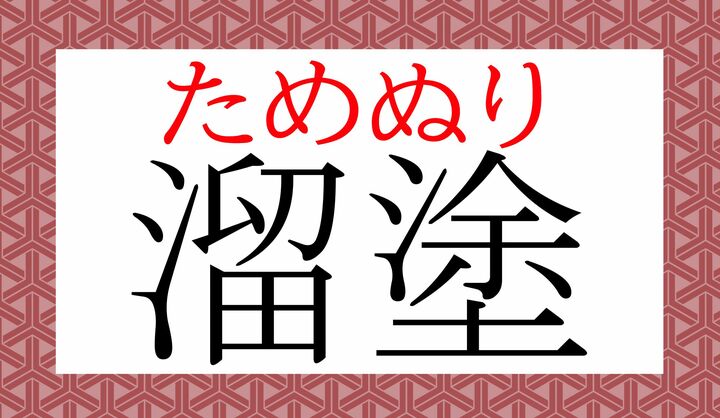
「溜塗(ためぬり)の漆器」と言えば、透明感のある上塗りの漆の下に、朱や黒などの下地の色を重ねることで、深みと奥行きのある色合いを楽しめる技法です。特に、器の角や縁の部分など塗りが薄くなる箇所では、下地の色がほんのりと透けて見えるのが特徴で、そこに独特の趣や風格が感じられます。
このように、光の加減や使い込まれることで表情が変化するのも、溜塗の魅力のひとつで、漆芸の中でも陰影や深みといった「美の余韻」を堪能できる技法として高く評価されています。実際に使用でき、かつ、美的な価値も高い和の伝統工芸・漆芸の特徴的な技法のひとつですので、この機会に覚えておきましょう。
「溜塗(ためぬり)」の透明感のある褐色の色味は「溜色(ためいろ)」とも呼ばれ、「たまり醤油の色から来た色名ではないか?」という一説もございます。
***
本日は、11月13日『うるしの日』にちなんで、
・漆黒(しっこく)
・溜塗(ためぬり)
の読み方、言葉の背景についておさらいいたしました。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- BY :
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/日本漆工協会ホームページ/山久漆工ホームページ/KOGEI STANDARDホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)
- ILLUSTRATION :
- 小出 真朱