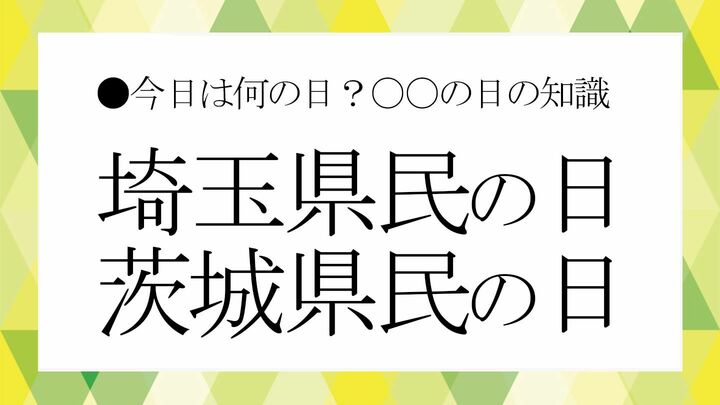【目次】
【 茨城県と埼玉県の県民の日が制定された背景】
■「茨城県民の日」は11月13日
明治4年(1871)年、廃藩置県の後の府県統合で「茨城県(いばらきけん)」という県名が用いられたのが旧暦の11月13日。昭和43(1968)年に、新暦でも日付を変えずに11月13日を「茨城県民の日」と制定しました。
■「埼玉県民の日」は11月14日
「埼玉県」という名称の誕生は茨城県と同じく、廃藩置県がきっかけです。明治4年11月14に「埼玉県」となり、その100周年を記念した昭和46(1971)年に「埼玉県民の日」が制定されました。
■全国にある?ない?「都道府県民の日」
あなたがお住いの都道府県に「県民の日」はありますか? あなたがお住まいの都道府県に「県民の日」「都民の日」があるか、ご存知でしょうか。例えば、東京都では10月1日が「都民の日」で、多くの施設が無料開放されたり、学校が休みになったりしています。ところが、全国47都道府県すべてに「都道府県民の日」があるわけでなく、調べてみると47都道府県中19。半数を満たしていません。
また、名称も一律ではありません。名称も「県民の日」というストレートなものだけでなく、「北海道みんなの日」(7月17日/北海道)、「ふるさとの日」(2月7日/福井県)、「ふるさと誕生日」(11月22日/和歌山県)などもあります。なかには愛知県の「県政発足記念日」(2月20日)などお堅いものも。このように、「都道府県民の日」は 地域ごとに日付・名称・運用が異なるため、住んでいる地域でどういう扱いになっているかを調べておくと、ちょっとした地元ネタとしても役立ちます。
■何をする日?
各都道府県の日には、公立の小・中・高校が休校になる場合や、動物園や美術館など都道府県運営の施設が無料や割引になったり、イベントが行われたりしますが、一律ではありません。
■最古と最新は?
一番古い制定例のひとつは東京都の「都民の日」で昭和27(1952)年に制定されました。一方、最新はつい最近、2022(令和4)年の「あいち県民の日」。明治5(1872)年11月27日に名古屋県から改称した当時の愛知県と額田県が合併して「愛知県」が誕生しましたが、その150周年を記念しての制定でした。
ビジネス雑談で盛り上がる茨城県と埼玉県、それぞれの魅力とトリビア】
■日本史で習いました…よね?「歴史」
茨城県/奈良時代の8世紀前半に編纂された『常陸国風土記』には、「土地広く、土が肥え、海山の産物もよくとれ、人びと豊かに暮らし、常世の国のようだ」と記されています。このように、茨城県は古くから人々が豊かに暮らした土地です。中世から近世にかけても有力な武将たちがこの地に居を構え、特に江戸時代には水戸に徳川御三家のひとつである水戸藩が置かれたことで大きく発展しました。江戸に近く水陸交通の要所であったため、地方における政治・経済・文化の中心地として栄えました。
埼玉県/この地域に人々が定住を始めたのは、なんと今から約3万年前とされています。所沢市の砂川遺跡や深谷市の白草遺跡などから出土した石器類から、当時の人々が獣や魚を食料としていたことがうかがえます。約1万年前には、煮炊きや貯蔵に使える縄文土器がつくられ、約2000年前には西日本から稲作が伝わり、大規模な集落が形成されました。奈良時代には法律や戸籍が整備され、農民に土地を与え税を徴収する制度が始まります。鎌倉時代には武士が政権を握り、室町時代の後半から戦国時代にかけては有力武将が各地に城を築きました。江戸時代には、中山道や日光(奥州)道中といった五街道が整備され、新田開発も進み、関東地方を代表する穀倉地帯として発展しました。
■朝ドラや大河ドラマになりそう? 県が誇る人物
茨城県/水戸藩主であった徳川慶喜公は、本木雅弘さん主演、司馬遼太郎さん原作により、平成10年(1998年)のNHK大河ドラマ『徳川慶喜』の主人公となりました。ほかにもドラマの主役や企画になりそうな茨城県ゆかりの偉人として、日本の近代美術の先駆者である岡倉天心さん、日立製作所の創業者小平浪平さん、そして「民俗学の父」と称される柳田國男さんなどが挙げられます。いずれも歴史や文化、産業に大きな足跡を残した人物です。
埼玉県/令和3年(2021年)の大河ドラマ『青天を衝け』は、現在映画『国宝』でも注目されている吉沢亮さんが主演を務めました。そのモデルとなったのが、深谷市出身の渋沢栄一氏です。渋沢氏は「日本資本主義の父」として知られ、2024年から発行されている新一万円札の肖像にも選ばれました。また、俳人の松尾芭蕉翁や、白樺派の文豪、武者小路実篤先生もこの地域にゆかりがあります(※松尾芭蕉翁は生誕地が諸説ありますが、関東との関わりは深い人物です)。
■秋におすすめの観光スポット
茨城県/紅葉スポットとして人気の花貫渓谷では、特に汐見滝吊り橋付近が紅葉の見どころです。2025年は11月30日まで「紅葉まつり」が開催され、地元グルメやお土産の販売も行われます。また、11月24日(月・祝)までは日没後のライトアップも楽しめます。このほか、関東屈指のパワースポット鹿島神宮や、日本三名園のひとつとして名高い偕楽園も、秋の観光におすすめです。
埼玉県/食べ歩きや町歩きが楽しいのが、江戸時代の面影を残す川越の蔵造りの町並みです。自然を楽しみたい方には、長瀞渓谷や、春の芝桜で知られる羊山公園もおすすめ。さらに、2019年春にオープンしたムーミンバレーパークは、秋の行楽シーズンにも人気のスポットとなっています。
■テレビネタにも欠かせないご当地グルメ
【茨城県のご当地グルメ】
・つけけんちんそば(大子町、常陸太田市など):温かいけんちん汁に冷たいそばをつけて食べる郷土料理。根菜たっぷりで体も心も温まります。
・那珂湊焼きそば(ひたちなか市):太めのモチモチ麺に甘めのソースが絡む、地元で愛される焼きそば。
・スタミナラーメン(水戸市、ひたちなか市など):レバーや野菜をとろみのあるピリ辛餡と一緒に炒めた、ボリューム満点のラーメン。
・笠間いなり寿司(笠間市):くるみ入りの酢飯を使った、ちょっと変わったいなり寿司。
・ゆでまんじゅう(結城市):もちもちの皮と、ほんのり甘いあんこが特徴の昔ながらのまんじゅう。
・うまかべすいとん(桜川市):小麦粉の団子を野菜と一緒に煮込んだ、素朴な味わいの郷土料理。
【埼玉県のご当地グルメ】
・煮ぼうとう(深谷市):幅広のうどんを野菜や味噌と一緒に煮込んだ、冬にぴったりの郷土料理。
・草加せんべい(草加市):日本有数の米どころでつくられる、香ばしくて歯ごたえのある名物せんべい。
・フライ・ゼリーフライ(行田市など):お好み焼きのような「フライ」と、おから入りのコロッケ風「ゼリーフライ」はB級グルメとして有名。
・五家宝(熊谷市):もち米ときな粉を使った素朴な和菓子で、熊谷の名産品。
・狭山茶(狭山市):香り高く、渋みと甘みのバランスが絶妙な緑茶。埼玉を代表する特産品。
・大宮ナポリタン(大宮市など):昭和の洋食文化を再現した、懐かしくてどこか新しいナポリタン。
***
子どものころは休校になってうれしかった「県民の日」も、大人になるとつい忘れてしまいがち。でも、ふるさとの歴史や文化、そして観光やグルメの魅力にふれるよい機会です。
茨城県は『常陸国風土記』にも「常世の国」と称されるほど豊かな土地柄。水戸藩の徳川慶喜公をはじめ、岡倉天心さんや柳田國男さんなど文化的にも深い歴史があります。秋には花貫渓谷の紅葉や鹿島神宮の散策もおすすめ。スタミナラーメンや笠間いなり寿司など、個性豊かなご当地グルメも楽しめます。
また、埼玉県は3万年前の定住跡が確認されるほど古い歴史をもち、渋沢栄一氏をはじめ多くの文化人を輩出。川越の蔵造りの町並みや長瀞渓谷など、秋にぴったりの観光地も豊富です。煮ぼうとうや草加せんべいなど、温もりのある地元グルメも魅力。
「県民の日」は、そんなふるさとの魅力にあらためて目を向けるチャンス。観光に出かけたり、ご当地グルメを楽しんだりしながら、地元のよさを再発見してみてはいかがでしょうか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/茨城県庁ホームページ( https://www.pref.ibaraki.jp/index.html )/埼玉県庁ホームページ( https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html )/いばらき観光キャンペーン推進協議会( https://www.ibarakiguide.jp/ ) :