毎年この時期は、花火大会に参加したり、仲間内で手持ち花火を楽しんだりする人も多いことでしょう。夜空を彩る大輪の打ち上げ花火も、手元でささやかに咲く線香花火も、それぞれ夏の情緒たっぷりですよね。
ただ、花火にばかり気をとられて周囲への配慮が欠けると、思わぬ迷惑行為につながるおそれも……。せっかくの夏の風物詩イベントで、誰かに不快な思いをさせたり、そこから何らかのトラブルに発展したりするような事態は、是が非でも避けたいですよね。
そこで、花火大会や手持ち花火を楽しむときのNGマナーについて、おもてなし協会の直井みずほさんから教えていただきました。
花火大会を楽しむときのNGマナー6選
■1:大きな荷物を会場に持ち込む

まずはマナー以前のお話から、念のため…。人がごった返す花火大会には、なるべく身軽な状態で参加したいもの。大きな荷物を持ち込むと、周囲の迷惑になるおそれがあります。とくに、出先で浴衣に着替える場合は、荷物がかさばりがちです。大きな荷物は必ずロッカーなどに預けてから会場入りするようにしたいものです。とはいえ、花火大会の際の駅などのロッカーは争奪戦は必須なので、まず持っていかないことが大切です。
■2:周囲に配慮せず自分たちの都合で場所取りする

花火大会の場所取りを巡っては、毎年トラブルが発生しています。自分たちだけが楽しめればいいと我が物顔に振る舞うのではなく、お互いに譲り合う精神が大切です。
ゆったり鑑賞したいからといって、必要以上に広く場所取りをするのはNGです。たとえば「たまがわ花火大会」の公式ページによれば、1人90cm四方が目安とのことです。
また、後方に他の観覧客やグループがいるのに、堂々と椅子や三脚を設置すると、視界の妨げになってしまうおそれも……。
「椅子や三脚の持ち込み自体は禁止されているわけではありませんが、使用にあたっては周囲への配慮が大切です。後ろの方やグループに『ここに設置してもよろしいでしょうか?』と必ず一言声をかけるのがいいでしょう」(直井さん)
これくらい邪魔にならないだろう……という自己判断は、トラブルの元! きちんとコミュニケーションをとって、心おだやかに花火を鑑賞したいものですね。
■3:花火観賞スペースで虫除けスプレーを使う
夏の野外イベントにおいては虫対策も必須。ただ、虫除けスプレーの使用は控えたほうがよさそうです。
「虫除けの中でもスプレータイプのものは、その場ににおいが立ちこめやすく、むせてしまう方も。花火大会では塗るタイプや貼るタイプの使用が望ましいでしょう」(直井さん)
普段はスプレータイプを使用している人も、花火大会では塗るタイプ、貼るタイプを準備しましょう。
■4:歩きスマホをする
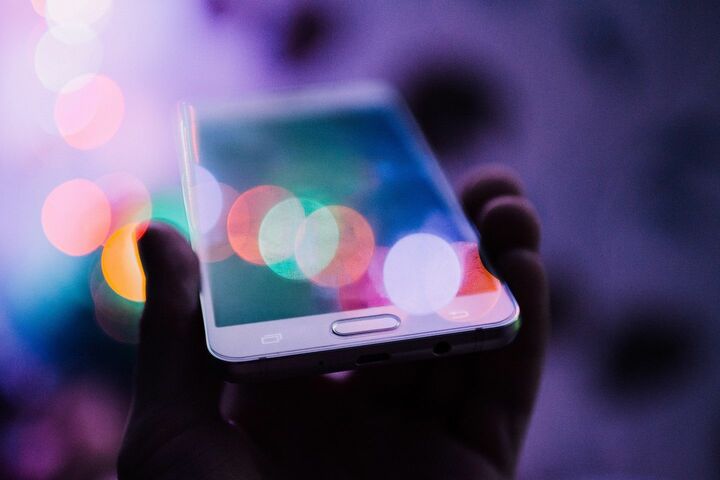
歩きスマホは、公共の場所ではどこでもNGですが、混雑する花火大会においてはなおさら危険。歩きながらの使用は避けて、必要があれば、通行の妨げにならない場所に移動してからスマホを操作しましょう。
また、花火の様子をスマホで撮影する行為自体はマナー違反ではないものの、歩きながらの撮影は控えたいところ。移動中にシャッターチャンスが訪れたからといって急に立ち止まると迷惑になります。花火の撮影も、周囲の状況をよく確認したうえで行うようにしましょう。
■5:花火にずっとカメラのレンズを向けている

写真や動画の撮影は、安全な場所から行うにしても、時間をかけすぎるのは禁物です。
「写真撮影では人が写りこみますし、ビデオでは周りの声を拾うことがあります。ずっとレンズを向けたままでは、近くにいる人に気を使わせてしまうかもしれません」(直井さん)
花火大会での撮影はあくまでおまけのようなもの。レンズ越しではなく、肉眼で花火を鑑賞し、風情を味わいましょう。
■6:肩がぶつかっても知らん顔する
満員電車と同じで、混雑する花火大会ではどんなに気をつけていても、周りの人と肩がぶつかることはあります。その際、たとえわざとではないとしても、知らん顔をするのは大人としていかがなものか……。
「たった一言『すみません』だけで、ギスギスした雰囲気が和らぎます。誰かとぶつかった際は、自分から『すみません』と声をかけましょう。おもてなしの精神が流れる茶道では『一座建立』といって、主人も客も互いにおもてなしの精神を発揮して、気持ちのいい状態が生まれるという考えがあります。花火大会においても、”一座建立”の精神で、みなさんで花火を味わうようにしたいものです」(直井さん)
花火大会をより美しい思い出にするためには、ひとりひとりの心配りが大切なのかもしれませんね。
手持ち花火を楽しむときのNGマナー5選
マナー以前の常識的なNGとしては、花火が禁止されている公園や住宅街で音が出る花火やロケット花火で遊ぶ、人や家に花火を向ける、燃えやすいものの近くで遊ぶ、といった点が挙げられます。その他、手持ち花火で遊ぶ際は、下記の点に注意しましょう。
■7:露出の多い服装で参加する

夏なので薄着なのは仕方がないにしても、火を扱うことをふまえたコーディネートを心がけましょう。はだしにサンダル履きやタンクトップに短パンなど、肌の露出が多いと、そのぶん、やけどの危険性は高まります。特に、子どもを連れて手持ち花火をする際は要注意!
「小さなお子さんが肌をむき出しの状態で参加していると、周りの方に気を使わせてしまうおそれもあります。安心して花火を楽しむためにも、お子さんを守るためにも、過度の肌の露出は控えましょう」(直井さん)
大人はまだ自己責任ともいえますが、お子さんの服装では安全面にしっかり配慮しましょう。また、BBQやたき火などと一緒で、石油由来の服など「可燃性の高い」お洋服は避け、コットン100%や麺混合のお洋服にしたほうがベターです。
■8:花火の説明書を暗闇で確認する
安全に遊ぶには、花火の注意書きを守ることが必須ですが、説明書をただ読めばいいわけでもありません。暗闇で説明書にさっと目を通すだけでは、重要事項を見落とすおそれも……。花火の注意書きは、必ず明るいところで、事前に確認するようにしましょう。
■9:風向きに気を遣わない

わざと人や家に花火を向けるような乱暴な人はなかなかいないと思いますが、常識人でも意外と見落としがちなのは風の影響です。
「本人に悪気はなくても、風向きに無頓着なまま花火で遊ぶと、煙や火花で自分よりも風下にいる人に不快感や恐怖感を与えてしまうおそれがあります。風向きと、周りの人との距離感には常に注意を払うようにしましょう」(直井さん)
日中よりも夜間のほうが、状況判断には注意を要します。いつの間にか自分の風下に小さい子どもがいた……なんてこともありうるので、花火に着火する前に必ず周囲をよく確認しましょう。
■10:両手に花火を持つ

見た目は美しくても、花火が“火”であることには変わりはありません。安全を期すためには花火は1本ずつ持って遊ぶようにしましょう。
「片方の手で未使用の花火を束にして持ちながら、もう片方の手で火のついた花火を持つのは危ないです。何かの拍子に火が束に燃え移ると、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、スマホを持ったまま花火で遊ぶのも、やはり危険だといえるでしょう」(直井さん)
何か不測の事態が起こった際にすぐに対処できるように、片手は何も持たず空けておくのが大事なのですね。
■11:深夜まで遊び続ける
深夜に及ぶ花火遊びは、条例によって禁止されていることもあります。また、明確に時間帯が指定されていない地域でも、21時には花火をストップして、後片付けを始めましょう。もちろん、公園など公共の場であれ、誰かのお宅の庭であれ、ゴミ出しのマナーを守ることもお忘れなく!
*
この夏、花火を楽しむ機会はまだまだあります。ぜひ上記のNGマナーを念頭に、風情を満喫しましょう。
おもてなし協会
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- WRITING :
- 中田綾美



















