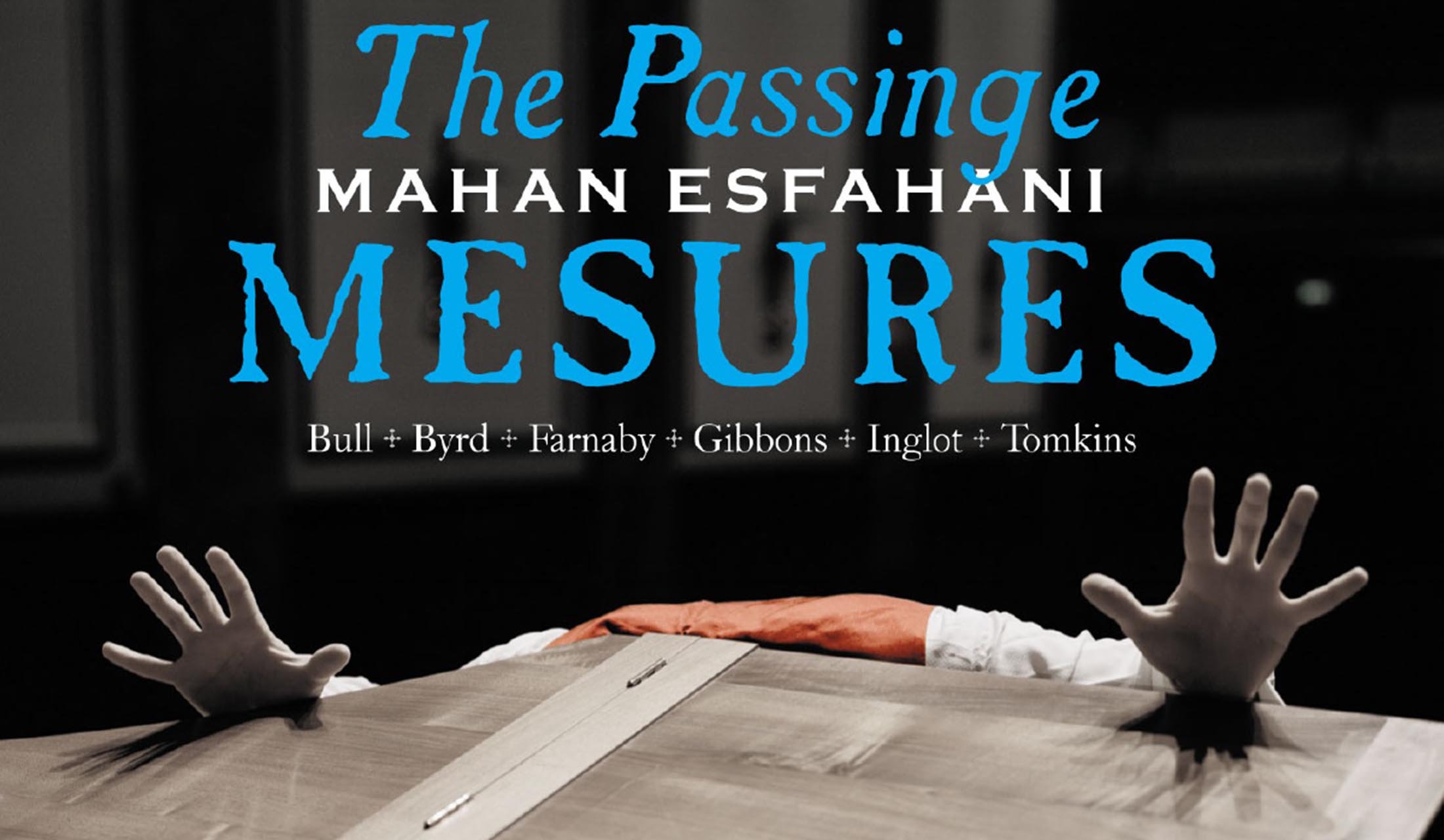年末年始の、わずかな余裕を利用して聴こうとピックアップしたいくつかの作品。その中には、イラン系アメリカ人のチェンバリスト(ハープシコード奏者)、マハン・エスファハニの『ザ・パッシング・メジャーズ〜イギリスのヴァージナリスト(鍵盤奏者)たちの音楽 バード/トムキンズ/ファーナビー』もあった。エスファハニの名前は、何年前からか耳にしていたが、その録音を聴く機会はこれまであまりなかったからだった。ちなみに彼がつい先日、12月に来日していたことはチェックミスだった。生で聴いてみたかったと、彼の音楽に親しんでいる今となっては実に悔やまれる。
生き生きとした、今を感じるチェンバロ
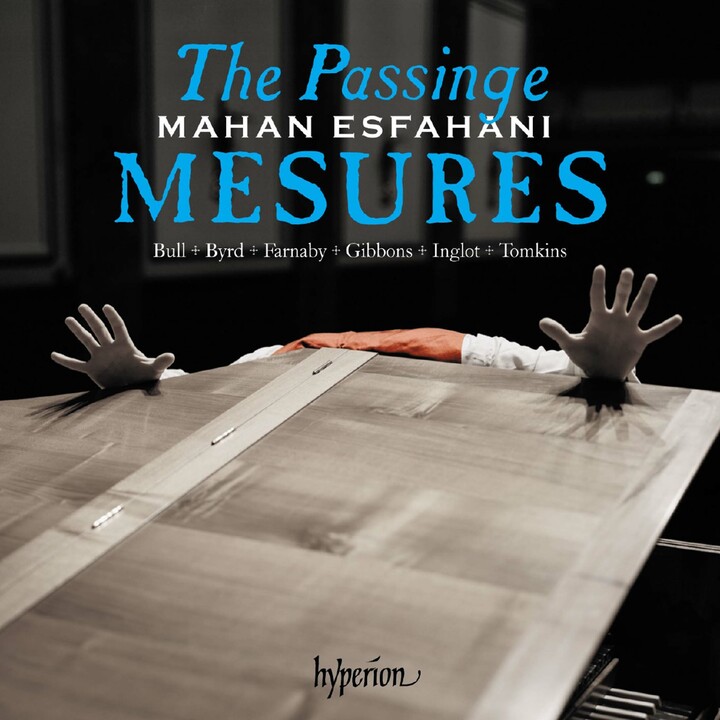
正月に穏やかな気持ちでチェンバロの音を味わおうなどと思っていたこちらの気分を裏切る、歯切れ良いチェンバロのサウンドにまず圧倒された。とかく「優雅」などと形容されがちのチェンバロという楽器だが、エスファハニの演奏はギターのような激しさと、ピアノのドライヴ感を併せ持つものだ。バッハほど整理された音世界ではなく、どこか素朴さや古色を感じさせる英国のルネサンス期の作品が、彼の手によって生き生きとした音楽として迫ってくる。緩急(アゴーギク)や装飾音の配置などから、なんというか、活動性を感じるのだ。その一方で、例えばダウランドの歌に基づく曲「Can she excuse my wrongs?(彼女は私の過ちを許してくれるだろうか?)」などは、重層感ある演奏がこの曲が本来持つ歌らしさを覆い、どこかアブストラクトな雰囲気すら漂わせるサウンドになっている。
これまで他のチェンバリスト、とくにグスタフ・レオンハルトのような演奏家の録音を聴く際は、どこか「古楽的世界観に浸る」ことを求めるようなところがあった。レオンハルト自身が17世紀の家具や調度品に囲まれ生活していたといったことを聞いていたせいか、最初の一音から彼の演奏は聴き手を作曲家たちの時代にタイムトリップさせるように感じていた。ところがエスファハニの録音はそれとは全く異なっている。彼は現代にリアルな音楽として、チェンバロ演奏を捉えているように、そのサウンドから感じられる。

チェンバロが鍵盤楽器の主役だった16世紀〜18世紀の作曲家の作品だけでなく、エスファハニはなんとスティーヴ・ライヒの「2台のピアノのためのピアノ・フェイズ」を独自にチェンバロ版にして弾いている。そのことからも、彼がチェンバロ演奏の可能性をより拡げようとしていることがわかる。ピアノやマリンバによるライヒ作品の演奏は、聴いているとミニマルな構成の中に一音一音の「丸み」が際立ってくるが、エスファハニの録音はそれと一線を画すような硬質な風合いになっているのが面白い(それはテクノ風味すら感じられる。マニュエル・ゲッチングの『E2-E4』を思わず連想した)。こんなパルス的なサウンドが「古の楽器(たとえモダン・チェンバロだったとしても、楽器の起源としては古いものだ)」であるチェンバロによって生み出されることに、ただ驚かされた。
現状でのエスファハニの代表作ともいえる、2016年にドイチェ・グラモフォンからリリースされた『バッハ:ゴルトベルク変奏曲』を聴いたのは前出の『ザ・パッシング・メジャーズ』の後だったが、この順番で聴けてよかったと思っている。というのも、もし、『ゴルトベルク変奏曲』からエスファハニの演奏を聴いていたら、彼の独創性や音楽性を味わう前に、「あざとさ」を感じ取ってしまったかもしれないからだ。有名なアリアの導入を、原曲のリピート指定そのままに2回演奏するだけでなく、1回目をどこかバラつきを感じさせるアーティキュレーションで弾いている。その後も緩急、強弱など、『ゴルトベルク変奏曲』に親しんでいる人ほど気づく独特な見解が随所に感じられる。少なくとも、ここでのサウンドには「不眠症の貴族を慰める」ような穏やかさはない。むしろバッハが晩年に発表した変奏曲に盛り込んださまざまな楽想を探り、それを最大限演奏に反映させようと奮闘するチェンバリストの姿が感じられる。それはグールドによる最初の録音などともまた違って、チェンバロゆえに生み出されるサウンドのスケール感も備えている。
ただ、『パッシング・メジャーズ』にあったような、巧みな演奏に見え隠れする「歌ごころ」のようなものは、『ゴルトベルク変奏曲』の録音からはあまり感じられなかった。バッハの器楽作品が持つ、怜悧な佇まいがより強く出ているのかもしれない。そんなことを考えながらネットを調べていたら、エスファハニが弾くラモーの動画に行き着いた。「雌鶏(La Poule)」や「エジプトの女(L’Egyptienne)」、「無頓着(L'indifferente)」といった、ラモー作品のユニークなタイトルも考慮したという演奏からは、奏でられたさまざまな音の粒が生き生きとした歌へと集束していくような印象がある。その様子に、エスファハニの魅力がよく表れていると現時点では捉えているのだが、いかがだろうか。
- TEXT :
- 菅原幸裕 編集者