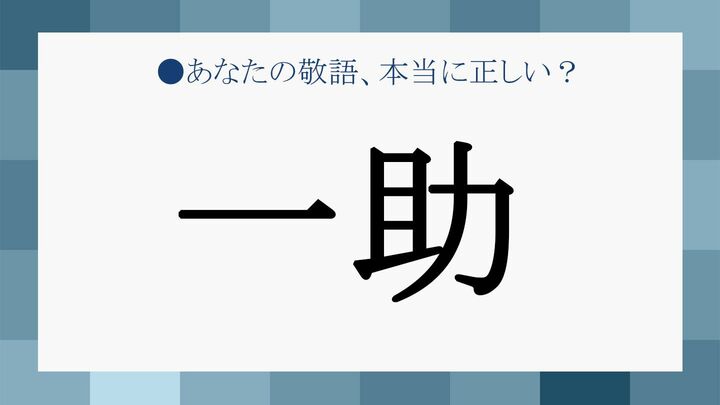【目次】
【「読み方」「意味」は?「基礎知識」】
■読み方
「一助」は「いちじょ」と読みます。「いちすけ」ではありませんよ。「助」という漢字から推測すると、「誰かの、何かの助けになること」を表す単語だと想像できますね。では「意味」を見ていきましょう。
■意味
「一助」は、「わずかばかりの助け」という意味の名詞です。漢字の「一」は、「1位」や四字熟語の「一番人気」、「いちばん好き」などと、最上級を表す場合と、「少し」「わずか」など少量を表す場合があり、「一助」は後者の意味。「大きな助け」という意味ではありません。
■使う相手は?
「一助」は、他者に力を貸す場合によく使われます。謙譲表現として用いられることが多く、大きな力を貸したとしても、「微力ではありますが…」といった意味合いを添えます。自分サイドの行為を示す文脈であれば、「一助」そのものは、使うのが不適切な相手はいません。目上の人には、あとに続く言葉を敬語にすればOK! 「助け」より「一助」のほうが、スマートな印象を受けませんか? ビジネス文書では、「助け」ではなく「一助」がおすすめです。
■使う際の注意点
「一助」という言葉は、「微力ながら」や「わずかばかり」といった、謙遜の意味を含んでいます。そのため、相手の力添えを表す際に使うのは、とても失礼にあたるのでご注意を。以下、実際に使える例文でチェックしてみましょう。
【そのまま使える「例文」】
■1:「若輩者ではございますが、プロジェクト成功の一助となるよう精一杯努力いたします」
■2:「弊社からの提案が、御社にとっての一助となれば幸いです」
■3:「弊社のプロジェクトが、お客様の安心安全を守る一助を担えますよう精進いたします」
■4:「匿名の情報提供が、問題解決への一助となった」
■NG:「先輩にご一助いただきましたことで大幅に進捗し、大変感謝しております」
「一助」に接頭語「ご」を付け、相手への敬意を表したつもりかもしれませんが…この用法は誤りです。感謝の気持ちを表したつもりが、相手には「ほんの少しの足しにしかならなかったのか…」と受け取られてしまう可能性も。「一助」の使用は自分サイドに限定、と徹底しましょう。
【「類語」と「言い換え」表現】
「一助」と似た意味の言葉は「一翼」のほかに、「一端」や「助力」などがあります。重要な働きや大きく貢献した場合でも、「小さな助け」だと謙遜して「一助」や類似語を使うのが、日本人らしいビジネスマナーです。
■「このチームの一助となれますよう、努力してまいります」を言い換えると…
→「このチームの一翼を担えるよう、努力してまいります」
→「このチームの一端をなせるよう、努力してまいります」
→「微力ながら、チームの力となれるよう、努力してまいります」
→「微力ながら、チームに貢献できますよう、努力してまいります」
***
「一助」は「ほんの少しの助け」を意味し、謙譲表現として使われます。ビジネスシーンにおいても、相手に協力を申し出る際や、意気込みを語るときには、便利な言葉です。その反面、相手からの助けに対して使うと、とても失礼な文脈に。稚拙な表現では、社会人としてのレベルも品格も問われかねません。正しくスマートな敬語を身に付けていきましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『敬語ネイティブになろう!!』(くろしお出版) :