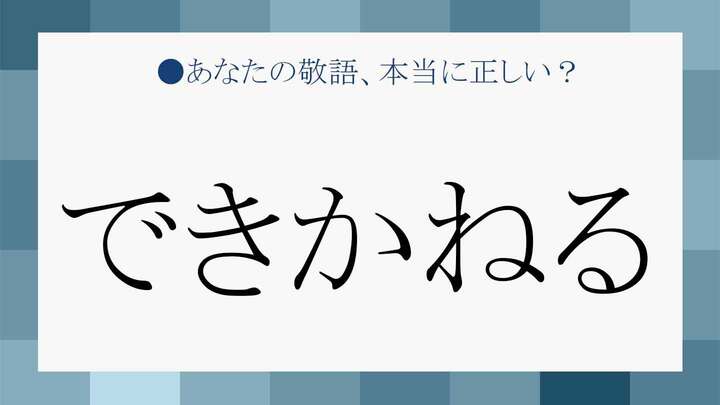【目次】
【「できかねる」の「意味」は?「漢字」で書くと?】
ビジネスでは取引先などからの依頼に対し、「できません」と伝えなければならない場面があります。無茶な依頼であれば、きっぱりと「できません」と言えそうですが、「無茶ではないけれど、事情により不可能」というケースも少なくありません。
そんなときに便利なのが 「出来かねます」 という表現です。これは「しようとする気持ちはあるけれど、実現は難しい」というニュアンスを含んだ、丁寧なお断り表現。相手に敬意を示しつつ断ることができるため、上手に使いこなせば「しっかり断る」ことと「相手に好印象を残す」ことの両立が可能になります。
※注意点として、「できかねません」と言うと二重否定になって意味が曖昧になるため、正しくは「できかねます」と使うようにしましょう。
■「意味」
「できかねる」は、次のように校正されています。
でき(動詞「できる」の連用形)
+
かねる(補助動詞:「〜しようとしてもできない」)
つまり「できかねる」は、「できない」という結論の前に「やろうとする気持ちはあった」ことを含む表現です。
ニュアンスの違い
-
できません
→ 最初から拒否しているように響く。 -
できかねます
→ 「努力や意志はあったが、事情により不可能」と伝わる。
そのため、最初からやる気がないように響く「できません」よりソフトな言い回しとなり、相手によい印象を残すことができるのです。
■「漢字」で書くと?
「できかねる」は漢字で書くと 「出来かねる」 ですが、表記の使い分けには注意が必要です。
-
「できる」
- 名詞として使う場合(例:「出来ることから始める」) → 漢字「出来る」
- 動詞として使う場合(例:「それならできる」「参加できる」) → ひらがな「できる」 が一般的 -
「できかねる」
「できる(動詞)」+「かねる(補助動詞)」で構成されているため、通常は ひらがなで「できかねる」 と書くのが自然です。
ビジネス文書でのポイント
依頼に対して返答する際は、「できかねます」 とひらがなで表記するのが一般的で、読み手に違和感を与えません。
一方で、「出来かねます」 と漢字で書いても誤字ではありませんが、やや硬い印象を与えるため、ビジネス文書ではひらがな表記の方が無難です。
【「敬語」や「丁寧な言い方」にする方法は?】
■「できかねます」
「できかねる」は婉曲な表現ではありますが、敬語そのものではありません。
例えば上司が部下に対して「この予算案は納得できかねる」といった使い方をします。
一方、目上の方や取引先に対して使う場合には、「できかねます」 と丁寧な形にするのが適切です。
■「いたしかねます」
「できかねます」とほぼ同じ意味をもつのが 「いたしかねます」 です。
これは、動詞「する」の謙譲語「いたす」と、否定を表す「しかねる」から成り立っています。
「いたす」とへりくだることで相手を立てるニュアンスが加わるため、取引先や目上の人に断りを伝えるときにより丁寧な表現として適しています。
■心苦しい気持ちをプラスするのが「大人のお断り」
依頼や申し出を断る際には、双方気持ちよく収めたいもの。小さな軋轢も、度重なるとトラブルを生みかねません。そんなときに「できかねます」は最適といえる言い回しです。
依頼をお断りする際には、「お応えしたい気持ちはあるのですが、諸事情があって難しいので断るしかありません」と、「個人的にはとても残念です」という感情や、無念な気持ちをにじませるのが会話巧者。そこで活躍するのが「残念ながら」「あいにくですが」「申し訳ありませんが」などのクッション言葉です。
次に、それらを使用した例文を見てみましょう。
【「やんわると断りたいとき」に使えるビジネス例文】
■大変ありがたいお話なのですが、ご依頼はお受けできかねます。
■申し訳ございませんが、今回はできかねますことご容赦ください。
■あいにくですが、お申し出をお受けすることはできかねます。
■お手伝いしたいのはやまやまですが、お引き受けできかねます。
■残念ながら、調整できかねるという結論に至りました。
■できかねますこと、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
■ご希望の期日までにはできかねるのですが、いかがいたしますか?
さらに、「言い換え」表現を使用した例文も挙げておきます。
■「残念ながらお役に立てることがないかと存じます」
■「あいにくですが、今回はお力になれません」
■「一存ではお返事が叶いません」
■「確約することが難しい状況です」
■「厳しいかもしれません」
■「今回はご遠慮させていただきます」
■「お断りせざるを得ないことをお詫び申し上げます」
【「できかねません」はどういう意味?】
■「できかねない」とは?
「〜かねない」とは、動詞「かねる」の未然形に打消しの助動詞「ない」が付いたもので、【…しないとは言えない/…するかもしれない】という意味です。
たとえば「彼ならやりかねない」といえば「彼ならやるかもしれない」ということ。
したがって「できかねない」は「できるかもしれない」という意味になり、「できかねる(=できない)」とはまったく別物です。
■「できかねない=できない」ではありません!
「できかねません」を「できません」という意味で使うのは誤用です。
本来は「できる可能性を否定できない=できるかもしれない」と解釈されるため、断ったつもりでも曖昧な表現になってしまいます。
ビジネスの場では、波風を立てたくないからと曖昧な言い回しをすると、相手に誤解を与えかねません。
「申し訳ありませんが、できかねます」と明確に伝えることで、相手への配慮と正確さを両立させましょう。
***
「できかねます」は「〜しようとする気持ちはあるけれど、できない」というニュアンスを含むため、依頼を断りながらも誠意を伝えられる便利な表現です。
ただし遠回しな言い方ゆえに、状況によっては誤解を招くこともあります。そのような場合は、お引き受けできません」などストレートな表現を用いた方が適切なこともあるでしょう。
また、「できかねます」は丁寧な表現ではあるものの、最終的には「できない」という意志表示です。
したがって、「こちらはできかねますが、△△であれば可能です」といった代案を添えると、より前向きで建設的な印象を与えることができます。
これはまさに「デキるビジネスパーソン」の心遣いといえるでしょう。
なお、似た表現に 「できかねません」 がありますが、これは「できる可能性を否定できない=できるかもしれない」という意味になり、「できません」と同じ意味では使えません。誤用にあたるため、ビジネスでは使わないよう注意しましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『印象が飛躍的にアップする大人の「言い方」練習帳』(総合法令出版)/『大人なら知っておきたいモノの言い方サクッとノート』(永岡書店)『とっさに使える敬語手帳』(新星出版社)/『くらべてわかる 日本語表現文型辞典』(Jリサーチ出版) :